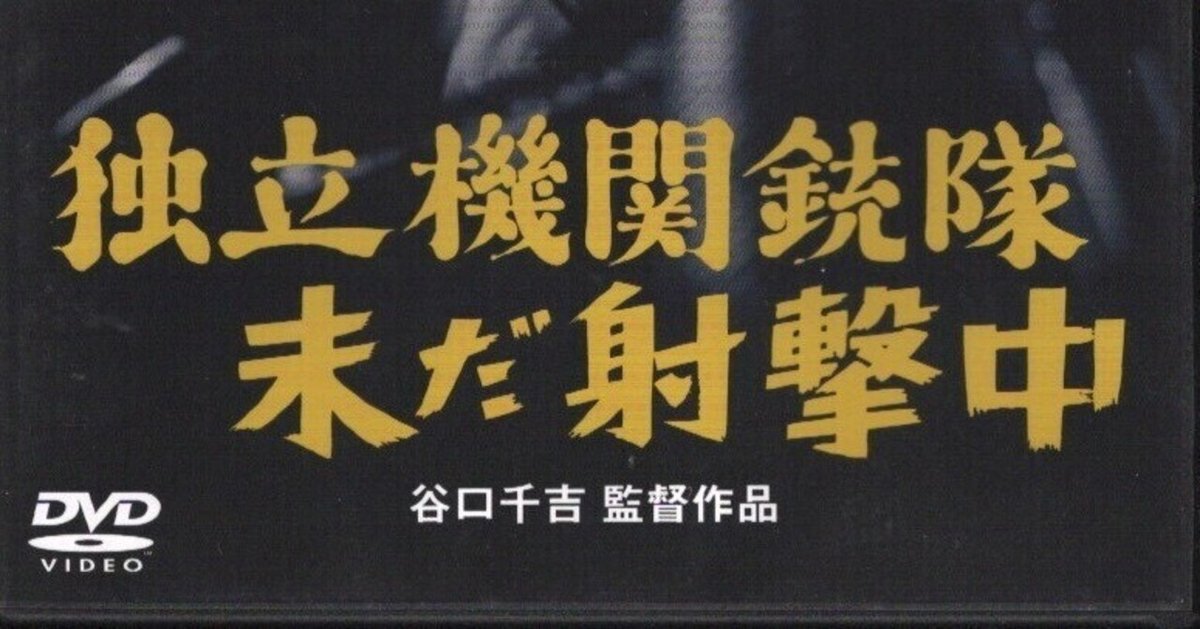
『独立機関銃隊未だ射撃中』のラストシーンで失われたもの
1963年公開の東宝映画『独立機関銃隊未だ射撃中』。
わたしのなかではこの作品は日本の戦争映画のベストテンに確実に入る作品である。
力のこもった戦争映画であるにもかかわらず、この作品は忘れ去られている。
タイトルの「独立機関銃隊」の独立という言葉が、岡本喜八監督の戦争アクション映画『独立愚連隊』を想起させるのは当然なところだが、これはその系譜の作品ではない。
1973年に刊行されたキネマ旬報の『日本映画作品全集』のなかで、本作は「独立愚連隊シリーズ」の一本として数え上げられたことから、この作品は戦争活劇のなかに組み込まれてしまっている。
もっとも公開当時もそれを誤解した人も多かっただろう。
しかし、「独立機関銃隊」の起源は「独立愚連隊」ではない。
この言葉の由来は戦前の戦記小説『独立機関銃隊猛射中なり』から来ていると考えられる。『独立機関銃隊猛射中なり』は日中戦争を舞台にした戦意高揚小説の一つであって、これとは真逆の反戦の立場から描かれたのが、『独立機関銃隊未だ射撃中』なのだ。
映画の舞台は旧満州のソ連国境付近の日本軍トーチカ陣地である。
現地の少年志願兵の白井二等兵(寺田誠)がトーチカに着任するところから始まる。
トーチカは指揮官のバターン攻略戦以来の歴戦の勇士でベテランの山根軍曹(三橋達也)、農民出身で朴訥とした射手の渡辺上等兵(佐藤允)、軍隊に住み着いている調子のいい皮肉屋の金子一等兵(堺佐千夫)、戦争に馴染めないでいる学徒兵の原一等兵(太刀川寛)が守備に当たっていた。
やがて、ソ満国境を超えたソ連軍の部隊がトーチカ陣地へと迫ってくる。
絶え間ない航空機の空爆。
戦車部隊がトーチカの手前まで攻めてくる。
狭いトーチカの中の極限状態で、兵士たちは冷静さを保てなくなってくる。
まず金子一等兵が、自傷して逃げようとし、班長の山根軍曹が戦車への肉薄戦で戦死し、トーチカ内は渡辺、白井、原の3人になってしまう。
彼らのトーチカ以外はことごとく潰され、最後に猛攻撃を受けて彼らのトーチカも壊滅する。
一人生き残った学徒兵の原は脱出して、野辺の百合の花に手を伸ばした瞬間、飛んできた友軍の弾に当たり落命する。
全く救いのないラストでこの映画は終わる。
終始、重苦しい描写と緊迫感、戦争のリアリズムはユーモアを見せる余裕もない。
これが「独立愚連隊シリーズ」の一本に数えられたことは、明らかに間違いであることがわかる。
当時としては既にB級アクション映画造りなどで、作品との出会いに恵まれず、精彩を失いかけていた谷口千吉監督の手腕はこの作品では、一転、戦争映画の傑作となった。
谷口演出よりも、その功績は脚本にある。
シナリオを担当したのは井手雅人である。
井手はこの脚本を書くにあたって、故意に無機質な印象を与えるカタカナで書いている。
カタカナの持つ効果はひらかなの情感的なものが一切排除されて、シナリオを読んだだけでも戦争の冷たい機械のような無機質さが強調され、これは映画設計図としてのシナリオの域を超えて一つの文学的な価値さえ感じさせる力作であった。
花を積もうとして敵弾に落命するという明らかに戦前のアメリカ映画の名作『西部戦線異状なし』のラストシーンの焼き直しである。
映画が、原作ともいうべき井手雅人のシナリオをうまく拾えなかったのは、映画のラストシーンの改変であった。
映画評論家の佐藤忠男の著書『現代日本映画』にも記述があるが、井手雅人のシナリオの最後は、無茶苦茶になったトーチカで一人生き残った渡辺上等兵がロシア兵に捕まり、惨めに身体検査をされて殴られて倒れるが、若いロシア兵に抱き起こされて、水筒の水をもらう。
そこへ飛んできた自軍の砲弾で渡辺は倒れ、若いロシア兵に抱き起こされた時は死んでいた。
日本軍を追撃するために、渡辺の死骸を道に残して、ソ連軍部隊が前進してゆくところで「世界に平和を」というテロップが重なり映画は終わる。
佐藤忠男が指摘しているように、このラストシーンは東宝という映画会社には承服し難いものだったのだろう。
既に冷戦の時代、キューバ危機が起こった1963年の時点で、西側にとっての最大の敵であったソビエト連邦の部隊が進撃してゆくところに「世界に平和を」というテロップが重なるというのは「共産主義の勝利によって平和がもたらされる」という政治的メッセージに映ったのかもしれない。
しかし、井出雅人の意図は決してそうではなかっただろう。
このラストのリアリズムは1945年8月9日以降の満州における現実でしかないからだ。
ここに政治的な匂いを感じる方が、逆に歴史に対しての誤謬であると言わざるを得ない。
シナリオのままのラストなら、この映画は日本戦争映画の傑作としてのレベルをさらに上げたことだろう。
最後まで生き残って、ロシア軍兵士に水をもらうのは渡辺上等兵(佐藤允)である。
映画のラストで生き残るのはインテリの原だったが、シナリオでは素朴に厳しく生きてきた農夫の渡辺であり、それを救おうとする若いロシア兵もまた広大なロシアの農村の青年であっただろう。
佐藤允の劇中の抑えた演技は、彼の東宝映画における持ち前のバイタルさや軽妙さ、「いいから、いいから〜」という楽観的な決め台詞の笑顔とニヒルな態度、あの雰囲気を一切押し殺している演技は、井出雅人が書いたラストシーンのためにあったものであると考えられるだろう。
『独立機関銃隊未だ射撃中』における佐藤允の抑制された演技は、異色作の『みな殺しの霊歌』における、あの朴訥さとも違う、そこにはあのアンバランスでユニークな熱狂がないのだ。
あそこまで、冷静沈着に朴訥と軍務に従事してきた渡辺という人物を劇中で、支え続けた佐藤允の演技が、たった一回の火炎放射器の放射によって焼き殺されてしまうという展開はあまりにも残念であり、これは映画における政治的裏事情が、一人の俳優の力量も脚本家の仕事をも、台無しにしてしまったのだ。
それでも完成した『独立機関銃隊未だ射撃中』は力作である。
本年2023年をもって公開から60年目を迎える本作は今一度、再評価が必要であると、わたしは強く思うのである。
そして、この映画を鑑賞したのちはシナリオも読み返していただきたいと思う。
付記:
わたしは20代の頃、シナリオ作家修行の時代に、この作品のシナリオを読んで強い衝撃を受けたのを記憶している。
映画を鑑賞する以前に、シナリオを何度も何度も読み返したことは、わたしにとって幸運であったと思う。
『独立機関銃隊未だ射撃中』のシナリオは日本シナリオ協会刊『日本シナリオ体系』第4巻に収録されている。

