
長野で観光まちづくり企業に勤めてみたら仕事が余暇になった
東京で生まれ育ち、親の期待に応えねばとあくせく勉強に励みそれなりの私立大学に進学し、教員として英語教育に携わったのち英語も使えて今後産業の中心になっていくであろうIT企業に転職しソフトウェアの品質管理を経験し、長野に移住して現地の観光まちづくり企業(観光業と宿泊業)に就職し身軽に?職を変えてきた。長野の観光まちづくり企業で働いて約1ヶ月が経ったので、働き方についてこれまでの考え方が激変したことを中心に記録してみます。
最初にオチを述べておくと、私はここで働いて、仕事が余暇になりました。
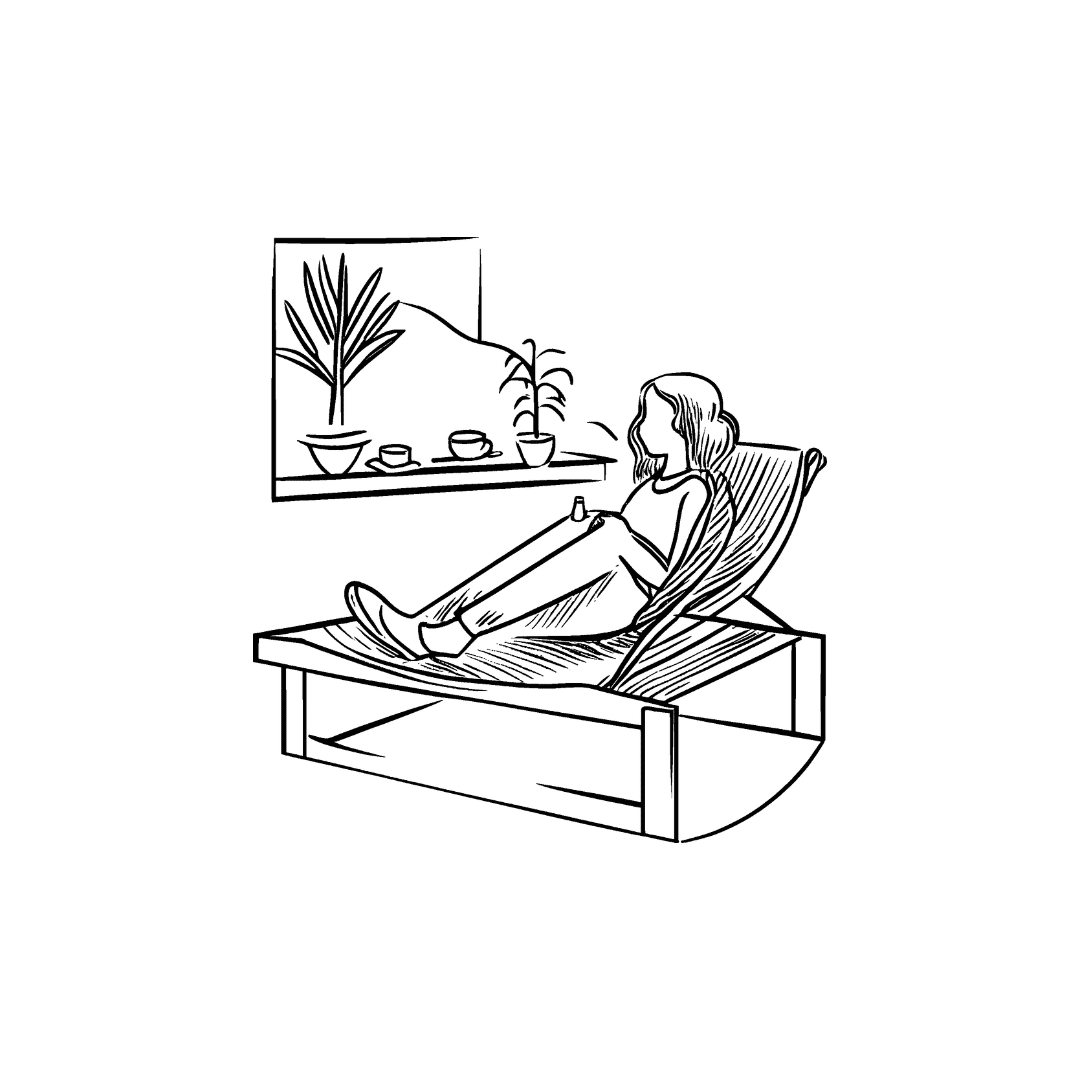
忙しいと当たり前だけど燃え尽き症候群になる
現代病の燃え尽き症候群と鬱病や適応障害などのメンタルヘルス系精神疾患。職場での人間関係やポジション争い、評価、責任感、義務感など人によって状況はさまざまだと思うけれど、とにかく現代は働いているだけで燃え尽き症候群(メンタル不調も)になりやすい。
私が経験した燃え尽き症候群の「忙しい」パターンは2つ。
1つは、その職業の虜になってしまい熱中してしまうパターン。新卒の人や憧れの職についた場合に多そう。自分で自分を仕事に前のめりにさせ、短期的な結果を求めてひたすら行動している。早く社会に認められたい、誰かの役に立ちたい、成果を出したいと休日も仕事のことが頭から離れない。自分の本来のキャパシティを超えて仕事をし続けている。
2つ目は、業務量が多すぎて長時間労働になっているパターン。IT企業やベンチャー企業で勤めている人に多そう。毎日10時間も12時間も働いているのになぜだか仕事が終わらない。チャットが鳴りやまずむしろ仕事は増えるばかり。周囲の同僚も忙しそうにしている。みんなで頑張っているのになんで終わらないんだろう…。
世の中にはAIや業務効率化ロボットなど人がこれまでやってきたことを自動化し、働いている人々がより創造的な仕事ができるような便利ツールが生まれているにも関わらず。結局、今までやってきたことと変わらない業務を長時間かけてやっているような。
忙しいと脳も身体も疲れてしまい、燃え尽き症候群を発症する。燃え尽き症候群になると創造的に働いたり新しいことを生み出したりすることができなくなる(製造業から知的産業に移り変わっている現代で生き残っていけるのだろうか)。
私は長野のとある企業で観光と宿泊に携わりながら、今までの教員時代やIT企業で働いていた時期とふと働き方を比べてみたときに、ハッと気づいたことがある。
燃え尽き症候群になってしまう「忙しさ」の2パターンとも関係することだが、私たちは無意識に無理やり忙しさを作り出しているのでは?
労働をしなければいけないという強迫観念がどこかで人々に自らの首を絞めさせている気がしてならない。業務量やタスクを増やさないと、忙しくならないと勘違いさせられているのではないか。
教員のときもIT会社員のときも薄々気づいてはいたことだが、一日にたくさんのことをこなしたり処理をしたりしても、そうすぐに結果は跳ね返ってこない。

1日8時間も必要ないタスクで暇なはずなのに忙しくしてしまう
業務の分業化が進む現代では、専門職ごとに細かく仕事が分かれてきている。職務の領域が狭まりより専門的な知識や高度な技術が求められる。幅広く色々なことをやらなければならないことも減っている。
ゆえに、ひとりの人が色々とやらなければならなかった頃よりも、今のほうがやるべきことの量自体は減っているのではないかと単純に思う。
1日8時間も必要なの?
必要かどうか、ではなく給料は1日8時間の労働した時間に対して支払われているから忙しさをアピールしておかねばならない。IT会社員時代に一緒に働いていた職種が異なる同僚は「とにかく先々までGoogleカレンダーに予定を入れておくことが大切なんだ」と言っていた。
働いている感が労働している本人たちには必要だし、なにしろ働いている時間でしかその人の働きぶりを評価するすべが今のところないのかもしれない。
あれ、知的産業で働いているのに生産性や創造性は重要ではないの?
みんなが忙しくしている職場では自分も嫌でも忙しくしていないと怠けていると思われかねない恐怖心もあるが、そんなことをしている暇があるならもっと意味のあることをしたいぜと思う葛藤もある。
分業化、専門性、そういった働き方の良い側面もある一方で、それによって最終的には時間でしか頑張りを測ることができない状況に置かれてもいる。
こっちで働いていると、忙しさの概念がそもそも消え去っている感覚がある。誰かと忙しさを張り合う必要もないし、忙しさアピールをしても誰がそれをみているのだという感じだ。むしろ忙しくしている方が格好悪く思えて恥ずかしささえ感じてしまう。
幸運にも、創造性を発揮したアウトプットを上司がかってくれているので(働いている時間を重要視しているわけではないので)想像していた以上にのびのびと働かせてもらっている。
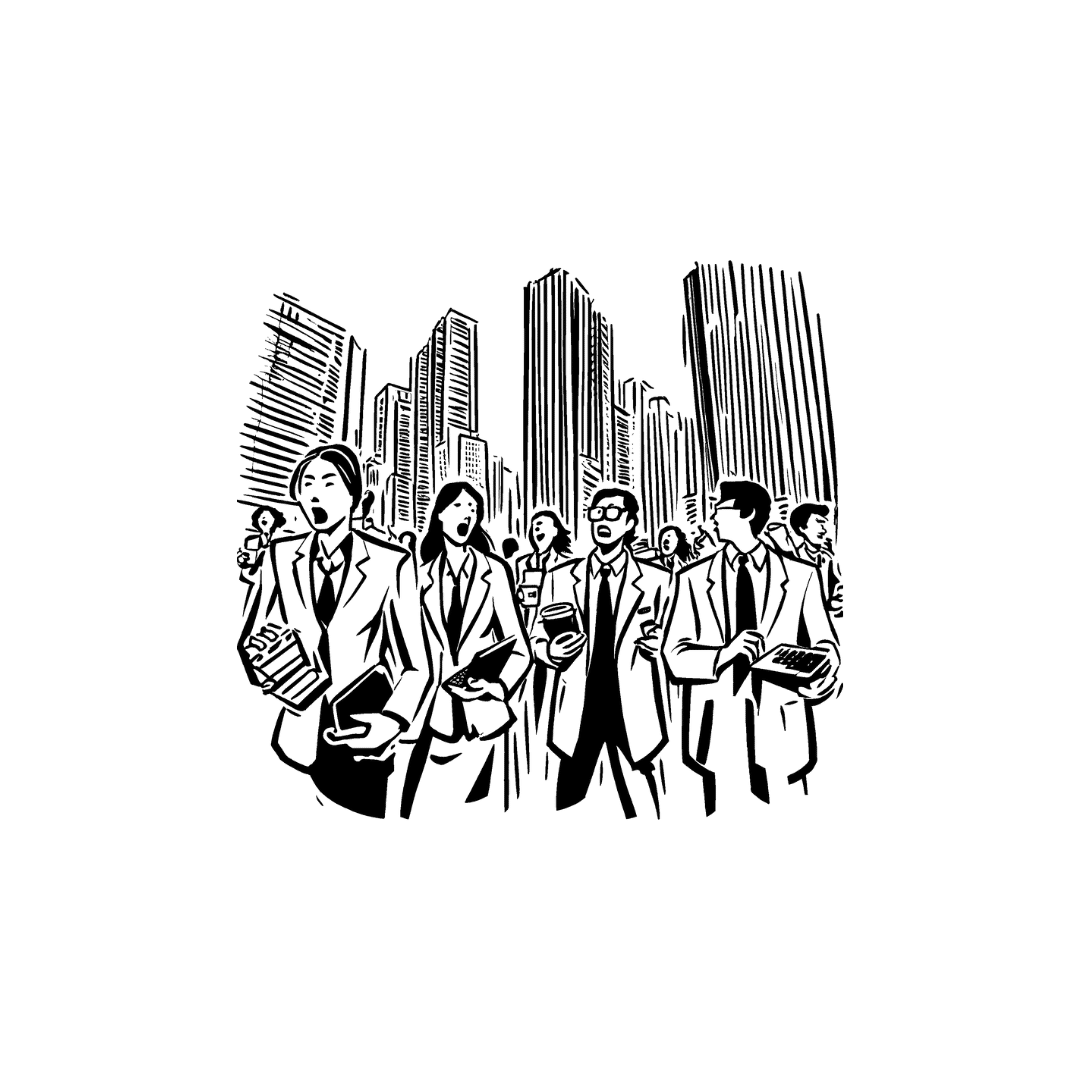
生産性のかけらもなく人生の時間が削られている気がしてくる
リモートワークしていても、オフィス出社していてもslackのどのチャンネルもピコピコ鳴りまくり。返答を急がされ作業が中断する。作業に戻る頃にはやる気と集中力が欠け、再びフロー状態に入るまで労力がかかる。話したら一瞬で終わりそうなこともテキストを打って会話している。
今考えたら、なんなんだこれは!
あまりにも生産性が低すぎる。slackから逃れられない。土日もslackは動き続ける。少しでも読んでおかないと月曜日の作業時間が減ってしまう恐怖…。
ほかにも、IT企業といってもムダなことが多いなと思ったりもしたが、会社の方針だったり上司の考え方だったりがあるので、やるのみ!と自分を騙し騙しやるが、それが遅かれ早かれ自分の人生の時間をムダしているかも(惨めさ)に繋がってモチベーションが一気に下がる悪循環。
生産性が高そうに見えて低いという闇。

仕事が余暇になると生産性と創造性が爆上がりする
労働みたいな仕事をするのか、余暇のような仕事をするのかで生産性と創造性にだいぶ影響があるのではと実感しているところだ。
今までの職業人生を振り返ってみて、私は「労働」とは本来やりたくもないことをあえてやることだと思っている。それに対して「余暇」は有益か無益かを気にしない単なる意味の追求だと思う。
「労働」は、頑張って生産性を上げるために、生産性を上げると称した結果的には生産性を低めてしまうオンラインミーティングをわざわざスケジュールを組んで実施したり、会議のための会議をしたり、作業のための会議をしたりして成り立っている。本来やりたくもないことをやるので各人の時間を確保して(確保しないとやりたくないようなこと)やっているのが労働だ。前述の通りモチベーションや生産性はダダ下がりだ。ついでに疲労感も満載のはず。
「余暇」は、特にだれに言われるわけでもなく、過度に要求されるわけでもなく、純粋に目の前のことを追求しているだけなので、わざわざお互いの時間を合わせてまでミーティングを開いて、、、なんてことはいらない。〇〇のための▲▲をやるのではなく、直で▲▲をやるのだ。忙しさを作るためのタスクを増やしたりせず、その分思考に時間を充てる。会議やタスクや忙しさの量ではなくアウトプットの質を高める(質にこだわることができるのは、「利益にならなければやっても無駄だ」という思想ではないから)。利益を追求しすぎるがあまり、あれもこれもで、最終的にあれもこれも効果を発揮しない。
目先の利益を追っていまいまコネコネやってもその後につながっていかず一発屋で終わる。量は少しずつでも質を高めてアウトプットすることで、長期的な生産性アップにつながると私は信じている。典型的な例としては、俳優。駆け出しの頃はドラマにも出たいし映画にも出たいしCMも、、、って気持ちは焦るだろうが、目の前にきた役を丁寧に演じ切ることで、ドラマの主演やCM出演の話もくるようになる(年収も当然高くなっていく)。これが生産性向上なのでは。
生産性アップには熟成が必要なのだ。熟成にはもちろん時間がかかる。
質を大事にしながら根気よく自分が信じたものを熟成するまで続けられるかが企業成長のカギなのでは。そして働く人にとっては仕事が労働ではなく余暇であること。

頑張って働くことほど意味のないことはない
ここまで書いてきて、素直に思うことは、仕事に頑張りは要らない。頑張っても燃え尽き症候群になるし、生産性も上がらないし、企業も成長しない。
『頑張って結果を出したら次はもっと頑張らないと結果出ないってことでしょ?頑張らないで結果を出すことが大事だよ』
と私が大学生時代に経営を教わったある起業家(社長)の言葉がいまでも忘れられない。
いいなと思ったら応援しよう!

