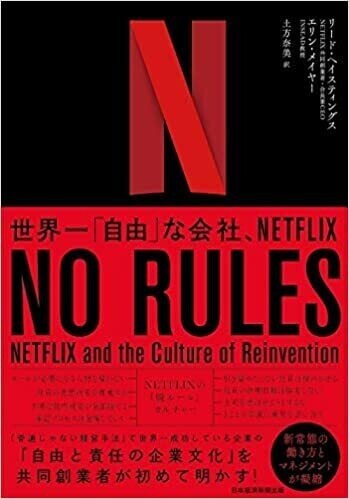上司が意思決定しない。『NO RULES』 の一部をチームに導入しました
書籍『NO RURLES』に記載されている内容の一部を人事チームに導入した話です。
書籍『NO RULES』のうち、
— 人事のなべはるさん (@nabeharuj) January 5, 2021
・意思決定は組織図上の上司ではなくそのことをいちばん深く考えている人が行う
・前向きな意図の率直なフィードバックを増やす
の2つをチームに導入することにしました!
NETFLIXの組織・人事制度を解説した『NO RULES』
『NO RULES』はNETFLIX創業者が書いた、同社成功の秘訣を人事制度・カルチャー面で解説している本です。
NETFLIXの人事といえば、2018年に発売された『NETFLIXの最強人事戦略』が思い出されますね。『NO RULES』と『NETFLIXの最強人事戦略』はどちらも「最高の人材を採用し、信じて任せる仕組みをつくることが最高のパフォーマンスを生む」という一貫したメッセージが発信されています。
私見では、『NO RULES』のほうがかみ砕いて現実的な施策まで落とし込まれており、参考にしやすい内容になっています。『NETFLIXの最強人事戦略』を読んで、「内容がマッチョすぎてついていけないな」と感じた方にもオススメです。
意思決定は上司ではなく、「そのことにもっとも詳しい人」が行う
今回、わたしのチームで導入したのは、『NO RULES』6章「意思決定にかかわる承認を一切不要にする」の内容です。
6章の内容は、わたしの Twitter で要約しています↓。
『NO RULES』の6章「意思決定にかかわる承認を一切不要にする」の読書メモをツイートしますー。このスレッドにて。https://t.co/MUqvlpv5sP
— 人事のなべはるさん@人事募集中 (@nabeharuj) January 6, 2021
NETFLIXでは部下が新たな取り組みを始めるとき、上司の許可・承認を得る必要はないそうです。意思決定するのは上司ではなく、「そのことにもっとも詳しい人」=「情報に通じたキャプテン」であり、それがもっとも勝率が高いとされています。
この考え方を、わたしのチームでも導入しました。
上司が正解を知っているとも限らない。一番詳しい人が決める方が勝率が高い
わたしのチームは3人で採用・教育研修・制度・労務・総務などの仕事を行っており、組織図上はわたしがマネジャー(=上司)です。
従来のやり方では、チームの意思決定はマネジャーであるわたしが行うのがふつうでしょう。しかし、必ずしもマネジャーがメンバーよりも業務に精通しているとは限りません。むしろ、前線で戦っているメンバーの方がその業務に詳しいことのほうが多いと思います。
となると、マネジャーが意思決定するよりもその業務にもっとも詳しいメンバーが意思決定するほうが勝率が高いはずです。そこで、業務範囲ごとに意思決定する人を決め、「キャプテン」と呼んで運用しています。
例えば、「新卒採用活動のキャプテンはこの人」という使い方です。意思決定は上司ではなく業務に精通したキャプテンが行うのです。
キャプテンを明示的にすることで責任範囲が明確になる
実は、「キャプテン」制度をチームに導入する前も、同じような運用はしていました。できるだけマネジャーではなくメンバーが意思決定するように権限移譲していたつもりです。
今回、『NO RULES』にしたがって「キャプテン」を明示的にすることで各メンバーの責任範囲がさらに明確になりました。これまでは、「メンバーが決めてもいい」だったものが、「メンバー=キャプテンが決めるもの」と明確になったわけです。
また、業務を整理したり人員配置をする際に「キャプテンは誰か?」の視点が入ることで、決める人不在のこぼれ球が発生しづらくなりました。「担当はいるけど決める人がいない」状況はうっかりやってしまうんですよね。
キャプテン制度が成立する4つの条件
上司ではなくキャプテンが意思決定するやり方はメリットがたくさんありますが、無条件に導入して効果があるものではないと思っています。
まず何より大事なのが、キャプテンを任せられる人がチームにいること。
その業務について、誰よりも詳しく誰よりも考えている人だからこそ良い意思決定ができるわけです。そんなメンバーがチームにいることが絶対条件です。
次の条件は、意思決定の際の相談や情報共有が密になされること。
キャプテンが意思決定するといっても、1人で好き勝手になんでもしていいわけではありません。意思決定の勝率を高めるために、事前に周囲と相談し、意見を集める必要があります。
キャプテンを任されたメンバーが、「勝手に決めていいんだ」と捉えているとうまくいかないでしょう。
3つめの条件は、周囲がキャプテンに率直にフィードバックすること。
キャプテンの考えや方針に懸念や反対意見があれば率直にフィードバックすることが求められます。キャプテンが決めるからといってキャプテンに任せっきりにするわけではないのです。
最後の条件は、チャレンジによる失敗が許容される文化であること。
難しい意思決定をすれば失敗することも当然あります。失敗することが許されない企業文化であったり、失敗することが評価査定でマイナスになるような制度だと、誰もキャプテンをやりたがらず、従来どおり上司が意思決定したほうがいいでしょう。
【上司ではなくキャプテンが意思決定するやり方が成立する条件】
・キャプテンを任せられるメンバーがいる
・意思決定の際に相談や情報共有が密にされる
・周囲はキャプテンに率直にフィードバックする
・チャレンジによる失敗が許容される
以上、わたしのチームで導入した「キャプテン」制度でした。お読みいただきありがとうございます!
いいなと思ったら応援しよう!