
昭和新山(洞爺湖有珠山ジオパーク)と石狩炭田(三笠ジオパーク)
約2万年前に誕生した有珠山は1663年から活動期に入り、20世紀だけでも4度の噴火を繰り返しており、1944年〜1945年の噴火では昭和新山が形成されました。
Armadas
有珠山の誕生
2万〜7,000年前に、
有珠山は火山活動によって、洞爺カルデラの南麓で生まれました。最近でも、20年から30年ごとに噴火しています。
縄文時代早期、
北黄金貝塚付近で暮らしていた縄文人は、噴石の被害や津波に見舞われた可能性があります。
昭文社

洞爺湖有珠山ジオパーク
昭和新山の誕生
1943~1945年、有珠山の東麓に溶岩ドームができました。
もともとあった粘土質の土壌が押し上げられ、粘性の高い溶岩で焼き固められました。
昭文社

洞爺湖有珠山ジオパーク
(1)昭和新山(有珠山・山系)
(2)標高・・・398m
(3)最新噴火・・・ 1944年
(4)火山の分類・・・溶岩ドーム
(5)火山帯・・・那須火山帯
石炭と地層から読み解く北海道・三笠1億年のモノ語り
石狩炭田の地層の誕生
約8000万年前(白亜紀)、
北海道の東半分はユーラシア大陸のはるか沖に浮かぶ島々でした。
約6600万年前(古第三紀)頃に、
北海道の大地となる様々な場所は、オホーツクプレートの動きにしたがって少しずつ近づきました。
約5500万年前(古第三紀)頃に、太平洋プレートと「クラプレート」の境界にあった海嶺が(現在の北海道の位置まで)北上して、ユーラシア大陸の下に
沈み込みました。
約5000万年前(古第三紀)頃に、陸上となった現在の北海道の中央部には広大な湿地が広がるようになりました。
国土交通省
(1)石狩炭田の歴青炭
(2)地層の場所・・・夾炭層に挟まれた地層
(3)時代・・・古第三紀
(4)地層の分類・・・炭層
フィリピン海プレートの回転説
国土地理院のGPSによると、
北海道南西部に位置する渡島半島の日本海側沿岸部がユーラシアプレート方向に、局所的に移動していることが分かります。このプレート(移動)の局所的異常を説明するようなマントルの流れは見つかっていません。
フィリピン海プレートの回転説・・・
フィリピン海プレートがユーラシアプレートに対して回転すると仮定して、
回転軸を計算してみると、回転軸の位置はカムチャッカ半島の南端になります。
火山フロントと有珠山
火山フロントの西側に位置する渡島半島が局所的に西進しているため、有珠山周辺の地盤には東西方向に引っ張り応力が発生していると予想されます。
そして、この地盤の変動は有珠山の噴火をより活発にしているかもしれません。
瀬野徹三

日本最古のお墓は?
現在、日本最古のお墓といわれているのは「湯の里4遺跡」です。
北海道上磯郡知内町にある「湯の里4遺跡」は、昭和58年に調査発掘され、約2万年前の旧石器時代の墓と考えられる日本最古の土坑(地面に掘られた穴)が発見されました。
お墓きわめびとの会
玦状耳飾り

山内丸山遺跡の時代(約5900-4200年前)の遺跡から、
玦状耳飾りが北海道から九州全域で出土します。
当時の日本では確認されない鉱物が用いられており、
中国からの交易品の可能性があります。
旧約聖書の「東倭伝」説(=田中英道先生)
それゆえ、(あなたたちは)東で主をあがめ、海沿いの国々でイスラエルの神、主の御名をあがめよ。
(わたしは)地の果てから、賛美の歌を聞いた、
「栄光は正しい者にある」と。
しかし、わたしは言う、
「わたしは衰える、わたしは衰える、わたしは災いだ。あざむく者があざむき、あざむく者のあざむきが(わたしを)あざむく」。
「旧約聖書」
「イザヤ書」24:15,16
北の縄文人の衣装(縄文時代後期)

文化局文化振興課
当時の衣服が完全な形で発見された例は今のところありません。
このイラストは出土した土偶(縄文時代後期)の文様や繊維の断片等を参考にして、復元されています。
北の縄文の人びとは、着飾ることに大変熱心だったようです。
衣装・・・「アンギン」布?の着物と動物の毛皮の防寒着。
文化局文化振興課
「アンギン」布の編布製作機具
尾関清子氏によると縄文時代晩期には、
技術革新により編物と織物の両方が作られました。
布目順朗
小学館
九州の縄文人からの贈り物
有珠モシリ遺跡
(教科書の記載内容とは異なる見解)
縄文時代晩期、
北西九州(=現在の長崎県)の有力者は津軽海峡圏に上陸したかもしれません。そして、イモ貝の腕輪を交易品として持ち込みました。

有珠モシリ遺跡
イモ貝の腕輪
北海道の海の幸
大規模なエルニーニョによる、よい影響
(教科書の記載内容とは異なる見解)
縄文時代晩期、
北海道北海岸や樺太、南千島の縄文人は、
漁業や狩猟を中心に、海に依存した生活をしていました。
プランクトンの豊富な海水が南下して、北海道沿岸は豊かな漁場になりました。

「婦人倶楽部」
昭和10年12月号付録
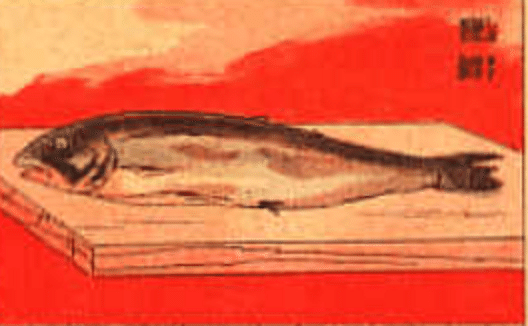
「婦人倶楽部」
昭和10年12月号付録

「婦人倶楽部」
昭和10年12月号付録

「婦人倶楽部」
昭和10年12月号付録

最北の海鮮市場
ノース物産株式会社

最北の海鮮市場
ノース物産株式会社

こばさんのブログより
海峡を越えるイノシシ
海峡を越えるイノシシ
(教科書の記載内容とは異なる見解)
紀元前750年頃(縄文時代晩期)、北海道が寒冷化すると
西部道南の有力者は、北東北からイノシシを持ち込みました。
また、ヒエ、そばなどの雑穀栽培は紀元前6000年頃(縄文時代前期)から
始まりました。トチの実などの採集も盛んに行われました。

函館市、日ノ浜遺跡
イノシシ型土製品
祭肜と許黄玉、檀石㟴
後漢の祭肜
(教科書の記載内容とは異なる見解)
紀元45年、
鮮卑の騎馬兵、一万騎が後漢の遼東郡に侵入しました。
このとき、遼東太守の祭肜が
鮮卑の騎馬兵を撃破しました。
(その後、渡来系の先祖?は疎開を始めます。)
インド・アンドラ朝の許黄玉
(教科書の記載内容とは異なる見解)
紀元48年、阿踰陀国(インド・アンドラ朝?)の国王の娘・許黄玉が船に乗って伽耶に渡来しました。
(この時代、ドラヴィダ語の宮廷文字が伝来したはずです。)
鮮卑の檀石㟴
(教科書の記載内容とは異なる見解)
紀元178年、
鮮卑の檀石槐が汙国(潘汗県)を撃って、千余家を捕えました。
逃げ遅れた「汙人」は大陸で離散しました。
烏垣・鮮卑列伝
平和な時代の周堤墓
縄文時代後期の周堤墓は、
二重の土堤だけの境界施設。
1900年頃に発見されたときは、祭祀遺跡と考えられました。
1950年以降は、墳墓遺跡と考えられるようになりました。
北の縄文時代は、戦争のない平和な時代だったようです。
続縄文時代の「チャシ」
古墳時代(大和時代の崇神王朝以降)の「チャシ」は、
カムイミンタラ(神々が遊ぶ聖域)で、環壕のみの境界施設でした。
巫術師は祭祀が終わると、他の人々と同じ日常を送っていたようです。
