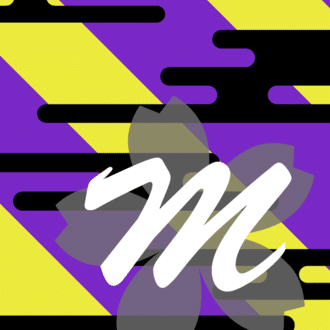トレモロ
トレモロ(tr)は、連続音で「伸ばす音」を「表現」する技法です。
疑似的にそう聞こえればいいので、高速で細かく振る必要はありません。ゆっくりできれいに、長く安定して振る練習からスタート。目安は8拍から24拍程度かな。ロングトーンと一緒で、「キープできる」ことが一番の目標です。
苦手になることが多いので、攻略法を少しだけ。
1.姿勢
構えをきちんととってから振り始める。
途中で姿勢を変更するのは難しいため。(当たり前のようだけど、姿勢のこと意識できないと苦戦するかも)
①絃の位置に合わせて前傾・後傾。(上半身=肩の位置を調整する)
↓
②肘の位置を調整する(腕の向き=振りの向き)
↓
③指先を調整する(あてる爪の角度向き・力のいれ加減など。最終段階)
①肩の位置
絃が低音なら意識的に前傾、高音ならやや後傾。
特に低音の時に姿勢が取れない 場合が多いので、絃に近いところへセットする感覚で。 (低音で腕がのびてしまう=振りの向きが変わってしまう。fの音量が作れないなど、色々出てくる)
*前傾は、おへそを前へ。後傾は、おへそを後ろへ引くように。背中が丸まる猫背は頭の位置が低くなるだけで、実は身体自体はあまり移動しません。
肩の位置を動かすことで、トレモロの移動しながらの演奏が安定してできるようになります。基礎練習の「tr 巾→為→……→一」、また逆も、ここに気をつければ練習しやすいかも。
(音の移動とともに肩を移動=肩を動かせば、ひじの位置や手の角度は腕ごとそのままをキープできるので楽です。)
②ひじの位置・振りの調整
ひじの位置で振り方(腕の向き)が変わってくるので特に注意。
脇のあけ具合+ひじの高さで手の角度と位置が変わるので、振りやすい位置を探そう。
(ひじの重要性については後述)
*絃に対してナナメ振り(糸目・ヨリに添う形)の場合は脇は締め気味でも OK。
*絃に対して直角振りの場合は脇をあけ、ひじを絃の真横へ置くように。あけすぎると振りにくいのでいろいろ試して下さい。
手首で力尽くで振る人・変に腕が疲れる人はここを修正。(*振りの練習の方法については後述)
雑音が多い、ジャリジャリする、ときも、振りの向きが変わると、爪のヘリで絃を擦るような音が少なくなることが。
③手・指先の調整、爪のあて方
トレモロの時、爪は、水平に絃を往復する運動をします。
(うちの部では、絃に対しほぼ直角振りの、爪は垂直(直角)あてのトレモロをしていますが、いろんなやり方があるので、自分に合う方法を研究するのもアリです。
爪の向きを、ふつうに弾くのと変えないトレモロの方法もあります。絃の向きと爪が平行のまま)
(以下は、垂直(直角)あての場合です。)
★爪の角度は、45°+45°
往復するときの角度。(*わかりづらいので後で図を入れますね。)
水平方向180°の中で90°角の爪をおいたとき、残りの角度を二等分=45°の状態になるようにセット。
あてる角度がそろうと、往復の行き/帰りが同じ力で往復でき、ひっかかったり音が変わることはなくなります。

往復時に音が凸凹したり、爪が引っかかるような場合、爪の絃に対する角度が偏っていないか、龍尾方向(奏者の左側)から誰かに見てもらって下さい。
直すときは、手首の甲をどっちにまわすか(甲を向こうへ or 手前へ)の調整になるかも。
この45°がキープできていれば、振りの向きが直角でもナナメでも、トレモロは振れます。(私は絃に対してだいぶナナメに戻した角度でやってました)
-*-*-*-*-
2. 腕の振りのコツ
テコの原理って知ってますか。中学くらいで習うアレです。力点・支点・作用点。長さと力加減。
あれがトレモロの理解に役に立つのでは。
作用点=実際に音を出す爪かな。じゃぁ力点は。
わっかんないな、となったら、「ひじを脇腹へぴったり固定して、手首だけで絃に対して直角振りになるように動かしてみて」(自分から見て前後方向へ動かします)。めっちゃやりづらい。
このやりづらい、というのは、力点~作用点の距離が短く、大きな力を必要とするからでは。たぶん。たぶん。(私文系なので、それ違うよーってなったら教えて下さい。足らない頭で分かったつもりになってると思うのですよね)
そこでひじです。ひじを使うと!力点が遠くなって!小さい力で!トレモロが可能に!なってるんじゃない???(文系)
…そう思ったのは、トレモロの動きを知ろうとして、自分の左手で右の手首あたりを掴んで固定し、動作をしてみたのがきっかけです。
「おっ!振れる。ってことは、手首は仕事していないなこれ」
ひじを上手に使えば、手首は使わないことがわかりました。だからそこに力は要らない入れない。なるほど。
手首あたりを支点にしてひじを振れば、すなわちトレモロ。机上の空論的には。そして作用点でそんなに大きく動かさなくていいなら、力点で大きな力はいらない。のです。
(これ、続き記事の上級生編の「トレモロのなめらかさの追求」の部分に関わるからちょいとだけ)
初歩の腕の使い方の練習
腕の振りの感覚の掴み方。初歩の、力を入れない場合の振り方です。
「バイバイ」しよう
①腕全体の力を抜いた状態で、「床に向かってバイバイして」。
力を入れていない、ぶらぶらの状態で、バイバイと手を振ります。
「二の腕のお肉がプルプルする感覚」があったら、それを覚えてほしい。
②その状態で、今度は「箏に手をのっけて、触る程度にバイバーイ」。
ジャラララララと音が鳴ります。腕のお肉がプルプル。その腕の使い方が、そのままトレモロの基本動作です。
(ちなみに、バイバイは「手を振る」って言葉を使いますが、実際は肘を振ってるんですこれ。机にひじをついて固定して手を振ると、同じ動作をしようとすると全く力のいれ具合が変わります。面白いです。)
-*-*-*-*-
さてそれでは。上記「基本動作」に、前述の「姿勢」をプラスして、少しずつ、感覚を掴んでいきましょう。
わかんなくなったり、腕に力が入ってきた(二の腕が硬くなる、見た目で二の腕の位置ブレが少なくなり動かなくなってくる)、となったら、全部リセットして、休憩して、バイバイからスタート。
リセット回数は気にしなくていいです、よい練習=よい状態をどれだけ味わったか、ですので。
-*-*-*-*-
実際の所は。
実際に演奏中に使うようなしっかりしたトレモロのときは、実はそこまで力が抜けているわけではないのです。トレモロを長く続けたりする場面で、キープするための力は使います。腕のお肉がプルプルしなくても本当は大丈夫。(でも初心者さんはそこが難しいので)
上記は、最初の最初、基本動作の習得のときに、「変なところに力が入って動きが悪い」というのを改善するための練習法です。
なので、練習が進むと、腕のお肉のプルプルは忘れてもらう必要がでてきます。でもそれは、腕(ひじ)の振り方が身についた段階での話かな。
-*-*-*-*-
基本動作についてはこのくらいで。
続き↓ トレモロがうまくいかないときの改善点の拾い出しパターンです。
「ダブルトレモロ」という、ごくたまーにあるやつは別記事を書きました。知ってればすぐできる感じのことです。
いいなと思ったら応援しよう!