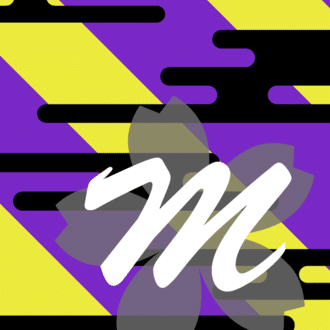掛け合い と 受け渡し
曲中でよくあるのが「元々ひとつだったフレーズを、複数パートに分割する」という、作者の遊び()。
読譜の時にそれに気がつかないと、演奏しても元の形に戻せなくてなんか中途半端でまとまらない、ということに。
1.よくあるパターン「たら+たら」
たぶん一番短い掛け合いの形は「2音まとまり」の連続。音の組み合わせはいろいろあるけど。
例。

これに気がついた場合、とるべき練習は楽譜の「歌い合わせ」。
① パート二つで「たらたら…」
全部の音を出し、形を確かめながら、全員一緒に声で歌う(言う)。
② パート1「たら」+パート2「たら」…
各パートが担当部分だけ歌って結果的に①と同じように聞こえるように、うまくタイミングをとる練習をする。この時、テンポが遅くならないように注意する(聴きすぎると発声が遅れがち。最初は手を叩きながらやるとよい)
③ 実際に楽器で音を出し、「たらたら…」の形を再現。
この時も、テンポが遅れないように注意。慣れないうちは①のように元の形を歌い(第三者に歌ってもらい)ながら、自分のパートだけを演奏する。
*「たこやき」という単語を使って「たこ」+「やき」をなめらかにつなぐ練習も、歌い合わせの練習としてよいかも。不自然なブツ切れにならないようにするのがポイント。
*
この形、「たら(ら)+たら(ら)」で出てくることも多いです。
本来の元の形は「たら+たら」なので、そう聞こえるように演奏するのがポイント。
例。

受け渡しのコツ:
音の重なる部分に注意。上記の場合、全体の音量が上がらないように、色枠外三音目(ら)になるところは音をやや控えめにする。そこに気をつけると全体がなめらかにつながって聞こえる。
(この形、初心者さんは「たららん」と後ろを重く弾きがちになる。特に注意して練習。弾き終わりをやや軽くし軽快に!)
(全体の音量のバランス調整、合奏の時に必要になってくることがあります。別記事にまとめたのでどうぞ→「全体の音量の調整。パーセンテージの感覚」
ざっくりいえば、全体のどれくらいを自分が担当すればいいか、というのを、必要な音量を奏者の数で割った感じで捉える考え方です)
✁-------
2.よくあるパターン「たららら」+「たららら」
フレーズが長めになってくると、難易度は上がります。
上記のタイミングの取り方以外に、「フレーズの形をそろえる」という作業が必要になってきます。ユニゾンです。
*ユニゾン=同一の旋律。全く同じ形で演奏することと同義かな。
違う楽器で同じ形の音を作るのは、時々とても難しいのですが(手の移動とかが影響)、それでも、掛け合いとして成立するには、「同じ形に整形する」という作業は必須。
(「たららら」と「たららら」では同じとは言えないので、統一する必要がある。奏者のクセもあるので、気をつけて削ったり盛ったりしよう)
・アクセントの位置、サイズ
・音質の硬さ柔らかさ
・フレ-ズの抑揚、強弱の幅(サイズ)など
…を意識的に調整することになると思います。
演奏するときは、相手と同じ音を自分の楽器から出すイメージで。
(箏で尺の音を、尺で三絃の音を、三絃で十七絃の音をなど、いろいろ試してみて下さい。相手の楽器の特徴を掴めているかどうかでも変わってきますが、尺は「対絃=音をキッチリめに、角を出す」絃は「対尺=響きを重視する」などを意識するだけで、少しお互いへ寄せた感じにできるときがあります。再現性の高い音が出せればいいな)
一年生には、上級生が「歌い合わせ」で形をインプットさせると楽かな、自力での細部の聴き取りはまだ無理なので。音出しに移ってからは、細かく「アクセントをもっと強めに」「フレーズの収めは弱めて」とか、具体的に指示を出しながら、練習すると、うるさがられるだろうけど、形にはしていきやすいかも。
✁-------
「受け渡し」のコツ
掛け合いの時に、弾き始めるタイミングだけに注意して練習すると「たららら(ぷつ」「たららら(ぷつ」と、パーツが切れて聞こえることが多いです。なので、タイミングが合ってきたら「受け渡し」ということを練習していきます。
入りのタイミングができてきたら、終わらせる時のことまで気をつかおうという感じ。プラモとか組み立てるやつの、バリとりみたいな感じかも。境目を無くしていく作業かな。
コツは、歌ってつなげるときと同じ意識で、演奏します。それだけです。
不思議なことに、「つなげる」気持ちのあるなしで、音の形が変わってくるのですよ、これがまた。
簡単だと思ってあなどりがちですが、ここ無意識にはできないことが多いので、意識的に、心の中で歌いながら演奏するといいかも。弾き終わりを相手に向かって飛ばすようにしてもいいです。
とにかく、相手が音を出しているときは手が休みになりますが、「弾きっぱなし+空白」にしないのが、大事。
合奏の時に気をつかうこと、色々ありますが、「掛け合い」ってすごく突っ込まれることが多いポイントです。なので注意点とかをちょっと書いてみました。
楽器が違う同士だと差が目立ちやすい。ちょっと気をつけるだけでずいぶん変わってくるので、試してみて下さい。
✁-------
なぜ「わざと分割するか」、その狙いとは
ステレオって知ってますか、スピーカーとかで普通にあるステレオ。左右で違う音がでるタイプのものです。
楽器の演奏、大体メインで使ってる楽器は決まってきますね。箏なら一箏(たいてい向かって左側)。出てくる音もそっちからが多いです。
そればっかりだと、お客さんって、すぐに「慣れ」てすぐに「飽き」てしまう。
そこへ、いきなり別方向から音をぶつける。別のパートからいきなりメインフレーズを出す、音の発生源をあちこちへ移動させる。
お客さんにとっては、びっくりすると同時に楽しめるわけです。分割=難易度の少し高いことをやってるって、分かって喜ぶし。
そこ、けっこうポイントになってくるんですよね、人前でやることを前提としている場合は、稼げるポイントは外しちゃいけません。
* *
ステレオ効果、意識できれば積極的に曲作りに取り込めると思います。
他にも、「なぜこんな面倒なことを?」と思ったら、どういう効果を狙ってるかと考えてみると、曲作りに活かせるよい材料を手に入れられるかもしれない。色々「?」ってなったら考えてみて。
演奏会の準備期間に入ると「曲作りってどうしていいか分からない」と言われることが多かったのだけど、材料探し、もっと上手になろう。がんばろ。
いいなと思ったら応援しよう!