
インターンプログラム【16】~「情報過多」と「博物館疲労」~
この回では、ミュージアム、特に「常設展示」にあると言われる「博物館疲労」について、その最大の原因となる「情報過多」とその背景、について考えます。(2022.2.4)
🌕〈S〉
ミュージアムには、「博物館疲労」があると聞きましたが、どういうことでしょうか?
🌑〈AC〉
解釈はさまざまにあると思いますが、ミュージアム空間の中で、「利用者が疲労感を感じていく」状態のことを言います。
🌕〈S〉
ミュージアム自体が疲労して「使い物にならない」状態とは違うんですね!?
使い物にならなくなると「博物館行き」になる、とも言いますし……。
えーっと、それでは、
ミュージアム空間の中で、「利用者が疲労感を感じていく」のは「なぜ」なんですか?
🌑〈AC〉
はい。
特に「常設展示」に関してですが、
「博物館疲労」の最大の理由は、
「情報過多」です。
それも、日常的でない情報が「過多」だからです。
🌕〈S〉
広い展示室に、たくさんの展示があって、
全体としては「立派な展示」ですけれど、
多すぎて見られません!
🌑〈AC〉
学芸員と展示会社のスタッフたちが、
何年もかけてつくりあげた「展示」を、
1~2時間で見られるはずないです!
🌕〈S〉
図書館に置いてある本を、「1日で全部読め!」と言われてるようなものですね。
でも、図書館は、
「一冊」という「利用単位」があるので、自分が読める冊数しか借りていかないです。
🌑〈AC〉
「点=モノ」をピックアップし、
「点=モノ」を「順路」にそって見る
「順路形式」の展示では、
展示点数が多すぎると、それだけで「疲労」していきますし、
付帯している「文字情報」を立って歩いて移動しながら読んでいくわけですから、どんどん疲労していきます。

「点=モノ」をピックアップし、
「線=物語」を構成するタイプの展示空間では、「モノ語り」を読み取らなくてはなりませんから、「展示の出来不出来」に大きな影響を受けます。
🌕〈S〉
いくら、たくさんの展示物、たくさんの展示情報があっても、「利用者の許容量」の範囲でしか意味がない、ということなんですね。
🌑〈AC〉
よく、「展示解説ツアー」などで、「すごくわかりやすかった」というようなことがありますが、
それは「適度な情報」を「切り取って」伝える「プログラム」になっているからです。
🌕〈S〉
「常設展示」は、いろんなコーナーに分けていますが、情報はつながっていて、一つの「巻物」を展示スペースいっぱいに広げたようなものですからね。
🌑〈AC〉
「常設展示」はプログラムの要件を充たしていないので、「利用」の対象になりません。
ですから、
利用者が自ら、①時間を限定して、自分でプログラムの4つの要素を充たし「セルフ」で「プログラム」にする必要があります。
「利用者の許容量」には、「情報量」だけでなく「時間」もあります。
どんな方法でも、ほんの一部しか「利用」することができないのが「常設展示」ということになってしまいます。
🌕〈S〉
大きなミュージアムでも、
それが、30年間も改装されずに、そのまま変わらずにあるなんて、
やたぱり、ミュージアムも「疲労」しているじゃないですか~。
🌑〈AC〉
でも、方法はありますよ!
「常設展示」を「原状回復ライン」に、
「利用プログラム」をレイヤーとして、どんどん入れ替えていけばどうでしょう。
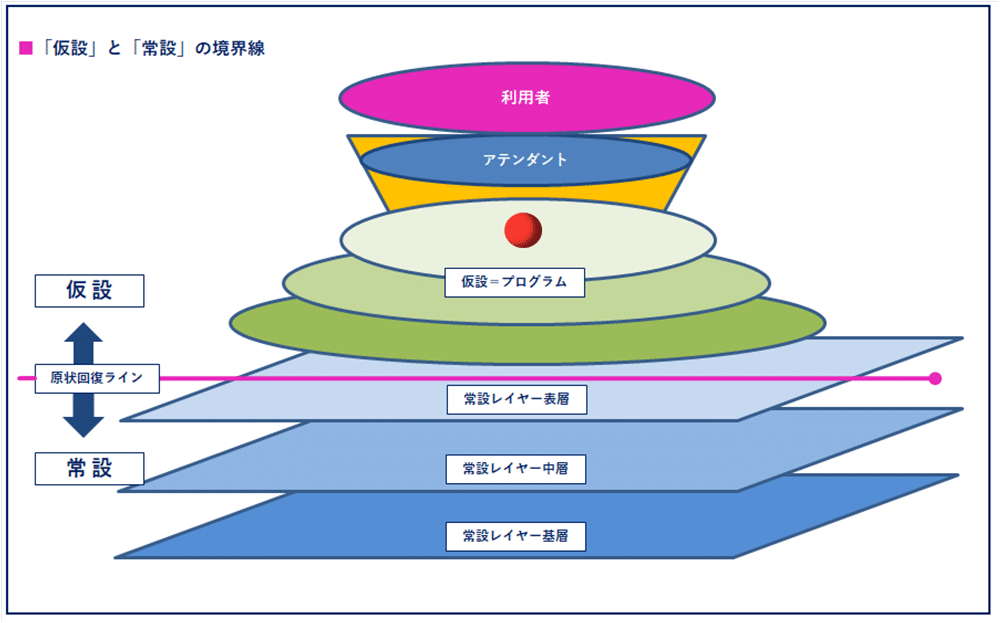
つづきは、また次回。
☆
