
インターンプログラム【24】~「アテンダント」と「ボランティア」~
この回では、「変化の主体」となりえるのは何かという視点で、「アテンダント」と「ボランティア」の位置づけと可能性、について考えます。(2022.2.22)
🌕〈S〉
今日のテーマは、
「アテンダント」と「ボランティア」
です。
【23】ミュージアムと「変化の主体」
のつづきですね。

🌑〈AC〉
ミュージアムが「より良い変化」を必要としている場合、
「変化の主体」となりえるための条件は、何でしょうか?
🌕〈S〉
その条件は2つ。
【条件1】
ミュージアムに「より良い変化」が必要だと考えている人
【条件2】
ミュージアムに「何らかの関わり」を持っている人
つまり、
◼️学芸職の職員
◼️学芸職以外の職員
◼️アテンダントスタッフ
◼️運営ボランティア
◼️展示会社の専門職
◼️プログラムの講師・制作者
◼️博物館学を履修した学生
◼️博物館学の大学教員
それから、
◼️さまざまな利用者
ということでしたね。
🌑〈AC〉
◼️学芸職の職員
◼️学芸職以外の職員
による
「内発的な変化」が以外と難しい
と考えた場合、
「内部と外部の中間的」である
◼️アテンダントスタッフ
◼️運営ボランティア
の可能性を考えてみましょう。
🌕〈S〉
「アテンダント」は、
【1】「運営論」と「利用論」
での「キーポイント」になっていました。
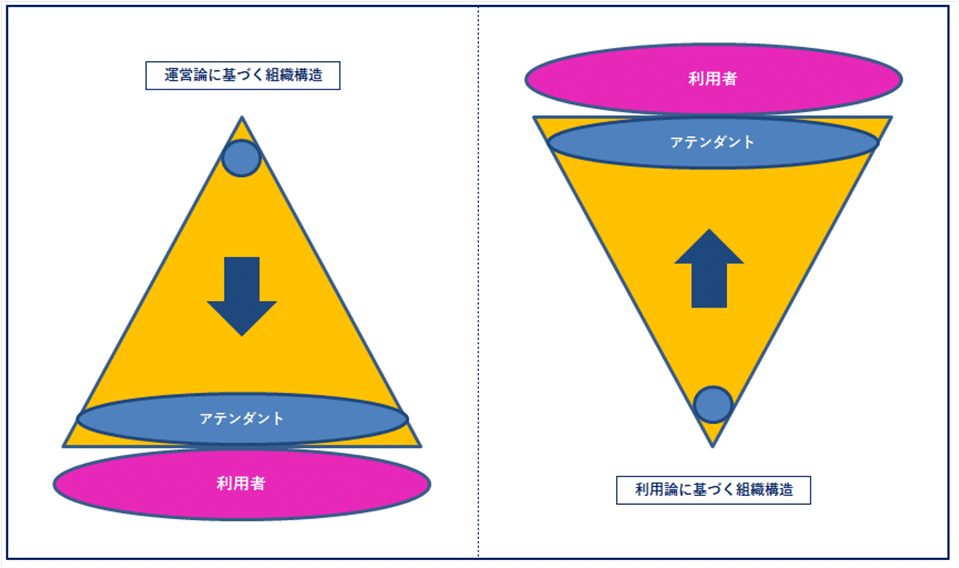
🌑〈AC〉
「アテンダント」を、
「利用者の“利用“をサポートする人の総称」
だとすれば、
「図書館」(左図)や「劇場・ホール」(右図)のように、「▽」の「利用構造」でなければなりません。

🌕〈S〉
「図書館」も「劇場・ホール」も、
お客様(利用者)に利用していただくために存在しているのが、ハッキリしている感じがします!
🌑〈AC〉
表向き「アテンダント」という職名であっても、
内部の予算資料などには「監視員」となっている場合も少なくありません。
「利用者を監視する」という感覚は、
「△」のピラミッド構造の最下層に「利用者」を置いていることにほかなりません。

🌕〈S〉
これでは、
先の展望(利用者それぞれの上位目的)を持って、ミュージアムを利用することにつながっていかないと感じます。
では、
「ボランティア」は、どう考えればよいのでしょう。
🌑〈AC〉
「ボランティア」は、基本的には「利用者」です。
「ボランティア活動により利用者をサポートする」という「プログラム」に参加している「利用者」です。
まさか、
「ボランティア=安い労働力」などと考えている所はないとは思いますが、ボランティアに対しては、運営スタッフによるサポートをしなければなりません。
また、
「利用者の“利用“をサポートする人の総称」が「アテンダント」だとすれば、
「ボランティアはアテンダント」でもあるということになります。
🌕〈S〉
「アテンダント」も「ボランティア」も、
先の展望(利用者それぞれの上位目的)を持って、ミュージアムを利用することを実現する「利用構造」の中で「重要な機能」を果たさなければならない、ということになりますね。

🌑〈AC〉
「アテンダント」と「ボランティア」の認識と行動の変化が「利用構造」を支え、「利用者行動」の変化にもつながっていく可能性は高いと思います。

つづきは、また次回。
☆
