
インターンプログラム【22】~「利用の基本単位」とプログラム~
この回では、ミュージアムにおける「利用の基本単位」とは何か、また、利用の基本単位としての「プログラム」の性質、について考えます。(2022.2.18)
🌕〈S〉
今日のテーマは、
「利用の基本単位」とプログラム
です。
🌑〈AC〉
「利用の基本単位」を考える前に、
「利用と目的/手段」の関係をおさらいしておきましょう。
どんなことでも、
「目的」の側面と「手段」の側面があり、
「なにかの目的」となっていることでも、
「より大きな目的のための手段」になることで、つぎつぎと「連鎖」していく。
より大きな「目的」が見えると、「手段」としての側面が浮かび上がってくる、
ということでした。

🌕〈S〉
「図書館」は、その「手段」としての機能を高度化したものでしたね。

🌑〈AC〉
それでは、
「図書館」での「利用の基本単位」は何でしょうか?
🌕〈S〉
図書館利用での「上位目的」は、
人により、ざざまな「目的」につながるものですが、
直接的には、
「本を読む」や「本で調べる」ですから、
一冊、二冊の「冊」です。
🌑〈AC〉
そうですね。
「意味や価値を伝える媒体」のうち、
文字媒体(1次元/文章)と平面媒体(2次元/グラフィック)は、
「ブック形式」になることで、
「冊」という「利用の基本単位」を持っている、
ということになります。
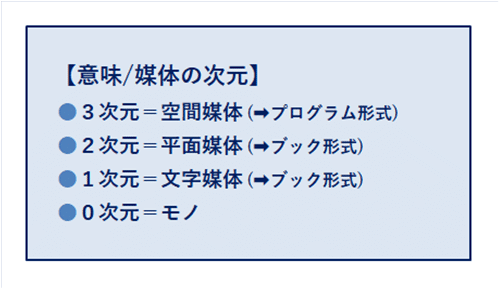
🌑〈AC〉
「利用における大原則」を覚えていますか?
🌕〈S〉
はい、
「選択しなければ、利用できない」
です。
「選択」するには、「選択肢」と「利用単位」があることが必須であることを考えると、
「冊」という「利用の基本単位」を持つ「ブック形式」が、豊かな「選択肢」を提供することで、「利用」を促しているように思えますね。
🌑〈AC〉
図書館の「選択肢」の豊かさは、
「ブック形式」でのコンテンツ生産者(作者)の幅の広さと層の厚さが基盤となっています。
さて、それでは、
「ミュージアム」の「利用の基本単位」は何でしょうか?
🌕〈S〉
「常設展示」は、一回。
「企画展」も、一回。
「講座・講演会」も、一回。
その他のプログラムも、一回。
ミュージアムでは、
どのパターンも、すべて「回」です。
🌑〈AC〉
ミュージアムは、
3次元の「空間媒体」なので、
「利用するもの」は、基本的に「プログラム形式」になります。
そのため、
ミュージアムの「利用の基本単位」は「回」なんですね。
🌕〈S〉
「プログラム形式」でも、「選択肢」を豊かに提供できるかどうかが、「利用」のボリュームを左右するように思いますが……。
🌑〈AC〉
3次元の「空間媒体」を代表する「劇場・ホール」の場合、
コンテンツ生産者に空間媒体自体を貸し出す「貸館事業」を中心にすることで、
コンテンツ生産者(制作者)の幅の広さと層の厚さを確保しています。

🌕〈S〉
「図書館」や「劇場・ホール」は、
「選択肢」を用意しなければ「利用されない」ことの理解が基本にあり、その仕組みを形成してきたように思います。
それと比べると、
「ミュージアム」は、
「選択肢」を十分に用意できていないのかもしれません。
「選択しなければ、利用できない」
ことを理解すれば、変わらざるを得ないような気がします。
🌑〈AC〉
ミュージアムに共通する課題は、
いかにして「選択肢」を豊かに提供できるか、
ということにありそうです。
つづきは、また次回。
☆
