
12/22 印度乳業あらため「ケニア乳業」開催! 〜マサイ族の墨入りミルクを試そうの会〜
私、武蔵野デーリーの木村が今年3月に訪問したケニアのマサイ族で飲んだ炭入りのミルクが忘れられず、なんとか再現すべく日本でも何度か実験していました。

そして、その墨入りミルクをみんなで試して飲んでみようということで、イベントにすることにしました。
日時は12月22日10~12時
場所は東京・三鷹「天神山須藤園」 ※なんで須藤園さんなのかは後述
ミルクは東京・八王子の「磯沼ミルクファーム」さんのミルク6種(予定)
墨入りミルクというとみんなどんな味かと怪訝がりますが、炭で燻したような香りがミルクに乗っかり、独特のミルクになります。最後に炭カスが口残るのもご愛嬌。 日本ではまず飲むことがないだろうマサイ族の墨入りミルクを飲んじゃおうという趣旨のイベントです。

とはいえ、肝心のミルクもケニアのそれに寄せたい。
そこで、日本でも多くの品種の牛を飼っている東京・八王子の「磯沼ミルクファーム」さんから6種類のミルクから最も合うミルクを選定し、 そこからケニアの墨入りミルクを再現しようということになりました。
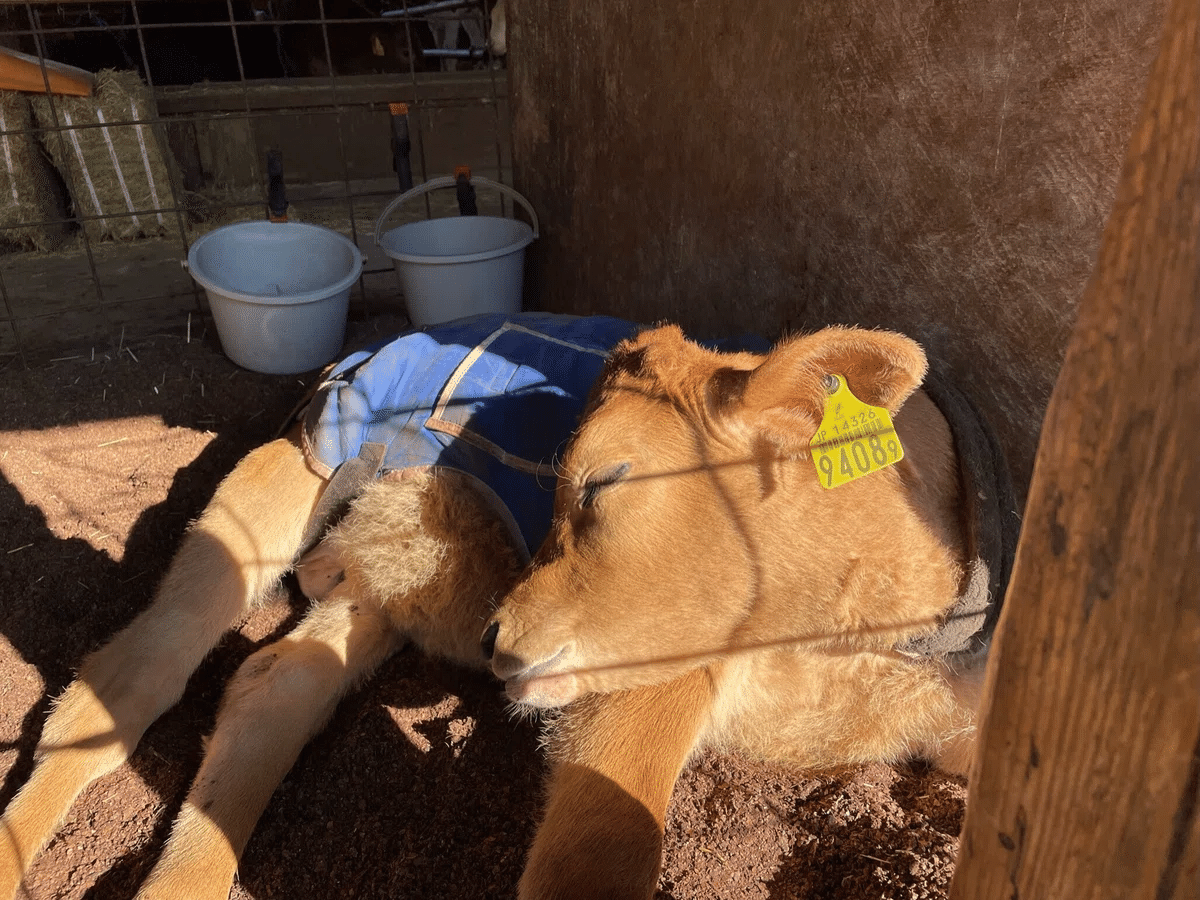
ケニアやマサイ族に興味がある方はもちろん、ミルクの奥深さを感じたい人はぜひきてください!
基本は6種類のミルクで墨入りミルクを試してみるという会ですが、冬にミルクを飲むだけではあまりに寂しいので、印度乳業によるチャイを提供するのと、焚き火で焼き芋を作ろうと思っています。
ただ、おもてなしをするというよりは皆さんと一緒に実験を行うような感じになると思います。その点、ご了承ください!
以下詳しい説明です。
マサイ族のミルクって?
ケニアのマサイ族の炭入りのミルクは「キブユ」と呼ばれるひょうたんを加工した容器を使って作られます。

まず水を使ってキブユの中身を洗うのですが、その際にオリーブの原種の木の枝を利用してしっかり中身をこすり落とします。

次に枝を焚き火で燃やして、周りが炭状になったら、キブユの中に入れて今度は炭を擦り付けるように何度も出し入れします。

一通り炭でコーティングされたら、中に溜まった墨のカスを外に出してミルクを入れます。

これで完成です。
完成したミルクをキブユからコップに注ぐと、コーティングされた炭がミルクに入り、黒みがかかった炭入りのミルクになります。

マサイではこうすることでミルクが常温でも一日程度持つようになるといいます。
ちなみに、そのまま1週間保存すると、発酵乳「コレナオトック」になるといいます。
※ただし、乾燥しているケニアだからできるのあって、日本ではできるかどうかわかりません。ここら辺はまだ追って実験したいと思います。

さて、実際に作った炭入りのミルクですが、燻された炭の匂いがたまりません。 オリーブの枝だからこその匂いなのかはまだわかっていませんが、ここは皆さんと議論したいと思っています。
あとは現地で飲んだ時、炭がとても小さく砂状になっていたので気にならなかったのですが、前回実験した時はまだまだ炭のカスが大きく、口に入ると違和感がありました。まだ改良の余地がありそうです。
なんで須藤園なの?
マサイ族の墨入りミルクを作るのにひょうたんの容器「キブユ」も大切ですが、炭となって味に加わるオリーブの原種の木の枝がとても大切だと思いました。

とはいえオリーブの原種の木は見当たらないので、なんとかオリーブの木があればなと思って探していたところ、東京でオリーブオイルを作る三鷹の天神山須藤園の須藤さんに辿り着きました。
何度か訪問し、実際にオリーブの枝を拝借して実験させていただくなど様々な協力もいただきました。

しかしこの須藤園さんがすごいんです。東京でオリーブオイルを作っているんです。しかも、一流ホテルなどでも使われるほど高品質なオリーブオイルです。
さらに、農園自体もすごいんです。東京のど真ん中ににこんな場所があるのかというほど驚くような広い農園でした。見渡す限り自然で、訪れた人は一瞬東京にいることを忘れると思います。

そんなことからオリーブの枝を使わせていただきながら、こちらでイベントができたらいいなと思い、今回会場としても使わせていただくことになりました。
ミルクは磯沼ミルクファームのミルク6種
ケニアで飲んだ独特のミルクをどう再現するか。正直全く答えを持ち合わせていません。
ただ、日本で一般的に飲まれる(日本の99%以上)のホルスタインとはちょっと違う癖がありました。
また、濃くてクリーミーと言われるジャージー牛でも、チーズなどに使われるブラウンスイスでもありません。
そこで、色々な品種のミルクで飲んでみようと思い相談したのが東京・八王子の「磯沼ミルクファーム」さんです。
磯沼ミルクファームさんは現在6種類の牛を飼っています。
ホルスタイン、ジャージー、ブラウンスイス、モンペリアード、ミルキングショートホーン、エアシャーの6種です。
今回はこの6種をお持ちいただき、飲み比べをしたいなと思っています。ただし、状況によっては全種類持ってこれないかもしれないので、当日のお楽しみです。

以上になります。イベント告知と言いながら、情報もりもりとなりました。
興味ある方はぜひご参加ください。詳細は以下に書いております。なお、イベントといってもワークショップに近く、みんなで実験するイメージです。あまりおもてなしなどがうまくできないかもしれませんが、そのてんだけご容赦ください。
イベント詳細
内容: 磯沼ミルクファームの6種類のミルクで墨入りミルク実験 、印度乳業特製のチャイ提供
、焚き火で焼き芋など
日時:12/22 10時〜 12時過ぎには終わる予定。13時には完全撤収
場所:天神山須藤園(東京都三鷹市新川2-5-33)
持ち物:特にないですが、農園であり、冬なので、汚れて良い服と、防寒対策だけお願いします。
移動:各自バス等で来場ください。
参加費:2500円 人数:10名くらいの予定 ※ワークショップのような形で少人数のメンバーで協力しながら作れればと思っています。
申し込み:印度乳業(@indiadairyjp)のDMでご連絡ください。
印度乳業インスタグラム
