
所属コミュニティは文化で選ぼう。[新・群れラジオ#9]
こんにちは、群れ研究所です。
新・群れラジオ#9は11月28日に行われました。
パーソナリティは所長となかそねさんです。
記事はマイクとみさわ担当です。
______________
所長:高校は義務教育と違って受験を経て入ってきたと思うんですけど、学校に対する帰属意識は義務教育の方が強かったという感覚があるんですけど、コミュニティっぽさはちがうのかな?と思うんですよね
なかそねさん:それは高校でなじめなかったっていう話じゃなくて・・・?
所長:wwww
それはあるかもしれない(笑)ほぼ行ってなかったですからね
なかそねさん:たまたま高校が合わなかったというのもあるかもしれない
文化がコミュニティー維持コストをさげる
文化を理解し、作り上げるのは難しい。文化というものは一連の規範が繰り返され、広い集団に受け容れられることでできあがる。
さて、「失敗をしてもそれを学びに変えられる場」として群れ研究所のあり方が提案されています。それを「失敗できる場」と称しているのですが、失敗を学びに変換させる効率をあげるための装置として「場」が機能するということだと思われます。
個人は失敗を通じて成長していくのですが、その失敗を共有できる場であれば「群れエラー」が多く集まるため、知見もアップデートされ結果的に個人の成長を促進させることも可能にします。人々は、よりよい社会生活を求めて群れ研究所にアクセスし、周囲の人々のトライを見ることでモチベーションが保つことができるのではないでしょうか。
先月は、試験的に「わくわく群れようちえん」というチャンネルを開設してみました。そこで、100年ぶりぐらいに飲み会に行ったという報告があったのを見て、私もそういう場にも顔を出してみるかとも思いました。
「失敗できる場」を実現させるために、群れ研究所に必要になるのは実践の基礎となる群れ活プログラムと、交流の場、それから群れ活を促進させる文化ではないでしょうか。失敗をし続けられるというのはそれだけ機会に恵まれていることでもあるので、一時的な失敗に囚われないような文化がつくられるといいのでは、と思いました。
リスナーさんからの質問:
群れ研究所は「失敗できる場であろう」というのを見ました。所長が想定する失敗とはどんなものですか?
所長:僕は課題図書を読んで知識を得る場として群れ研究所を活用しているんですけど、(現実の群れに持ち帰り)その実践によって得た知見を、群れ研究所に持ち帰りフィードバックをしてもらうというのをやってます。なので、(実践を経て)思てたんとちがうというのが僕の想定する失敗です。
なかそねさん:会社でこれ悩んでます。みたいなところからはじまるんだろうね

群れ研は広域カルチャーセンターに?!
『遠くへ行きたければ、みんなで行け』には、文化をつくっていくうえで、核となるスタンスが10、開発されています。本日は、それを紹介したいと思います。
1.オープンであろう(Be open)
可能な限り常にオープンであること。オープンに自由に書き、話し、さまざまな文脈を提供し、過剰なぐらいにコミュニケーションを取ろう。それは不安を減らし、関係を作り、信頼を築く
スラムでは、「日本語を読める」というステータスが存在するように見えますが、それは個人のスタンスであり健康であるためのひとつのスキルだと考えます。規範ではありません。なぜなら、ルールブックに書かれていないのでね。フォッフォッフォ
オープンであることは、さまざまな文脈で読まれることが想定できます。私は「誤読しないようにしなくちゃ」という気持ちがつよいのですが、気にするべきは読解の正確さではなく、自分がどうしたいかなのだなと思いました。
文脈の数だけエラーもあるのでいたずらに誤読に怯えるのではなく、自分の読んだ文脈を相手にわかりやすくオープンに伝えようとするのが大事で、時にそれはコミュニティにとっての財産にもなります。自分の読み取った文脈を丁寧に共有しようとするスタンスはコミュニティ内での社会関係資本を保護するといえると思います。
2.実務的であろう(Be pragmatic)
コミュニティは、(楽しい時間を過ごしながら)結果を出すのが仕事だ。
ここで重要なのは、「何をするか」であると思います。群れ研究所もスラムも成果を目的としたコミュニティではないので、楽しい時間、健康的な時間を過ごすために、何をするか?になるのかなあと思いました。
3.個人的であろう(Be personal)
コミュニティが成長すると、多くのことを自動化したくなる。
コミュニティの成長に伴い、個人的な触れ合いを減らしてしまう。
人がコミュニティに参加するのはコンピューターを話すためではなく、人々と触れ合うためだ。
コミュニティのためとはいえ、人と触れ合わずに「個人」を放棄していると、「なにやってんだろう」なんて思ったりもしますもんね。
「個人的であること」はメンバーの活動に大きな影響を及ぼします。というのも、他人や社会と個人の接点には力が生じると思うからです。その力がアクセル方向にはたらけばメンバーの活動は加速しますし、ブレーキ方向にはたらけば活動は停滞してしまうでしょう。コミュニティ活動は人との関わり合いですから、これを加速に利用しないのではコミュニティ活動に意義を持たせることはむずかしいといえるのではないでしょうか。
4.ポジティブであろう(Be positive)
物腰がきわめて重要な理由の1つは、他の人もそれを知らないうちに真似るからだ。
群れ研究所3人の研究員は、それぞれ雰囲気も違うのですがみなポジティブであると感じています。あきらめとも違った余裕とでもいいましょうか。これが古参パワーなんですかね。
みんなで学ぶ場として群れ研があって、それぞれ実践して、経験を共有していく
5.協調的であろう(Be collaborative)
コミュニティは、共有と協力という基盤のうえに形成されている。そういう文化から外れると批判される(そして追い出されかねない)。
協調的であろう、と言われると協調的でないと批判されたことがある身としては引き締まる思いです。私の抱えている課題のひとつに、「それがそうなってるってことはそういうことなんですね」と自分の中で完結してしまう癖があり、同僚から指摘を受けました。以後、自分の考えた過程を共有するようにしたら、いくらか関係が改善されたので大事なことだよなあと思いました。「協調したいと思ってますよ」というスタンスを表明することが大事なんですよね、きっと。
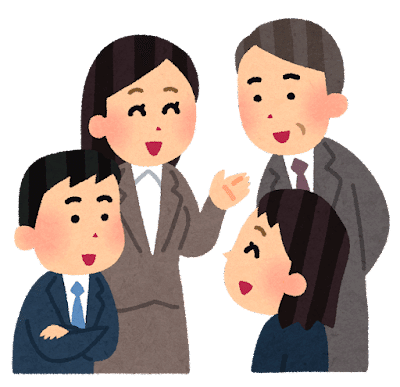
6.リーダーであろう(Be a leader)
リーダーになるのを恐れないこと。新しいコミュニティマネージャーの一部は、人々に敬遠されるのを嫌って、先頭に立つのを恐れる。他の大事な文化である、オープン性や協力を重視していれば、そんな心配は無用だ。
これから起こりうる想像のできない無数の問題を考えると、人々の先頭に立とうという気にはなかなかなりません。しかし、協調的であったりオープン性があるなど、組織に健康の土壌があればマネジメントコストを下げることができるので、リーダーになること・主体的に活動することを恐れる必要はないということではないでしょうか。
7.ロールモデルになろう(Be a role model)
ポジティブやネガティブな態度がまわりに伝染するように、リーダーシップも伝染する。
自分の理想形を自ら体現することで、他人にとって理想のリーダーになれる。
8.親身になろう(Be empatheic)
向こうの視点からものごとを見て、それを相手にも示そう。意識的にやろう。心の中で相手の立場になるだけじゃダメだ。それを言葉にして、実際に相手に目に見える形で示そう。これはすべての信頼を築く基盤だ。
9.地に足ついた人であれ(Be down-to-earth)
人は「自分と同じレベルだ」と感じた人に共感し、気に入る。つまり、こちらも相手と同じ水準だと自覚し、エゴは捨てて、常に謙虚さを表に出そう。自慢するんじゃなくて、他人からほめてもらおう。それは、向こうの選択でこちらが押しつけるものではない。
10.不完全であれ(Be imperfect)
完璧な人なんかいない。人は失敗するし、まちがいを犯す。まずこれを認め、失敗を受け入れることに慣れよう。
ここまでで、文化をつくるための10の核をご紹介しました。みなさんの所属するコミュニティにはどのような文化が見られますか?
コミュニティの色はさまざまなので、交流を兼ねてお聞きできればおもしろそうだと思いました。
失敗できるコミュニティっていうのを、もう少しわかりやすくするにはどうしたらいいんだろう
まとめだよ

群れ研は今のところ「くらがりチャレンジ応援幼稚園」みたいな感じですが、群れ研が「失敗する場」ではなく、各自の群れで失敗するのを応援してるだけだから、結局自分でリスク取ってくしかないじゃん。それだといま安全な群れにいる人しかチャレンジできないよね。
もっと群れ研内で何かやって失敗しなきゃだめだよね、みたいな話をしました。
それではまた、
とみさわでした。
