
河原枇杷男句集考――答えのない存在の問い
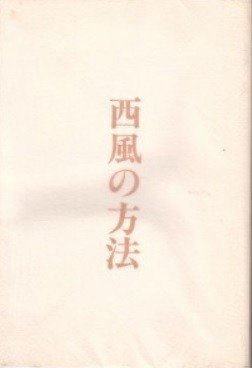
◇ 河原枇杷男の危ぶまれた旅立ち
河原枇杷男の師に当る永田耕衣が、彼の俳句表現について、処女句集『烏宙論』の序文で次のように述べている。
河原枇杷男は形而上的思考に富む俳人であるから、その作品は超現実の形をとりがちである。(略)それが極めて頭脳的であるため、却って危なげが無さすぎるということはある。危なげがないということも一つの危なげかも知れないが、或るばあい、
その呪術的な表現も、操作の跡方が優秀無類な頭脳のはたらきの跡方らしく歴然としすぎるかたむきがある。(略)
河原枇杷男の観念操作的作句法に対する師としての率直な危惧の表明だろう。
俳句表現において、具象的で身体的な直接性を離れた観念的な表現は、表現としての強度を失うと考えられている。
俳句はなるべくあれこれ頭の中だけで弄り回さず、またその痕跡を読者に感じさせることない自然さで、具象的に詠むべきだとされる。
だが枇杷男は次のような俳句を詠み続けた。
野菊まで行くに四五人斃れけり
身のなかのまつ暗がりの螢狩り
或る闇は蟲の形をして哭けり
存在の深淵を覗き込むような象徴的な表現である。ここにある「野菊」「螢」「蟲」は従来の俳句表現的な具象ではなく、作者の表現意図である観念を象徴している。河原枇杷男が、このような観念的、呪術的、操作的な自分の詠法に、耕衣が指摘したような「危うさ」を感じていたかどうかは不明だが、このことは枇杷男のみならず、主題先行型の俳人すべてが抱える問題ではないだろうか。
新興俳句や前衛俳句は、日本の伝統的な抒情、詠嘆を排除し、自分独自の表現内容を模索し、もっと自由に俳句を詠もうとした。結果として、表現主題にそれまでになかった多様な観念を持ち込まざるを得なくなる。具象性を重んじる俳句観では、そんな観念性は表現の弱点として論じられる。例えば「観念が勝る俳句表現は、現実的な実体から乖離、遊離して、作者だけの閉じられた観念的美学(平たく言えば言語遊戯的な世界)の中に閉塞してしまう弱点がある」というような批評である。
それは伝統俳句派からの批評というより、新興俳句や前衛俳句派の俳人自身の自己批判の文脈にも見られる観点でもあった。
枇杷男俳句は先ず表現しようとする主題があり、その造形的具象化を目指すような手順(これは敢えて図式的に語っているだけであり、いつもそのように作句していたとは限らないが)で主題先行型の表現をしている。
その主題は現実体験よりも、主に作者の観念的思弁のうち発される傾向があり、現実的実体から発するということは稀だろう。そのことが、一般的な俳句表現としては、具象的な強度に欠けるとして危惧されるのだ。
河原枇杷男は実作に見合う形で、そんな危惧を払拭できるほどの、独自の俳句表現論を提示できたのだろうか。
できているのなら、どのようにして。
先ず、彼の俳句観に耳を傾けてみよう。
◇ 河原枇杷男の俳句観
『現代俳句全集五』(立風書房) の「自作ノート」で、河原枇杷男は、自分の俳句観についてこう述べている。
俳句とは何か、俳句はつねに己れ自身を問いつづけながら歩いている何かであろう。(略)その緊張を見失うとき、忽ち自壊してしまうであろうことを知っているからである。(略)俳句は、おそらく如何なる答をもついに諾うことのない何かかもしれない。
また同書の別の箇所ではこう述べる。
現代の人間そのものが、崩壊と埋没の大きな危機にさらされている時、もう詩歌の究極が単なる知性や情緒の表現としてでなく、それを通して人間をその根源において支えるものとしてほかに考えようがない。
詩の根源にむかうとは、存在の故郷にむかうことであるかぎり、私の詩と真実とは、絶望さえ絶望し、ニヒリズムのニヒリズムともいうべき創造的無の志にほかならない。
詩の源が、可視と不可視の二つの世界の対立の自覚に発するとすれば、形而上的思惟を缺く詩業などありえないであろう。(略)視えざるものとは闇であり、聴こえざるものとは沈黙であるならば、詩の表現行為とは、闇と沈黙の言葉を視聴せんとする内なる劇に他ならないであろう。
この「自作ノート」を発展させて書かれたという『西風の方法』(序曲社)ではこう述べている。
詩の本質などと言ってみても、所詮、それはこの世界の根源からくる或るかなしみに尽きるものかもしれない。
ベラ・バルトークの、たとへばその無調的半音階と不協和な書法による弦楽四重奏曲においてさへ、対人的な感傷とは異質なかなしみが、われわれの心を捉らえる。それは不思議な孤独感、あるいは形而上学的な感傷とでも言へるものかもしれない。二十世紀のすでに代表的な古典とされる「管弦楽のための協奏曲」にしても、華麗なパッセージの奥から生きて在るものの非情の悲しみともいへる彼の肉声が聴こえてくるが、又、そこに無類の詩を読むことができるであろう。
詩とは、反感傷的なかなしみを土壌として生えてくる薮の中の蔓草のやうなものかもしれない。花など淫らにつけたりはしない。
このように「形而上学的な感傷」と呼ぶ詩歌観を披露している。
彼の作句法はこのような俳句観に基づく、観念的な主題優先型であり、その中心的主題が「死」だった。
それも実体的な死の表現ではなく、観念としての死の表現だ。死という観念と季語の取り合わせという方法で「反感傷的なかなしみを土壌」とした「不思議な孤独感、あるいは形而上学的な感傷」、言い換えれば存在の根源的哀しみのようなものを表現している。
表現内容に身体的直接性に訴える回路がないので、鑑賞をする者には、実感的な把握が困難な表現となる。失敗すれば観念的な軽さの中で閉じている俳句になりかねないと危ぶむに充分な要素がある。
河原枇杷男はその危うさを克服して、独自の俳句世界を構築し得たのか。
以下、その検証に入ることにしたい。
◇ 『鳥宇論』昭和四十五(一九七〇)年
淵に来てしばらく水の涼むなり
季語の収まり具合といい、一見伝統俳句と見まがう表現である。
だが伝統俳句では「水の涼む」という言い方ほとんどしないだろう。
涼むのはあくまで人間である作者側であって、この句のように水自身が意識という主体性を持ったかのような表現をすることは余りないだろう。擬人法とも少し趣が違う。
何故、敢えて枇杷男はそんな表現をするのか。万物に神が宿るという意味でのアミニズム的思想をここに見出せばいいのだろうか。
それも少し違う気がする。
伝統俳句以来、その後の大半の俳句が詠まれるとき、俳句作家の立ち位置は(対象に感情移入することはあっても)、観察者的位置に立っている傾向がある。
枇杷男のこの俳句は、観察者的な位置ではなく、作家が俳句の中の「水」として主体的に行為している。
ここが従来の俳句表現と決定的に違う。
これは作家の表現精神が、詠まれた俳句世界の中を行為しているような、独特で新しい表現であり、以後の枇杷男俳句を貫く表現方法である。
たとえば次の俳句はどうだろうか。
何もなく死は夕焼に諸手つく
この「何もなく」は唯物論的に言えば死は身体が物質に還ることであり、生きていたときの現象としての精神活動の停止、それが無となる意味の「何もなく」と解するだろうか。その読み方はこの俳句について東洋思想の味わいを見るよりも、その主題に近いかもしれない。日本人が好むのは、ここに宗教的な諦念、つまり死に臨んで後は何もないと冷静に受け止めていること、あるいはそういった感慨の受け止め方であろう。
先の俳句で見たように、枇杷男俳句は表現主体がその幻想的な俳句世界を、生きて行為する現場を表現するという方法で詠まれる。
その観点でこの俳句を鑑賞すると、死という観念そのものである精神主体が「夕焼けに諸手つく」という行為をしていることが解る。「何もなく」は死ねば何も無くなるとか、死後の無を表現しているのではなく、それ以外に為すべきことが何もない状態を表しているのだ。他に為すことが「何もなく」、ただ死という行為をする精神主体が「夕焼けに諸手つく」という幻想的表現世界から、象徴的な文学的主題が立ちあがってくる。
読者はそこに何をどう読み取るか。
唯物論的「無」の前の冷たい真理を読み取るか、実存主義的な不条理感を読み取るか、宗教的諦念、自然との一体感を読み取るか、それは読者の自由だ。
従来の俳句表現的には具象性に欠ける、閉じられた観念世界の表現だが、ここには、無限の解釈、鑑賞を可能にする表現の可能性がある。その可能性の開拓の前では、従来の俳句表現でいう表現の強度を保証する具象性など、河原枇杷男にとっては考慮にも値しないと思われていたのではないだろうか。
この俳句においては、「死は夕焼に諸手つく」という表現自身が、観察者の位置で描写し得る具象的な場面ではない。
そこに俳句としての表現の危うさを指摘するのであれば、そもそもこの俳句自身が成立しないという地点に、河原枇杷男は立って詠んでいる。次の俳句も同じだ。
野菊まで行くに四五人斃れけり
野菊は現実の野に咲く花というより、枇杷男の幻想的俳句世界という虚構の荒野に、あるときは希望の、あるときは不吉な予兆のような象徴物として置かれている。
作者はその野菊の元へ、辿り着くことなく斃れてしまう「四五人」という群像と共に、同じ精神状況を生きて行為している。
何故そう感じられるかと言えば、枇杷男俳句の作句法が、表現主体が俳句世界を生きて行為する表現だからだ。
詠まれている世界が、このように俳句的具象性から解放された、象徴性を備えた言葉による表現であることによって、読者はここから多様な主題を受け止める。どんな主題を感受するかは人それぞれだ。
これは俳句に従来からある「喩」の技法でいう象徴性を超えている。純文学でいう、多様な読みへと読者を誘う「文学的主題」の表現に匹敵するといっても過言ではないだろう。
このような観点で、この句集に収められた俳句を読んだとき、句集全体から汎文学的な「文学的主題」が立ち上がってくる。
河原枇杷男は、従来の俳句表現でいう表現の強度を保証する具象性を超え得る、文学的表現の強度を獲得しようとしていたのではないだろうか。
他には次のような句が収められている。
蝶交む一瞬天地さかしまに
身を出でて杉菜に踞む暗きもの
薄氷笑ふに堪へて物は在り
外套やこころの鳥は撃たれしまま
冬暗き渚は鈴をひとつ秘む
死の襞をはらへばひとつ籾落ちぬ
我失せつつあり手のひらに梨置けば
野遊びにわれの見知らぬ我もゐし
温みつつ水はおのれに飽きにけり
顧みれば虚無は菫にまだ跼む
◇ 『密』昭和46(1971)年
ある闇は蟲の形をして哭けり
この句を、闇の中の例えば草叢、林などから漏れてくる蟲の音を聴いていると解して、それを最初は闇の形そのものだなという感慨を持ったと推理し、闇そのものが蟲として哭いていると表現した、と読むことも可能だろう。だが、その読みでは枇杷男俳句の最も大切なものが零れ落ちてしまう。
「ある闇」とは他にもたくさんある闇のうちの一つということだ。それが「は」という助詞で受けられ、「哭けり」という述語動詞にかかっているのだから、幻想的俳句世界の行為主体は「ある闇」そのものである。その主体が「蟲の形をして哭けり」という行為をしているのだ。いろいろある闇の中の一つであるのが、私という主体だ。闇の一つである私がその時は「蟲の形をして」哭いている。
そこに「反感傷的なかなしみを土壌」とした「不思議な孤独感、あるいは形而上学的な感傷」という「文学的主題」が立ち上がる。
読者がそこにどんな思いを紡ぐのか、それは読者の自由である。
この句集には他に次のような句もある。
蛇いちご魂二三箇色づきぬ 枯草に二人の我のひとりすむ
身のなかを北より泉ながれけむ
誰も背に暗きもの負ふ蓬摘み
◇ 『閻浮提考』昭和50(1975)年
枯野くるひとりは嗄れし死者の声
この句には作者自身の「自作ノート」がある。死者も生者も一つの「幻想」世界に住んでいるのだ、という言葉が添えられている句である。
自分が創造した幻想的俳句を生きて行為する枇杷男らしい言葉である。
「ひとりは」と限定しているので、他にも複数の者がいる。限定した方を「嗄れし死者の声」と表現しているで、複数のその他の者は生者ということになる。生者と死者が共存して「枯野」を来ているのだ。
この俳句を読んだ読者一人ひとりの心に多様に立ち上がってくる思い、つまりそんな「文学的主題」を表現している俳句である。
昼顔や死は目をあける風の中
昼顔が白昼のどこかで咲く。中七以下は昼顔が開いていること、そのことの隠喩的表現とも解せるが、もっと動的であると同時に存在の本質的あり方に迫る表現が読みとれる。
「死」という俳句中の表現主体が「風の中」で「目をあける」ように昼顔が咲く。
花が開く、つまり生きる、または生き始めるということは、死への覚醒に他ならない。
そういう表現によって、深く多様に呼び覚まされる特別な思いが、この俳句の「文学的主題」だろう。
この句集には次のような俳句がある。
身のなかの逢魔が辻の蛍かな
揚雲雀死より遠くは行きゆけず
一頭の闇のいななく粉雪かな
死はひとつ卵生みけり麦の秋
天の川われを水より呼びださむ
◇ 『流灌頂』昭和55(1980)年
野遊びの二人は雨の裔ならむ
ぜんまゐのこの一本の嗤ひかな
月天心家のなかまで真葛原
てふてふや水に浮きたる語彙一つ
「野遊び」の句の瑞々しさ。
「ぜんまゐ」の句の大らかな解放感。
「月天心」の句の野晒し感。
「てふてふ」の句の、言葉さえ浮遊する軽やかさ。
句集中のこの四句をこうして抜き書きして並列してみると、吹き曝しの野の只中にいるような気持ちになる。
この、ある種の精神の自由さの表現は観念的であり、身体的直接性の思想であるアミニズムにはそぐわない別種のものだ。
これらの句に於いては、むしろその観念的な軽さが齎す解放的な浮遊感を語るべきところだろう。これを伝統俳句以来の観察者的詠法で描写的に表現しても、この解放的な浮遊感の味わいは出ないはずだ。枇杷男俳句の、俳句世界を生きて行為するという詠法が可能にした表現世界ではないだろうか。
◇ 『訶梨陀夜』昭和58(1983)年
昔より我を蹤けくる蝶ひとつ
薄氷天に奥山在るごとし
くれなゐの夢より蝉かひとつ落つ
前の世になに忘れきし蕨狩り
私たちを内側から生かす精神世界が、ある強度を持って広がり強まるのを感じる俳句群である。身体的な生の実感より、精神的な幻想を抱え込むと、精神世界が拡張する。
時間は過去と未来を抱え込み、空間は地の底、天の奥を押し広げる。此岸彼岸も地続きの、「澄み切った混沌」とも言うべき世界の中に息づく、魂のリアリティがここにある。
観念的であるが故の俳句表現としての弱点を、魂のリアリティの方に重きを置いた観念の強度で克服しつつあるとまで言えば、少し言い過ぎだろうか。観念の強度とは思弁の深さ、言葉の射程の広さのことである。
◇ 『蝶座』平成元(1989)年
蛇苺われも喩として在る如し
「蛇苺」も「われも」というのだから、双方とも共に何かの「喩として在る如し」である。ではこの二つは何の喩なのか。
それは明らかにせず「在る如し」と結ぶ。明らかにしないのではなく、明らかにできないことだから、それはそのままにして、植物と人間という存在の在り方だけが表現されている。
蛇苺は人の命を奪いかねないところのある植物だ。われという存在も他に害を与えかねない危うさを抱えた存在である。そんな在り方で存在していること自身が、何かの比喩のようだ、というのである。
その精神の形は、そういう在り方ではない何か本来的在り方というものが、別の世界にはあるような気がするという思いから生じている。
それがそもそも幻想である。
身体も、それが育んだ精神も幻想世界に生きる存在である。
鳥雲に石は千年答へざる
もしかしたら石は何かを証言してくれるかもしれないという幻想へ、読者を強引に引きずり込む表現だ。
だが季節が廻れば鳥が無言で飛び去るように、いくら待っても石が何かを語ってくれる日は来ない。
この句に日本の神話的アミニズムを読み取ることには無理がある。万物に神が宿るという自然信仰的感性が共有されているという背景はあるが、そのことがこの俳句の文学的主題ではない。私たちは何故、このような在り方で存在しているのか。自分はもちろんこの世界のことを何も知らされることなく、私たちはこの世界に投げ込まれるように誕生し死んでゆく。
哲学でいうところの「存在の被投性」というものだ。それがこの俳句の主題の背景にある思いだ。それを軽やかにこう表現する力に思いを致すべきであろう。
それは、この句集に収められた次のような俳句にも通底する主題である。
冬菫この世四五日離れたきに
綿蟲の一つが我を呼びゐたる
誰かまた銀河に溺るる一悲鳴
星月夜こころに羽打つもの棲みて
◇ むすびに
河原枇杷男の俳句は、身体的な直截性に裏打ちされた、表現の具象性を条件として獲得する表現の強度よりも、魂のリアリティの強度を優先させた俳句であると言えるのではないだろうか。
一般的な句集の境涯詠集的な在り方も、それはそれで俳句的文学の一つの在り方である。例えば石田波郷の「俳句は文学ではない」とする俳句観の、「俳句は生活に随ひ、自然に順じて生れるものである。作句の心は先づここになければならぬ」とする、その方法によってしか表現できない俳句独特の世界がある。波郷は創作的な技法としての文学的虚構性を徹底して排除した究極的な境涯詠俳句を切り拓いた俳人である。そうやって生み出した俳句もまた、一つの文学であるとも言っている。
その正反対の位置に立っているような河原枇杷男句集は、波郷のそれとは違うが、俳句の表現方法としても成り立ち得る「文学的主題」表現の可能性の開拓に挑んだと言えるのではないだろうか。
河原枇杷男が切り拓いた俳句表現の地平は、作品と読者の間に確かな手触りで立ち現れる「文学的主題」の表現だったと言えるのではないだろうか。
正反対の、文学的虚構性を排除し、究極の境涯詠に徹した石田波郷の俳句は、徹底して生の実感を身体に刻むように表現することで、読者の胸に深く刻まれる普遍性を獲得した俳句であると言えるだろう。
河原枇杷夫俳句は身体に刻むのではなく、精神世界に深く沈潜し、そこに幻視した世界を、主体的に行為するように詠むことで、文学的な普遍性を獲得したと言えるのではないだろうか。
そんな枇杷男の「文学的主題」は「答えのない存在の問い」であった。
存在の深淵を覗き込むような、象徴的な表現方法で、自分の「文学的主題」を表現している。
だが、その主題は枇杷男独りのものである。
枇杷男の方法論を継承するのであれば、その一人ひとりが、独自の「文学的主題」を確立し、表現しなければならない。
それは、現代を生きる俳人たちが、俳句表現の可能性の一つとして、より豊かに耕してゆくべき、貴重な分野の一つであると言えるだろう。
だがそれは簡単なことではない。それが俳句表現である為には、ただの観念の表出に陥ることなく、豊かな俳句的表現の地平を獲得していることが求められるからだ。
