
短歌界では今、九螺ささらが面白い 『神様の住所』(朝日出版 2018年6月11日刊)
2018年06月26日 記
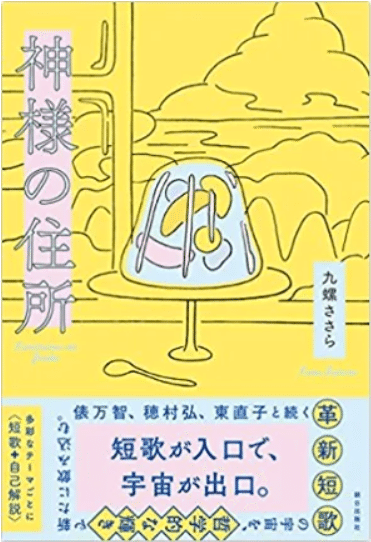
本書の帯に次のような惹句が記されている。
「俵万智、穂村弘、東直子と続く革新短歌の宇宙を、哲学的な輝きで新たに飲み込む。短歌が入口で宇宙が出口。」
だが、同じ革新短歌の流れと言っても、九螺ささらは、俵万智、東直子、ニューウェーブ短歌と言われる加藤治郎、荻原裕幸、穂村弘、西田政史はもちろん、それ以外のどんな歌人にも似ていない。
革新的な哲学的短歌である。
その独創性は以下の理由によって担保される。
一つ、九螺ささらという歌人にとって、この表現が短歌でなければならなかった、という必然性があるということ。
一つ、旧来の伝統的な短歌観を脱して、日本短歌的抒情ではない、生きる上での形而上的思念の発生する現場から言葉を立ち上げる、魂のリアリティの表現がされていること。
一つ、これこそが韻文学の本来的なあるべき姿ではないかという形を提示し得ていること。
一つ、それまでになかった内容と形式の表現を創造する上での明確な方法論が自覚されていること。
本書の作者も編集者も慎重に、本書を「歌集」とは呼んではいない。
だが、表現と編集出版という作業を含めて、新たな形式が創出されているという意味で、これは新表現の「歌集」と定義されるべきではないか。
本書が生まれる原点について作者の九螺ささらが、本書の「あとがき」で述べている。
この「あとがき」にも、私が今述べた独創性の条件を満たすに充分な新しい短歌観が示されている。
その一部を以下に摘録させていただく。
※ ※
(略)
わたしには、形而上的世界を愛する「宇宙酔い」の持病もあった。
「宇宙酔い」には哲学が効く。
哲学は、見えないけれどたしかに人類が感じているこの世の不思議を言語化して、人類が感じているこの世の不思議を言語化して、人類脳同士で共有しようとする叡智である。
しかし、不可視不可思議を追い求めると、脳は酔ってしまう。
短歌は、このような過多な理性を受け止めてくれる器にもなりうる。
『神様の住所』は、短歌という器で受け止めた感情と理性を言葉にし直して、新しい世界の見方を探ろうとした試みの軌跡である。
(略)
わたしは、「ただ短歌が並べてあるだけの歌集」や「短歌=与謝野晶子的情念」というシメージに疑問を感じていた。
(略)
※ ※
この「あとがき」の一部を読んでも、九螺ささらが、自らの表現方法論をしっかりと持って、短歌を詠んでいることが解る。
私は俳句界に溢れる句集の編まれ方の非文学性について、しばしば言及してきた。
九螺ささらがここで述べている「ただ短歌が並べてあるだけの歌集」と指摘することと同じ意味である。
通常の句集・歌集の編まれ方といえば、一定期間、俳人や歌人が境涯詠的に詠み溜めてきたものを、編年式、あるいはテーマ別などの方法で編んだ句集・歌集がほとんどだ。
だから、収録されている一句一句、一首一首に感銘を受けることはあっても、その句集・歌集全体を通して訴求するものが感じられない。
たとえば優れた一冊の純文学を読んだときに感じる、何か一言では言い尽くせない作者の深い思い、つまり文学的主題というものが、句集、歌集には感じられない。
句集や歌集とはそういうものだと言われてしまえば、話はそこで終わってしまう。
そうではない、一貫した文学的主題を持つ句集や歌集があってもいいではないか。
句集には稀だが「テーマ性俳句」といって、一つのテーマに基づいて詠んだ俳句で全篇を編んだ句集がある。
だが、俳句界ではそんな句集はどこか鬼っ子扱いで、正当に評価されない傾向がある。
短歌界も同じような傾向があるようだ。
九螺ささらは、そんな非文学的歌集と絶縁しているとこから言葉を立ち上げている。
一つひとつの短歌も、全体を貫くテーマも、一つの文学的主題で詠まれている。
本書はそういう意味で、本物の短歌文学であると言ってもいいだろう。
また、今の俳句界や短歌界は、韻文に本書のように散文を混ぜた句集・歌集を、本来的ではないとして認めたがらない風潮がある。
歌集には稀に日記体の散文と短歌を組み合わせたものがあるが、全体的な統一感には欠けることろがある。
「俳人なら散文に頼らず、俳句だけで勝負すべし」「歌人なら歌だけで勝負しなさいよ」という暗黙の掟のようなものがあるかのようだ。
それは、今までに無かったというだけで、割引評価している感情論に過ぎない。その言い分に、文学的な、なんの正当性も根拠もない。
本書は、韻文と散文を組み合わせ、短歌と散文に統一感があり、全体を貫く明確な文学的主題があるという意味で、今までのどんな歌集より文学的である。
日常性から哲学的思弁への口語韻律的跳躍。
旧来的な短歌的情念ではなく、理知的で、精神的な「思念」の吐露なくしては、生き辛いと真剣に思う人間の、魂の真実がそこにある。
本書の文学的主題はずばり、命とは、存在とは何かという問いである。
人が生きて在るということの、根源的で深淵な問いに、しなやかな感性で挑んでいるのだ。
日常生活のただ中で、なにげないものごと、なにげない言葉などに触れて、そのようにして、そのような言葉を使って生きていることの不思議に目を凝らし、心の中に沸き上がるもやもやとした思い、その奥に潜む何か大切なもりを求めて、それに言葉を与えながら模索してゆく。
まだ言葉にならない何かに、言葉を与えること、それこそが文学の役目ではないか。
〈体積がこの世と等しいものが神〉夢の中の本のあとがき (10 哲学)
寝て何を入れてもわたしとはたわしにならない固有のわたし (質量保存の法則)
というような軽妙で深淵な短歌と、その思弁の周辺、どんな思いを抱えて生きていて、やがてそれが韻律を持った歌として昇華してゆく過程を記録したようなエッセイ風の文章が続き、最後にまた異相の違う短歌が添えられて、各章が閉じられるという構成になっている。
以下がそのテーマであ。
84のテーマ
体と心
さびしいから
魔法
アナグラム
絵画
ゲシュタルト崩壊
黒柳徹子
レシピ
地図
哲学
なぞなぞ
クラゲ
前略
レーズンバター
濁点
両生類
因果関係
エロス
味の素
部首
たましい
物理
ふえるワカメ
無限
枕
基準
神様
対
重複
生まれ変わり
境界
シベリア
鬼籍
アレの名は
住所
いつか
オノマトペ
夢
額縁
トマトと的
漢字
端
絵のような文字
オブラート
絵日記
質量保存の法則
デジャヴ
今
同音異義・異音同義
数な言葉
箱または穴
まちがい探し
音楽としての短歌
水
匂い
ストロー
地名
丸い三角
分かる
言葉にならない
ものごころ
〇〇用
記憶
似て非なるもの
不思議四文字
省略
丘の上
ゼリーフライ
動物
菌類
アイムカミング
比喩
脚本
同心円
G線上のマリア
さんたんたる鮟鱇
生け贄
岡本太郎とムンク
ベン図
公園
中身
聖書
幸福
選ばれているテーマはあくまで誰にでも身近な素材である。
だがそこから紡ぎ出される韻律(散文にも独特のリズムがある)は、伝統的な短歌的抒情とわたくし性への貼り付きのベタつきがない。
読後、読者はここに確かな九螺ささらという、他と取り替えのきかない「私」がいることを感受する。
革命というほど浮足立たず、改革というほど地味でもなく、新次元の表現地平が、かすかな微熱を伴って展開されている。
すべて読んでいて面白い章ばかりだが、特に印象に残った章を以下に抜粋して紹介する。
※ ※
〈体積がこの世と等しいものが神〉夢の中の本のあとがき (10 哲学)
哲学は、「時間とは?」「空間とは?」「わたしとは?」を問う学問である。
この世とは、「時間」と「空間」と「わたし」を内包したものである。
だから哲学は、「この世とは何?」と問うている。
自分を客観視することが、哲学の第一歩なのだと思う。
小学校に上がる前、電車の車窓から、遠くの、山裾の家々が見えた。
「その中」を見たときだ。
そこに「動く人」がいた。わたしの人形の家の中の、人形ではなく。
その瞬間わたしは、「世界はわたしのものではない」と気づいた。
この世とは、煮詰めてゆくと、「我思う、ゆえに我り」であり、拡大してゆくと「宇宙の果てはない。完璧な絶望が存在しないようにね」なのらしく、実際一個体の我であるわたしもそう感じる。というそう感じるほかない。
そう感じるほかないというのは、宇宙の類似品である我は、自分の眼球で自分の眼球を見ることができないように、宇宙の客観が拒絶されているからだ。
この拒絶が、イコール神の手触りなのだ。
この拒絶を「禁忌」や「タブー」と言い換えて解釈してもよい。
一卵性双生児のように外見がそっくりな親子が、「死ね!」「お前が死ね!」と罵倒し合っている現場を目撃したことがあるが、宇宙と我もこの親子のような関係である。
相手の死は、つまりイコール自分の死だ。
我々も、共存(共依存)関係にある宇宙を殺せない。
宇宙とは、それぞれのわたしだ。
だから宇宙は、実は生きている人の脳の数だけ存在している。
宇宙とは、点在する濃密である。
NとN、SとSのくっつかなさをこの世の極みの手応えと思う
※ ※
いきなり、本書の文学的主題に関わる重要な章を引いてしまったかも知れない。
こんな感じの章で本書全体が構成されている。
冒頭から「自分を客観視することが、哲学の第一歩なのだと思う。」という哲学的思考が陳述されて、その調子で進むかと思うと、「小学校に上がる前、電車の車窓から、遠くの、山裾の家々が見えた。」の行から、その哲学的思考に連なる、思い出の具体描写へと転調する。
子どもらしい狭い主観世界の「外側」で、自分とは無関係に生きている人間が、遠望される小さなおもちゃ世界のような家の中で、勝手に動き回っている、という気づきこそ、私たちが世界と出会い、疎外され始める第一歩の大事件なのだ。
そんなことが淡々と語られる。
そしてもう一度、同じ流れだが、別の哲学的思考が記述され、そこからまた一卵性双生児親子の愛憎現場逸話が挿入され、全体を総括する別次元の哲学的思考が記述され、最後はそこからもっと遠くへ、読者を投げ飛ばす。
そして別の一行の短歌で締め括られる。
この章を紹介しただけでも、全部読んでみたいという思いに駆られただろうと思う。
2018年6月24日の朝日新聞の俳句短歌のページのコラムに、大辻隆弘が「ニューウェーブの今」と題して、次のようなことを書いていた。
※ ※
今月、名古屋で「ニューウェーブ30年」というシンポジウムが開催された。
一九九〇年代、口語や記号を多用する新しい短歌が生まれ、若者らに大きな影響を与えた。その中心となった加藤治郎・荻原裕幸・穂村弘・西田政史が一堂に会し、ニューウェーブ短歌を総括した。
一九八〇年代後半、俵万智らの登場によって歌壇には口語によるライトな歌が流行した。そのなかで西田は「短歌で面白いことができないか」と思ったという。また加藤は、当時普及し始めたワープロの文字が自由に加工されることに注目し、その自由さが記号短歌に結びついたと述べた。当時の若者が感じていた自由な雰囲気がニューウェーブ短歌の出発点だったことが窺える証言であった。
ニューウェーブ短歌が、若者に支持されたのは、彼らの作品のなかに圧倒的な自由さがあったからだろう。近代短歌の呪縛から解放されているという自在感は、パネリスト四人の作品の背後に流れている共通した時代感覚であった。
おりしも、加藤治郎『Confusion』(省肆侃侃房)と穂村弘『水中翼船炎上中』(講談社)が出た。二人の新歌集である。
てのひらは湖だからゆっくりとあわい光があふれてゆくね 加藤治郎
灼けているプールサイドにぴゅるるるるあれは目玉をあらう噴水 穂村 弘
二人の歌は、今なお若々しく自由である。その背後には、実年齢を重ねながらも短歌的な成熟を拒否しようとする強靭な意志がほの見える。ニューウェーブ短歌の栄光と労苦がそこにある。(歌人)
※ ※
九螺ささらという新進の歌人は、この「ニューウェーブ」歌人たちの後継者に位置づけられることになるのだろうか。
「ニューウェーブ」という言葉が、表現の仕方の新しさという評価による呼称だったということなら、確かに、九螺ささらは、その「新しさ」の流れの中に位置づけられるだろう。
先行するこの「ニューウェーブ」歌人たちの歌集には「圧倒的な自由さ」が溢れている。
彼等は表現の改革に挑んだのだろう。
だが、旧来の歌人同様、彼等の歌集には全体を貫く「文学的主題」というものは感じられない。
九螺ささらがいう「ただ短歌が並べてあるだけの歌集」の域を出ないように感じられる。
短歌を詠む姿勢に一貫した姿勢は感じるが、詠まれている内容に統一感のある文学的主題というものは読み取りにくいように思われる。
本書には全体を貫く統一感のある文学的主題があり、九螺ささらは、そのことについての確固たる方法意識を持っている。
彼女がこれから生み出してゆく歌集が、全体を貫く統一感のあるどんな文学的主題のある歌集を実現して見せてくれるか、とても楽しみである。
きっと短歌の新時代を切り拓いてくれるものと信じている。
現代短歌が彼女の登場を機に、もっと文学らしくなってゆくことを切望する。
最後に著者情報をメディアに公開されているものから転写しておく。
九螺ささら(くら・ささら)
神奈川県生まれ。2009年春より独学で短歌を作り始める。2010年、短歌研究新人賞次席。
2014年から新聞歌壇への投稿を始め、朝日新聞「朝日歌壇」、日本経済新聞「歌壇」、東京新聞「東京歌壇」、ダ・ヴィンチ「短歌ください」、NHKラジオ「夜はぷちぷちケータイ短歌」などに掲載。
2018年8月に初の歌集も刊行予定(東直子監修、書肆侃侃房「新鋭短歌シリーズ」)。
