
高橋修宏「六林男をめぐる十二の章」
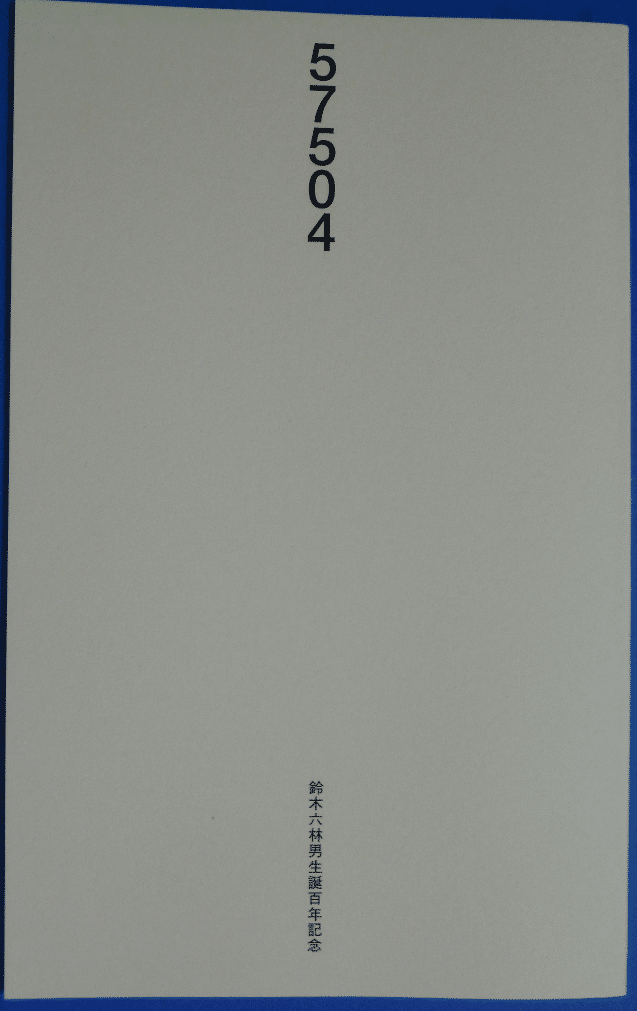
俳誌「57504」鈴木六林男生誕百年記念号
二〇一九年九月二十八日刊
はじめに
俳誌「57504」鈴木六林男生誕百年記念号の表紙裏に六林男の次の句がそっと置かれている。
短夜を書きつづけ今どこにいる(鈴木六林男)
まるで、六林男俳句論を書き継いできた高橋修宏自身の呟きのようだ。本号に収められている唯一の諭考の表題は次の通り。
「六林男をめぐる十二の章」
十二の章に亘って六林男作品の論考が掲載されている。「あとがき」に当たる「編集後記」によれば、本稿は二〇一六年に「山河」誌上での三回の連載、その後断続的に「連衆」誌上などで発表したものに手を入れ、新たに書き下ろした数篇で構成されているという。
これらを遡ること十数年前、高橋修宏の「六林男俳句論」の執筆は二〇〇二年に「現代俳句評論賞」を受賞した「持続と断念―鈴木六林男」に始まっていると思われる。
いわば高橋修宏俳句評論は、師である六林男俳句を深く掘り下げて読み込み、高橋修宏独特の詩学的視座による文学論的な検証と論評から始まったともいえるのではないだろうか。他の四編を含む六林男俳句論は、他の俳句論とともに、二〇一一年八月に上梓された現代俳句評論集『真昼の花火』(草子舎)に収録されている。
この評論集での六林男論は、戦争詠俳人という伝説的レッテル貼りから鈴木六林男を解放し、オリジナリティ溢れる作句法と、独自の根源的詩論、表現方法論の稀有なる持ち主であった実像を描きだし、そういう意味で俳句の明日を切り拓いた俳人であったことを論証して、俳句表現論的な正しい位置に鈴木六林男世界を、鮮やかに置き直してみせた画期的論考であった。
その鈴木六林男論を含む評論集『真昼の花火』の上梓が二〇一一年、つまり「三・一一」に東日本大震災が起きた年の八月である。
そして高橋修宏が六林男論を再び書き始めたと思われるのが、今回の「六林男をめぐる十二章」に纏められることになる連載評論の二〇一六年。東日本大震災から五年後のことである。
年月についてわざわざ確認したのには理由がある。
この震災から五年という歳月に及ぶ、内面化、熟考の時間が必要だったことを指摘するためである。
詩人でもある高橋修宏の、同時に俳句の表現者としての、震災直後から続く一時的な「熱狂」の期間、震災詠や震災論にコミットせず、深く自分の内面を耕し続けた姿勢を、この意思ある「空白」の時間が間接的に浮かび上がらせる。
こういう言い方はできないだろうか。
震災が高橋修宏を、再び鈴木六林男俳句世界に呼び戻したのだ、と。
この言い方が的外れでないことを、「編集後記」の彼自身の次の言葉が証明している。
※
三・一一東日本大震災を経るなかで、それまでとは明らかに異なった手触りを伴って、六林男の俳句作品が立ちあらわれてきたことも感じている。
※
わたくしごとになるが、この体験と実感は、私にとっての石牟礼道子文学世界とほぼ重なる。私もまた震災によって石牟礼道子文学に連れ戻されている。石牟礼作品が文学として読まれていないことに批判意識があり、文学論として論じる必要を長い間感じていた。だがそれをどう論じればいいか解らずに手つかずになっていた。石牟礼道子が俳句を書き始めていたこととも重なり、私の中で石牟礼俳句が「それまでとは明らかに異なった手触りを伴って」「立ちあらわれてきた」という体験をしている。それが、高橋修宏も受賞している現代俳句評論賞を得た、私の石牟礼俳句論となって形になった。それが、高橋論文に私が深いシンパシーを感じる所以である。
そしてそれ以上に指摘しておきたいことがある。
逆の言い方に感じられるかもしれないが、それはつまり、鈴木六林男俳句世界が、カタストロフを潜り抜ける体験をした文学的感性によって、再読、再評価されうる表現の強度、内容の深度を、あらかじめ備えていたということの証明でもある、ということだ。
そしてこの視点を再反転させると、高橋修宏にはそれを見抜く独自の詩学的な批評眼があり、高橋修宏によって六林男俳句世界が、作品行為論的に生き直されることによって、文学が今論じなければならないことを明確に提示するように、本稿が書かれている、ということだ。
実はこのことが、この論考を熟読し、文学的評論ということを考える上で、最も大切なことだと思うのだ。
文学評論とは何か。
評者が文学作品を生み出す作家である場合、作家でもあり評論家でもある者は、その内的な必然性に裏打ちされない評論に現代的な価値を見出さない。
この「現代的」というのは、作者と生み出す作品が、いかに「今」という時代と切り結ぶ視座を備えているかどうか、ということだ。
換言すれば、作家と作品がつねに「何故、今、それを書く必要があるのか」と、常に内的な問いを発し続けている、ということだ。それが文学評論とは何かという問いに応えうる条件でもあるのだ。
もう一つ、高橋修宏は「編集後記」で大切なことを述べている。
暗闇の目玉濡らさず泳ぐなり 鈴木六林男
暗闇の下山くちびるぶ厚くし 金子 兜太
この二句をめぐって高橋修宏はこう述懐している。
※
「暗闇」をめぐる二つの俳句の隔たりと、その間に広がるものこそ、戦後俳句と呼ばれる荒涼とした領土のひとつであったと、いま差しあたり考えてみることができるかもしれない。
わたしたちは、その荒々しい豊饒な領土を、どのように見ればよいのか。語りつづけることができるのか。あるいは、すでに失いつつあるのだろうか。
※
戦後の俳句表現における問題点を、この二句の対比で象徴的に指摘する高橋修宏独自の、詩学的な視線は深く鋭い。彼にはこの二句の精密な鑑賞を起点とする問題の在処を、具体的に詳述することも可能だったはずである。だが、このように総論的に触れるに留めている。なぜ詳述しないで示唆するに留めたのか。
それはここに収録された十二章ですでに論証・詳述しているからだ。すくなくとも彼はそう思っているに違いない。そのことを理解できるか否かで、その読者の戦後俳句表現観の違いが浮き彫りになる。
戦後俳句表現には、そのような層的な分裂があるという指摘も含んでいる「編集後記」なのである。
暗闇の目玉濡らさず泳ぐなり
この「暗闇」は「泳ぐ」人の身体状況にだけを覆う闇ではない。不可視の範囲が、この俳句自身の表現範囲を超えてしまうような深さを湛えた闇である。
なぜそう「読める」のか。
六林男の句では、「泳ぐ」ことをしている行為者には、その行為の目的すら把握されていない。何処へ行くのか、闇は晴れるのか、晴れた後のこの闇の先に何が待ち構えているのかも判らない。その表現されていない不明さ、不安感故に行為者は「目玉濡らさず」、闇を凝視する他はない緊張状態に置かれている。
ここでは身体的存在感は肯定されていない。あるのは視界不良の得体の知れない広がりを持って自分を囲繞する「暗闇」的情況であり、ただ「泳ぐなり」という、意思的ではないぎりぎりの人間的な自己表出だけである。そんな自己表出のあり方こそが文学ではないか。そういう意味で、この六林男の句は、まるで戦後的闇と格闘した戦後世代が詠みそうな俳句ではないか。
この句は戦場体験が元になって生み出されたという「還元方式」の読みが喧伝されてきた。例え契機がそうであっても完成した作品はそれを超えてゆくものだ。
高橋修宏は最初の六林男論から始まる、今回に続く論考で、その「還元方式的読み」に異を唱え続けているのだ。
高橋修宏が〈「暗闇」をめぐる二つの俳句の隔たりと、その間に広がるものこそ、戦後俳句と呼ばれる荒涼とした領土のひとつであった〉と指し示しているのは、このような違いのことではないか。
高橋修宏は、この二つの句の違いを指摘しながら、その違いについて詳述せず、それが本論の主旨であったことを最後に表明し、読者のその視座による本論の「読み直し」を促しているのだと言えよう。
ここにあるのは透徹した震災後詩学の眼差しに他ならない。
そのような眼差しで三・一一を潜り抜けてきた高橋修宏が、新たに発見した六林男俳句の表現の可能性を、十二の章で論述しているのだ。
以下、私見を交えながら各章の要点を紹介しよう。
一、道化としての六林男
この章では六林男俳句の「戦闘」よりも深い「戦争」の底なしの不条理の表現について論考され、表現者は道化的な位置に自分を置くことでそれに対峙する他はなかったという視座が提示されている。
※
だが戦争体験者の多くが、口を閉ざしていくなかで、なにゆえに六林男は執拗なまでに語りつづけたのか。それは誰彼に伝えることのできる自慢話でも、輝かしい勲章でも、決してなかったはずだ。
正直に言って命はおしく、積極的な反戦行為に出る勇気は勿論なく、殺戮、略奪の戦争ルールの渦中にあって疲労困憊の憂鬱な毎日であった。(……)この戦場の中に僕もいたことは、僕も弱く、自信も勇気もなかった証拠である。それ以外に理由はない。
(鈴木六林男「人間について」一九七四年)
※
そして高橋修宏はこう思索を深めてゆく。
※
六林男に則して言えば、「戦争」という巨大な暴力に対して、「弱く、自信も勇気もなかった」と語りながらも、かろうじて〈道化〉という場所に立つことによって、俳句を書きつづけること、さらに戦場体験を語りつづけることができたのではなかったか。それゆえ軍隊からの「逃亡」という行為を、自らの俳句の中に書きとどめながらも、ついに彼自身は「逃亡」を選ぶことはなかったのだろう。
ねて見るは逃亡ありし天の川
秋深みひとりふたりと逃亡す
シェイクスピアは喜劇『お気に召すまま』のなかで厭世家の貴族ヴェイクスに「私に斑の服を着させてください。」とかたらせている。この白・黒いずれとも簡単に判別しがたい「斑の服」こそ、〈道化〉にとって真実を自由に語るための、まさしく象徴であり、武器だったのだ。
※
この章の〈道化〉という言葉に触れて、私は山口昌男の著書の一つ『道化の民俗学』のことを思い出した。70年代半ばだったと思う。学術的な枠組みを超えて縦横に論を展開する山口昌男は、この頃の「時代の寵児」的な存在だった。レビ・ストロース、エリアーデなどの論文収めた『未開と文明』の編著、『本の神話学』『アフリカの神話的世界』『人類学的思考』など、既存のアカデミズムの枠を超えた著作を発表した文化人類学者である。その基調になっている視座は、世界は周縁的な要素によって活性化されるとする「中心と周縁」理論、「道化」や「トリックスター」といった中心と周縁を転換させるキャラクターをモチーフとした多彩な論考を展開した。『道化の民俗学』では、エロスと笑い、風刺と滑稽に満ちた祝祭空間で演じられる「道化」の意味を解き明かしていた。日本の狂言の太郎冠者、中世劇の悪魔と道化、ギリシャ神話のヘルメス、アフリカのトリックスター神話、古代インドの黒き英雄神クリシュナ、アメリカ・インディアンの道化集団など世界の民俗について、縦横無尽に論を展開していた。
二十代の若造の私にはまさに瞠目の書であったが、その論調に、言葉にできない「違和感のようなもの」を抱いていたことを思い出したのだ。
大事なのはその「違和感のようなもの」の方である。この高橋修宏論考によって、私が抱いた個別的な違和感が、道化が文化的英雄として論じられていたことに基づくものだったことに気づかせてくれた。
現実的にはとても英雄的ではいられない、道化的精神が育まれる現場、その実体的な個の命の手触りは、これらの論考では排除されている、という違和感だったのだ。論考の主眼はそこにはないのだから、その視座が欠落するのは仕方がないことかも知れない。論文を文学的に受け止めていた私の個人的な感性からくる違和感だったとも言えるだろう。
今、認識を新たにして、私の違和感を定義すれば、次のようになるだろうか。
私の中には原点として水俣病問題があり、その「周縁的な要素」そのものを体現したかのような、生身の被害者たちと、その魂に寄り添って、その聞こえない声を文学に転換してみせた石牟礼道子という存在と、彼女の著書を通して出会ったという原点的体験がある。
彼女のような存在が、文化論として語られるとき「英雄」的位置づけになるにしても、この満身創痍の「道化」の現実に対する視座を欠くところに、文学は成立しない、ということだろう。
後年、石牟礼道子が社会学的に論じられようになっていったときも、同じように抱いた違和感の正体も同根である。そこに欠落していたのは、このような文学的視点ではなかったか。
高橋論文は、ずばり、その盲点を突いてくる。
オープニングであるこの章において、六林男の「戦闘」よりも深い「戦争」の底なしの不条理の表現について言及し、表現者が道化的な位置に自分を置くことで「それに対峙する他はなかった」という、「道化」的精神の発生する現場を、鮮やかに描き出している。
高橋修宏が見据えているのは、「道化」の文化的な英雄性ではなく、表現者としての誠実な詩念のあり様であると言えよう。そのことが理解されれば、何故、そのことを本論考の冒頭に置いたのかという、高橋修宏の論考の主旨の一端が理解できようというものだ。
六林男が語った壮絶な戦争体験を引用して、高橋修宏は次のように述べている。
※
(……)いっしょに行軍していて自分の脇を歩いていた奴が、急に倒れる。撃たれて死ぬ。その戦友の腕を、遺品がわりに切り取って、腰に吊るして歩く。しばらく行くと、さらに次の奴が倒れる。その腕も切り取って、もう片方の腰に吊るす。それが歩くたびに、ピシャンピシャン当たる。前を行く奴の方を見ると、両の腰に吊るされた腕がブランブラン揺れている。(……)「吊るされた腕がなぁ、おいで、おいで、って言ってるみたいなんや。まいってしまうわ(笑)(……)
こんな話をしたとき、われわれは一体、どのように対応すればいいのだろう。「想像を絶する」という言葉があるが、このような光景こそ、まさしく想像を絶するものだ。はじめに言葉を失い、やがて話者である六林男の「まいってしまうわ(笑)」に連られて、また笑ってしまうほかはないのだ。
※
改めて私は、次のような思いに誘われるのだ。
東日本大震災では「にわか英雄」たちの言動が喧伝された。「オール日本」「頑張れ東北」という「励まし」と、仮構された「不屈の精神で立ち上がろうとする被災者」像が、バーゲンセール的表象と化していった。その仮構された表象に相応しい振る舞いをして見せることを強要するようなメディアの前で、被災者たちは、困惑したような微笑を浮かべるか、奇妙に明るい自虐的な言葉で応じるしかなかっただろう。まさに高橋修宏が六林男の俳句と述懐に見出している「道化」そのものではないか。その目の奥に、まだ真に泣くこともできないで、溜り続けている涙の色に気づいた者が、あのとき、何人いただろうか。そんな彼等に対して、「オール日本による励まし、復興支援」などという言葉がいかに空疎なものか、そんな違和感を抱いた者が、あのとき、何人いただろうか。
高橋修宏が指摘するように、「戦争」同様、震災禍や原発事故禍の、「底なしの不条理」のただ中で「道化的な位置に自分を置く」ことで「それに対峙する他はなかった」であろう被災者たちの現実に、目を凝らした日本人が、あのとき何人いただろうか。
あのとき以来、言葉が深まってゆくどころか、限りなく表層化して、グズグズに崩壊してゆくような有様を、私たちは「目撃」してきた筈だ。誤解を恐れずに言えば、俳句界もそこから免れていなかったと思う。
そんな震災後体験が、高橋修宏を鈴木六林男俳句へと連れ戻したのだ。私が石牟礼道子文学に連れ戻されたように。
二、生き続ける遺書
この章では人間として基本的に備えているはずの能動性が、ことごとく奪われ、極限的な喪失の状況の表現が論じられている。六林男のその表現が現在にまで届く「遺書」のようだと述べている。その「遺書」の言葉は、三・一一という「極限的な喪失の状況」を体験した今の私たちに確実に届いている。
この章は二つに分けて書かれている。
1 受動/無季/ツェラン
2 ロマン/季語/安吾
という二つの節である。
1 受動/無季/ツェラン
東日本大震災後、鈴木六林男の俳句作品を読み返して、「それまで気づかなかった名付けがたい異様さが、立ち上がってくるのを感じた」として、高橋修宏は次の俳句を摘録している。第一句集『荒天』(一九四九年刊)の「海のない地図」の章の俳句である。
かなしければ壕は深く深く掘る
泥濘をゆき泥濘に立ち啖う
遺品あり岩波文庫『阿部一族』
倦怠や戦場に鳴く無慮の蠅
をかしいから笑うよ風の歩兵達
砲いんいん口あけてねる歩兵達
水あれば飲み敵あれば射ち戦死せり
射たれたりおれに見られておれの骨
高橋修宏はこう述べる。
※
これらの作品に通底する基調音をひと言で表すならば、何ものかに強いられた受動性ということになろうか。おそらく極限的な喪失の情況に置かれるとは、このように人間として本来そなえているはずの生への能動性を悉く奪われてしまうことではないのか。
もちろん六林男の場合、この「何ものか」とは、人間としての日常を奪われた戦場という苛烈な情況であったことは言うまでもない。だが、そのような「何ものか」とは、現在であっても世界中に遍在しているのではないのか。あの東日本大震災のような自然災害であっても(また、それに伴う原発禍も)、さらに強制収容所と名付けられた忌しい存在においても、人間としての生への能動性を悉く奪い取ってしまうものとして現前しつづけている。
※
この後、高橋修宏はパウル・ツェランのナチによる強制収容所のことを書いた詩篇「追奏(ストレッタ)」を引き、またその詩篇を携えて被災地、南三陸を尋ねた中里勇太の「記録文学論」としての言葉も踏まえて、六林男の俳句、
月の出や死んだ者らと汽車を待つ 『櫻島』
を引いて、「はからずもツェランと六林男は、無言の死者たちを共有する同じような詩的な場所=トポスへと歩みを進めていたことが知らされるのである」と述べている。
ここにも高橋修宏の震災後詩学の眼差しがある。
私たち読者は改めて「詩的な場所=トポス」とは何か、どこに立てば震災後の言葉を打ち立てることができるのかということについて、沈思黙考する他はない。
ヒントはその前の言葉「無言の死者たちを共有する」にある。六林男の「月の出や」の句は、すでに日常的にそうしている者としての自分を表現している。
高橋修宏がこの節の冒頭で引いている俳句群が、戦死した戦友たちでもあり、いっしょに「死んでいた」六林男自身でもある「存在」たちの、「非日常的日常」を言葉で創出しているのではないか、と高橋修宏は問うているのではないか。
非日常の「戦場」であろうと、日常的な暮らしであろうと、そこに流れる時間は「繰り返し」によって維持されるものだ。毎日が違うことの連続である場合、連続的であることで初めて認識される「時間」は流れることはない。激しく折れ曲がり、その中で生きる人間に時間感覚を喪失させる。過度の緊張が生の充実感と錯覚され、虚しさの忍び込む余地すらない。
日常の時間ならば日々のそんな穏やかな「繰り返し」は、幸福感に満ちているはずだ。だが、それが無限に続くと閉塞感が生れ、たちまち苦しみと化す。
非日常の戦場における繰り返しは、人からその人間らしい二つの現象をも奪い去るのである。まるで無であるかのような時間感覚の喪失状態は、人間的な「苦しみ」の感覚すらも奪うのだ。「苦しみ」が実感できないところに、人間的な歓びも感受できまい。
このことを言葉で表現することは、不可能ではないかとさえ思われる。
だが六林男はそこに言葉を与えているのだ。
六林男に言葉を与えられたことによって、この深々とした虚無感が支配する戦場という非日常が、そこに「存在」し始めるのだ。高橋修宏がいう「無言の死者たちを共有する」「詩的な場所=トポス」とは、このような表現を可能とする、震災後詩学の眼差しが発生するところである。特に次の句、
かなしければ壕は深く深く掘る
泥濘をゆき泥濘に立ち啖う
をかしいから笑うよ風の歩兵達
水あれば飲み敵あれば射ち戦死せり
ここで創出された〈場所〉は、現実にあった場所ではない。兵士たちの惰性のように繰り返される自同律的な空虚感の漂う「行い」は、六林男がこう表現したことで、そこで「行われていた」こととして、存立し始める文学作品としての「行い」である。
2 ロマン/季語/安吾
第一章の後半の、この「2」では、「1」で引かれていた無季俳句群とは一転して、「戦場」にも存在したかも知れない一瞬の美的な景が、有季俳句で詠まれている例を、高橋修宏は対照的に収集してみせる。
長短の兵の痩身秋風裡
追撃兵向日葵の影を超えたふれ
流弾がぷつりと棉の花月夜
ねては見る逃亡ありし天の川
大陸に別るる雪の喇叭鳴り
交る蜥蜴弾道天に咲き匂う
月明の別辞短し寝て応う
死角出て大夕焼に消えにけり
「1」の節で引かれた句群の、高橋修宏よる分析を念頭にこの「2」の節で引かれた句群を読むとき、この句群があることで、六林男の「海のない地図」の言葉たちが、ただの創作的「虚構」ではなく、「真実」となっているのだということを了解する。
死と隣り合わせ、あるいは目の前での戦友の死かもしれない、それは確実に近未来の自分の死である情況というものが美化できるとしたら、政治的な意図による英雄化しかないのではないか。だがこの句群の調べはそんな虚妄の美化ではない。この通常のリリシズムすら損なうような「ロマン」性、不埒ともいえるほどの調べの「美しさ」は、いったい何事だろう。
それは「詩的な場所=トポス」を成立させ得た者だけが獲得する表現の地平というものであろう。
これらの表現について、坪内稔典の「日常をリアルに見ようとする眼よりも、日常を超えて言語空間を構築しようとする意志の方が強く感じられる」という評言や、倉橋健一の「疲れきった躰で、作品をかきとめたあと、睡りこけた戦友のかたわらに背筋をのばしたときの、ひそかな充溢とはどんなものであろうか」という評言を引きつつ、高橋修宏はこう述べる。
「はからずも季語のもつ虚構性が、六林男の戦場俳句におけるロマン性を支え、その作品の詩的水位を保証しえたのである」
このような句を詠もうとしている精神主体は、ある種の「興奮」または「酩酊感」の中にいる。俗なことばで言ってしまえば、六林男は「戦争」に興奮し、取り憑かれているのだ。その倫理感などとは無縁の、嘘のない心情が、これらの句群を単なるセンチメタルなリリシズムに堕すことなく、「その作品の詩的水位を保証しえたのである」。それが文学的表現の、もう一つのリアリティというものではないか、ということだ。
この言葉から、東日本大震災における震災詠問題の大切な視座を取り出すことができる。
東日本大震災が起きたとき、被災地ではない場所にいて、報道によってもたらされた、圧倒的な破壊の衝撃的なビジュアルに、ある種の「興奮」を覚えなかった者はいないはずだ。その衝撃体験を後付け的に「語る」とき、自分の脳裡に浮かんだのは、果たして「反原発」や「自然に還れ」というようなお題目だったか、と振り返ってみれば理解できよう。あの「興奮」にはそんな柔な倫理感などこれっぽちもなかったはずだ。
映画よる作り物の圧倒的な破壊のシーンを見ているような錯覚を起こしそうな体験だった。だが決定的に違うもの、それはその錯覚と同時に沸き起こる、「あの暴力的な破壊のただ中に居る、膨大な人の死」という現実が、私たちに説明不可能な「興奮」をもたらしていたのではなかったか。
人間の精神は人の死や、死ぬほどの悲惨の状況に、興奮してしまうものなのだ。そこにはどんな倫理観も入り込む余地はない。その現場を見に行きたい、たくさんの人の不幸や死の子細を確認したいという衝動も、その興奮の中に含まれていたはずだ。
そうであったはずなのに、後付け的に震災を語るとき、指示表出言語が、私たちに嘘を語らせてしまうという現象が生じてしまう。それが「反原発」だったり、「自然に還れ」だったり、「オール日本、復興支援」「がんばろう東北」などという空疎なスローガン言語の正体である。そんな言語に毒されてしまう者は文学的表現を理解できないし、生み出せもしないはずだ。
人間の死や不幸を他人事のように「眺めて」しまう精神が、そんなスローガン言語、指示表出に感染してしまうのだ。
動植物を含むあまねく命の危機、死、死ぬほどの不幸に、精神が興奮しない者に文学は生み出せない。
また、この言葉から、東日本大震災における震災詠問題の一つ、季語をめぐる議論のことを想起する。
原発事故禍の衝撃を念頭に置いた「季語が陵辱された」「季語は死んだ」「震災禍や原発事故禍さえ、季語を用いた花鳥諷詠的に表現するところに、真の震災詠は成立し得ない」という声が上がった。
今振り返れば、当時の独特な「熱狂」的な雰囲気の中では、多くの人が肯った意見だったが、「季語」の本質を外した視座であったことが見えてくる。
高橋修宏が「はからずも季語のもつ虚構性が、六林男の戦場俳句におけるロマン性を支え」というとき、その文学的な表現における「虚構性」の機能を的確に指摘していることに人々は気がつくだろう。
季語を表現上のただの便利な措辞として使用しているという意味の「虚構性」ではない。便利な措辞として慣習化された表現の中では、季語はすでに「死んで」いたのだ。大震災や原発事故で季語が死んだのではない。その前からある意味で季語は死んでいた。どのように? 表現者の内なる「ロマン性」と切り結ぶことなく、表現上の「約束事」と化すという姿で。
季節感も失われつつあった大いなる喪失体験の中で、本来なら今頃はその季語の季節であるという思いを滲ませて、淡々と喪失体験とその景を詠んだ、多数の一般の人たちの膨大な量の俳句が記憶に残っている。俳人たちの「励まし俳句」「無常観俳句」「自然の回復力の賛美俳句」などとは違う、語弊を恐れずいうならば、「どこか厖大な死という体験に酔っているかのような」一般の人たちの素朴な震災詠。あの人たちは、あのとき、ちょうど、この六林男のように「はからずも季語のもつ虚構性」が、あの人たちを内側から生かす「ロマン性」を支えていたことに気付かされる。
だから今も私の心に深く刺さって残っているのだ。
季語とは本来、そのような力を秘めたものではなかったか。一時的ではあれ、一般の人たちの震災詠の中で、季語が一瞬、原点に立ち返って蘇生していたのだ。
芭蕉がそれまでの日本的詩歌の伝統と決別して、自然と自然の中の人間そのものを詠むことを俳諧としようと決心したのも、その俳諧に季語という装置を明確に措定しようしたのも、そんな意図からではなかったか、そんなことを考えさせられたのである。
夏草や兵(つわもの)どもが夢の跡
むざんやな 甲(かぶと)の下の きりぎりす
旅に病んで夢は枯野をかけめぐる
諷詠の対象である自然の中には、膨大な量の死、喪失体験が含まれている。そういう意味で、季語とは死者たちや、喪失体験を虚構化したものではないかと、高橋修宏は指摘しているのだ。
これは季語問題を離れて、文学論的に論考しても同様なことを、私たちはあの震災体験でしてきたのではなかったか。高橋修宏はこの節で選出した句群に、その原初的な姿を見出しているのだ。
六林男の句の中の、秋風裡、向日葵、花月夜、天の川、雪、蜥蜴、月明、大夕焼という季語は、単なる約束事的措辞ではなく、身体感覚に直に触れてくるように感じられる表現になっている。
これはあくまで私見に過ぎないが、高橋修宏がこの節で引いた句群は、自分もあのとき一緒に「死んでいた」六林男による、死者たちの記憶と、死者たちに手向ける仮構された花束ではないか。
石牟礼道子文学が私たちの胸に深々と届くのは、死者である既知の被害者たちの受難や悲劇だけを描いたからではない。生前、自然との生きいきとした交感の心を失わなかった漁師たちの命の煌めきを同時に描いたからだ。それが厖大な死と拮抗しているからだ。
六林男の句の痩身の兵、仆れた狙撃兵、流弾の直撃をくらった戦友、逃亡の果てに命を落としただろう戦友、戦場で慌ただしく別れたままになった戦友たち、二度と異性と交わることもなかった戦友たち、敵の標的になる危険を覚悟で壕を出て、大夕焼に染まって消えてしまった戦友たち、あたかも彼等の墓標を建てるかのように、その夥しい死を見届け、永遠の詩の言葉に刻もうと、六林男は句を詠んだのだろう。
さらに踏み込んで高橋修宏は思索する。坂口安吾が安直な反戦思想ではく、兵隊という命令系統で成立する組織への嫌悪を述べたあと、「命令されない限り、最も大きな生命の危険に自ら身を横たえてみることの好奇心にひどく魅力を覚えていた」と書いた言葉を引き、さらにジョルジュ・バタイユの「エロティシズムとは、死に至るまで生を称えることなのだ」という言葉も引いて、高橋修宏は次のように述べている。
※
ここで安吾が「好奇心」と呼んだものこそ、人間が戦争を欲望する、その根源的な情動と決して無縁ではなかったはずである。
※
安吾の言葉には「安易ヒューマニズムも反戦思想も入り込む余地がない」と評する高橋修宏の批評の眼差しは、大震災後、熱病的に盛り上がった「反原発」や「自然に還れ」という指示表出的言語情況に向けられていると言えるだろう。自己表出としての文学は、そのような表層的な指示表出に与してはいけない。あのとき、多くの俳人はそんな指示表出に囚われてしまっていたのではないか。そのことが、いまだに自己総括されていないのではないか。
ここにも高橋修宏の震災後詩学の眼差しが窺える。
この節の高橋修宏の結びの言葉を引用する。
※
これまで六林男の「海のない地図」は、戦場という苛烈な情況を捉えた記録文学として、ともすれば狭義のリアリズムにのみ偏って評価されがちであった。だが、再々読していくたびに、そこにはパウル・ツェランの詩篇にも通じる受動性、さらにはロマン性や青春性などが錯綜した詩的言語の層を成していることに気付かされるのだ。極限的な情況を生き抜き、ただ自らの言葉だけを信じつづけた六林男の軌跡は、今日もなお、未知なる読者の前に遺書のように生き続けている。
※
この節の結びの言葉を読みながら、私は震災後、ツェランの詩篇と同様によく読まれたというヴィクトール・エミール・フランクルの次の言葉を思い出した。
※
「肉体がなくなってもなくならず、私たちが死んでもなくならないもの、私たちの死後もこの世にのこるのは、人生のなかで実現されたことです。それは私たちが死んでからもあとあとまで影響を及ぼすのです」
(『それでも人生にイエスという』山田邦男 松田美佳訳 春秋社) (注 太字処置=武良)
※
フランクルはナチスの強制収容所での体験を綴った『夜と霧』などの著書で有名になり、その後、人間に宿る「ロゴス〈愛、生命力、原理〉」を目覚めさせる「ロゴセラピー」を開発した精神科医である。
フランクルは人生の「究極の意味」について、人間は決して知ることはできないと言っている。このことを「超意味」といい、それがロゴスであり、ロゴスは私たち人間の本質であり、ロゴスと一体化しロゴス自身になること、「本質的な自分自身」になること、そうなったとき人は自らを意識することはないという。 「完全に根源的な〈自分自身〉であるとき、精神は自分自身に対して無意識である」「人間の実存的本質は、自己超越にある」という。
自分探しばかりする狭い自我から解放され、表層的な反戦思想や、スローガン的社会批判語から距離を置く、広い視座を持つ言語表現が文学というものだ。
六林男の「海のない地図」は、フランクルのいう「私たちの死後もこの世にのこるのは,人生のなかで実現されたこと」そのものではないか。それが、高橋修宏がいう「未知なる読者の前に遺書のように生き続けている」という言葉の真の意味であろう。
三、動物たちのゲルニカ
ピカソの「ゲルニカ」や、バタイユの『ヒロシマの人々の物語』を援用しつつ、六林男のあまり評価されていない群作「動物集」(句集『稼賊』)に注目し、俳句という定型によって動物たちをデフォルメし造型していると指摘している。高橋修宏はそこに人間を中心としたヒューマンな視線だけでは捉えることが不可能な、底知れぬ危機、不条理が形象化できたのだと論考している。
八月ノ犀ノ歳月動クナヨ
明日ノタメ水ノム豹ガ前肢折リ
めーめート青イ嵐ニ抗ウ山羊
駑馬ヲ描ク楳本(うめもと)某ノ前ニ出テ
大猩猩(ゴリラ)可愛イヤ芭蕉ノ中カラ甘焦(ばなな)トリ
虎達ニ蝶蝶トナリマタ病葉
国会中コチラハ獅子ノ交尾中
縞馬ノ犢鼻褌(たふさぎ)盗ム月明リ
木菟ヤ耳ニハ槍ノ降リソソギ
象ガ鼻掛タルハカノ機関銃
河馬ノ尻ニ西日ト音楽〈戦争デスヨ〉
鰐トナリ原子爆弾ノ日ノ少女
この一見難解な俳句群を、高橋修宏は『ゲルニカ』のような「爆撃直後の絶望的な光景というより、どことなく不安に満ちた諧謔が立ちこめているようである」と読み解いてゆく。
前半の通俗性を帯びさせたユーモアに、六林男の不敵な哄笑を聞き取り、後半は一転して「戦争をめぐる殺戮のイメージが顕在化してくる」と指摘する。十二句目の「鰐トナリ」の句については次のように述べている。
※
原子爆弾が投下された日、その苦しみから水を求めて川に飛び込んだと伝えられる人々の光景が重ね合わされているのだろうか。「鰐」という言葉からは、ケロイドとなって苦しみぬく少女の惨たらしいイメージさえ立ち上がってくるようだ。
※
そしてバタイユの「彼は意識をはっきりもって絶えず自分にこう言いきかせねばならなかった。これは人間なんだぞ、と」という『ヒロシマの人々の物語』の言葉を引いた後、次のように述べている。
※
ピカソが人や動物をデフォルメして描いたように、俳句という定型によって動物たちをデフォルメし造型しえた群作「動物集」―。
いわゆる代表作と呼ばれることのない、そのささやかな二十の群作こそ、かつて戦場俳句を書き切った六林男にとっての、もうひとつの『ゲルニカ』であったのかもしれない。
いま私は、もし六林男が生きていたならば、震災後に殺処分されていった馬や牛たちを、どのように眺め、そして描き出したのかと考えている。
※
この後、六林男の「馬」の句を抽出して、この節を次の言葉で結んでいる。
※
いずれの作品も六林男らしい野太く、どこかアイロニーに満ちた光景ではないだろうか。彼にとって「馬」をはじめ動物を対象とすることは、人間を中心としたヒューマンな視線だけでは捉えきることのできない、さらに底知れぬ危機や不条理を形象化するための、かけがえのない存在であったのかもしれない。
※
この章を読みながら、わたくしごとだが、私の童話創作に関連する古い記憶を思い出した。
石牟礼文学の洗礼を受けて、童話作家として物語を書き始めていたが、石牟礼道子が書いていない「水俣」をどう書くかということが、私の密かな課題であった。(編集者たちは私にそんなことを期待していなかった。彼らは私をSF童話賞出身のエンタメ系童話作家としか見ていなかったようだ。)
熟考の末、私は次のような童話を書き上げた。水俣病の原因究明のために、工場排水の拡散可能エリアで採ってきた魚介類を与えられて苦しんでいた猫たち、工場排水に混じる毒を吸い上げている草とは知らずに、自分が飼育していた兎に与え続けた結果、目の前で「水俣病」そっくりの症状で全身痙攣させさながら、兎が悶絶死したことなどを軸に、被害者側の少年、加害者の家族の一員でもある少年の眼差しで書くことで、なんとか物語化できた〈「へんじのない手紙」〉。
被害目線の被害の現状と怒りや悲しみ、公害批判、加害企業告発調ではなく、自然の中のあらゆる命の、存立基盤の危機の物語として書いたつもりである。
そのとき、自然がテーマの童話アンソロジー集刊行のために、プロの作家を対象として作品が募集されていた。それに応募して採用された作品である。だが本当は、その選考会議で、選考委員のプロの童話作家たち全員の反対で、落選していたのだということを、後日、編集長から聞かされた。編集長はこういう視点の作品もあってもいいのではと思い、彼の権限で復活採用し、最終話として掲載してくれたのだという。
何故、プロの童話作家たちは私の童話を落したのか。
児童文学界には童話というものは「向日性の文学」であり、どんな悲しい話であろうと、最終的に救いがあり、読者の子供たちに希望を与えるものでないといけない、という不文律のようなものが存在する。私の童話はその不文律に反している、というわけだ。この「自然」がテーマの童話アンソロジーは、自然賛美の感動物語の作品集刊行を主眼としており、その視点からも、私の童話は「気持ちが悪く」「救いがなく」「異様だ」というわけである。
東日本大震災後、日本社会を熱病のように席捲した被災地復興支援、被災者を励ますという「希望を与える」物語の粗製乱造の光景と、その善意の「思い込み」と、私のこの体験と、何か通底するものを感じないだろうか。近代文明は人間中心主義的過ぎた故に、命に対して過ちを犯した。そして人は人間中心主義的な、表層的な正義にすぐ感染する傾向がある。
私が違和感を抱いたこの問題に対する批判の眼差しを、高橋修宏の本論に感じるのはそういう経緯からである。その眼差しを私は石牟礼文学から継承した。
この章でも、あの震災体験が、私を石牟礼文学に、高橋修宏を鈴木六林男俳句に連れ戻した心的状況の共通性を感じる。
私たちの本当の危機は、その視座の欠落故に生じ、数々の不条理をもたらしているという確かな視座が、この六林男論に提示されている。
その震災後詩学の眼差しによって。
四、原初の眼玉
この章で、先述した六林男の俳句が論考されている。
暗闇の目玉濡らさず泳ぐなり 第二句集『谷間の旗』一九五五年
私のこの句の読みについてはすでに述べたので、ここは、高橋修宏論考の要約紹介文ではなく、彼自身の言葉を転記しておこう。
※
人間存在にひそむ動物的とも呼べる生命の危機を孕んだ揺らぎが描き込まれているのではなか。言いかえれば、安易なヒューマニズムの底板を踏み抜いてしまう、荒々しい動物的本能にまで接近してしまう情動と呼びうるものが、「暗闇の目玉」というモチーフの可能性として秘められているのではないだろうか。
※
高橋修宏の「読み」では、先に私が解したような、「暗闇の」の「の」は不可視の状況という表現的な外側に係る「の」ではなく、その真下の「目玉」に係り、「暗闇の目玉」という剥き出しの(安易なヒューマニズムの底板を踏み抜いてしまう)野生性の表現であるとされる。
読者はここで改めて気づくはずだ。対比された兜太の「暗闇俳句」の身体性の肯定感とは、次元を異にしている「生命の危機を孕んだ揺らぎ」表現であることに。
高橋修宏は六林男のもう一つの、
オイディプスの眼玉がここに煮こごれる
を引いて、この「眼玉」と「煮こごれる」に、禁忌を破って「見て」しまった六林男の、晩年の「断念」を読み取り、この章を次の言葉で結んでいる。
※
近代主義的なヒューマニズムの論理では括りきることのできない、原初的な〈眼玉〉の孕むラディカリズムが脈動している気がしてならない。
※
三・一一体験を潜り抜けて、初めて明確に浮上してきた視座、高橋修宏独特の震災後詩学の眼差しがある。
高橋修宏が「編集後記」で示唆した、金子兜太の「暗闇」俳句との、容易に超えることのできない「差」の理由が、ここに明示されている。
五、死後からの眼差し
今を今としてしか生きない経済的人間は、分厚い過去を喪失しているために、その存在自身が限りなく薄っぺらになってゆくしかない。そしてもっとも深刻なのは、「死」という悠久の未来さえ、電子アルゴリズムの中では、「未来予測」という推計可能のことの埒外であることから、存在さえしない。
経済成長神話のただ中にいた日本人は、そんな漂うただの「今」にぷかぷか浮遊する物体と化してしたのだ。津波はすでに押し寄せていた。
人間を実体のある存在という岸に繋ぎ止めることができるのは何か。
それが「死」に他ならない。一瞬の顕現の連続として消滅を続ける「今」に、「死」という未来を張り付ける。「今」という消滅の時間に永遠が宿る。この章で高橋修宏が次のように論述するとき、六林男俳句の永遠性が明確な輪郭をもって浮かび上がる。
※
永遠に孤りのごとし戦傷の痕 『雨の時代』
戦後五十年もたっても、このような一句を書き記さざるをえない六林男にとって「戦後」とは、いかなる時間だったのか。「戦後」という時間を生きるとは、どのようなことだったのか。(略)表現者としての六林男は、まさに死者の眼をもって、言いかえれば〈死後〉としての「戦後」を生きてきたのではなかったのか。
※
戦場で戦友たちの夥しい死を目の当たりにした六林男の精神的「現在」とは、その死者たちにとっての死後である。自分もあのとき死んでいたという実感を宿して戦後を生きる六林男には、それは自分の死後という「今」であり「未来」であり続ける。
※
月の出や死んだ者らと汽車を待つ 『櫻島』
(……)「死んだ者ら」を作者の戦争体験に即して、若くして死んだ戦友たちと捉えることは順当な読み方と言えるだろう。だが、この一句には、そこに止らない大震災などの未来を含めた歴史的なさまざまな「死んだ者ら」の累積さえも、はからずも呼びこんでいることも無視できない。
※
晩年の句集『櫻島』に出現した死後を含む句を取り上げて、高橋修宏は六林男の俳句との出会い直しの旅を続けている。そして自らが向き合った東日本大震災後という「今」の「死後」をそこに発見している。
「無言の死者たち」がいる「詩的な場所=トポス」を。
六、沈黙の痛み
殺された者の視野から我等も消え 『櫻島』
高橋修宏はこの六林男の句と、ハンセン病の療養所で人生を送った女性の所有物だった「太郎」という抱き人形のエピソードとを貫く、とても重要な視座を、考古学者的な筆致で描きだしてゆく。その発見的眼差しでなければ探り当てることは不可能だったような、放置したら埋もれてしまっていたかもしれない過去の大切な水脈を復元する。
高橋修宏は「太郎」と、熊本市現代美術館で二○○二年に開催された企画展で出会っている。企画展のキュレーターを務めた南嶌宏が所有者の女性から借りてきて企画展に出品したものだった。隔離された療養生活の中で子供を持つことが許されなかった夫妻が購入して愛玩し続けた人形だったという。南嶌宏が記した『最後の場所』という書を援用しつつ、高橋修宏は次のように述べている。
※
いわゆる世間と名告るものから存在を消されるように隔離され、「その闇の中で一瞬一瞬の生を辛うじて灯し続けてきた人々」(南嶌)。そのような人々の傍に、つねに寄り添うように共にあった「太郎」という存在と出会ったとき、私の中で六林男のあの一句が、たしかな手触りと衝迫力を伴って、ふたたび立ち現れてきたのである。(略)
この一句が書かれた一九六○年代の日本は、高度経済成長と名付けられた未曾有の欣快事に湧き立っていた時代であった。だが、一方、戦後という時代の意味が風化し忘却されていくなかで、水俣病をはじめとする公害が顕在化し、そしてハンセン病患者の存在をも世間の目から完全に遮断されてゆく過程でもあったのだ。
きっと「我等」が欣快事を享受する時代とは、そのような無数の「太郎」を殺すことに成り立ってきたのだ。だが、目を反らしてはいけない。「太郎」を殺すということは、同時に「吾等」自身の存在が消え去ることであったことを、戦場という極限的な体験を底に沈めた六林男の一句は、そのように私たちに語りかけているのではないか。
※
この高橋修宏の眼差しは、明らかに東日本大震災体験を、深く内面化しえた文学者のものである。
水俣病はもとより、原発事故禍による帰還困難地問題の本質もそこにある。
原発事故後、原発再稼働の是非をめぐる公開ヒアリングの席に、加害企業から一般人を装って送り込まれた社員は、ぶるぶる震える手でマイクを持ち、「この事故によって死者は一名も出てない」という本音を開陳してみせた。その直後、保守政権の総務大臣とやらの女性代議士もまったく同じ言葉をメディア会見で述べている。事故の影響でたくさんの死者が出ているにもかかわらず、原発事故自身による直接的な死者が出ていないことをもって、自分たちの無罪性を言い募ろうとする思考が、たくさんの「太郎」を殺すのだ。
稼働前の原発建設、原発稼働中の原発保守作業員の恒常的被曝など、間接的な被害で命を危うくした無数の人たち、原発事故による過酷な避難行為で命を落とした病気の人たち、農地を不毛の地にされたことに絶望して自死した人など、彼等にとっては無であり、存在しないも同然という姿勢が生み出す、結果としてのジェノサイド(大量虐殺)の上に、この国の戦後経済発展は保証されてきたことが露わになった。
私は小中学生時代に水俣病の原因企業が、水俣病の原因を「風土病説」「米軍不発弾の有害物質の流出説」「漁師達の魚介類偏食説」など、今振り返れば耳を疑うような珍説を、権威ある大学教授、医師、ジャーナリストを使って発表させた振舞いをリアルタイムで見聞してきた。だから、そんな原発事故の加害企業の振舞いに、私はうんざりするような既視感があった。
殺された者の視野から我等も消え
六林男の句は、我等の視野から死者が消されていることを常態として、もっとそれが進行した果てには、その死者と道連れとなって、在るか無いかも不明な、いや無いも同然の我等の行く手の非ザイン的結末がすでに表現として刻まれているのを、高橋修宏は「発見」しているのだ。
ものごとを深く考えようする者にとって、それらのことが可視化されてゆく契機となったのが東日本大震災であった。文学者は虐殺された者たちの「沈黙の痛み」を背負うのは無論のこと、この文明の命という存在の希薄化をこそ表現するときであろう。
高橋修宏はこの章でそう主張しているのだろう。
七、見られることの異和
違和感という感覚上の「違和」ではなく、認識としての「異和」の話である。しかも「見る・見られる」という主客の逆転の話でもなく、その固定的な双方の関係性にさえ揺さぶりをかける、という表現上の認識の可能性への挑戦の話である。
寒鯉や見られてしまい発狂す 『國境』
六林男のこの句を引いて、高橋修宏はこう論考する。
※
(……)そこには〈写生〉と呼ばれる近代俳句の方法との鋭い異和が、あらかじめ孕まれているのだ。〈写生〉という方法や態度においては、あくまでも見る主体となるのは人間であった。さらに、人間が見ることによって、その対象が「発狂」するという過激な変容は、ついになかったはずである。つまり〈写生〉においては、人間からの特権的な眼差しによって、その方法的な立脚点は担保されていたのである。
しかし六林男は、「見られてしまい」の一語を、ひとつの解読不可能性を帯びた表記として句中に置くことによって、〈写生〉の中に、その特権的な眼差しを切断する劇薬と呼ぶべきものを仕掛けたのではなかったか。
※
前章の「沈黙の痛み」で思索された、わたしたちの「主体」の無意識状の危うさの指摘よりも、もっと根源的な六林男の過激な思想性、妥協無き疑いの眼差しの鋭さを、高橋修宏は掘り起こしている。
私たちの視野の外にあるものからの、私たちの生の在り方、認識の在り方に対する挑戦的な揺さぶりである。この後、高橋修宏はジャック・デリダの『動物を追う、私は(動物で)ある』を援用して、「絶対的他者」という概念と、西欧における「見ること」をめぐる特権性=政治性に対する脱構築というテーマに触れて、「この一句こそ、俳句という詩型が達成しうる、ひとつの極限であると同時に、謎と呼ぶしかない何かを現前させているのではないだろうか」と論述している。
六林男の次の言葉を添えて。
※
俳句は省略の文学である。省略とは不要なことをすてることのみでなく、必要なものも削除することである。
(……)切りすて、省略され、削除されたものに支えられた、残ったものの強靭さを知るものでなければ、リアリズムは糞の詰まった陥し穴におちこんでいくだろう。
「リアリズム小感」
※
不要なものの自明性など相手にしていない。
必要性という認識の根拠すら疑っている。
必要という概念は、そのことの自明性を前提とする。この「自明性」という合「目的」的な表現自身が、非文学的なものだ。あらかじめ、それが何か判っているものや、ことを語るのは指示表出という理屈の言葉だ。自己表出である文学は、解けないない永遠の謎を問いつづける行為の中にしか生まれない。
ここにも、震災後言論の、表層的過ぎる動向への、鋭い批判の眼差しがある。
同時に、前章の人間中心主義の死角をさらに深く突く論考である。
八、叛意としての笑い
この章は六林男の俳句表現にある反逆的諧謔の調べについて論考されている。引かれているのは次の句だ。
僕ですか死因調査解剖機関監察医 『谷間の旗』
傷口です右や左の旦那さま
一句目について高橋修宏は「敗戦後、グロテスクな死体と化した日本の〈国体〉なるものへのアイロニーさえも漂わせているのではないだろうか」と書き添えている。
二句目については、「否応なく戦争を体験させられた一人ひとりの生活感情に刻まれた『傷口』であり、敗戦国となった日本という国の『傷口』ではないのか。敗戦後風景の通俗的なイメージを駆使しながらも、読む者が「吹き出し」、そして「ふざけるな」と呆れ返る俳句表現の中に、二重にも三重にも、六林男ならではの叛意としての笑いとアイロニーの毒が仕掛けられている」と述べている。
俳句を含め現代文学者たちは一応に、そしてあまりにも単純に真面目過ぎないか。まともに論評にも値しないものを、しかつめらしく論評しても虚しくなるとき、私たちには笑いという武器がある。小説で言えば高橋源一郎の『恋する原発』のように、原発問題とエロ映画の企画制作を企む者たちの物語を意図的に混在させるような諧謔精神が必要ではないか。高橋修宏がいう「敗戦後、グロテスクな死体と化した日本の〈国体〉なるもの」という言葉が、ことの本質を串刺しにする。
この章は、第一章の「道化としての六林男」における「笑い」の考察と深く呼応する章である。
九、ひとりの音楽へ
この章で引かれている六林男の句は次の通り。
池涸れる深夜 音楽をどうぞ 『國境』
髪洗う敵のちかづく音楽として 『王國』
おんがくのさかのぼりゆく天の川 『一九九九年九月』
俳句にも「定型」によって調律されることを拒否する無季自由律俳句というものがあるように、現代音楽にも調性のない雑音のような音楽がある。雑音のような、と言ったのは、調性音楽しか音楽として聴くことができない耳には、という意味である。
では現代雑音音楽は何を表現しようとしているのか。私たちの身体の持つ原初的音楽性、自然界のあらゆる現象、人の営みの複雑化する現象に生じる音楽性の、剥き出しの原初的姿に向き合おうとしているのだ。
この章で高橋修宏は日本現代音楽の作曲家、武満徹の著書を援用し、また坂本龍一の試みを取り上げて思索を深めてゆく。
津波に流されたビアノから直接的に音を取り出した、坂本の「津波ピアノ」をめぐって、高橋修宏は次のように論考する。
※
(・・・・・・)自然の律動と言うべき音が、けっして安定したものでも、やすらぎに満ちたものでもいなことを突きつけてくるのだ。
おそらく坂本の「津波ピアノ」は、単なる励ましでも、慰撫でも、もちろん癒しを与えるものでもない。今日の時代の流れの中で、やがては遠のき風化する大震災の記憶を、たえず召喚させつづけるモニュメンタルな音の装置であり、そして、あの大震災の記憶の前に、聴く者を一人ひとり立たせるものなのであろう。
※
坂本龍一の「津波ピアノ」ではなく、本稿における高橋修宏の「津波ピアノ」には、不慮の災害に遭い、世間的には「無用のもの」として、私たちの視線の外に「隔離」され、打ち棄てられるしかなかった物という「モニュメンタルな」な含意が込められている。
そんな隔離または廃棄された「物」から、どんな「存在論的」な「音」が取り出せるのか、文学は問われているのではないか、という含意でもある。そのようなものとして、高橋修宏は冒頭に引いた六林男の三句を詠み込んでいる。
そしてまた、「津波ピアノ」は、本論第六章「沈黙の痛み」における「太郎」ではないかと、私の思いを導きもするのだ。
その音楽は決して聴くことの叶わぬ「太郎」の声そのものでもあるのではないか。
十、王とは誰か
平成時代も中期から後期にかけて、俳句界では金子兜太を起点としていくつかの俳句団体が「アミニズム」特集をするなど、にわかに、それが恰も俳句の「新傾向」の思想とか主題になるかのような盛況をみせたことがあった。兜太のアミニズム推奨は東日本大震災より以前からだが、俳句的世間がそれに注目して盛り上がったのは、明らかに東日本大震災後ではなかったか。震災後、それまで無関心だった人まで挙って原発批判を声高に唱えるようになり、その熱狂の果てに担ぎ出されてきたのが「自然に還れ」というスローガン的思考の末のアミニズム熱だった。
にわか原発批判人、にわかアミニズムかぶれたちのお祭り。そんな一時的な熱狂など、すぐ冷め切ってしまうのは必定だった。
そのことに違和感を抱いた俳人がどれほどいるだろうか。
私の鑑賞方法が正しければ、という仮定の上でのことだが、本章で高橋修宏はその表層的すぎる「アミニズム」観を批判しているのだと思われる。
むろん高橋修宏はそれを直接的に論うことはしない。
鈴木六林男の句集『王國』所収の群作「王國」の、石油コンビナートを題材にした不思議な俳句を取り上げて論じている。
冬の日息をしているパイプの森 『王國』
君はどこの油音立てて走る
油送車の犯されている哀しい形
司祭者よ走りつづける陽気な油
爆発の途中の油ここに待つ
油槽原女神の声は夜する
凍る夜の塩化眠らぬエチルやビニル
氷雨の夜こんなところに芳香族
恋愛の貪欲のパイプ濡れている
高橋修宏はこれらの句を引いて、次のように述べる。
※
いま、「王國」(句集『王國』一九七八年所収)という象徴的なタイトルの群作を読み返して再認識されるのは、それらの作品の中で「油」たちが人間よりはるかに生きいきと躍動していることである。(略)擬人的に形象化された「油」たちは、ほとんど人影のない世界の主役となっているような印象だ。さらに「芳香族」と名づけられた彼らは、貪欲なまで恋愛(性愛)に耽り、子を生み、孫を生む。それは、まさに人間の営みのようでありながら、どこか不吉な聖性さえ帯びている。
※
このくだりを読みながら、私は高校生時代までを過ごした水俣で、チッソ水俣工場の夜景を丘の上から見下ろしたときのことを思い出した。海に有機水銀混じりの毒を垂れ流して、「水俣病」を引き起こした工場、石油精製過程を持つ塩化ビニールや多様な化学肥料を生産した工場の夜景も、このような不夜城の様相を呈するものだった。そんな工場を題材に文学作品が書かれるとき、通俗小説家たちの作品(例、水上勉『海の牙』)のように、人間を疎外するような工場の側面が描かれ、正義を振りかざした告発調の、底の浅い表現に足元を救われた表現をしてしまうのではないか。
六林男のこの石油コンビナートは、高橋修宏が分析してみせたように、そのような通俗的な表現とは一線を画している。
驚くべきことは、高橋のその筆致が、六林男俳句に根源的なアニミズムを見出していることだ。
高橋修宏は、一九五〇年代より戦後日本の写真表現を牽引しつづけたという重松照明の石油コンビナートの写真集のインパクト、六林男が好んだロバート・キャパの写真、最後は二〇一五年の現代俳句全国大会での中沢新一の記念講演の言葉を引いて、次のように述べている。
※
(……)そもそもアニミズムとは、「物体とアニマ(魂)は別もので、物体中にアニマが入り込むことによって、生命をもって、活動しはじめる」という二元論的な思考ではない、と断言する。本源的なアミニズムによれば、宇宙とはあまねく動くものであり、「大いなる〈動くもの=スピリット〉があって、それが立ち止まるところに存在があらわれ、(……)それぞれの存在者は生物も無生物でも、もともと一体」である、と語られている。(以下略)
※
この中沢新一が説くような宇宙生成以来の時間の流れの中での、一元論的アミニズム観と通底するものを、先にあげた六林男の群作俳句に見出しているのである。
物も生きものも、魂も、宇宙的生成物としての存在であって、動的様態から「立ち止まる」通過点において、それぞれの様態をその時々に示現するものに他ならない。そこから詩念を立ち上げてこその文学ではないか、と問うているのだ。正義を振りかざして原発批判をすることや、自然に還れと俄かアミニズム熱狂症に罹患したような表現の、非文学性を問うているのだ。多様な存在が互いに害を為す事態が生じていたとしても、どちらかの正義を言い立てる言説には根拠がない。分かり易い大衆好みの一時的な熱狂に過ぎない。
石牟礼道子の言説が私たちの胸を刺すのは、「水俣病」という大量無差別虐殺、あるいは未遂事件を告発的にではなく、文明の軋みのただ中ある、漁師たちの、それこそアミニズムを体現しているような命の営みの輝きを、発見的共感、巫女的憑依の文体で、初めて描き出してみせたからだ。
その「存在」としての輝きは、六林男俳句の「油」たちの輝きと、基本的には等価であり、そのような様態として、そこに「存在」していることを描き出しているのだ。この文学的な深い視座は、なかなか俳句的世間のよく理解するところではないだろう。
ここにも三・一一を潜り抜けた高橋修宏の深い思索がある。
十一、星雲となる群作
この章は六林男俳句に頻出する「群作」に光を当てている。
「連作」ではなく、何故「群作」か。
まず「連作」の方の俳句表現史を高橋修宏は次のように総括する。
※
ところで俳句における「連作」という方法は、一九二七年に水原秋桜子によって発表された「筑波山縁起」五句が嚆矢とされる。これが短歌の連作方式を応用した、設計図式と呼ばれる「連作」の始まりだ。その一方、山口誓子はあらかじめ設計図を必要とする方法に対して、一句一句の作品の配列に主眼を置いたモンタージュ式を主張した。その中で誓子は、一句の独立性を重んじながらも、群としての「感情の流れ」を重視する考えをとり、それまでの俳句表現において不可能とされていた散文的な主題性を打ち出すことを可能にしたのである。このような流れに沿えば、明らかに六林男の「群作」という方法はモンタージュ式を踏まえたものであることが了解できる。
※
こう述べて、六林男俳句には「連作」俳句と袂を分かつという彼自身の矜持が込められている、と見ている。
第三句集『第三突堤』の「吹田操作場」六十句、「大王三崎」五十四句、第六句集『王國』の「王國」七十七句、第八句集『悪霊』の「十三字と季語によるレクイエム」五十句余りに至る「群作」、そして六林男死去の半年前に発表した「近江」三十二句(「俳句」6月号、二〇〇四年)を六林男俳句の「到達点、集大成」(宗田安正)であり、未踏の俳句の可能性さえも予感させるとしている。
その可能性の一つが六林男の「季語情況論」であるとしている。高橋修宏はこう述べる。
※
(……)季語を自在に入れ換え、その作品群をより明確なイメージへと導くための装置として季語を活用する六林男の「季語情況論」と言われる方法論。それこそが有季定型という擬制の共同性を脱構築し、それら六林男の「群作」を作品内部からも保証するもののひとつであったことは確かである。
※
すでに単なる俳句表現上の約束事、措辞と化していた伝統俳句派的な季語観と一線を画す視座である。
本稿の第二章「生き続ける遺書」の「2 ロマン/季語/安吾」の節で、六林男の戦場俳句の中にある有季定型句を取り上げ、死者の眼差しと共にある「詩的な場所=トポス」を論じ、「はからずも季語のもつ虚構性が、六林男の戦場俳句におけるロマン性を支え、その作品の詩的水位を保証しえたのである」と指摘したときの「季語」の「虚構性」についての論点と、深く呼応している。「季語」を「虚構」と視る視座がなければ、六林男の「季語情況論」に対する評価は成立しない。
そこからさらに高橋修宏は一歩踏み込んで、俳句表現の可能性について論を展開しようとしている。
それが晩年の六林男俳句の「近江」という「群作」の〈星雲説〉である。高橋修宏はこう論述する。
※
(……)最晩年の「近江」に至って、一句一句の俳句における協約は流動化し、「全体」としての世界の出現は留保されたまま、固定的な物語を語ることはないのだ。
言いかえれば「近江」という「群作」は、読者のレベルによって様々に読むことが可能なテキストとして開かれているのである。それまでの「群作」が「全体」として世界を描き出す、いわば静的な〈星座〉であるのに対し、「近江」は読者によって、たえず変動しづつける〈星雲〉と言ってもよいだろう。ここに至って六林男の「群作」という方法は、まさしく未踏の俳句の可能性を開くものであったことは確かだがその試みは死によって中断したままになってしまった。
※
この後、高橋修宏は写真家の東松照明の「組写真から群写真」という表現についての考え、写真家による明示的な一つのテーマによる表現ではなく、「名付けられる以前さまざまな現実の対応物として、写真の鑑賞者の前に「投げだされる」、つまり、鑑賞者の数だけの多様な受け止め方を可能にする表現についての視座を援用して、この章を次の言葉で結んでいる。
※
(……)最晩年における六林男の「群作」もまた、東松照明が、その先に企んだマンダラのような多層性、多義性をあらかじめ含みこんだ〈星雲〉を目指したものであったのかもしれない。
※
この章はこれまでの三・一一以降の詩学という本論の主題から、一見、離れたテーマにみえる。六林男の「群作」俳句を評することで、高橋修宏は何を述べようとしているのだろうか。
この章を読みながら、その論考の主旨を受け止めつつ、私は自分が日頃、批判的に考えている俳句界における通常の「句集」のあり方の「非文学性」について思いを馳せていた。少し遠回りなるが、そのことを先に述べておきたい。
今出版されている句集の編まれ方は、ある一定期間、俳人が詠んできた「境涯詠」的な作品を、時間軸に沿ってそのまま編集したものが大半を占める。
そんな句集の編まれ方の常識自身が「非文学的」だと常日頃感じていた。所属する「小熊座」で担当している「俳句時評」でも、そのことを数度に亙って論じたことがある。そのことを思い出したのは、本章の高橋修宏の次の文章に触れたせいである。
「俳句表現において不可能とされていた散文的な主題性を打ち出すことを可能にした」と高橋修宏がいうときの「散文的な主題性」という言葉は、私が俳句論を書くときに「普通」に使っている文学的主題という言葉の意味に極めて近いと感じる。
だが、私には「普通」の論述用語であっても、俳句界では意味不明のようで、「何を指しているのか不明」と評されることが屡々あって驚かされてきた。
文学的主題とは言葉通り、文学的主題である。
俳句界では、この言葉によく似ている「モチーフ」とか「題材」という言葉しか通用しないようなのだ。
だが「モチーフ」「題材」と文学的主題はまったく別のものだ。
いちばんの違いは、「モチーフ」「題材」はそれを表現上使用するか、表現の目的とすることが明示的であるが、文学的主題はそれを表現することを目的とはしない非明示的なものである、という明確な相違だ。
創作の時点で作者は出来上がった作品が、どんな文学的主題を孕むものとなるかを知らない、謎を含んだ、いや、その謎を作者が問うている深淵なものだ。
何を表現するかということが予め解っている合〈目的〉的な作品は、消費材的な娯楽作品でしかない。
この章の論考に沿って換言すれば、誓子までの「連作」はこの合〈目的〉的な俳句表現論に感じられる。
六林男俳句には「連作」俳句と袂を分かつという彼自身の矜持が込められている、と高橋修宏が述べているのは、六林男俳句が、「モチーフ」「題材」というレベルで「連作」表現をしたのではなく、純粋に文学的主題の表現という文学作品として、俳句を書きたいと思っていたからだと、述べているように、私には感じられる。
事実、六林男の俳句は、作者自身にも、その俳句がどんな文学的主題を孕みうるのか把握されていない、ということが感じられる俳句である。
誰かによってその文学的主題が、それぞれに発見されるという、文学的な通常の作者対読者のスリリングな関係が成り立つ作品である。
ということは、そのとき初めて俳句というものが、普遍性を持つ文学表現となりうるということを意味しているのである。
私が使っている文学的主題とはそういう意味であり、この章の高橋修宏の六林男群作俳句論も、そのような主旨ではないかと読んだのである。
そして、ここに至って、この章の主題も、高橋修宏にとっては三・一一以降の詩学という本論の主題に沿ったものであったことに気づかされる。何故か。
震災直後、大量に詠まれた、津波被害、原発事故禍を「モチーフ」や「題材」として、それを表現することを「目的」として詠まれた俳句は、真に震災詠になど、なりうる訳がない。表現できるのは和歌以来の伝統的な喪失感、無常観であり、悲しみ、嘆き、励ましなどという流行歌レベルの消費歌謡の域を出ない作品しか生まれない。中にはそのレベルを超えて、あの体験から独自の文学的主題の表現に立ち向かった俳人もいた。だがそれは極めて少数だった。
句集の境涯詠的、順次的な編まれ方への批判も含めて、このような批判意識を持ちながら、私は「では、そうではない、真に文学的な俳句表現とその可能性とは何か」について、具体的に論述するには至っていなかった。
だが、本章で高橋修宏はその可能性を六林男の「星雲」としての「群作」に見出して、具体的に提言しているのである。これは驚くべき視座だ。
高橋修宏は六林男の、主題の明示性を拒否する豊かな表現方法に、文学的可能性を見出しているのだ。題材、モチーフ自身を多様に交差させて、読者に多様な感慨を引き起こさせる謎を含んだ表現、という意味での文学的主題の表現に成功していると指摘している。
優れた純文学作品を瞥見すれば、同様の表現のされ方をしていることに気が付く。リアリティのある多様なエピソードが、一点向かって輻輳し、未完結の完結というような終わり方をする物語が紡がれることで、読者の心に一言では言い表せない複雑で深い感慨を与えることに成功している名作が多数存在する。石牟礼道子の文学作品もその一つだろう。
こ の章について、そんな思いを巡らせて初めて、高橋修宏がここに籠めた本当の主旨が見えてくるような気がしないだろうか。
十二、六林男の家
この最終章をこと細かに紹介するのは止めておこう。
この章の主題に関わると思われる部分を次に摘録する。
※
このように六林男の俳句を詠んでゆくと、彼の作品に表象された「家」とは、単に住まいとしての「家」であることを超えて、自らの記憶や生活習慣はもとより、まさしく安息という言葉がふさわしい場所であり、自らを育む拠点と呼ぶべき存在であったことが浮かびあがってくる。このような場所こそ、六林男が自らの表現思想を語る際にしばしば口にする、愛という言葉が生まれるトポスと考えてよいのかもしれない。
※
考えてみれば、先に掲げた涅槃のイメージを彷彿とさせる「寝ているや」という、どこか無防備に見える身振りこそ、そんな記憶の場所にふさわしいものである。このような「寝ている」という身振りを含んだ六林男の俳句に一貫して通底するものは、そんな無防備な振るまいを許容してくれる安息という言葉がふさわしい「家」であり、自らの精神を育みつづける神話的な世界のイメージが、つねに、その背後に確かな手ざわりを伴って感じさせるのだ。
※
裏口に冬田のつづく遊び人 『國境』
寝ているや家を出てゆく春の道 『王國』
二人して何を作らず昼寝覚め 『雨の時代』
※
しかし、あの大震災後、二〇一九年の今日でも、いまだ「寝ているや」と、ゆったりとした充足のなかで呟くことのできない二万人を超える人々がいるのだ。そのことを、終生にわたり愛という言葉にこだわりつづけてきた六林男が、もし生きていたならば、どのように見たのだろうか。
※
これが本論考、結びの言葉である。
震災詠というものをしなかった詩人にして俳人、高橋修宏が沈思黙考の末に書いた、いわば「震災詠代わりの震災後表現論」であると言えるだろう。
まだ誰も獲得していない深度と強度を備えた、震災後詩学の眼差しがここにある。
このような視座を持つ高橋修宏のような論考を、私は待っていたのだと思う。
私の震災詠批判の視座が、この高橋修宏の「六林男をめぐる十二の章」に出会ったことで、より鮮明にされてゆく思いがした。
これから大切なことは、震災詠批判よりも、震災後の表現の在り方の批評だろう。
私は社会批判という形而下の事象をも含む地平から論考を立ち上げて、表現論に向かう。気を付けないと、その論考の過程で「正義」「正論」に傾く危うさがある論法である。そのことに自覚的でありたいと思う。
高橋修宏の論考は、純粋に詩学的な眼差しに徹している。六林男俳句の表現の在り方を解題する方法で、震災詠の盲点を鮮やかに指し示している。
高橋修宏はその詩学的視座をどうやって、自分の内面に育み得たのか、これから検証してゆきたい。
それこそが、俳句表現の明日を拓く可能性についての論考となる、確かな予感がある。 ―了
