
大きな成果は、小さな実績の積み重ね
ONE JAPANの濱松誠(マック)さんの講義だった。
マックさんはONE JAPANの前に、One Panasonicを実行した。
いまのパナソニックは2011年、旧パナソニックとパナソニック電工と三洋電機とが合わさってできた(パナソニックが2社を完全子会社化)。
文化が違う3社をまとめるために、「One Panasonic」のスローガンのもと、
社長まで巻き込んで活動をして成果を出した。
その経験から、ONE JAPANを友人と共同で立ち上げた。
その大きな実績は、実は少人数の飲み会から始まった。
同期との飲み会、新入社員との飲み会、ミドル層との飲み会、
それごとに出てきた意見や抱負や不満をメモって、
経営層に届けて、One Panasonic活動をコミュニティ化した。
マックさんは、「挑戦の文化をつくる八策」を示した。
・「出る杭」から「出過ぎた杭」へ
・出る杭の輪を広げる
・行動の連打
・大きな実績と小さな実績
・本業に還元
・絶対的な支援者、パトロンをつくる
・諦めずに継続する
・外科治療(制度)と内科治療(対話)の併存
One Panasonicを成し遂げるまで、
10年かかった、という。
それはずっと、小さな実績の積み重ねだった、という。
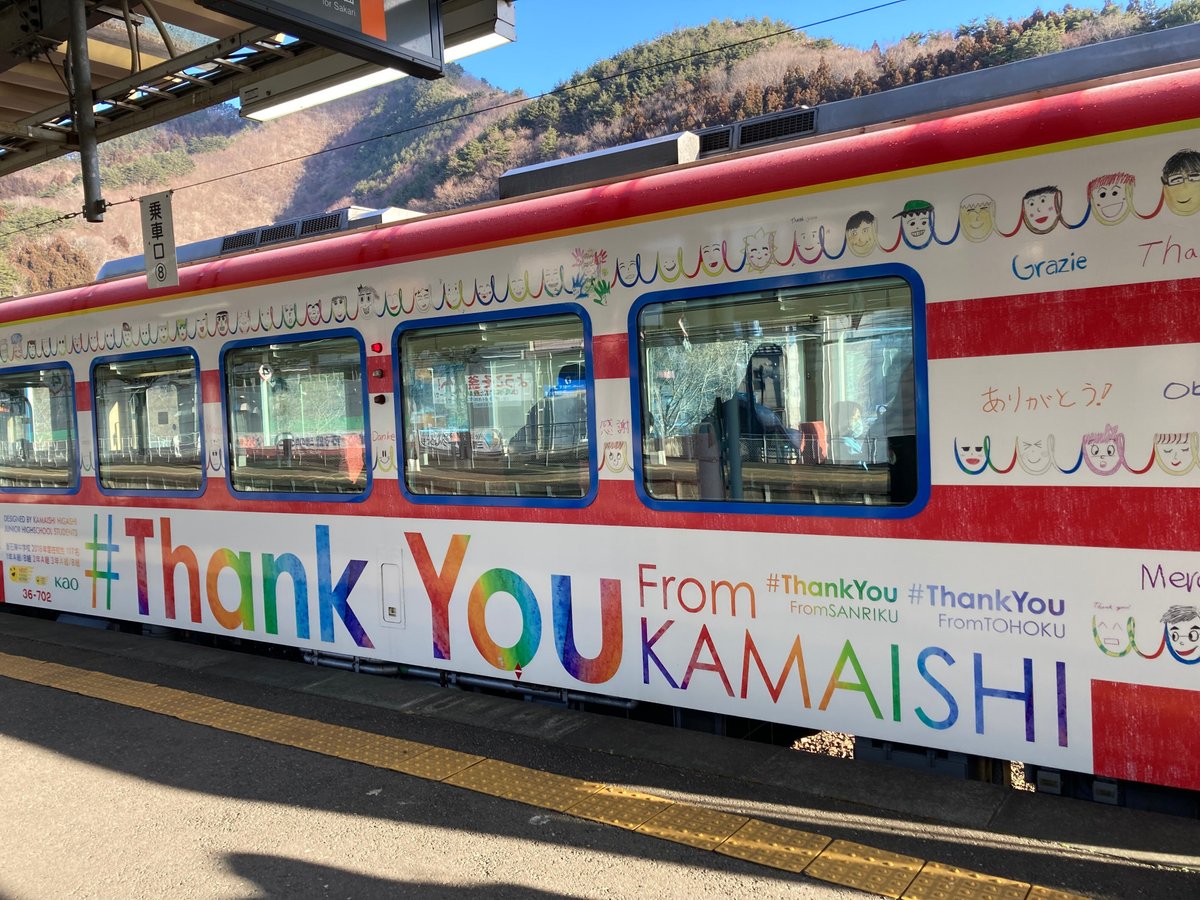
地方創生も同じだ。
「人口が減っても、地域は簡単にはなくならない。だが、小ネタが尽きると、あっという間に地域は衰退する」
小ネタとは「ちょっとしたきっかけ(材料、仕掛け)と、そこから生まれつつあるささやかな兆し(証拠)」と定義されている。
そこに住む人々の毎日の営み、でもある。
これに対し、大ネタというのもある。
大ネタは、有名な歴史、文化、産業、自然などを頼りに、経済の活性化や関係人口の拡大、あわよくば定住人口の増加を目指す。地方創生に向けた行政は、得てしてその志向が強くなる。
だが、大ネタを不必要だと切り捨てることもしない。
計画と目的が明確にされ、予算と大人数が動く大ネタも小ネタと同時に必要不可欠である。
ただしそれは、あくまでも小ネタと小ネタと小ネタを紡ぎ合わせたものである。(同p395を参照)
マックさんの「八策」でも、
大きな実績よりも小さな実績
とはしてない。
大きな実績と小さな実績
である。
そしてその大きな実績は、小さな実績の積み重ねだった、
と繰り返して書いておく。
