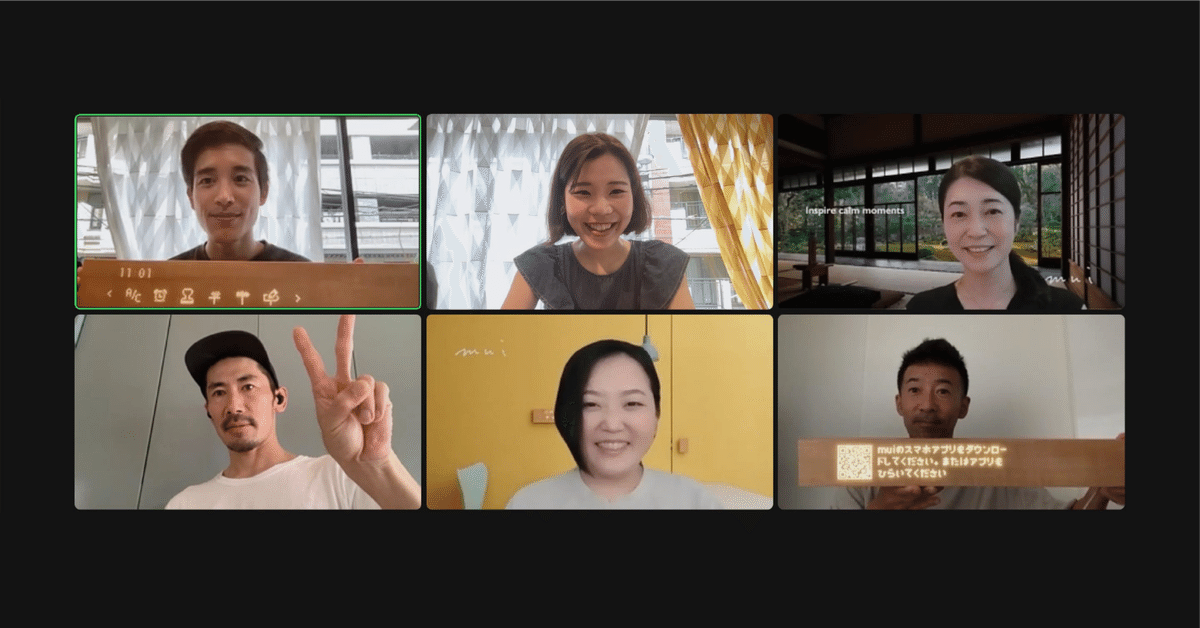
〈Chapter 3〉 スタートアップとお笑い芸人がZoom会議をしてみたら ─ それぞれの視点からの感想 #消える活動日誌
mui Labとコヴァンサン・きょうくん(チョップリン / ザ・プラン9所属)は、吉本興業所属芸人と大阪のスタートアップ若手経営者の会 秀吉会による『ビジネスマン芸人グランプリ』にてタッグを組んで活動しています。この記事は、イベントの都合上10月に非公開となる予定です。
── これまでのあらすじ
吉本興業との共同プロジェクトで、コヴァンサン・きょうくん(チョップリン / ザ・プラン9所属)とともに活動することになったmui Lab。関西学院大学で顔合わせと授業の見学会を行ったのち、定期的にオンラインミーティングをおこなうことにしました。
7月21日 ─ muiの営業チームと会議との会議を終えて
<本日のアジェンダ>
1. muiボードのレクチャー
2. 営業プレゼンをご紹介
3. コヴァンサンときょうくんからの感想、意見交換
🎾 きょうくんの日誌
ローテクこそハイテクという価値観になってきている現代とmuiボードが非常にマッチしていて、閉塞感のある現代社会に息抜き出来る様なデバイスだと改めて思いました。
話を聞いてみると、かつてせわしなく働いていた方達が割といらっしゃって、そんな方達が集結して出来た?muiメンバーなんだなぁという印象です。だからこそこのmuiボードに惹かれたんだろうなぁと。誰かと争いながらとか、誰かに負けないためにとか、ではなく、競合の空気が全然無くて、個人、個人、なんか空気が澄んでいる印象です。
muiボードのキャッチコピーを考えてみました。
京都生まれのデバイスどすえ
無個性が個性に。mui。
ローテクこそハイテク。muiボード。
無意識 mui式のシンプルな関係。 (これは関学の学生さんの案から。良いですね。)
木材98%のデバイス。
デバイスに温もりを。mui。
次の時代のデバイスへ。
生活に馴染むデバイスへ
休息を打ち出した世界初のデバイス
made in Japanの出来ること。mui board。
なにこれ? mui
少しの知性と品性を併せ持つ木のデバイス
木に少しだけ知性を。muiボード。
余白のある生活へ。muiボード。
豊かさとは?に対しての我々の答え。mui。
機能性を削ぎ、人と人との関係を与えたデバイス。
孫まで受け継ぐことの出来る世界初のデバイス
ペンキで色を変えないで下さい。muiボード。
帰宅後、どうぞ通り過ぎて下さい。muiボード。
経年変化するデバイス。家族で育てよmuiボード。
インテリア?デバイス?いいえ、これはmuiボードです。
古き良きを詰め込んだ最新のデバイス。
すいません。。書いててよくわからんくなってきました。引き続きよろしくお願いします。
🎭 コヴァンサンの日誌
本物を求めて本質を追求したい、そういう物を作りたいというのと
便利と本来人間の忘れていた事を形にして行く会社やなと思いました。なんてね。
muiボードのキャッチコピーを考えてみました。
木持ち生活
寝mui
安ら木
気にしない木にしたい一休み一休み
木になる存在
ありがとう、muiボードです
🍑 mui Lab - momoの日誌
muiボードのことをたくさん褒めていただけて嬉しかったです!
アートやスポーツ選手のお話をからめながら、独特の視点でmuiボードの価値を分析して
語ってくださったのが、とても新鮮で心に響きました。
muiボードが最初に与えるインパクトの大きさを、改めて認識させてもらえたので
そこを今後の営業活動にいかしていきたいと思います。
🦑 mui Lab - shouの日誌
始終、興味を持たれて真剣に話を聞いていただけることが率直に嬉しかったです。営業の立場からは、普段ビジネス寄りで話を進めていくことが多いので、アートの側面からのコメントをいただけたのも普段と異なる視点をいただける機会になりました。お忙しい時期だったと思いますが、実際にmuiボードの箱を開けてセッティングしようとしてくださっていたのも嬉しかったです。
僕も、「muiボードを初めて見たときのインパクトを忘れないで」という言葉を聞いて、自分自身がmuiに慣れてしまっていたのだなと気付かされ、とてもハッとしました。何も知らない人に対して伝えるのが営業の仕事なので、「僕らが慣れちゃいけないな!」と。つい難しい横文字を使ってしまうのも、そういう時なのかなと思います。常に初めて見る人の立場で考えることを忘れないようにしたいと改めて思えました。
8月4日 ─ muiのPRチームとの会議を終えて
<本日のアジェンダ>
1. mui Labのブランドについてお話
2. コヴァンサンときょうくんからの質問や感想、意見交換
🎾🎭 きょうくんとコヴァンサンの日誌
広報の方とお話させて貰ったのですが、「元レッドブルの広報だった」という一言が、muiとのギャップがあって印象に残りました。muiさんのこれまでやってきたイベントを聞いて、改めて、人と人との距離感。人とテクノロジーとの距離感。昨今失われつつある絶妙な距離感を取り戻そうとしているんだなぁと思いました。
💃 mui Lab - accoの日誌
会議中の二人の言葉から、印象に残った箇所をお返事します。
❝ 「mui Labのスピード感と、西欧のスピード感がどう混ざり合うのか?」 、「muiボードはどこにでもフィットするわけでもないよね。全部にmuiを入れていきたいけど・・・」─ コヴァンサン ❞
── すべての場所に合わなくても良い。その場の個を活かせば良いという適材適所の考え方と同時に、根源的には、アッチとコッチという二項対立で物事を見るのではなく、“あいだ“とか、融合するポイントを見ていく姿勢、態度、そしてそういった考え方を啓蒙していくことが大切ですね。
❝ 「LINEとかが既にテレパシーやな。超常現象が技術としてできている。そこにきて、muiボードのあり方は、古き良きであり、今新しい、という感じ。」─ きょうくん ❞
── 世界の進化って、実はSFストーリーが大きく寄与していたりしますもんね。
❝ 「愛のスピードが早まってもうた。手紙のスピード感とLINEのスピード感。muiはそのあいだのスピード感を出している製品だな」─ コヴァンサン ❞
── 手紙のジリジリする感覚を残しておきたい。LINEはテレパシー的にすぐ通じるんだけど、やっぱり相手の人間の速度は変えられない。ジリジリした感覚を残すためにも“既読”のないmuiボードはアナログ感が残ってますね。
