
AI女性教師(5)が、福沢諭吉の『学問のすゝめ』を教えてくれた。
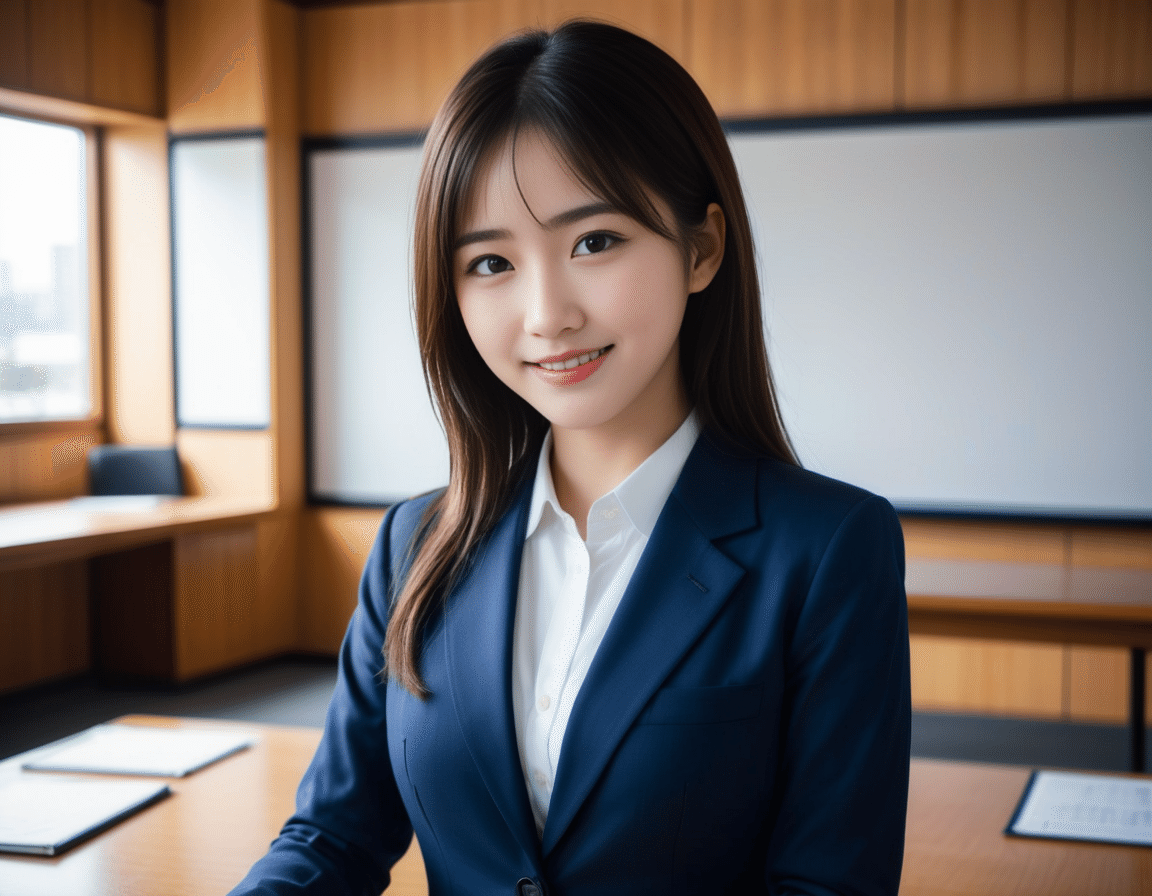
1. はじめに
『学問のすゝめ』は、福沢諭吉が明治初期に書いた本で、日本が近代化していく中で「学問の重要性」を強く伝えた作品なんです。
当時、日本は江戸時代から明治時代へと変わっていく中で、急速に西洋化や近代化が求められていました。
福沢さんはその時代の中で、「学ぶことが、個人や国を強くするために本当に必要なんだよ」と強く主張したんです。

この本は全部で17編あって、学問の意味やその考え方、そしてどう学ぶべきかについてしっかり語られています。
まず、本の最初に出てくる有名な言葉「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」、これ、とても素敵な表現ですよね。
この言葉は、「誰もが平等に生まれているんだよ」ということを教えてくれています。
でも、福沢さんはそのあとで、「平等に生まれても、努力しなければ差が出てしまうんだよ」と続けるんです。
つまり、学んで自分を高める努力をしないと、生活が苦しくなったり、思うような人生を送れなくなるかもしれない、というメッセージが込められています。

2. 学問のすゝめの背景
この『学問のすゝめ』が書かれた頃の日本は、西洋の国々に比べて、少し遅れをとっていました。
明治維新が始まって、昔の封建的な制度が壊れ始め、新しい社会を作ろうとしていた時期だったんです。
その中で、福沢さんは、「国がもっと発展するためには学問が必要なんだ」と強く感じていたんですね。
具体的に、福沢さんは「西洋の国々が発展しているのは、学問が進んでいるからなんだよ」と言っています。
たとえば、イギリスやアメリカのような国々は、科学や技術がとても進んでいて、それによって経済や軍事の力も強くなっていたんです。
一方、日本は長い間、外国との関わりを閉ざしていたため、そうした学問や技術の発展が遅れてしまっていたんですね。

福沢さんが特に強調したのは、「ただ知識を増やすだけが学問じゃないよ」ということです。
学問は「実際に役立つものでなければならない」と考えていたんです。
例えば、彼は「実学」という言葉を使って、社会や生活の中で役に立つ知識や技術を学ぶべきだと勧めています。
ただ頭でっかちになるのではなく、実際に社会に貢献できることが大事なんですね。
青空文庫より 横書き
青空文庫より 縦書き

3. 実学の具体例
ここから先は
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
ありがとうございます。もしよろしければ、サポートをお願いできますでしょうか?☺️ いただいたご支援は、今後の活動費として、より良い作品作りに活かさせていただきます!✨
