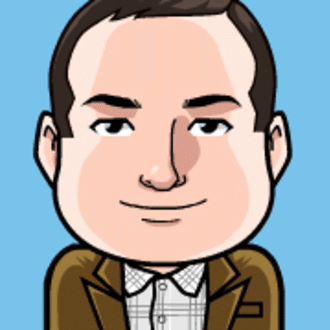幕末三舟
4月14日は、『オレンジデー』(二人の愛を確かにする日)だそうです。
オレンジが、【花嫁の喜び】という花言葉を持っているからだそうです。
そうだ。女房殿にオレンジのスイーツを買って帰ろう。
で、もう一つが、『タイタニックの日』ですね。
明治45年(1912年)に、北大西洋ニューファントランド沖で氷山に激突して沈没。
多数の犠牲者が出た日です。
船で思い出したのが、幕末三舟です。
最初に浮かんだ人物の名前は、高橋泥舟です。
次が、山岡鉄舟ですね。
幕末三舟の中で、最も有名な人物といえば、勝海舟ですが、なぜか、上記の二人の方が強く印象に残っています。
勝海舟は、司馬遼太郎先生の小説『竜馬がゆく』で有名になった坂本龍馬が師として仰いだ人物です。
江戸の無血開城で西郷隆盛との談判も有名です。
勝海舟の活躍は、人口に膾炙されていますが、高橋泥舟や山岡鉄舟(鉄舟の方は、まだ知られているでしょうね・・・) については、意外と知られていないなぁ、と寂しく思っています。
高橋泥舟や山岡鉄舟は、武士と呼ぶにふさわしい人物ですし、特に山岡鉄舟は、実際に面談した西郷隆盛からも称賛されている人物です。
ということで、この二人について、エピソードを少々。
(勝海舟は、エピソードがありすぎますし、有名ですので割愛ということで・・・)
浮かんだ方ではないですが、先に山岡鉄舟から。
山岡鉄舟は、本名が小野高歩。
通り名が、鉄太郎になります。
山岡の苗字は、忍心流槍術師範の山岡静山が急死した際、静山の弟の高橋泥舟は、母方の高橋家を継いでいたため、静山の妹・英子の婿養子として迎え入れられたことで得た苗字になります。
鉄舟とは、居士号で、出家信者が使う号ですね。
鉄舟は、武術(剣や槍)の達人で、禅にも通じ、書道も一流と文武両道の人です。現代の日本剣道の基礎を作った人物で、今なお剣道界では、山岡鉄舟に私淑する剣道家が多いと言います。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yamaoka_Tessyu.jpg?uselang=ja
江戸へ向けて進軍してくる新政府軍に対する徳川慶喜の使者として、西郷隆盛に会いに行った人物です。
徳川慶喜は、高橋泥舟を使者として向かわせようとしましたが、泥舟は、慶喜が朝敵扱いとなり、鳥羽伏見から逃走してきたこともあって、身辺が騒がしいことを危惧し、慶喜の警護に留まります。
代わりに、義弟にあたる山岡鉄舟に全てを委ねます。
この義兄弟は、どちらも剛毅かつ誠実な人柄でして、お互いに全幅の信頼を置いていたことが知られています。
慶喜の命を受けた鉄舟は、陸軍総裁・勝海舟と面談。
勝は、鉄舟の男ぶりを見て、信頼に値するとして全面的に協力を行ないます。
鉄舟は、新政府軍の指揮を執っている西郷隆盛に会うため、駿河へ向かいます。
新政府軍の真っ只中で、
「朝敵・徳川慶喜が家来、山岡鉄太郎まかり通る」
と大音声を発して、官軍に取り囲まれる中を平然と押し通っていきました。
鉄舟と面談した西郷は、
江戸城を明け渡す。
城中の兵を向島に移す。
兵器をすべて差し出す。
軍艦をすべて引き渡す。
将軍慶喜は備前藩にあずける。
という条件を提示しますが、最後の慶喜の身柄引き渡しに関してだけは、猛然と拒否し続けました。
これに立腹した西郷が、
「朝命である! 」
と凄んで見せたが、鉄舟は動じる様子もなく、
「もし、島津侯が同じ状況に置かれたなら、貴殿も同じことをするだろう。」
と反論しました。
鉄舟の命を顧みない真っ直ぐな忠義に感嘆した西郷は、最後の条件を預かりとした(事実上は容認)上で、江戸無血開城の基本的枠組みは合意に達したのです。
後世、西郷が勝に述懐したというお話が、『鉄舟随感録』にあります。
海舟の「評論」で、西郷の次のような言葉が記されています。
「西郷が曾て己に云うた事があるよ。
山岡と云う人は、・・・(中略)・・・
あんな命も金の名もいらぬ人間は始末に困る。」
この西郷の述懐は、西郷南洲翁遺訓にもあって、
命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、仕末に困るもの也。
この仕末に困る人ならでは、艱難を共にして国家の大業は成し得られぬなり。
とあり、いかに山岡鉄舟の剛毅誠実な人柄が、西郷の心を打ったかが、良く分かります。
明治維新後、江戸無血開城の手柄は、勝海舟が独占することになりますが、山岡鉄舟は、いちいち目くじらを立てて手柄を言い出そうとしませんでした。
この件では、新政府側(岩倉具視や三条実美が、鉄舟を諭したほどで、それぐらい鉄舟は、手柄を誇示するようなことはしない人物だったのです。
山岡鉄舟は、新政府に請われ、明治天皇の剣術指南役に就任しました。
明治21年(1888年)7月19日、山岡鉄舟は、胃がんの苦痛の中、結跏趺坐を崩すことなく絶命しています。
最後まで誇り高き武士だったと言えるでしょう。
これほどの人物の義兄として、相互に全幅の信頼関係を置き合ったのが、高橋泥舟です。

1946年(昭和21年)以前に撮影(製作)された。
『ビジュアル幕末1000人』世界文化社
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takahashi_Deishu.jpg?uselang=ja
勝海舟をして、
「あれは大馬鹿だよ。物凄い修行を積んで槍一つで伊勢守になった男さ。あんな馬鹿は最近見かけないね。」
と勝流儀での最大級の賛辞を贈っています。
(この辺の表現は、勝海舟らしいです。もっと世渡り上手であれば・・・という思いもあり、でもまた、その一途さが羨ましくもあり、敬愛できるという意味で言っていますので。)
高橋泥舟は、歴史の表舞台に出ようとはせず、後半生は隠棲しました。
義弟の山岡鉄舟が亡くなった際、山岡家に借金があったのですが、その保証人になっています。
財産を持っていたわけではないのですが、
「この顔が担保でござる」
と言い、金を貸す方も
「高橋様であれば・・・」
と、請け負ったと言います。
日本の武士道を語る上で、この二人は外せないよなあ・・・と、改めて思う朝なのでした。
いいなと思ったら応援しよう!