
グレーゾーン事態について考える
前回、尖閣諸島国有化から12年を振り返り、破竹の勢いで変貌を遂げた中国海警局の実態と、尖閣諸島を巡る見通しを述べました。
その中国海警局が追求している手法が「グレーゾーン事態」と呼ばれるものです。今回は、このグレーゾーン事態についてご説明します。
1 グレーゾーン事態とは
グレーゾーン事態とは、純然たる平時でも有事でもない幅広い状況を端的に表現する言葉として、防衛白書では次のように定義されている。
国家間において、領土、主権、海洋を含む経済権益などについて主張の対立があり、少なくとも一方の当事者が、武力攻撃に当たらない範囲で、実力組織などを用いて⋯(中略)⋯現状の変更を試み、自国の主張・要求の受け入れを強要しようとする行為が行われる状況
例えば、漁民を装った武装勢力が尖閣諸島に上陸した場合など、主権侵害ではあるが武力攻撃とは言えず、自衛隊に防衛出動を命じることができない状態が、それに当たる。
相手が軍でない限り、原則として自衛隊ではなく海上保安庁(以下「海保」)や沖縄県警などの警察力がこれに対処することになる。

2 グレーゾーン事態における問題点
こうした状況で問題となるのが、我が国の防衛・警備態勢の能力的・時間的な間隙(ギャップ)を突かれることである。
(1) 能力的なギャップ
警察力としての海保と、軍事力としての海上自衛隊(以下「海自」)の間には、必然的に攻撃・防御能力に大きなギャップが存在する。
つい12年前までは海保の足元にも及ばない海洋機関のひとつだった中国海警局は、極めて短期間のうちに、その中間的な能力を獲得し、準軍事組織(パラミリタリー)の第2海軍へと変貌した。

《Created by ISSA》
先ほどの話の続きで、尖閣諸島に上陸した漁民を保護するという名目で、海保や沖縄県警の対処能力を上回る中国海警局や人民武装警察(武警)が乗り出して来たらどうなるのか。
この場合、現状では「海上警備行動」を発令して海自に一定の権限を与え、あくまでも警察力の援軍として部隊を差し向けることになるが、中国側は自衛隊の出動を軍事介入と見做して中国軍を投入するので、事態は一気に地域紛争へとエスカレートする。
そこに、グレーゾーン事態の難しさがあるのだ。
(2) 時間的なギャップ
中国軍の正式名称は「人民解放軍」と言って、実態は国軍ではなく共産党の軍隊なので、いつでも即座に党の意のままにコントロールできる。
一方、日本では、自衛隊の出動命令を下すまでに一定の情勢判断や手続きが必要になる(下図左)。

また、尖閣諸島は中国側に有利な位置にあり(上図右)、命令を受けた自衛隊が対応を開始する前に、中国側の援軍が尖閣諸島に到達する恐れもある。
このような時間的なギャップが積み重なると、中国に実効支配を固める余地を与えることになる。

《Created by ISSA》
これら能力的・時間的なギャップを、如何に埋めるかが尖閣諸島防衛のカギになるのだが、中国側の変化速度に見合う有効な対策は打ち出せておらず、これらのギャップは未だ完全には埋まっていない。
その理由は、次のとおりである。
3 ギャップが埋まらない理由
(1) 法制面の問題
海上保安庁法第25条には、次のような記載がある。
この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。
他方、自衛隊法80条では「有事の際、海保は防衛大臣の統制下に入る」とされ、長年、法のねじれが指摘されてきた。
2023年4月に政府が策定した「海上保安庁統制要領」(後述)で、ある程度の方向性が示されたものの、海保は平時・有事を問わず非軍事組織であるという大原則は何も変わっていない。
(2) 意識面の問題
この問題は、海保の創設時にまで遡る。
海保は、76年に及ぶ歴史の中で、徹底して軍事色を排除してきた経緯があり、彼らには「自分たちは海を守る警察官である」という誇りがある一方、「決して、戦場に繰り出すことはない」という反戦意識のようなものが深く根付いている。
戦後、海保と海自の創建に携わった吉田英三・元海軍大佐は、GHQから押し付けられたこの条文は、日本を弱体化させる恐れがあるとして、当初から問題視していた。
海保から分離独立し、海軍の伝統・文化を色濃く継承してきた海自とは、国防に対する考え方が根本的に違うのである。
(3) 運用面の問題
仮に、この第25条を撤廃し、有事対応のための新たな権限・能力を付与したとしても、海保職員の考え方を変えることは容易ではない。
また、海保が海自や米国沿岸警備隊との間で軍事的な互換性を有するようになるには、恐らく10年単位の歳月を要するであろう。

右:海自護衛艦と海保巡視船
4 グレーゾーン事態への対策は
ここからは、我が方のグレーゾーン事態への対策状況をみていきたい。
(1) 海保の対策状況
海保は、現行法の範囲内で出来る限りの能力向上を図っている。
2016年4月、海保は中国公船に対応する巡視船をクルー制で運用する「尖閣領海警備専従体制」(注1) を構築した。
(注1) 高速巡航が可能で20ミリ機関砲や遠隔放水銃、停船命令表示装置などを装備した巡視船とヘリ搭載型巡視船で編成。また、第11管区の定員を増員し、うち数百名を尖閣専従要員とした。
2020年2月から、那覇航空基地に中型ジェット機「ファルコン2000」を配備。
2022年10月、海自の八戸航空基地を拠点として、無人機MQ-9B「シーガーディアン」の運用を開始し、2025年からは、無人機の拠点を北九州空港に移転する計画となっている。
また、2024年10月から、鹿児島県の七ツ島運航支援センターの運用を開始した。
しかし、僅か1.4万人で日本中の海上警備・救難に当たっている多忙な海保に、これ以上の変化を求めることは極めて難しいだろう。
(2) 自衛隊の対策状況
一方、陸上自衛隊(以下「陸自」)は、2016年3月に与那国島、2019年3月に宮古島及び奄美大島、2023年3月に石垣島に駐屯地を開設し、尖閣周辺海域を射程に収める地対艦ミサイル部隊の配備を進めている。

《sankei.com》
また、海自は共同訓練等を通じて海保との共同対処能力の強化に取り組んでいる。
2023年4月、政府は防衛大臣による「海上保安庁統制要領」(注2) を定め、翌5月から6月にかけて、武力攻撃事態を想定した初の机上演習及び実働訓練を行った。
(注2) この統制要領では、海上保安庁法第25条で規定される海保の非軍事性に配慮がなされ、防衛大臣が指揮する対象は海上保安庁長官に限定され、巡視船などへの指揮は回避している
更に、海自の人的・物的資源がひっ迫する中、陸自が輸送船部隊の創設に取り組んでいる。
2024年10月、陸自初の輸送船である「にほんばれ」が進水した。排水量は2,400トンと、さほど大きな船ではないが、砂浜に艦首を乗り上げて物資を陸揚げする「ビーチング」能力を有する。
この船は、今後、海自呉基地に新編される「海上輸送群」に配備され、2027年度末までに10隻を保有する計画となっている。
(3) 政府の対策状況
一方、政府は、2018年5月に、中国との間で、自衛隊と中国軍の不測事態を回避するため、「海空連絡メカニズム」に合意した。
自衛隊と中国軍の艦船や航空機が国際基準(CUES)に基づいて連絡を取り合うことや、防衛当局間にホットラインを設け(2023年3月に開設)、毎年、幹部会合を開いくこと等が盛り込まれたが、尖閣周辺での緊張緩和には至っておらず、その実効性には課題が残されている。

《nikkei.com》
5 米国のスタンス
(1) 米国沿岸警備隊
日本の防衛に欠かせないのは、同盟国である米国の海軍力だ。
米国土安全保障省の管理下にある米国沿岸警備隊(USCG)は、海上警察権を行使する連邦政府の法執行機関だが、合衆国法典(United States Code)では、陸・海・空軍・海兵隊に次ぐ5 番目の軍種とされている。
有事の際は、大統領の命令によって海軍長官の指揮下に入る。
2020年9月に署名・交換した「米国沿岸警備隊と海上保安庁との間の覚書」に基づき、共同訓練や職員の交流等を定期的に実施していおり、米国沿岸警備隊が日本周辺海域に来訪する機会も増えている。
(2) 米政府の考え方
米政府は、尖閣諸島の領有権について「一義的には当事国間での平和的解決に期待する」として中立的立場を示しながらも、オバマ政権以降、歴代米政権は「尖閣諸島は、日米安保条約第5条(注3) の適用範囲内」との見解を示し、中国をけん制している。
(注3) 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。(以下、省略)

また、在日米軍は、1950年代から尖閣諸島のうち久場島と大正島に射爆場を設置し、沖縄返還後も引き続き米軍提供施設としている(ただし、1979年以降、使用実績はない)。このことも尖閣諸島が日本の施政下にある論拠を後押ししている。
なお、中国が尖閣諸島や台湾の実行支配に打って出るか否かは「米国の意図と能力次第」と考えている中、もし、気まぐれなトランプが、米国の安全保障能力にタダ乗りする同盟国を許さないとして、「尖閣諸島は日米安保適用外」と言ったらどうなるだろうか。
また、無人島に過ぎない尖閣諸島への米軍の武力介入に懐疑的な見方もある。そう考えると、国の安全保障を、揺らぎ始めた米国にいつまでも依存し続ける訳にはいかないのだ。
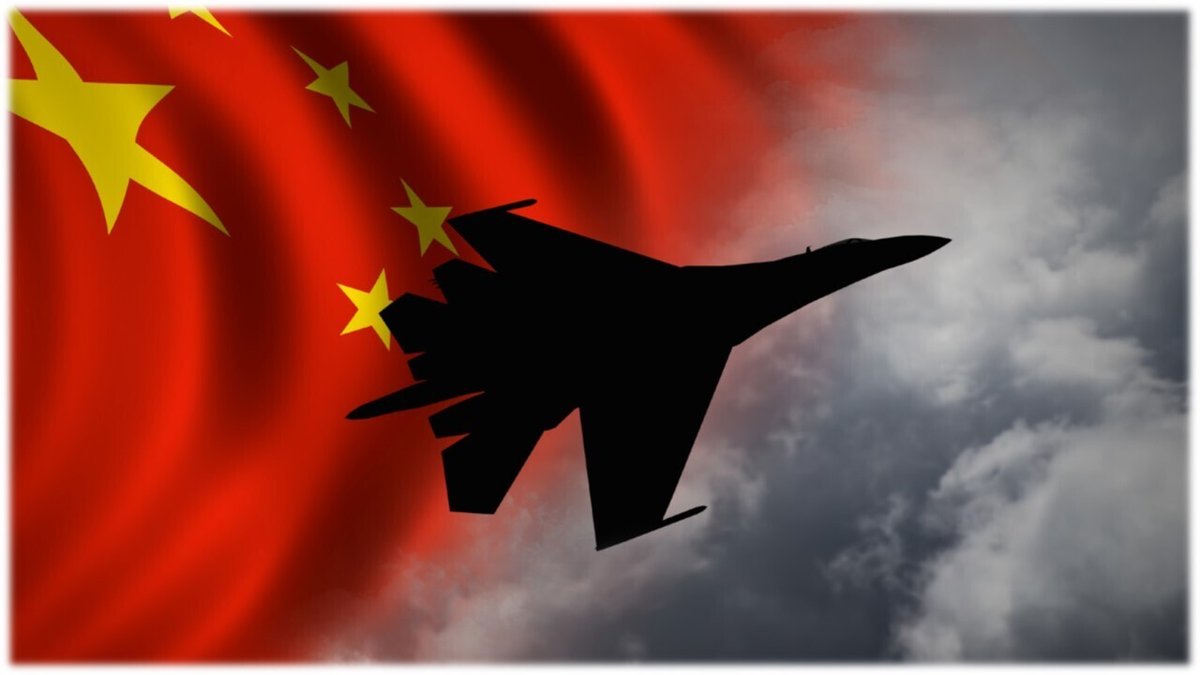
おわりに 〜
今こそ日本版「国境警備隊」の創設を
先日、台湾の頼総統がハワイ・グアムを訪問したことに反発した中国は、台湾周辺海域で、海軍や海警の艦船約90隻による、1996年以来、最大規模となる海上軍事演習を実施しました。
その際、76mm砲を搭載した海警船4隻が尖閣諸島周辺で活動したことが確認されています(尖閣周辺を徘徊する海警船4隻すべてが76mm砲を装備している状況は初確認)。
前回、お話しましたが、76mm砲は海保巡視船を粉砕する威力があり、通常、沿岸警備隊の武装としてはあまりにも過剰です。
海保は、これまで頑張って情勢の変化に対応してきましたが、僅か1.4万人と小規模であることに加え、任務の多様さや非軍事組織として育ってきた経緯を考慮すると、海保にこれ以上の改編を求めるには、物理的にも心情的にも無理があります。

ならば、新たに準軍事組織(第2海軍)としての日本版「国境警備隊」を創設し、グレーゾーン事態を追求する中国海警局に対応可能な権限・装備を付与すべきではないでしょうか。
海保を海上警察限定機関に規模縮小し、海洋に活動領域を広げてきた陸自と、海自・海保・水産庁・水上警察等の一部を統廃合すれば、中国によるコスト強要戦略に敗れることなく、実効性のあるグレーゾーン対策が実現可能です。
この問題は、あまり時間的猶予がありません。石破政権は、防災省やアジア版NATOよりも、先ずは日本版「国境警備隊」の創設へとドラスティックに政策転換して欲しいと思います。
