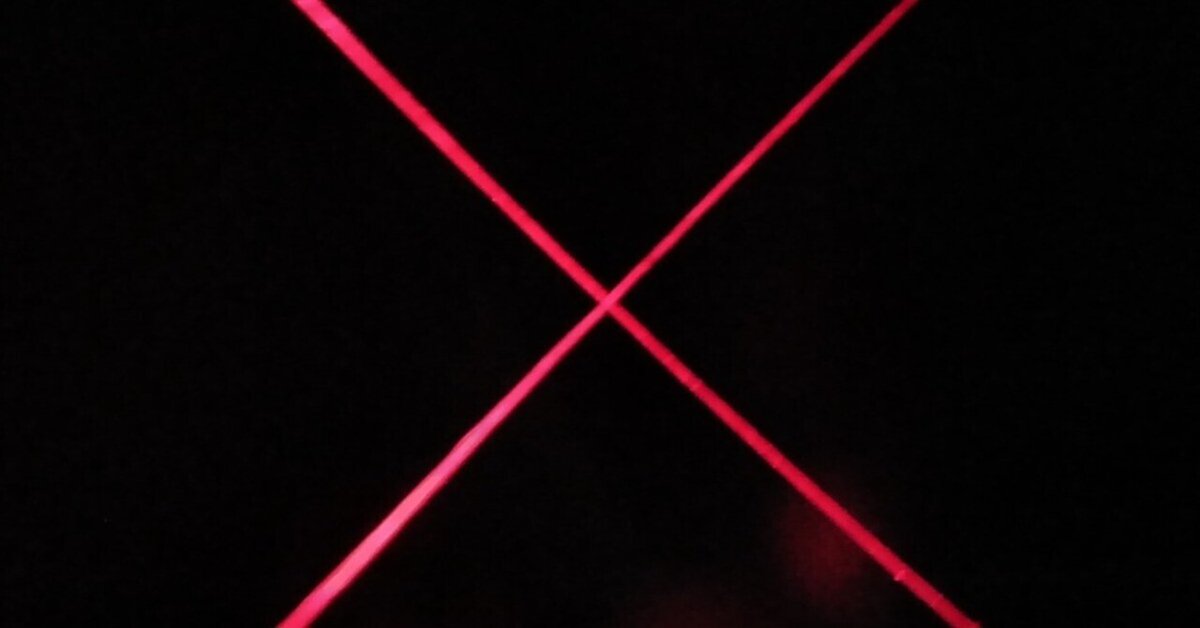
DIY: 暗視野十字線アイピース & ファインダー低倍率化
5cmファインダー(安いやつ)
5cm 9倍の安価なファインダーがある. KenkoとかSkyWatcherとかの望遠鏡の付属品だったりもするし, Amazonで「9x50 ファインダー」で探すと7000円前後から1万円ちょっとの価格でいろいろ出てくる. たぶん光学系は同じようなものだろう. 5cmファインダーは3cmと比べると格段に集光力があって暗い天体を探しやすいし, 夕方の薄明のときに北極星を探すのにも, 極軸望遠鏡よりずっと早くちゃんと光っている北極星を見ることができる.
この安価なファインダーはもちろんレチクル(十字線)の照明装置なんか付いていないし, 線が太くて星が隠れたりするという欠点もある. それに9倍という倍率は広視界が欲しいファインダーにはちょっと高すぎるかもしれない. (星の並びを把握しにくくて導入に苦労することがある)
以前, 倍率はさておき, 十字線を細いジョロウグモの糸に張り替えて暗視野照明を付けるというDIYをしたことがある. 真っ暗な山の中で月のない夜に使うと, (たぶん)市販品よりも細く控えめな明るさの十字線は微かな星の光も邪魔しない. とても快適な愛用品になった. あとの問題は倍率だけとなった.


(このように暗い視野内でレチクルが光るように照らすのを暗視野照明, 前から光を入れ視野を薄明るくしてレチクルを影にするのを明視野照明という)
その後, 何かの付属品として似たようなファインダーがもう1本来た. この手のファインダーの対物レンズの焦点距離を測ると170mmくらいだから, たぶん組付けのアイピースは19mmくらい. ならばSVBONYの23mm(激安)アイピースを使うと約7倍の計算になる. 試しに接眼部を外して23mmアイピースで覗き込むと, 元より視界が広くなることが確認できた. (周辺像はやや乱れる) だから, この23mm激安アイピースを改造して暗視野照明レチクルを組み込み, ファインダーの接眼部を改造してアイピース(1.25インチスリーブ)を付けられるようにすれば, 理想の広視野ファインダーになる. (2倍以上のお金をだせば売っているんだけど(笑))
DIYだ!
材料
(たぶん)SkyWatcherの付属品9x50ファインダー
(たぶん)Vixenの36.4mmネジ〜1.25インチアイピースアダプタ
SVBONY激安アイピース 23mm
赤色LED (幅3.5mmの小さい角型)
CR2032用のスイッチ付き電池ボックス
抵抗器 (330Ω, 上のLEDがこのくらいでちょうどよい明るさになる)
ファインダー接眼部の切り貼り工作
ファインダーの接眼部の板(アイピースを外したもの)の穴をヤスリで広げ, アイピースアダプターの36.4mm雄ネジはヤスリで削り取り, ハマルようにする.
鏡筒の後ろを少し切る. どのくらい切るかは, 鏡筒後端が空いた状態でアイピースアダプタに挿したアイピースを挿入してみて, フォーカスが出る位置を確認して決める. だいたい, ファインダーの光軸調整のXYネジを当てる溝の後端のちょっとだけ後ろで切れば良さそうだった. 切り取る長さは5mmくらい誤差があっても大丈夫. 対物レンズの位置の調整(元々のフォーカス調整機構)でなんとかなるから.
切ったり削ったりが完了したら, きれいに洗浄してエポキシ接着剤でくっつける.


これで鏡筒側の工作はOK.
アイピースの暗視野照明レチクル加工

このアイピースはプラ製のレンズバレル(黒いやつ)とアルミバレル(1.25インチスリーブ)に分離できる. レンズたちは黒い筒に入って留め環で固定されている. 焦点面はレンズ群の外側(対物側), アルミバレルの内側のリング状の突起の前端あたりにある. レチクル(十字線の糸)をそこに張るために, 金ノコで切り込みを入れて, 糸を貼り付ける座とする. 切り込む深さはリング状の内面突起を切るまで.

照明LED用の穴は, プラスチックバレルの先端から8mmくらいの位置を中心に, 直径3.5mmの穴を開ける. (使ったLEDは幅3.5mmの四角)

こうすると, アルミバレルのネジ部分に干渉せずに削孔, LEDの挿入ができる. LED用の穴から90°の位置でプラスチックバレルの外側を少し削って平面を作っておく. ここに電池ボックスを接着*するため. (プラスチック部分の長さと電池ボックスの幅がほぼ同じ)

本当はジョロウグモの糸を使いたいのだが, この季節はまだ巣を作っていなくて, 10月終わり頃まで待たねばならない. でも放っとくのも何なので, 仮の糸で十字線を張ってみる. 使ったのはポリエステルの手縫い糸#40を解して作った細い糸.

電池ボックスを貼り付けて, リード線や抵抗器もエポキシで固めてひとまず完成!

完成!

下: 今回のやつ, 約7倍
9x50と比べてみると, 確かに倍率は下がって視野が広がった. このSVBONY 23mmは比較的広視界(62°)というのも効いている. 但し周辺像は乱れる. 乱れても, ファインダーの機能としては広い範囲が一応見えて目標の導入を助けてくれれば良いということで, OKかも. アイピースが大きくなったので少しカサが増えた感じ.
【了】
*この手のプラスチック(ABSかな?)とPPだかPEだか(電池ボックス)の接着にはエポキシが使えない. PP/PE用の接着剤(ボンドGPとか)だと強度に不安があるしエポキシのように樹脂で覆って固めるようなやり方ができない. それで, 最初にボンドGPを塗って貼り合わせ, やや乾燥してから剥がして, その面にエポキシを塗って接着するという方法をやってみた. ボンドGPがプライマーとしてPP/PE表面に付き, それにエポキシを付けるということになる. 今のところ取れないで使えている. 正しい使い方かどうか分からないが…
