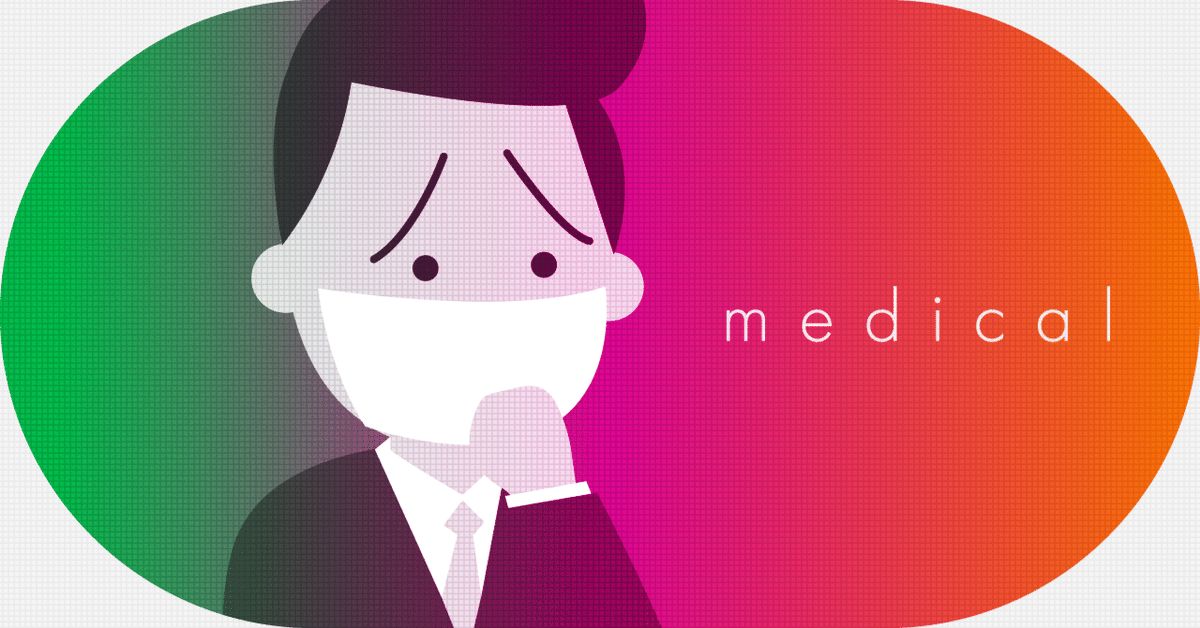
西洋医療・西洋医学と病み癒される臨床
病み癒される臨床、ひとつの共同体とその流儀としての西洋医療・西洋医学についてリンクしてみました。AI時代になっていろいろ変化もありそうですね。
西洋医療といっても国によって異なっていましたが…
医学がない現代医療教育
かつて、Medicine は science ではありませんでした。
「英語で「メディスン Medicine」の語源は「イブンシナ」ペルシア語で 「マダディシナ-Aid of Sina」から来ている」http://t.co/ZMGRQgSvGh'
— 石部統久 (@mototchen) July 13, 2014
イブン・スィーナー(イブンシナ)https://t.co/IiDkwmMgW1
「日本の医療社会学の問題点」は、近代医療・近代医学の多様性・多相性を認識しないでの研究が多いことである。本稿では、その問題点を次の4つの落とし穴(pitfall)をもって説明する。
(1)「医療=医学」とする誤謬、
(2)近代社会における多元的医療の無視、
(3)「近代医学=科学的一枚岩」の幻想、
(4)「近代医療=病院(臨床)医療」という思い込み。
医学と称している現代のメディスンは、いかに早く病名を特定しその治療法を適用するかに終始します。そこには体系的論ありません。
大学ではトップを走っていたつもりだった。
でも、…現場に出たら本当に頭でっかちの役立たずだった。
理屈を本で知っているだけだった。
大学では、この病気はこんな症状で、こんな検査をして、こんな風に治療すると学んだ。
ところが現場では、「食欲がなくて、吐いていて、ぐったり」という感じでやってくる。
よくある症状の話をしながら紐解いていき、どの病気かという結論を導き出し治療を決定する。
学んだこととは正反対の方向から攻めないといけない。
獣医を辞め営業職に就き、そして再び獣医として活躍している女性のストーリー。全くの異業種を経験することで、彼女はどんな学びを得たのでしょうか。https://www.huffingtonpost.jp/storysjp/different-occupation_b_9640700.html
医療と医学の違い
中世ヨーロッパの大学では学問フィロソフィと医術は区別されていました。
「カントは最後の著作『諸学部の争い』で、中世モデル以来の大学を、法学と医学そして神学の上級学部と哲学の下級学部に分けられているその意味を、批判的に分析しました。上級学部の三つは、いわば国家システムが社会を統治する三つの基準を示している。人間社会を統治し計る基準は法学。身体を統治し管理する基準は医学。人間社会を越えた世界を統御するのは神学。例えば、何かの技術がある。それが何の役に立つのか、良いか悪いかと問うときに「健康によい」とか「精神にうるおいを与える」とか言えば、社会的な合意が獲得される。となるとこれは、最終的に医学の領域となるわけですね。あるいは「泥棒してはいけない」というのは法学の領域である、と。これらの三つの分野は、国家があらかじめそのシステムに組み込んでいる正当化の三つの領域を代表している。大学はそういう正当性を与える理論や権威を勉強する場所なのです。しかしながら、下級学部として位置づけられていた哲学は」「そうした社会のプログラムに組み込まれ得る目的に基づいていない。ではそれは必要でないか? という論争があった。それに対する応答が、カントの『諸学部の争い』です。 簡単に言えば、以上の法学、医学、神学という三つの学部は、既存システムに対しての合目的的な判断、つまり合システム的な判断しかできないということです。すると、このシステムそれ自体の良し悪しの判断はどのようにやるか? そのシステムが機能不全になったときにどうするか? 法学、医学、神学は通常の技術(学部)よりも上位ではあるけれど、規定的判断を前提にしている。であれば、規定的な技術を習得させる専門学校の理論編くらいにすぎないことになる。ところが哲学は、こうしたそれぞれの技術内の都合、規定的判断、すなわち突き詰めればそれぞれのシステムの効率、エコノミー、利害に作用されない。いかなるシステムの都合からも離れて判断できる。反対に言えば、下級学部としての哲学は、すべての技術の基礎を学び直すことで、それを問い直すことができる、哲学部のなかにはすべての専門領域が含まれているという」
以下臨床「医学」と称しているのはメディスンでありかつては学問(フィロソフィ)ではなく技術でした。進化医学が目指しているものこそが、ガレノスから流れる学問としての医学なのです。
「病気は、どのように(How)して起きるのか」については臨床医学の世界になる。もちろん病気の原因もそこで追究はされるものの、その病気を引き起こしている至近要因までになる。そもそも、「その病気がなぜ(Why)あるのか」という究極要因まで踏み込むのが、進化医学になる。発熱という症状がどういうプロセスで起きているのかだけでなく、そもそもなぜ身体は発熱しようとするのか、という発想の転換だ。
一例として発熱における医学と医療研究の違い
発熱についてある医学における回答、医療研究における回答を付記しておきます。違いをご覧ください。
西洋医学のそれぞれ
西洋医学について歴史的なものを抜粋して並べてみます。
アリストテレスのフィロソフィから医学を確立したガレノス
ガレノス医学の後継 ユナニ医学
実験で医学確立を目指したクロード・ベルナール
第一点は,科学的医学体系の構造を『生理学,病理学,治療学の基本的三部門を含み,病理学と治療学は生理学の基礎の上に建設されなければならない』と一般的に措定したこと,第二点は,その基礎となる生理学における数々の事実的解明をなしえ,さらに生理学の重要な概念である『内部環境』を措定したことである。
しかしながら,ベルナールは第二点においては歴史的に大きく評価されていても,第一点についてはなんら評価されていないのが現実である。すなわち,ベルナールは生理学者としては認められたが,医学者としては認められてはいないのが,悲しい現実である。
これまで彼の著作でみてきたように,本来第二点にあげた生理学的解明は,第一点,つまり医学体系の構造を一般的に構想したうえで,その医学体系の完成へむけての第一歩として,彼自らが位置づけていたものであるにもかかわらず,すなわち第一点がなければ第二点はないにもかかわらず,生理学の業績のみを医学全体から切りはなし,生理学者として位置づけるだけの実力しかないのが,医学界の淋しい現状なのである
哲学で医学を目指した澤瀉久敬
瀬江千史の医学
医学の復権
http://gendaisha.co.jp/syoseki/syoukai/fukken.html
病気とは、人間の正常な生理構造が、外界との相互浸透の過程において、徐々にあるいは急激に量質転化して歪んだ状態になったものである
「医療とは,現実の病の治療,つまり病を治すための実体的・認識的技術である。それに対して医学とは,病の形成過程と回復過程の構造を一般的にとらえ,病とは何か,それに働きかける治療とは何かを体系化した認識であり,科学である。」
https://web.archive.org/web/20160321221220/http://www.seitai-pt.com/%E3%81%94%E6%8C%A8%E6%8B%B6/
「体系とは、読んで字のごとく体の系である。すなわち、人間の体のようにつながってひとまとまりになっているものである。人間の体はみればわかるように、頭がありその下に体幹があり、体幹から手、足が出ている。そして、全身が頭に存在する脳によって、神経・ホルモンを介して完全に統括されている。
このようにあるべきところにきちんとあるべきものがあり、それが一貫してつながってひとかたまりになって脳の支配の下に統括されながら活動していけるものが、体系なのである。」
「学問体系は、これにたとえて、本質論が頭、構造論が体幹、現象論が手足であり、全体系を貫く論理性が神経ということになるが、これまた当然に脳、すなわち本質論によって統括されていなければ、つまり本質論につながる構造論でなければ、そしてそれが活動できなければ学問としての体系ではないのである。」
津田敏秀の医学
臨床人類学
臨床を人類学の目でみると医療をみる目が変わるようです。
この本を読む前の私は臨床心理学を深く信奉する共同体の下級構成員だったから、ユタや占いのような霊的治療文化を「遠い他者」だと思っていた。自分の想像力では届かないところで活動している歴史的な「何か」、そういう風に思っていた。だけど、朝が来たときには変わっていた。彼らは親戚だった。人間が病み、癒されることについて、人間は様々なやり方で介入してきた。心理士も、医者も、看護師も、ケースワーカーも、そしてユタも占い師も、そういう系譜を生業とした一族なのだと私は痛感していた。
それだけじゃない。その朝の私には、自分自身が、そして自分が属する臨床心理学という文化が「遠い他者」のように見えていた。
クラインマンのこの本が素晴らしいのはここだ。彼の関心はエキゾチックなものではない。つまり、見知らぬ土地の物珍しい治療を理解するために、彼の理論は作られていない。その後の『病いの語り』や『精神医学を再考する』がそうであるように、彼は生物学的精神医学や心理療法という西洋由来の治療を批判し、その独善性を解毒するために理論を語っている。
目から鱗のようなものが落ちる。すると、あまりに当たり前のものであり、自明のものであった臨床心理学が、その日を境にある種の「宗教」や「教団」のように見えるようになる。
これはいったい何なんだ? 俺はいったい何をしているんだ?
クラインマン『臨床人類学』の再刊に寄せて
https://bunshun.jp/articles/-/49720?fbclid=IwAR0r6vVT9ez8e2OSefiyRfstzWkR4duPInGapm60pmLOLNhaPaX2ZyXNsVg&page=3#goog_rewarded
クラインマン医療人類学の意義 -沖縄シャーマニズム研究をふまえて 大橋英寿 (放送大学教授・副学長:東北大学名誉教授)
https://www.ritsumeihuman.com/hsrc/resource/01/pdf/01_04.pdf
ユタについて
病と医術の歴史
過去のまとめ
病と健康の境の一例
乳糖不耐は、かつては「乳糖不耐症」と病気あつかいされていましたが、実は病気ではありませんでした。
相対し聞くこと
患者さんの話を聞く、話を聞けるようになる。
そんなことがワークの目的なの?と誰しも思うだろうが、実際普段の日常を見ていても、そこが全く噛み合っていないのだから、そういった現場でも同じなのだ。
自分の主張は出来ても、相手の主張を聞くことは出来ないし、その主張を相手のこころに届かせる事は出来ない。
ましてや、相手のこころを「聞く」ことなど出来ない。
こころは言葉に乗っているが、言葉の理解しか出来ないのだから、そして、理屈としての主張しか出来ないのだから、そこに関係性が発生する筈もない…
相手の身体に触れることが仕事の人は、知らず知らずの内に、相手に違和感を与えている事が多い。
それがお客さんを遠のける原因の一つでもある。
