
1年前に発売された、霊使いストラクチャーデッキに愛を込めて。 【未完による執筆断念・遊戯王小説】YuGiOh Special
タイトルに有る「霊使い」。カードゲーム遊戯王におけるキャラクターの総称を指します。
遊戯王の世界からは離れて幾年経っているのですが、あのファンタジー世界の「公式から語っていないのに明らかに作り込まれているクオリティ」には尊敬しており、今回における霊使いもその一端を感じています。
今回取り上げる「霊使い」もそうであり、見て取れる限り『遊戯王における6属性に配属された少年少女の魔法使いであり、マスコット調の使い魔モンスターを携えている』『数奇な運命に翻弄されている(想像)』モンスター群です。
遊戯王にはマジック・ザ・ギャザリングのようなカードキャラクター主軸の小説作品等がないので、イラストから背景を読み取るほかないのですが、だからこそ妄想の余地がふくらむプレイヤーが多いのです。
今回はそんな霊使いに対しての遊戯王古参のプッシュ記事、そしてそんな「霊使い」を主軸としたガチファンタジー小説を過去に書いていたことから再公開いたします。

例えば霊使いの一人「水属性」の「エリア」を公式データベースから検索してみるとこのように種類があります。
初期作品は《水霊使いエリア》であり、それ以外は派生ではありますが、特に《リチュア・エリアル》の表現性の違いとかは特に「何があったか」を想起させるのに十分な違いがありますし、これらは他の属性の霊使いモンスターについても同様です。
そういった、特にストーリー性を大事にするプレイヤーから愛されているシリーズなのですが、「霊使い」を主役とした構築デッキが発売され、そしてそれには、過去のカードのイラスト違いやトークンカードが封入されていました。
それでこれらイラスト。本当に古参プレイヤーとしては「解釈一致」なんですよ。
「アウス」は物憂げにダウナーに戦場をマクロな判断で断罪できそうだし、エリアはいかにも主人公然とした凛とした動きをしそう、ヒータはいかにも一人称が「俺」のサバサバボーイッシュだし、ウィンはしとやかにほんわかに動きそう。
かつての遊戯王オタク(プレイヤー側)が監修してないとこんな解釈のすり合わせでまとめ上げられないだろうという仕事であり、トークンイラストも関係性オタクが喜んでやまないシチュエーションとなっていますよね。
ちなみに、今回イラスト再録されなかったりフィーチャーされていない霊使いが2キャラクターがいるんですが(光の「ライナ」と闇の「ダルク」)、霊使いオタクはめんどくさいので、注目されないことに関しても妄想して「○○な理由だから今回いないんだ!(早口)」とかストーリーを考え出すんですよ!(ちなみに私なら、ライナとダルクは主人公サイドじゃないから(敵サイドだから)うんぬんかんぬんとか妄想しだします)
そういった妄想が極致となり、全盛期の私は霊使いを主軸としたファンタジー小説を執筆していました。これは、ポケモン世界でいう公式コミックス「ポケットモンスターSPECIAL」を目標としておった態度であり、『公式作品が語った背景をとんでも角度で膨らませて解釈する二次創作を作る』ものでした。
執筆しているうちに多忙となり筆を折ることとなったのですが、「ちゃんと書けてたら……!」とか「書き上げたかった」という自責の念が耐えない作品です。
書き直すことはきっとできない作品ですが、私の執念の極致であったことからここに墓標を立てておきたかった。私はそういったライターでありクリエイターでしたので、今後とも宜しくお願いします。
Yugioh Special
(小説:めたぽ 挿絵:天龍)
「どうして、こんな世界になっちゃったんだろうね」
憂いげな瞳が呟く彼女の視線を揺らがせる。ある時は足元を、ある時は今立っていた位置から遠く見渡せる岸壁に。落ち着かない視線は、あまりにも見渡しが良すぎる光景のせいでもあるだろう。
魔法都市エンディミオン――その中心部にそびえる広大な建造物――『ステイプル』の頂上に彼女は器用に立っていた。そこは本当は人が立つように設計がされていない場所。幅にして5センチもない場所。しかし、彼女はバランスも崩すことなく、恐怖も感じることなく、地上に足をつけるように佇んでいた。
緑色のタートルネックのセーターを落ち着きなく人差し指でつつく。茶色く、短い髪を揺らす彼女の名前はアウス。エンディミオンの中では「地魔のエキスパート」と恐れられる魔女。彼女にとってつま先だけでも地に足がつけばそれはすなわち大地と同義――地を掌握しているということ。しかし、
「……」
その事実を彼女は憂う。齢十幾つの彼女にその荷は重すぎた。現に隕石が飛び交い、ミサイルが発射され、エンディミオンの『外殻』が揺らされる光景を目の前にして何も打開策が見つからない。
「私には……何も……!」

「……」
「アウス」
首をかしずくアウスの後ろから、透き通った――ダルクと呼ばれた――名を呼ぶ声が響く。声の主は禍々しい杖を肩に構え、サイズのあわないカジュアルルックを持て余すように調節する、これもまた年齢にして若い、『男の子』。
「アウス、こんなとこにいたのか」
「ダルク……貴方こそこんなところで」
「どうしたもこうしたもない。他の皆は既に待ちかねてる。早く行かないとまたアレにどやされるぞ」
ダルクは首をくいっと後ろにやり、移動を急かすような仕草。しかし、 「うん」
ダルクの呼びかけにアウスが答えしぶる。何か、ついていけない理由があることを心の中で咀嚼するように動きが鈍い。
「ごめん、でも、行けないや。だって」 アウスが目を細め、ダルクの方を向き――
パァン。
瞬間、アウスの肩甲骨より上部から顔面にかけてを――青白色の『何か』が――抉っていく。
「だって、ごヴなるうんめえだっだがら」
風船がはじけるような音。噴き出す潜血。ダルクはその一秒を目の当たりにし、事態をつかめない。
思考が廻った瞬間――彼は、叫び倒していた。
その時より約2時間後、ダルクはエンディミオンの一角にある会議室に召集、事情聴取をされていた。目的は「先のアウス逝去についての事情聴取のため」――体よく言えば原因の解明と『原因が外部因子にあることが確定するのならば』報復材料の捜索だ。
それほどまでに世界は荒んでいた。種族間の対立と縄張り争い、そして生存戦争。その光景が、性急に報復させる精神を育てている。
「ダルク、それでは君はアウスを殺害したそのエネルギー体の正体はわからないということでよろしいのだな」
長机の上座で声をしゃがらせつつ堂々と構える老魔術師――『ビンド』が表情を変えずダルクに問いかける。その横では見目は子供だがその魔法技術は一線を画す「光属性首領代行」『ピケル』が当議会の書記役として淡々と筆を走らせる。ビンドの問いに、息一つ挟まない。
「もうちょっと物の言い方考えられねえのか! てめえは急戦派だったよな。隣国に対して開戦をつきつけるためのカードが欲しいだけじゃねえのか!?」
声を荒げ立ち上がるダルクに、一つ離れた席で座り、膝元に手を添えた――縮こまるような姿勢で佇んでいた「大気の魔女」『ウィン』が恐々と声をかける。
何かを言い倦ねるかのように声が細かく震える。その度、頭上にぽつりと存在を示す緑色のリボンが風にささめくように揺れていた。
「ダルくん……気持ちはわかる……けど、冷静になって。落ち着いて」
「これが落ち着いてられっかよ! 目の前で仲間が死んだんだ、むしろウィンこそ冷てえよなあ。主犯はてめえなんじゃねえのか!」
「……そんな」
その二人の掛け合いを壁際で見つめていた「業火使い」『ヒータ』と「大海の豪傑」『エリア』が見かねて口をはさむ。赤髪のショートカットに、前面からして軽量ルックで男勝りながんを飛ばすヒータと、青髪ロングカットでやんわりと戦況を見つめるエリアはあらゆる意味で対極的だった。
「ダルク。その言い方は感心しねーぜ」
「だよ。ヒータの言うとおり。今の言葉は撤回してウィンに謝って」
一瞬の静寂。窓の空いた部屋からは乾いた風が入り6人の髪を揺らしていく。
「……ああ。確かに今のは軽率な発言だった。……だがな、状況を思い返すだけで――正直色々と疑わしい。アウスの死に方があまりにも不自然だったからな」
「何を言ってる? ダルク、どういうことだ」
いやに素直な暴言撤回とともにひりだされた台詞。断片だけでは意図不明なそれに、ヒータが言葉をねじりこむ。
「いいか。俺は何も『アウスの死因がわからない』なんて言ってねえ。ビンドの言い方が気に食わなかっただけだ……攻撃の正体そのものは予測はついているさ」
俯き、嘲笑するようなしぐさを作りダルクが肩を震わせる。
「犯人そのものをつかんだわけじゃねえ。だが一つだけ言えるのは、あれは『魔法使い族の攻撃だった』ということだ」
「!?」
瞬間、霊使い3人・老魔術師――4つの視線が一気にダルクを突き刺す。
「な、なんですって!? ダルくん……その言葉に偽りはないよね? 悪い冗談なんかじゃないよね?」
昂ぶる気持ちを抑えつけ、こんこんと発言したのはウィン。その場にいた5人の気持ちを代弁する。一つの、想定される事実を携えて。
「その意味は、おまえらならわかるよな」
ダルクが一呼吸置き、続ける。片手を腰に当て、嘲笑うような表情で。
「片手で数えられるくらいしか存在しない『霊使い』の一人に攻撃をぶち込もうなんて実力と覚悟を持てる奴は、全員この部屋に集まってるってことだな。下っ端じゃ近づけもしねえだろうが、てめえらの精霊(カー)の魔力は相当なもんだ」
「ダルくん。それはちょっと穿った考え方じゃないかな」
持論を展開するダルクにウィンが差し込む。それは同じ世界に住む魔法使いへの慈しみの言葉か、それとも。
「……よくもまあ、しゃあしゃあとそんな台詞を吐けたもんだな。アウスが死ねば恩恵を受ける奴がこの部屋には複数人いるじゃねえか」
ダルクが一呼吸置いて、腕を組み淡々と言葉を吐く。ビンドはその言葉に何も返さず、長い白髭を撫で――次の言葉を待つ。
「ウィン、てめーが一番胸の内でほくそ笑んでるんじゃねーのか。地を牛耳るアウスが消失したんだ。相対する属性である風――てめえの立場はずいぶん高くなったよな。新首領が確立するまで――地属性の体制が整うまでは政治的にチャンスだ。不平等同盟も築きやすいだろうな」
「なっ……」
「ヒータ、てめーもだ。風があってこそ炎はその地位を確立する。ウィンの腹心を狙うには格好の状況が整いつつある」
ダルクの目は据わっていた。反論を受け付けないような、自分のロジックが世界を定義づけるとまでの怨念が感じられる目。それを冷ややかに突き崩したのはエリアだった。
「ダルク、私の名前を出さないでありがとうね。私は水属性を統べる立場、……今回の事件に関しては中立、得るものも失うものもない。はっきり言って中立、中立だよ。でもね、」
エリアの目には涙が滲む。
「ダルクの言葉を聞いて、私は自分の立場と責任が恨めしい。こんな事務的で、機械的なことを口にしなければいけないなんて、考え付いてしまうなんて! ダルク、あんたもね! 決して蚊帳の外じゃないんだよ! そもそもアウスを『破壊した』のが魔法使い族の攻撃という根拠は第一発見者であるダルクの証言のみ! もう墓地に行ったアウスを私達は可視出来ない! 私達には何も判断できないんだから……そこを信じるしかないんだから……!」
アウスの死体は既に『墓地』にある。ここに挙げる墓地の概念はいわゆる死体安置所のそれに留まらない。生きているモンスターがいる世界『フィールド』と相対する世界である『墓地』。学者によればそれを”天国”とも称する者もいる。
「ああ、その通りだ」
エリアの辛辣な言葉に、ダルクは表情を変えずただ肯定する。
「信じるか信じないかはおまえらの勝手だ。『第一発見者が犯人』……そりゃそうも考えるだろう」
「ふむ」
そこまでを静観していたビンドが唐突に相槌を打つ。
「して、ダルクはどうしたいのだ。……ここにある首領どもを全員『破壊』しつくそうとか考えているのではあるまいな。アウスの仇を取りたいということであれば、その手段を取れば愚直かつ簡潔に目的を達成できるぞ。正解がその中に隠れているか、それは迷宮に入ったままであるがな」
ビルドの言葉にダルクを始め霊使いの全員が俯き、黙る。狙う者も、狙われる者も、うかつな言葉を口にできない。
「わかんねえ。わかんねえんだよ……!」
ダルクの箍が、外れる。彼を堰き止めていた自我がころりと一かけら取れたかのように――額を抑えての嗚咽。
「俺も、……そりゃてめえらを疑いたくなんかねえ――属性は違えども力をしのぎ合ってる仲だ――! だがな、そういう……そう考えが巡っちまう状況なんだよ。もしかしたら俺がいつの間にか《精神操作》されて、俺の《D・ナポレオン》カーを媒体に《ディメンション・マジック》をアウスにぶちかましたとかとちくるった寸劇があったかもしれない! 別に《精神操作》されたのが俺に限る必要はない! おまえらがそういう憂き目にあ」
「おちつけえええ!」
まくしたてるダルクをヒータが杖の先を向けて、一喝。息が、きれる。
「馬鹿みたいな妄想を炸裂させるな! そんなことあるわけないだろ!」
ダルクの例示した『妄想』は言うなれば『被害妄想』。可能性としてなくもないが、それに疑惑を持ってしまえば真実も、手段も、目的も全てが暗闇に包まれる。その可能性は彼らにとって、あってはならないものだった。だからこそ、
「……そんなこと、あるわけ……!」
ヒータは論理立てての否定はできない。被害妄想ではあるが、酔狂ではない一つの可能性ではあったから。
「ねえ、ダルくん」
「……なんだよ」
ウィンがその間に殺されたかのように一言呟く。
「もう一度、アウスの……彼女の最期の言葉、教えてくれないかな」
「どうしてだ」 「いいから」
温厚なウィンの性格から普段は見せない即答で、強い声色。ダルクはその返答に、一つ大きくまたたき、口を紡ぐ。
「もう一度言う。最期の言葉は『こうなる運命だったから』……え? 『こうなる運命』……『だったから』……?」
「気付いたよね。疑問点はおそらく貴方と一緒だよ」
「なんでアウスは自身が攻撃されること――破壊されることを知っていたのか。そして、知っていた上で何故その運命を甘んじて受けとめたのか」
「……」
それは解決すべき『課題』。ウィンの指摘に対し、ダルクは反論ができなかった。
「そ、それは……」
「わからないよね。私もわからない」
ウィンが目を大きく見開き、嘘偽りない私感を述べ紡ぐ。
「だからこそ。だからこそ……」
それは、最後まで迷っただろう発言。本来、属性の首領というポジションを鑑みれば、ここの席で先にビンド初め他の首領に許可を仰がなければいけないような案件。しかし、ウィンはあえて言い放つ。
「貴方が世界を見てきて。この世界は壊れ、荒んでいる。戦争というファクターが、アウスを破壊した”何か”について重要な理由を持っているかもしれない」
「……だが」
「だが、何? 『てめーらが犯人かもしれねえのに目を離すことなんて出来るかよ』って? ごもっともよ。だけど、今現在ある情報で真実が何かを判断できる? ダルクの証言すべてに頼っている以上、ダルクが判断できない状況になってしまったら、それはもう手詰まりなの。ねえ、聞いてるのダルク!?」
それは、首領としての威厳。決して隠している本性ではない。だが、ヒータ・エリアは少なからず怯んでいた。畳みかけるように紡がれる言葉、そして言い訳させる隙すらない間。普段の愛称の呼称すら忘れたかのように、呼び捨てる姿はさももう一つの人格のように。
「だから、貴方が世界を見て、真実を判断して。……私も、貴方が犯人じゃないって信じているから、貴方にお願いするんだから……頼むよ――ダルくん……」
そこまで語ると、ウィンはこと切れたかのように尻切れの言葉を発する。それを受け止めた言葉をすべて飲み込み、ダルクは一つ歯ぎしりする。会議室へのドアへと翻り、
「魔力通電機(モバホン)だ。必要があればすぐに呼べ。座標検索もついてるから何処にいるかの見当もつくはずだ……決して逃げたりしない。大丈夫だ」
ダルクがポケットから一つの装置を取り出し、スナップを聞かせてウィンに放り投げる。ウィンは返す言葉なく片手でそれをキャッチし、再び俯く。その様子を確認したダルクが翻り、会議室から退室した。
「……ごめん独断専行。許してくれるかな、くれないよね。いやー、首領職……罷免されちゃうかなあ」
ウィンが俯きながら苦笑って呟く。対面の席にいたエリアが立ちあがり、ウィンの横へ歩を進め――
「ダルクは誰にも何も告げず、闇属性の首領として戦時地域の調査に赴いた。それだけよ」
ウィンの肩に手を置いて、視線は向けない。呟くように、しかし強い口調で。
「それって……」
「それ以上でもそれ以下でもない。そういう『事実』」
閉鎖された空間における事実は、事実を把握している者が他人にその事実を語り、それを受け手がどう受け取ったか。その真偽は別問題――。
「そういうこったな。ビンドの爺さんはどうする。俺達も正直あんたを敵に回したくないんだがな」
ヒータも立ち上がり、ビンドに強い視線を向ける。視線は、語る決意。
「……今後の対応は、可及的速やかに検討させてもらおう」
「誠実な対応を感謝する」
ヒータが大きく頷き、
「よし、会談は終わりだ。解散……!」
机を軽く叩く。木目の心地よい破音が響く。
「それじゃあ、各自 責務を 果たしていこう」
エンディミオンの廊下をダルクは歩いていた。普段と変わらない空気と、窓際からつんざくように響く爆音。いつも通りの光景。一つの決意を持って、静寂を切り裂く。
「ダルク」
声をかけあぐねていた高い声色。意を決して振りしぼった一声の主はエリア。振りむくダルクの態度は据わる。
「なんだ」
「行く前に、これ」
相槌にひるむことなく、エリアも決意をこめた視線でダルクに手を差し出す。そこには数枚の紙が握られている。
「これは……」
「今の会議の議事録。まだ会議室の外に『事実』は公開されてないけど、首領の公式会談だから主査に記録は提出しなきゃいけない。意味、わかるわよね?」
「首領として今の半刻の重みを肝に銘じろ、ってことを言いたいのか」
「……もっと、重要な意味はあるわ」
寸刻かけないエリアの返答にダルクは言葉を返せない。
「わからない? 内容が疑わしいと思うのであれば見てもいいから、リリーに提出しておいてくれる? もしかしたらダルクを告訴するとかなんとか書いてるかもしれないわよ」
「……わかったよ」
それじゃあね、とエリアは手をぶんぶんと振る。顔は笑顔、眼は隠していても鋭かった。真意を知るのは、自分のみ。
●
「で、のこのこと私のもとにやってきたというわけですか」
机の上が豪快に散らかるエンディミオンの主査監督室。室長のリリーは桃色の髪にノーフレームの眼鏡を携えており、見ようによると医者のような、研究者のような雰囲気でペンを握っていた。にそれまでのやり取りを主観客観交え話すダルクに、リリーは肘をついて答える。
「貴方、もっとご自分の立場を自覚された方がいいです」
「悪かったな。行き当たりばったりで」
リリーは掛けていた眼鏡を一度外し、鼻頭をいらう。目を細めて、言葉を紡ぐ。
「貴方の話を聞く限り、はっきり言いましょう。一番疑わしいのは確かに貴方です。本来ならばそんな人に議事録を提出する旨につきお願いをするどころか、指一本触れさせないというのがその他の首領としての筋です。ほんと、ほとほと貴方達霊使いさん達は味方に甘いですね……おっと、愚痴はよしましょう。お使いを頼んだのはエリアさんなんですよね? ビンドさんが聞けば天罰の一つや二つ下す処理してるんですよ」
「すまんな。常識が無くて」
「はい。それについては『いえいえ私こそ言いすぎまして』とかフォローはしません。だけど……」
リリーが視線をふっと外に逸らす。何かを言いあぐねるような、それでいて確信に満ちた表情。
「あのエリアさんが考えなしにすることじゃないでしょう」
よっぽどエリアを信じてるんだな、そんな嫌味の一つが口を突きかけたが、ダルクが思惑と別に違う台詞を吐いていた。
「……エリアは、この議事録の意味について『半刻の意味を肝に銘じろ』という俺の自戒については否定しなかったし、『もっと重要な意味がある』と言っていた」
その呟きにリリーがぴく、と眉を動かす。そうですか、ですよね、と呟き返す。
「エリアさんは口でその『意味』を伝えなかった。となると、それは『想い』。それを掴み取ってからエンディミオンを出て行きましょうよ」
「――直接エリアに聞けばいいじゃねえか」
「女の子に秘めたる想いを暴露させようとするとか貴方は見た目通りの鬼畜ですね。さすが闇属性」
一言多い、ダルクは頭を掻いて悪態をつく。
「ま、それは冗談として。『伝えたい想い』は『伝わるように出来ている』ものなんですよ。私の本職を何だと思ってるんです?」
リリーが自信満々な表情でダルクに笑顔を向け一言。
「心の専門家。《メンタル・カウンセラーリリー》ですよ?」
妙に説得力のある名乗り口上。言葉を返せないダルクに対し、リリーは続ける。
「といってもですね。難しいことを考えるわけじゃないんです。エリアさんの気持ちになって考えてみることが大事なんですよ」
リリーは人差し指を立て、はっきりとした口調で話す――が、ダルクは要領を得ない表情。わかんない人ですね、とリリーが一言付け加える。
「いいですか。誰も乙女心を読みとって……とか無茶かつ浪漫じみたことを言うつもりは毛頭ありません。そうですね……貴方が納得する言い方をするならば、『エリアという首領が議事録を貴方に委託したことにつき得るアドバンテージ及び交渉カードは何か』。で、いかがでしょうか?」
「有力殺人犯候補に議事録を渡すことによって得るようなもんはねーと思うがな」
ダルクは最初に言われた正論かつ急所を思い返すように即答。それに対しリリーはぴくと、口端を動かし、それです、と一言。
「そうなんです。明らかに異常。だからこそ、そこに何かあると思いたいんですよ。だけど……」
「どうした?」
「はっきり言って、見えません。ただ一点、エリアさんが貴方を犯人ではないと断じたうえで通常業務を任せたということしか」
リリーは机を見据え、数枚の紙をめくりながら呟く。そして、視線を外に逸らすダルクの顔を数秒睨みつけ――何かを、期待するように。
「それで、いいんじゃねえか」
「いいんですか」
「反抗する割にはニヤニヤしてんじゃねーか」
「えっ、私ニヤついてますか」
リリーが口元を押さえつつ本当に気付かない様子で答える。だが、その表情は誰がどう見ても緩んでいた。
「何がおかしいんだよ」
「いや、大体想像はつくでしょう? 貴方がそんな単直な理由で納得するなんておっかしー、……みたいなことを思ってるんですよ」
「――馬鹿に、」
「してません」
リリーがダルクの言葉をさえぎるように断じる。
「むしろ敬いの気持ちの方が強いです。貴方がそういう風に感じてくれるなんて。エリアには伝えないでおきますね」
「そうしてくれると助かるな」
ダルクが机の上に置かれた議事録――ここに来た目的を一瞥すると振り返る。
「それじゃ用件は果たした。後は煮るなり焼くなりどうとでもしてくれ」
「はいはい。それじゃどこにでも行ってきてください。あ、どこに行くんでしたっけ? 行くあてないなら《埋蔵金の地図》でも持っていきます?」
振られた右手には本当に地図が握られていたが、ダルクは帰しない表情。
「邪険にしないでくださいよ。貴方はエンディミオンから決してアクティブに外交しなかった引きこもりさんなんですから、外部事情には決して明るくないでしょう? そのための地図なんですから」
リリーが右手首をそのままくいと前にやると、スナップにふられた地図がダルクの元へ飛ばされる。丸まっていたそれはダルクの前でふぁさりと開いた。地図の北方、丁度エンディミオンの北に当たる方角が赤く丸で囲まれていた。
「ライトロードの国、《ジャスティス・ワールド》です。自衛騎士団によって強固な防衛体制を築く、非常にセオリー通りの成長を遂げる新進国家ですね。外務担当からも悪い噂は聞いてません。ただ、貴方が求めている情報として……魔法使い族は、います。そしてエンディミオンより最も近い国家です。貴方が求めるであろう最低限の検索条件で絞りました。文句は有りませんよね?」
「用意が良いうえに理解が早くて助かるな……」
ダルクの、その表情は本気の驚愕が混じる。実際リリーは議事録を見て、ダルクとエリアの心情について応対する間に並行して情報を回し、求められる情報を引っ張り出した。
「褒め言葉として受け取らせていただきますよ。ま、私の示したレールに乗っかるのが嫌でしたらちょっと場所は離れますが、いくつか国家はあります。霊使いの首領さんに聞けばおおよそその属性の隣接国家の様子は把握できると思いますよ」
「……あれだけ啖呵きった手前いけるかよ」
「そう思われるのならひとまずは《ジャスティス・ワールド》の訪問をお勧めします。――光属性の首領さんも『帰ってこない』状況ですからね。聞くのであれば代行のピケルちゃんが宜しいかと」
「忠告としておくよ」
リリーに背中を見せ、部屋の扉に手を触れる。入室時意識してなかったドアノブの感触が冷ややかにダルクの触覚を刺激する。
「いってらっしゃい」
送り出しの挨拶にダルクは答えない。退室したダルクが視線から消えたのを確認したリリーはほう、と息をつき――。
「アウス様――本当にお疲れ様でした。本当に……」
地属性の首領の喪失は、同じ地属性のリリーの敬愛たる人物の偶像を削ぎ取っていた。机に伏し、肩を震わせ――。
「《ジャスティス・ワールド》ですか?」
数刻後、ダルクはリリーの忠告通りにピケルの元を訪れていた。机の上には湯気を立てる飲み物があり休憩中を伺わせる。ピケルはそれをくいっと一口やり、一つ息をついて目を瞑る。考えをまとめるような沈黙。
「リリーさんからどこまで聞いているかわかりませんが、基本的には察しの通り光属性が全モンスターを占める民族国家となっています。ただ国家の性格は私達の《魔法都市エンディミオン》のように一種族・複数属性でなる国家ではなく、複数種族を一属性――つまり光属性ですね、で束ねている国家です。そのため、国家内にはヒューマンもいればビーストもいます。ある意味私達の国家とは性格上相いれません」
それはまるで辞書に載っている定義のように。ピケルが淡々と述べる。しかしその口調はまるで言葉を選び、私情を挟まないようにも見えた。
「えと、話を遮るようですが、ダルクさんは言語については学ばれました?」
「触りだけだな……《ジャスティス・ワールド》、か。俺達の言語に訳すと……」
「こちらの言葉だと”正義の社会”とかが適切ですかね」
「正義……か」
「ちなみに、『ライトロード』。こちらは”光の使者”ですね」
ピケルの二言目を聞き、ダルクが眉をひそめる表情。
「正義の社会に光の使者。なんというか……」
「正直、胡散臭いとは思います。同じ光属性ですが、そこは否定しません」
「使っている言葉も俺から言わせると抽象的だな。上手くは言えないが……」
「宗教の匂いがする、ですか?」
「……それだ。まさにそれが言いたかった」
「調べによると、確かにまごうことなき新興宗教によって国家内の団結は保たれています。ただし、勘違いして頂きたくないのは、新興宗教という概念がすべからく悪ではありません。今のダルクさんは私情で善悪を判断しかねない――感情のトリガーが緩い状態なのですから、そのあたりの分別は気を付けてください」
ピケルの瞳は強い決意を秘めている。もう、目の前の杯の湯気は、立っていない。
「そうだな。態度でそう受け取ったのなら、悪かった。すまない」
ダルクが頭をぽり、と掻く。ピケルがその様子を見て腑に落ちない表情を作った。
「……なんだか、あの会議の時に比べて随分しおらしくなりましたね。リリーさんに何かお灸を据えられました? もしくは何か吹き込まれたとか」
「――まあ、そんなとこだな」
リリーに言われた、エリアの真意を鑑みて、ダルクがぽつりと答える。
「そう、ですか。私から教えられるのはこれくらいですね。あと、これ。差し上げます」
ピケルがごそごそと服飾のポケットをあさり、そこから一つの『道具』を取り出す。
「これは……」
「ポケットに入れておいたままにしておいてください。大したことないお守りです。それじゃ、いってらっしゃい」
それから数刻、地図を片手にダルクが《ジャスティス・ワールド》の門前に居た。
外殻には人口掘が石を削った趣で組み立てられ、緑が生い茂る。外側からでも見える住居やコロシアムは、文明的な不足の無さを漂わせる。
(良いように言えば平和的。悪く言えば排他的。確かにセオリー通りの文明国家ではあるな)
門の前に白い護装で身を包んだ門番に、ダルクは歩を進める。
(一番近い国家に魔法使い族がいるからそいつが犯人、とかふざけたことは言えねえ。だが、あの『一撃』を目撃した魔法使い族でもいればいい。かすかでもいい、まずは取っ掛かりだ)
地図を畳むと外装に突っ込み、その右手の汗をぬぐう。
青空に燦々と照る太陽。とても、数刻前に惨劇があった世界とは感じられない。そんな世界の表情だった。
「《魔法都市エンディミオン》から来た、闇属性首領のダルクだ。貴国のトップに君臨する者に会いたい」
それが、ダルクの第一声。ともすれば慇懃無礼なその一声は当然門番の神経を逆なでした。屈強そうな佇まいの門番。いくらダルクが手練の魔法使いといえど、その身は無敵ではない。喧嘩を売らないに越したことはない。
「申し訳ないが、いくら其がエンディミオンから来た首領であるとはいえ、そう簡単に我らの首領に会わせるわけにはいかない」
当然と言えば当然の回答。ダルクはそういった反応を受けることは事前に予想していた。しかし、何故《ジャスティス・ワールド》に赴いたか、という本音を言える状況ではない。言えば門番の矛先に構える武器が牙をむく。
(強引に突破出来るとは言え……喧嘩を売りに来たわけではないしな)
「せめて、訳さえ話しては頂けませんか? 私達も決して邪険にしようというつもりではありませんので」
ダルクが思案する脇から、一人の甲冑戦士が歩を進めてくる。剣と楯を脇に構える、テンプレートにのっとった戦士の風貌。
「あんたは確か……」
「ジェインと申します。この国の聖騎士パラディンです」
門番が『あんた』という言葉に一瞬顔をしかめたような表情を見せるが、意に反さないジェインの言葉に口を挟まない。
「パラディンか……」
「もしかして、私どもの『攻撃』がそちらの国に『暴発』してしまいましたか? なにせ私どもも厳しい戦闘をしているもので、もし攻撃が」
向 か っ て い た の で あ れ ば 申 し 訳 な い。
ジェインがにこやかに言葉を吐いた。その文が終わるまでもなく――ダルクは、どこで思考を放棄したか、ジェインの言葉を脳内で反芻する前に――瞳の色を落とし――
やっぱりこいつらが敵か。ライトロードに魔法使いはどんな奴がいた? ルミナス――ジェニス――ライラ――いや、どいつでもいい。ここが『敵』だ。全部ぶっ壊せばいい。
踏み出した足で一気に距離を詰める。右手に構えていた杖でジェインを突く攻撃を見せるが、当然手だれの聖騎士に奇襲は通じない。盾を使う間もなく、剣でのつばぜり合いで接戦に応じる。
「……どういう、真似ですか」
ジェインの際にも先ほどまでの慇懃さはかけらも残らない。見えるのは敵に対する明確な殺意。
「どうもこうもねえよ……」
(威圧が違ェ……! 戦闘になると底の力を増しやがるな……!)
一瞬ダルクは『バトルフェイズ』に入ったことを後悔したが、一瞬でその雑念を振り切る。
その、隙。
(後ろ――!!)
ダルクは直前までその存在に気付かなかった。後方から飛んできたのは魔法攻撃。そのベクトルには黒髪の魔術使いマジシャン。
相いれない属性の、相いれる種族。それほどまでに矛盾した相手で、当然ダルクも名を頭にはべらせていた。
(ライラ――! 攻撃が――!)
直前に迫る攻撃。直撃を覚悟した瞬間、その魔術による一撃が『消失』した。そして、理解。お守りとして備え付けられていた小さな鏡。名は《閃光を吸い込むマジック・ミラー》。
(ピケルはこれを読んでたってのか! 流石は同じ属性じゃねえか……考えは見通してるってわけかよ!)
「インプリゾニング――魔法吸収か……古風な手を」
思わぬ奇襲の失敗に後方のライラは一言呟き、構え直す。――きゅっと屋外に鳴るヒールの音はライラが永続罠パーマネントの破壊の体制に入ったことを意味する。
(舞わせるかよ!!)
一瞥したダルクは杖の力を持ち、後方へ引き――ジェインから一気に距離を取る。そして、杖を地へ大きくかち鳴らし――詠唱。
「《魔法の筒》!!」
ダルクの慟哭と同時に、眼前へ円筒形のコミカルな物体。だが、ライラは同相ゆえ、その物体の危険性を予知する。
「辞めろ! 今その中に装填されているエネルギーは我らライトロードの物。闇属性のおまえがそんなものを使うとこの地で暴発することになる! ただちに詠唱を取り下げろ!」
「やめっかよ」
口端を吊り上げるダルクは筒をライラの方向に構え、
「無能属性が!」
ライラは対応するように、杖を回す。同時にダルクの脇差にあった鏡が砕け散る。だが、ダルクはひるむことなく筒を――
「おらあっ!」
蹴飛ばした。魔力による浮遊力を失い、地に豪快な金属音を響かせ落下した物体が、豪速の勢いでライラに転がる。
「け、蹴り……! 転がっ……!」
予想だにしない物理攻撃にライラの足が一瞬もつれ、速度を緩めない筒の回転がライラを直撃する。
質量を持った金属の塊の衝撃をもろにうけたライラは後方に弾き飛ばされ、それを確認したダルクは改めてジェインを見据える。
「思ったよりも武闘派ですね。気に入りました」
ジェインが呟き、盾を後方に投げ捨てる。からんと鳴る軽い音はジェインが『かなぐりすてた』決意の証明。
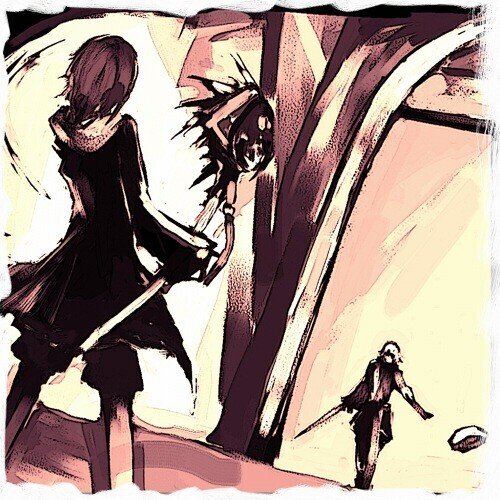
「だからといってそれは暴挙を許す理由にはならない!!」
剣の切っ先を向けたジェインの突進にダルクは振り返り、杖を構える。だが、
「はぁっ!」
前方に構えた杖の前を人影が一つ横切る。与えられた衝撃と共に杖は吹っ飛びながら回転。水晶音を響かせる。
ととん、と軽技の動きでその『人影』は杖を掴み取り、してやったりの表情。
「エイリン……!」
武器を失ったダルクは渋い表情。
「ははあん、あたしのことも存じ上げてるのかい! 嬉しいね! だが、」
エイリンと名前を指された僧侶モンクが屈託ない笑顔で返答し、途中トーンを落とす。
「あたしなんかにかまってると死ぬよ?」
「その通りだ」
一瞬で距離を詰め切ったジェインがダルクの首元に剣を構える。
「くっ……」
かすかに動けばジェインの剣。逃亡を試みればエイリンの拳。戦闘を試みようとも《閃光を吸い込むマジック・ミラー》は割られ1:2。勝てる要素を失った。
そこまでを考え切ったダルクはふっと目をつむり――
「俺の負けだ。殺すなら殺せ。だが、一つだけはっきりさせたいことがある――それだけを解明させる時間をくれ。それが終わったらなんとでも料理してもらっても構わない」
「――というわけで、つい先刻、俺達の国の魔法使いが一人『魔法使い族の攻撃によって破壊された』。意図しないものであったとはいえ、ジェインの発言がその死を挑発するように聞こえつい我を失った。言い訳に聞こえるかもしれないが、これがすべてだ」
「なるほど……そういった事情が。そうだとするとあの時の私の発言はあまりにも不適切でした。心より陳謝致します」
公衆の面前である《ジャスティス・ワールド》門前から来賓応接室に移り、ダルクの『弁解』をライトロードの使いらがなだめ聞く。ある時は真摯に、ある時には質問を交え。
ジェインが一礼すると同時に、ライラがダルクに詰め寄りダルクの手にかけていたワッパーを外す。
「ここからは特に内密にしてほしいんだが」
ダルクが意を決したように一つまたたき、後方を確認――続ける。
「破壊されたのは地属性の首領、アウスだ」
その言葉に一番反応したのはライラ。そうか、と呟いて――
「アウスがその憂いに……同じ魔法使いとしてあの属性掌握力は崇拝に値している。敬意はあれども、その力を妬んで影討ちを目論もうなんて計画と実力は私には持ち合わせていないと思っている。――まあ、いくらジェインが攻撃を受けていたからとはいえ、死角から攻撃を行った私に弁解できることではないとは重々承知しているが」
「ああ。そりゃあんたの事情も承知している。それに、これまでの戦闘と態度を見るに――ジェイン、あんたは相当人が出来ていると思う。そんなのが、いくら対抗属性の首領とはいえ、嫌味な台詞を吐いてくるとは思えない。だからこそ」
「……」
ジェインは壁にもたれ目をつむり、次の一言を待つ。
「本当に『魔法使い族が外部に攻撃を行わなければいけない状況』なんだな?」
「……、……はい。おっしゃる通りです。この世界は確かに混沌につつかれています。大抵はどこの『フィールド』も特定の国と争うことはありませんが、自衛という名目上『対象を狙わない攻撃』というのが黙認され、それゆえ『どこからされたものかわからない攻撃』というのものがゆめゆめあります。ダルクさんの……エンディミオンも非常に強固な外殻をお持ちであるため内部に被害があるわけではありませんが、外殻が揺れる機会はあるかと思います。しかし特に外務上『戦争(デュエル)』は行っていない。ゼロサムゲームを行ってしまえばそこには敗者が発生する。誰しも責任を……自分の決定で国が消失するなんて悲劇は避けたいものですからね。しかし……」
そこまでを淡々と語ったジェインが一言置き、
「だが、私達は『戦争』を行っている。そう……気がつけば私達はある一つの国と戦争を行っていた」
「その相手は……」
「はい、相手国は『AOJ』という国家です。ご存知ですか?」
「エー、オー、ジェイ……すまない、補足してもらえるか」
「わかりました。……通り名は『Ally of Justice』。『正義同盟』と名乗っています。恥ずかしながら、私達ライトロードと彼奴らの効果の相性は非常に悪い。応戦はしていますが、がむしゃらにやってるゆえにエンディミオンに攻撃が向かっていないと胸を張っては言い切れません」
そのジェインの表情は先の冗談めかしたものではなく、非があればそれを全面的に認めることを感じさせる凛々しい物。ダルクはそれを数秒見つめ、憂う。
(《ジャスティス・ワールド(正義の社会)》に「ライトロード(光の使者)」に、おまけに「AOJ(正義同盟)」。聞けば聞くほどキナ臭い話じゃねえか。本当にこんな闘いにアウスの『破壊』が入り込む余地はあるのか……?)
「なあ。あたしは馬鹿だから見当違いなことを言ってたらすまない。アウスが葬られたという事情はわかった。だが、あんたらの国エンディミオンの外殻は近代兵器でも破れないほどの強固なものだと聞くぜ。単純に内部犯である可能性を洗った方が確実なんじゃないのかい?」
眉を落とし腕を組み、悩む表情。そのダルクを揺り戻すようにエイリンが話す。自分の思いを単純にぶつけつつダルクの方に歩を進め、それまで手にしていた杖をダルクに手を渡す。ダルクはその行動に すまない、と一言添え数秒悩み、答える。
「ああ。確かに言っていることはわかる。そう考えるのは自然……だが、」
「ええ。だけれども、それだけで内部犯と決めつけるのはいささか尚早とは思うわよ」
ダルクの言葉を打ち切るように、入口から高い声が。
「初めまして。私はこの国で召喚師(サモナー)を執り行っているルミナス。ライラに呼び出されて挨拶しにきました」
「どうも」
「まま、そんなつれない挨拶はよして。挨拶だけして戻ろうかなーと思ってたら実に私好みの議題が出てたからね。ちょっと混ぜてよ」
ルミナスと名乗った褐色・金短髪の女は見目通りの明朗快活な声色でにししと笑い、
「私達は魔法使いだからね。その辺りの軸を逸らすのはいくらでもいけるってわけ」
自分で遮った話題をレールに乗せ、続ける。
「要は『外で行った攻撃』を『中で行った攻撃』であるように誤認させればその時点で真実が雲隠れする。言い換えれば攻撃の対象を逸らすということ。そうだね……一番に考え付くのが……」
「まあ、《魔法の筒》だろうな。自作自演だと言われないために先に可能性は潰しておきたい」
数秒の間もなく。ダルクが答える。その妙な即答にルミナスがなになに?と疑問ぶった表情を見せるがライラがいぶかしげな反応を見せるだけ。
「あれは攻撃を吸収するシリンダーと、射出するシリンダーを複合した魔法。《ブラック・ホール》から《ワーム・ホール》、そして《ホワイト・ホール》にまで至るエネルギーの転移を利用した科学の延長のような魔法だが……『使える』以上それは可能性だ」
「ええ。他にもエンディミオンの中の『モンスターのコントロールを得て』しまえばいい。ただ、この可能性は数多の種族が可能性に上がりうる。得手不得手はあれども、殆どの種族がやろうと思えばやれる手段ではあるね」
ルミナスが腰に手を当て補足する。次いで一言、
「まあ何が言いたいかっていうと」
「今一分考えただけでもスペシャリストは簡単に方法を思いつく。それも、それで犯人を決められるかと思えば逆に可能性が広がってしまうくらい。すまないね、発言としては墓穴だった」
話を聞くに徹していたエイリンが苦笑して軽率さを説く。
「だが、俺達魔法使いも神様じゃない。魔法という名目で何もかもをできるわけじゃない……完璧ならここに来るまでもないからな」
「ところで……」
ダルクがぐるりと周りを見渡し、
「俺の国が言えた義理ではないが、《ジャスティス・ワールド》の名士は女ばっかだな。男は情けないのか?」
その質問にジェインがふっと口端を上げ、剣の切っ先をダルクに――距離は遠く刺さる距離ではないがそれが匂わせる物は――
「名士たる男は皆、戦地に赴いてますよ。くっくっく、これで『おあいこ』ですね」
「…………だな」
ダルクのこぼれたひきつり笑いと、名士共のしてやったりな表情。来賓室はフィールドのアドバンテージを取り戻す。鼻先遠くに向けられたジェインの剣の切っ先。ダルクはふと目を瞑り口端を上げた。
「そう……だな。今の発言はあんたの感情を間違いなく逆撫でした。我を失って俺に反撃を仕掛けなかっただけ、あんたは俺より人間が出来ているってことなんだろうな……すまなかった」
「いえいえ。お互い冗談の間が悪かっただけです。お気になさらず」
ジェインも突き出していた剣を鞘に収め、にっこりと笑う。
「それにしても」
「なんだ」
「先ほどのちょっとした戦闘。あの中で見せて頂いたアイテム……《閃光を吸い込むマジック・ミラー》でしたか。あれには驚きました。簡便な仕掛けですが、実に効果てきめんなアンチスキル――エンディミオンにはあのような魔具が溢れているのですか?」
「さっきも言ったが別に魔法使いは万能じゃない。元来俺達魔法使い族が体内に持つエネルギーを道具に込めているだけだ。あんたらも知ってるかもしれないが、魔具として総称できるものはその名称に『マジック』『マジカル』といった装飾語がつく。逆に言えばそれ以外のものには俺達の魔力は及ばない」
ダルクは実にすらすらと自分の『庭』を語る。もっとも、ライラやルミナスといった同胞が既にいるから隠しだてする必要が無い、という名分もあったからだったのだが。
「ここは、良い国だな。シンボルを大事にしているのがよくわかる」
ダルクが来賓室の壁に祀られているか細い剣《ライトロード・レイピア》を一瞥し、呟く。
「いい、佇まいでしょう」
その言葉に応えたのはライラ。先ほどの戦闘で見せた敵意は感じさせず――隠しているだけかもしれないが――やんわりとレイピアを見つめて続ける。
「輝かしい色彩。その魔力は我らが首領である《裁きの龍》――ドラグーン様によって与えられたもの――通常、装備魔法も魔法の一種であるためその創生には私達魔法使い族の力が必要になってくる。しかしドラグーン様は自身の力のみで《ライトロード・レイピア》を作りだした。そのため、ここにあるレイピアは他の国には絶対に見られない――ライトロードのための武具なのです」
(俺達の国にも《魔術の呪文書》等、相応の限定装備魔法はある。ここの首領は魔法使いではないが創生する力があるということか……)
手入れされたレイピアからは後光がさし、本来のつやとあいまって輝きを誇る。ダルクはそこから目を外すとジェインと目が合う。
「エンディミオンに魔法具があるのと同様、この国に与えられた祝福と見るべきでしょうね。ときにダルクさん――先ほど少しお話しした敵対組織AOJについてですが」
「……ああ」
「AOJは闇属性を主体とした対生物兵器。これまでの応戦の過程で光属性に対して強烈なまでの耐性を持っているという報告を受けています。ダルクさんに誤解を招かないように先に言わせていただくと、決して我らは闇属性を嫌悪する立場にはありません。ただ、AOJは属性の観点を抜きに来ても非常に相性面で辛い。まるで我らライトロードを駆逐するような印象さえ受けています」
「そんなことを俺に話していいのか? もしかしたら俺はAOJから派遣された陽動かもしれないぞ?」
あまりにもすらすらと現状を解説するジェインにダルクが差し込む。それは反応を見ているのか、あるいは――
「そういった事情はないと確信しています。AOJは装備に頼ることなく、体内に光属性に対抗する術を持っています。言うなれば、先のダルクさんのような《閃光を吸い込むマジック・ミラー》といった小手先の手段を取らずに私達を駆逐することが可能な軍勢なのです」
「……そうか」
「それで先立ってダルクさんにお願いがあるのです。その《閃光を吸い込むマジック・ミラー》のような力――光属性に対する対抗能力があるのなら、きっと闇属性に対抗する能力もあるのではないでしょうか?」
その推測は真実に切り込む。だが、ダルクは言葉を返さない。
「ダルクさんの力を借りれば――例えば闇属性に対抗する術として、名付けるなら《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》のようなものがあれば私達はAOJに立ち向かう手段を持てます。お力添えを、頂けないでしょうか」
来賓室は、静まり返る。ダルクの解答を迎え入れる静寂。
「……勘違いは、するなよ。事実、《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》という存在はあるし、俺の力を付加すれば今ここで『作れる』。だが、お前らライトロードが絶対的に正しいのかはわかんねえ。まだそれを分け与えられるほどお前らに信用は、ない」
「――承知、いたしました。……ダルクさんも求める真実のために情報が必要でしょう。『男の名士たち』が居る前線に、一緒に向かいませんか」
「魔法使いという存在は貴重なんですよ」
ジェインとライラに追従する形でダルクが《ジャスティス・ワールド》を出国し、案内に従しつつ歩を進める。後ろに遮るものが無い平原――ジェインの呟きが木霊する。
ダルクは魔力の創成に異常がないかどうかを手を握りつつ確認しながら、ジェインの話に聞き入るふうな態度を見せた。
「魔法を使えば直接手を触れなくとも戦闘に一機を見いだせる。特に対光属性の直接戦闘に特化しているAOJを相手にするうえにおいてその能力を失うことは万死。そのため汚れ役は戦士(ウォリアー)のガロスと獣戦士(ビースト)のウォルフに一任されている。配備の定石から言って、またケルビム(審判員)様たっての提言となれば私達に抗う考えはない。だが、それでものうのうと後衛が茶をすする前で血肉争われるとなると心が痛む」
ジェインが俯き、心の内を畳む。手に持ったつややかな剣を見つめ、呟く。そのみねに血は滴らない。
「だからこそ……!」
ライラが唐突に眼を見開き、杖を掲げ、語気を強め後ろを振り向く。そこには、異形の機械が猛烈な勢いで迫る。
「任せろ!」
伴い、ジェインが振り向きざまの一閃。橙を誇る機械が上下半身分割し、地に転がる。断面は電磁ショートし、もはや機械は動かない。
ライラはその場にしゃがむと『機械』がブレードを持っていた手を持ち上げ、その裏に貼られていたシールを見る。
「AOJには個体名――シリアルが設定されています」
ライラはその鉄の塊を凝視すると、
「この個体はガラドホルグ――と命名されているようです。その情報も元々はガロスやウォルフが前線によって切り込んで得ていた貴重な情報だったのですが、昨今は《ジャスティス・ワールド》近くまで攻め入られている始末。決して状況は良くは無いでしょう」
「そいつは……」
「ええ、ダルクさんの危惧することはわかります。既にガロスやウォルフが『破壊』されているのではないかという懸念。私達もそれを考え、定時連絡の頻度は上げています。悪い報告はありません。――よく頑張ってもらっているのですよ」
草原になびく一陣の風。草原の青い匂いが三人の鼻を刺激する。
「ガロスやウォルフは我らライトロードの中でも屈指のアタッカー。苦戦はしながらも彼らが決してやられないのは戦闘でそれを打開できる地の差があるから。いくら相手が強力な対光属性能力を持っていたとしても、戦闘まで干渉するほどのものではない。例えば今のガラドホルグのように――」
ライラが語ったそれはライトロードがここまでの戦争で得た研究成果だった。ガラドホルグは既に解析がされており、その実『光属性との対峙時に微量のリミッター解除を自動で行う』という性質があるものとされていた。度重なる解析の後、その力量は《ライトロード・パラディン ジェイン》に満たないことは既に証明が行われていた。だからこそ、
「量産型相手への対策は根こそぎ済んでいます。だからこそ――それ以外の懸念。例えば『戦闘を行わずして光属性を破壊しつくす』ようなAOJが現れたら……その時は――」
『その時は』、その後の言葉は吐かれなかったが、3人の想定を揺らすのには十分の言葉。だからこそ、その30分後。
AOJのフィールド――そこはいわば漆黒の廃墟。先ほどまで太陽が輝いていた時間なのに、時間の感覚なく夜に追いやられたような錯覚を受ける。今この瞬間にも屋敷の壁が崩れ落ち、コウモリがいななくような不穏な雰囲気。
「話には聞いていましたが、実際に足を踏み入れると禍々しさが締め付けるようなものがありますね……」
ジェインが後方を警戒しつつ実直な感想を漏らす。油断はあっただろう――ここが『暗闇』に近い状況にあることから、視界すべてに映る物を是認できないという。
しかし、
ごり、と固形物の感触がダルクの足元から。
それは、なじみ深い感触。柔らかさと、固さが同居した感触。ダルクはその事態を考慮しただろう。
一方、ジェインはダルクの居た左方に反射的に目を向け、そして現実を直視する。
「うわああああああああ!!」
そこにはライトロードの戦士(ウォリアー)――ガロスが横たわっていた。屈強な肉体と無骨な顔つき。およそ肉弾戦に持ち込まれて負けそうにない戦闘人間が無表情で横たわっているギャップ。
「!!」
ライラがそれを一瞥し、一瞬目尻を震わせるが――すぐさま360度見渡し――敵が居ないかを確認する。
「くっ……!」
「ガロスッ!」
ジェインが膝を地につけ、ガロスの体を揺する。
「なあガロス! 気絶しているだけなんだろ! 目を覚ましてくれよ!」
そうリアクションしたのは無理もない。3人が見た光景は決して『惨状』ではなかったからだ。ガロスの四肢は満足状態、胴体にも外傷はなく、辺りに血痕すらない。しかし、
「そいつ、もう死んでるぜ。あんまり無下に扱うべきじゃないと思うがな」
一番冷静に状況を見ることができる第三者のダルクが、ガロスの青い顔色を見て淡々と発言する。
「確かに外傷はないが――思っていた『懸念』が現実のものになったんじゃないか」
目の色を変えない発言。ジェインとライラはその淡々とした表情にぞくりと悪寒を覚えるも、瞬間で冷静さを取り戻す。
「だ、ダルクさん……これは『物理攻撃』でも『魔法攻撃』でもない――近距離攻撃でも遠距離攻撃でも相手への接触を要する――これほどまでに外傷が無い『破壊』を見たのは初めてです……こういった『破壊』は存在するのですか!? 無知な私に教えてほしい!」
ジェインの慟哭が暗闇にこだまする。それはともすれば相手に自分たちの居場所が割れるかのような大声。しかしジェインは湧き出る怒りと悲しみを抑えられなかった。
「……ある。俺達魔法使い族にも『攻撃以外の破壊』を得手とする奴はいる。《執念深き老魔術師》のビンド――こいつはその『第三の手段』で敵を排除する手段を持っている。俺にもその種は吐いてくれないが、そいつの手にかかれば『中から』命がもがれる」
「なか、から……」
「単純に五臓六腑の機能を停止させるほどの力があるといえばそれまでだが、無機物相手でもその力は発動可能だからな。詳しいことはわからねえ」
「そういった力が相手にあるのなら……よりAOJの個体が能力を増して――戦闘に頼らずとも私達を排除できる可能性を持つようになったのなら――事態は一刻を争う……」
ライラが杖を持つ手に力を入れ直し、呟く。静寂が先刻より怖い。
「どうする。事態は一刻の予断を許さない事態らしいんだろ。退くか、行くか。戻ってガロスを弔うのも勝手だが」
「いえ、……私達は問題を先送りにしていました。本来、彼ら前線にのみ全てを任せて――立ち止まっている時間は無かった――先に、行きましょう」
「そうか」
ジェインの言葉に、ダルクは干渉せず相槌を打つ。
「ジェイン。ちょっと待って」
その言葉にかぶせるようにライラが呟く。
「焦る気持ちもわかるけど、緊急事態。先に国の方へ連絡を入れましょう」
「……お願いする」
その言葉を口にすることによってガロスの死を認めるようなものだったのか。ジェインの語気は決して強くなかった。その返答にライラは呟くと、腰元から魔力通電機モバホンを取りだす。
「――ケルビム様。ライラです――」
「そう、ですか。ガロスが……」
『はい。要因は不明。しかし戦闘以外の何らかの手段で内部から破壊されています。ケルビム様、ご指示を』
電話の先にいた主はケルビムと名乗る。彼女は厳格な雰囲気を漂わせる白調の一室の椅子に腰かける。場の名は《コート・オブ・ジャスティス》審判所。位は『審判員(エンジェル)』。
「前線に赴いてくれたこと、感謝します。そのままガロスの殉死を無駄にすることなく切り込んできなさい。ただし……」
『……ただし?』
「無理は絶対しないこと。死ぬことは、決して、美徳ではありません」
ケルビムの言葉は途切れる。その真意を掴み取ったライラは、
『……ありがとうございます』
その一言だけを、返す。
「それでは、武運を」
最後に伝えた言葉とともに、ケルビムは魔力通電機の電源を切り、体の力を抜く。
「いずれ訪れると考えられていた事態。しかしそれをいざ把握すると、決断もすくみますね」
ケルビムは審判所の一角で呟く。その眼前には青白く厳かに輝く龍。神々しく輝く胴体と反目するように――血ぬられたかのような紅い爪。
「……」
「《ジャスティス・ワールド》の長たるジャッジメント・オブ・ドラグーン様。それに仇なす業深い軍勢AOJ――”Anti of Judgement”とはよくいったものです。どうするのです? このまま保守的戦略を貫くおつもりで?」
そのケルビムの言葉はともすれば慇懃無礼。だが、自身の体格と比べ物にならない巨大な龍を相手にしケルビムは怯まない。それは自身の能力への自信の表れか。
「我が、直接赴こう」
「――今度は、随分と思い切りのいい決断ですね。当初からそうされていれば貴重な戦力を失わなかったものなのですが」
「口が減らぬな。その皮肉。言い換えれば『アレ』を出せということか?」
「御冗談を。まだドラグーン様がご出撃される方が幾分現実的です」
涼しい顔をしてケルビムが続ける。しかし、一人と一体の間には険悪な雰囲気はなかった。
「いずれにせよもう少し……様子見(ドロー&ゴー)、ですね。『アレ』は切り札。対応すべきはAOJに限らない。易々とは手の内を見せたりはしませんよ」
ケルビムの睨むような視線が、厳かな審判所に反射する。 魔力通電機の電源を静かに落としたライラが、ダルクの手元を見据え呟く。
●
「ダルク」
「……なんだ」
「私はガロスの仇を取りたい。そのためにお前に助力を請うのは馬鹿みたいなことなのだろうか」
その声は震えていた。冷静な情と、熱い怒りをかきまぜたような複雑な声色。
「何を正しいと思うか決めるのは最終的には俺だ。だからその質問には応えられない」
ダルクが即答で突き放す。「だが……」
「――」
「だが、このままウジウジしてても埒があかないってのも真実だ。俺の持ちうる力で、この場の『正当防衛』は手伝ってやる」
「ダルクさん……」
ジェインがその言葉に呟き、笑みを浮かべる。それ以上に感謝を述べず、慈愛のごとき視線だけを向けて。
「いみじくもあんたらはさっき言ったよな。”外傷が無い『破壊』”と。何故その考えに至った?」
「……!? ダルクさん、それはどういう意図の質問――」
「質問をしてるのはこっちだ。何回も言わせるな」
威圧がかった瞳で一瞬返す言葉。
「ジェイン、あんたは剣士だ。多かれ少なかれその剣で葬ってきたものも多いだろう。それとライラ――俺が暴走した時に向けてきた攻撃、ミラー越しでも相当な一撃だった。あんたも決して戦闘を不得手とはしてないはずだ」
「何が言いたい」
「あんたら二人で『物理攻撃』『魔法攻撃』の想定は出来るだろう。だがその知識のみで、あのガロスの状況を『破壊』と断定できるか? その想定が出来なければ単なる失神とも取れる状況――外傷の残らない攻撃だ。少なくとも、一度はその現場を経験しないとあれだけの材料でそこまでは至れないはずだ」
よどみなく吐き出される言葉。そのままダルクは続ける。
「少なくとも一人は『あんたらの中』にもそういう手法を得意とする奴が居るだろう。教えてくれよ」
その言葉に二人は息を呑む。
(こいつ……!)
(この期に及んでも正確に自分の目的を見失っていない……! ここでこの人を敵に回せない状況であることの弱み、そして『事実』を突き付けることによる私達ライトロードの解明すら同時に行う冷酷性――やはり同行は危険だったか……!?)
ジェインがライラの方を振り向くも、それに呼応するようにライラは首を横に振る。
「油断、してたのは事実だな」
ライラが大きく息を吐き、諦観した表情で答える。
「その通りだよ。私達ライトロードも決してそのような手段を持たない訳ではない」
「ライラ……!」
「いいんだよ、既に9割がた看過されている事実。責任は私が持つ。《ジャスティス・ワールド》にはケルビム――審判員エンジェルたる方が居る。その御方は卓越した戦闘能力を持ちながらそのことにうぬぼれることなく、打開が難しい敵に対し『排除』の能力をお持ちの智天使だ」
「なるほどな。それで、その手段は?」
「――知っているか知っていないかも言えないな。よしんば知っていたとしてもそれは墓まで持っていく所存だ。どんな拷問を受けようとそれを口外するつもりは無い」
瞳は強く決意を語る。黒いまなざしは決意を語る。
「そうか」
納得したような一言を呟くが、間もなく口は開かれる。
「じゃあなんでそいつケルビムは前線に出てこないんだ?」
「……。切り札は、先に使った方が負け……腐るほど世界に蔓延する戦術思考だろう?」
「そうか? 今の事態を見る限りカードは切らなければいけない状態だと思うがな。それでも出せない事情……そうだな、回数制限とか使用後の反動。おそらくはその辺だろう?」
ダルクはあたりを見渡しつつ、杖の水晶を軽く握る。それは魔力を込めるような行為でジェインとライラは口を挟まなかったが、淡々と吐き出された台詞にぴくりと反応は隠せなかった。
「まあ、けるびむさま には後でじっくり話を伺うさ。生きて帰ることが大前提だからな」
そのとき唐突に、目の前に現れた『機械』。見るに、さきほど対峙したシリアルとは見受けられない機体。 ジェインとライラは眼前に新たな敵を見据えて初めて、殺気を自覚した。ダルクはとうに戦闘態勢。ジェインはその『差』に息をのみつつ、覚悟を決めて体制を整えた。
「おい」
「……なんです」
ダルクの肝のこもった呟きにジェインが短い返答。それはおおむね、その後につむがれる質問の内容を互いに飲み込むような静寂。
「あいにくながら……」
「あれは初見だ。はっきり言って、先のガラドホルグとは異種の殺気を感じるな」
ジェインの言葉をさえぎるようにライラが返答する。眼前には四肢と胴体部分が輝かしく光る機械。手入れが済んでいると思しき金剛の輝きが、機械としての強さをにじませる。
「ダルクさん。貴方が持ちうる『魔法』で打開を望めますか?」
「……あんたら肉体派は軽々しく言うがな。魔法ってのは決してノーリスクじゃないんだよッ――!」
ダルクが返答をした瞬間、機械がダルクに照準を向けレーザー光線を発射する。すんでの所で殺気を感じ取ったダルクが距離を取りレーザーをかわす。
「例えば相手が『魔法を無効化する効果』を持っていたら? 相手にむざむざ俺の効果をさらけ出すことになってしまう。もっと悲観するならば『魔法を反射する効果』を持っていたら? 風車の理論で味方陣営が惨事になっちまう。だからこそ、魔法は正確な分析の元――」
「一撃で仕留められるように仕向けなければいけない。同意だな」
ライラが距離を取り、視線を軽く『機械』に向ける。
「おいライラ」
「……なんだ。――まあ、おおよそ想定はしているが」
「罠は無いか。もしくはあんたの力で『割れる』か」
ダルクは対峙を向ける方向を緩めることなくライラに問う。ライラは一つ息を吐き、
「全く……あの『喧嘩』一つでしっかり私の能力を看過するのは流石というほかないな」
そう言いながらライラが足元をひねるような軽やかな動作。
「ジェイン。割れる罠はない。戦闘による突破が見込めるようであればバトルに回ってもらえるか」
「了解だ」
ジェインが剣を構え直す。
「……念には念を」
その強張りを崩すかのようにライラが呟き、ジェインに片手剣の柄を向ける。
「これは……《ライトロード・レイピア》。隠し持てるような大きさではないはずだが……」
「《アームズ・ホール》で今、あの部屋からサーチさせてもらった。勿論事前に許可は取ってあるさ。……私が持ちうるとっておきの特殊魔法だ。大事に扱ってくれ」
「――。わかった」
ジェインは自身に力がみなぎることを感じていた。元より戦闘に対する潜在能力は自他共に認めるポテンシャルであること。それを含めたところで滅多なことで手にすることができない神聖武器《ライトロード・レイピア》を手にしている。盾を構えられないことによる防御性能の低下は斟酌しなければいけないとはいえ、それは守りに入らなければ大したリスクではないことは決して短くは無い戦闘経験から掴んでいた。
(いける。単純なパワーであれば今の私はケルビム様に肩を並べられるくらいの力の迸りを感じる)
「慢心は無い。今この瞬間バトルフェイズに入り、あの機械を叩き潰す……!」
鋭い視線。隙の無い構え。にじりよる歩みにも微塵と立ち入る瞬間が無く、それはまさに達人たる動き。
「はああああっ!」
ダルクが唾を呑んだ瞬間、ジェインが慟哭とともに一気に距離を詰め、
十字に剣を一閃。
鋭い太刀筋が機械の胴と頭部に食いこみ――食い込んだように見え――瞬間、 ジェインが・ ・ ・ ・ ・『爆散』した。
「!?」
支えを失った剣とレイピアが豪快に地面を転がりガランガラン!と金属音をなびかせる。
「な……」
どちらの口から漏れたか、状況を咀嚼するに足りない起承転結。
対峙する『機械』に傷は全くない。ただそこに存在する結論としての、手だれの剣士が機械を破壊しようと攻撃した瞬間、消し屑にされたというあまりにもむごたらしい現実のみがそこにはある。
●
「《ライトロード・ウォリアー ガロス》《ライトロード・ビースト ウォルフ》《ライトロード・パラディン ジェイン》……これで3体」
審判所の一角。ケルビムは何を見ることなく、ひとこと呟いた。
「尊い殉死により着々と準備は整いつつありますね。正直事態は膠着していると慮っていただけにまだまだ私も上司として甘いですね」
「甘い、か」
「ええ。部下の力を過信していました」
涼しげに吐き出されるその言葉に、ドラグーンは言葉を返せなかった。
「本当に展望は面白いですね……ドラグーン様は、我らライトロード陣営には切れる手札がいっぱいあることを自覚して頂いて、はったりを掛けることに積極的になって頂きたいものです。それに――」
浅く笑う視線は開きつつある審判所の扉へ。
「本来絡まる運命に無かった《闇霊使いダルク》の存在も面白いですね。事態は荒れれば荒れてくれるほどより私どもにとって優位です」
「やだな。そんなごちりと一緒に私に目線向けないでくれるかな。私はとても良い魔法使いだよ」
目線を向けられた先には銀髪の女魔法使い。麻色のローブを肩まで羽織り背丈に似合わない長い杖を構える押さない顔立ちはともすれば『子供』も思わせる。だが、この審判所の立地状況――警戒性の高さを考慮し――そこに飄々と現れるその力は――。
「ようこそライナさん」
「おじゃまします」
ライナと呼ばれた少女が深く一礼しひょうきんに笑う。
「光属性の魔法使い。ただしその血にはライトロードは流れていない……生粋の『裏切り者』」
「えっへっへ。お褒めに預かり光栄です」
淡々と吐かれるケルビムの言葉に、口端を全く震わせない『笑顔』でライナが応対する。
「《闇霊使いダルク》が事態に混入する前から貴方はこの事案に関与していた。全く……どういうことです?」
「どういうことでしょうねえ」
「貴方とダルクの関係を察するに偶然とは片づけられな――」
「んー」
ケルビムは瞬間、油断を自覚した。瞬きをした瞬間ケルビムとライナの距離は詰まり胴体に押しつけられる《閃光を吸い込むマジック・ミラー》。
実態は《死のマジック・ボックス》を利用した座標転移と、手持ちのミラーを素早く脅迫に転嫁しただけではあるのだが、一連の流れは『慣れている』。
「あたしの詮索はしないって約束でしょ? 大人なんだから約束は守ってくれたら嬉しいな」
表情は変わらず、だからこそ行動とのギャップはケルビムの頬に汗をつたらせる。
「貴方達の前では《光霊使いライナ》じゃない。ただの『ライトロード・ナビゲーター』。不服かな?」
ケルビムに押しつけていたミラーをポケットにしまいこみ、こつこつと逆方向に歩み――空席の椅子に着座。佇まいにケルビムとドラグーンは言葉を返せない。
「あい変わらず……私達に心を許してはくれない……ですね――!」
ケルビムは後悔した。ふと気を許せば対面の少女――ライナは無垢な少女に『見える』がその本質は決して神聖ではないということ、それを忘れた対応を取ってしまったことを深く顧みる。
「心を許すも何も、私は貴方達のような『光の使いライトロード』への信仰心は無いんだからね? ビジネスってことは忘れないでほしいな」
「承知、しますよ」
ケルビムの外見年齢から鑑みれば年端もいかない少女相手への態度とは思えない光景。ドラグーンはその様子を黙って見つめ、
「ライナ女史よ」
「はいはい、ドラグーンさん。如何なされました?」
心の底が震えるような重低音の声色が空間を支配する。それに怖じ気つく様子を見せないライナの軽い返答が違和感を増幅させる。
「取引条件としての『到達点』は押し迫っていると見ていていいのだな?」
「《ジャスティス・ワールド》の平和を守るため、私に協力を仰がれた。スーパーヒロインのライナちゃんは持ちうる知識と手札を総動員して駆逐法を提案し、稟議した。決裁は貴方の元も通っているはずだし、順調な進捗状況であることは理解しているとは思うけど?」
「うむ、それは承知している。だが、やはり実物を見ていないというのもどかしいのでな」
「確かにその辺の事情もあることはわかるよ。うん、今日中に完成品は見せられるように努力する。――ダルクくんが餌にかかってくれたとなると、なおのことやる気も上がるしね……!」
杖をこつこつと床に触れさせ、ライナは笑う。
「それじゃ、ちょっとご挨拶に行ってきます」
ケルビムとドラグーンの様子を尻目にライナは《コート・オブ・ジャスティス》を退席し――
「~~~~!!」
装備魔法による攻撃力の強化、アタッカーたるジェインの一撃。そう簡単に負ける要素はなかったはずだ。
「……くっ――!」
だからこそ不可解は恐怖。足は震え、杖を握る手は脂汗でぬめる。視界は気を張らなければ白くかすむくらいの光景。
「ライラァ!」
「ッ。ダルク!!」
腐っても二人は同種の魔法使い。
「絶対アイツには触れるな!」
過去の戦闘状況や魔法使いとしての知識は紆余曲折あれど同じ結論をたどる。
「一旦退却でいいか! 文句は言わせねぇぞ!」
「……異議は無い! いったん戻してくれッ……!」
ダルクは一瞬の返答に頷き、ジェインの遺体――いや、『肉塊』に目をやり、やり切れない表情を作るが――すぐに本分に意識を戻す。
「《ディメンション・マジック》!!」
●
そこはかつて『彼ら』が話し合った来賓室。
音沙汰もなく、いきなり壁際にダルクとライラが召喚され、どさりと重い音ともに壁にもたれこむ。
「!」
驚いたのは丁度その瞬間部屋にいたルミナス。
「ライ……! ッ――!」
息が上がっている二人。恰好を意識すらできずぶれのある座標転移で帰還した魔法使用。いたはずの『戦士』の未帰還。状況を咀嚼し、ルミナスは理解した。だからこそ、二の句は継げない。
「ライラ! ジェインは無事!? 治癒は可能な状況!?」
「……無理だ――既にあいつは――『肉塊』だ……!!」
ライラの口から放たれた事実は『嘘偽りない』。戦争の台風の目に放り込まれている状況下、下手な慰めは内部組織を攪乱してしまうだけ。ライラもルミナスもそれを理解して、意識を冷静に保つように尽くす。
「ルミナス……あんたの能力は『治癒』なのか……?」
ダルクが息を切らしながらルミナスの方に問う。ルミナスは表情を歪めながら、
「ええそうよ。墓地に行ってすぐであれば蘇生も不可能ではない。だけど、遺伝子レベルでの損壊となればいくらこの瞬間破壊されたとしても無理な相談……!」
「そうか――」
「ねえダルク。貴方も闇属性魔法使いの首領なんでしょ!? 貴方の効果でみんなを救うような大魔術はないの!?」
『ご挨拶』してきたときからは想像もつかない、すがるような声色。ローブを掴む手を振り払うこと無く、ダルクは答える。
「俺に……効果なんてねえよ……!」
「無いわけがないでしょう? 貴方は魔法使い族の中でも闇属性を統べる偉大な魔道師なんだから!」
間の悪い冗談を、そんな表情でルミナスが反抗する。だが、そのすがるような視線をダルクは意に反さない。
「……」
ダルクは冗談のつもりで言っては無かったから、次の言葉を継げなかった。
「俺達魔法使いの首領――『霊使い』は圧政のために効果を持ち、それによる恐怖政治をしているわけではないんだよ……各属性の霊使いの元にたまたま同属性の魔法使いが支持をしてくれる……自分で言うのは辛い物があるが、どうやら『カリスマ性』を見込まれて、らしい。逆に言えばそれ以外に戦闘やバックアップに特化するような効果を持ち合わせていない。それも『効果』なのか? それを『効果』とするのなら、――人間の性格ってなんなんだろうな」
「……」
「俺、アウス、ウィン、ヒータ、エリア。同種の扱いを受けている5人だが、それぞれ『牽引する力』があったんだろうな」
深く息を吐き、回顧するように呟く。
思い出に浸る。
「だるくくん。あたしをのけものにするなんて悲しいなー」
浸ることができた時間は、3秒も無かった。それまでなかった気配、声色。――だが、ダルクは湿った意識ですら、その元を判別するのに瞬く時間は一刻も無い。
「……!」
「《光霊使いライナ》も立派なカリスマ性あふれる効果を持つ霊使いの一人だよ。異論は無いよね?」
「ああ……国を放り出した期間が長すぎてマジで忘れてたがなあ――!」
視線がぎらつく。入口に立つライナの表情はやはり笑顔。ダルクの据わる視線を真っ向から受けても態度は全く怯まない。
「お勉強は、済みましたか?」
「……なんの話だ」
「ほんのちょびっとでも世界の歯車を見つめて、『設定』が見えてきたかって言ってるのよぉ」
ライナの声色は聖母のような包み込む広がり。だが、ダルクはそれを『受け付けない』。
「何を、言ってる」
「みんなそれぞれ効果を持っている。それがみんなの強みであり、みんな違ってみんないい」
「……」
「だからこそよ。なんで『カリスマ性は効果じゃない』なんて結論になるの?」
「それはただの性格じゃねえか! そんなもんが効果だったら、あいつを! アウスを慕っていた地属性の魔法使い族は! アウスに洗脳の効果を焚きつけられたってことになるじゃねえか!」
「アウス? ……ん、あー……その通り大正解! 私の議論で紆余曲折無くその結論にいくなんて――」
右手を広げ口元にあて、口元を隠すようなリアクションの大きな驚愕のポーズ。だがその下では――
「ダルクくん。ちょっとは『想定』してたでしょ?」
「ライナァァァァァ!!」
「ちょっと待ちなさい! 人の庭で暴れるな!」
震える表情のダルクと、薄く笑い続けるライナ。たしなめたのは項垂れていたライラ。今にも戦闘がはじまりそうなその光景にくぎを刺すように慟哭する。
「あえて失礼を承知で言いますが両首領! 場をわきまえてください!」
「ライラちゃんごめーん」
「……すまん」
周りに星が出そうな謝り方をするライナと、徹底的に落胆するダルクの行動は対極的。
「ね、ね。じゃあ首領らしく机に向かいあって『会談』しましょうよ」
自分の庭のように長机を慣れた手つきでガイドするライナ。その動きをライラとルミナスは口を挟まず見つめる。
ダルクは黙ったまま案内に従いライナの正面に座る。
「……なんでてめえがここに居る。もっと言えば今頃何故、この世界に顔を出した。もっといえばライラ、ルミナス。あんたらはライナのことを知ってたんだな。別に悪いとかは言わねえが、先に聞いておきたかった事実だな」
「やだ。第一声がそれ? 普通『会談』ったら握手してカメラ目線で笑顔でしょ? そうしないと外交カードにすらなりゃしないよー?」
「ふっざけんなよ……!!」
「私はずっとここに居たわよ。もっと言うなら、世界に顔を出してなかったのは私ではなく貴方じゃない? この引きこもりさん」
ダルクの第一声を撫で返すような反論。
「ここにいると世界がよく見えるの。なんでアウスが破壊されたのかも大体見えてきた」
「アウ――、……! なんでライナ、てめえがそのことを知ってるんだ?」
「腐ってもピケルの上司だからね。報告は頂いているよ。その時はさすがにちょっとビビったけど、展望は掴んでる」
「どういうことだ? 教え……てはくれないだろうな」
「きっと信じないだろうしね。それなら自分でたどり着いた方が御土産にはなるでしょ?」
らいらちゃんお茶ー。そんな軽い声を焚きつつライナは机の下で足をバタバタさせる。
「ここで感動の再会をして余計そう思ったわけですよ、ダルクくん。決して私は貴方を嫌いじゃないよ?」
肘下で湯気を立てるお茶にたたずむ湯気。吹き消すような声色でライナは呟く。
「……まあ、ね。決して私は自分の国を見捨てたわけじゃない。ただちょっと、外遊中にこの国が闇属性に苦しめられてる現場に居合わせちゃってね、同じ光属性で見捨てられなかったというか、捨て《マジキャット》を最後まで面倒みる形になったというか」
「……」
「だからこそ、折角闇属性のダルクくんが居合わせてるんだ。『設定』を知って、この国を救ってあげてよ」
「煙に巻くな」
「なんのかんの言って、私達の持つ『カリスマ性』は『効果』なの。これは挑発じゃない、事実。ダルクくん、貴方は自身のカリスマ性について思ったことは無い? ほんのかすかなことでもいい」
「他の奴らみたいに効果に『覚醒』――効果を発動した記憶が無い……ってことか。気付いたら慕う奴が出来ていた。そう、影響力はじわじわと増してたって感じだったか……」
「うん、大まかに正解。私達の効果が発揮するのは寝起きの瞬間。すなわち一日の始まり。その時に私達は無意識に効果を発揮するの。近く理論はまとまるとは思うけど、便宜的にその効果発生を私は『転生(リバース)』と呼んでる」
「『転生(リバース)』……」
「ええ。私達はリバースしたときに無意識に自身と同じ属性のモンスターを洗脳してるの。もっとも、洗脳と言っても『慕う』に過ぎないレベル。罪悪感を持つほどではないよ」
眼前のカップを一口すすり、続ける。
「信じないのも自由、だけど……私達『リバース効果持ち』の効果を強制的に起こすことは出来る。例えば《月の書》」
「《月の書》……本来は子供に眠りを誘うための本だが……使いようを誤れば大人ですら泥のように眠らせられる魔法――」
「要は眠れば、効果発動のトリガーはかかってくる。意識的に眠り、すぐ起きれば狙った範囲での洗脳は可能なの。結論は……見えた?」
「AOJは闇属性。俺は『闇属性モンスターを洗脳するリバース効果を持っている』。AOJの核となるモンスターを手駒にしろ……ってことか――!」
ダルクは傍目邪悪に笑い、ライナはその『結論』に同調も否定もしない。
同席するライラとルミナスはその様子を見ながらも、口を挟めない。ライナの導く戦術の正当性を咀嚼しながら――彼らは――。 「AOJの核となるモンスターを手駒にしろ……ってことか――!」
ライナは、ダルクの発したその結論に言葉を返さない。
(こいつの……ライナの考えにのっかるのは癪だが――)
癪、だよねー。
「!?」
だんまりを決め込んでいたライナが突如発した文節。
ダルクはぞくりと悪寒を感じるとともに『考えることをやめ』、ライラとルミナスは訳の分からないその『発言』にきょとんとした表情。
「くそアマ……ほんの数秒油断するだけで当然のように釘ぶっさしやがるな……!」
対面するライナは傾げ笑いを浮かべるだけ。――行ったことは単純、読心。光属性首領代行のピケルが元々は得手としていた能力ではあったが、
「部下ができることが上司が出来ないと恥ずべきでしょ? もっと褒めてよ」
独自の思考と努力によってそれを『身につけた』。さもそれが普通であるかのようにふるまっているが、それが普通であれば世界の摂理は狂ってしまう。たおやかに笑う裏、どれだけの努力を積み重ねたかは想像するべくもない。
「くそ……」
(だが……読まれたからってなんだ? こいつとは『そんなことで語れる仲』じゃあないだろう……? いいぜ、全部筒抜けにしておいてやる……!)
ダルクは数秒目を瞑り考えをまとめると、改めてライナに視線を向ける。その瞳は淀まず、だからこそライナは――
「へえ、素敵な覚悟――。でもでも、思いつめると胃に来るからね」

「?」
「おやすみなさーい」
意図が伝わらない会話の流れ。挨拶が放たれた瞬間、ダルクが膝から崩れ落ちる。
「……!?」
「大丈夫大丈夫。自分の気持ちに正直になって――」
場所さえ違えばその笑顔は聖母のような、気持ちを全て委ねたくなるような声色。
「くそ……!」
だが、ダルクは抗う。その奥に秘められた本性は体が覚えているから。
「抵抗しても無駄だよ。《月の書》に抗うなんて、サイレントちゃんみたいなことはやめてよねー」
意識が混濁する中、ダルクが最後に見た光景は片手に《月の書》を掲げるライナの姿。表情は変わらず――優しく笑う。
「ライナさん」
その様子をルミナスは口を挟まず見つめていた。ダルクが崩れ落ちた瞬間――額の汗をぬぐうことなくぽつりと呟く。
「んー?」
「私は光属性。ライナさんの考えがすべて正しいと思っています。だからこそ、ダルクさんとライナさんの関係は『尋常ない』と推察します……!」
「すべて正しい、かー。流石ルミナスちゃんは魔法使い……洗脳度合いも薄いね」
(真に洗脳されてるなら、正誤を考える力すら欠落している――からね――)
「尋常ないか、普通かと思うかは聞いた人次第の――単純な幼馴染だよ。別に隠すようなとんでも話でもないし、のろけてあげるよ。えっへっへ」
それは、とんでもないくらい過去の話。
「あたしのゆめは! 全世界を光で包みこむこと!」
身長いくばく足らずのライナが平原の中、いきなり立ち上がり、ぎらぎらした目で宣言する。その横では同じばかりの身長のダルクが寝転がりつつ、
「……寝言にしちゃポージングが派手だな。起きてたか」
「さっきから起きてるし、寝言じゃないよ!」
ぷいと頬を膨らませそっぽを向く。ダルクはその様子にいちいちの演技臭さを感じつつ、
「だってあいつら頼りにならないんだよ! そりゃ、あんなので首領とかほざいてたら『失われた黄金時代(THE LOST MILLENNIUM)』とも言われるよ!」
「……」
ライナの指す『あいつら』。その実をダルクは聞き返そうとしたが、直前で声を発するのを辞めた。それを口にするのは、どの道決して良い返答をもたらさないと思ったから。
「そうは言うが、おまえは何が不満なんだ。《停戦協定》の設立、属性間の調整、あいつらの働きは決して非難されるようなもんでもないと思うがな」
「ダルクくん何を言ってるの? それが不満なんだよ!」
「……」
その時ダルクは思った。『ああこいつとはこの先いくら時間があっても相いれることはねえ』ということを。だが、それもダルクは口にしない。その勇気が無かったこともあるが――、それを口にすれば――。
「ダルクくん。実際貴方も理解してるはずだよ。『失われた黄金時代(THE LOST MILLENNIUM)』の4人が世界に降りた後、遅れてダルクくんが世界に降りた理由を!」
「『闘争の創生(THE DUELIST GENESIS)』……世界をドンパチに落し込むカンフル剤になれ――そういうことを言いたいのか」
淡々と述べるダルクに、ライナはしおらしそうに一つ首肯するのみ。その様子をちらりと見たダルクは、
「知るかよ」
「ダルクくん! いい加減理解しようよ! そんなんだから私が――私が世界に生まれた!」
「何言ってんだよ。てめーは光属性。もともと俺とは相いれねえ。本望だろ?」
その言葉をきょとんとした表情で聞いたライナは膝の力を抜き、ぽすと平原に座り込む。
瞬間、青い風が平原を凪ぐ。二つのショートカットはさらさらと揺れ、瞬間の静寂を作り出す。
「ちがう、ちがうよ。そうじゃないんだよ」
「なにがだ」
「『SHINING DARKNESS』……それが私の生まれた理由」
「シャイニング――いいじゃねえか。光で、属性を照らしてやれよ」
「そうじゃない。『SHINING DARKNESS』――『際立つ闇(SHINING DARKNESS)』――」
『それ』を聞いた瞬間、ダルクに強烈な悪寒が走る。体が反射的に動き、立ちあがった四肢がライナと距離を取る。
構えた杖は防衛本能。先ほどまで全く様子も見せない脂汗が頬をつたり、息が短く切れる。
「怖がらせちゃった。ごめんね?」
「てめえ……!」
「私は光属性。だけど、ダルクくんの気持ちも理解してる。だって、光と闇なんて表裏一体。単独では生きられない属性なんだからね?」
意味はわかる。思想としても理解は出来る。だが、ダルクはその言葉に返す言葉が見つからない。
「だから、ちょっとだけ喧嘩、しよ? 幼馴染の軽い喧嘩。後腐れもなあんにもない、じゃれ合いを!」
瞬間、ノーモーションによる『霊術』の発動。猛烈な風速が一瞬でダルクの頬を切り、すんで遅れてつうと血がつたる。
「あんしんしろー、いまのはみねうちだー」
けたけたと笑うライナの表情は冗談のかけらもない。『本気で殺しにきているし』『外れたんじゃなくて外した』。その意図は十二分に伝わる。
(風霊術――ウィンの十八番じゃねえのかよ!?)
「危機感を煽らないと、きっとお話は進まない。ぬるま湯の平和じゃ駄目だってことをなんでわかってくれないかなあ!?」
ごうと、ライナの後ろで蜃気楼が揺らめく。熱気ではない、そこにあるのは灼熱。注視すればダルクの足元には魔法特有の揺らめきを見せる炎が一つ。
(今度は「紅」……火霊術――それもさっき風であたりをえぐったから大気が不安定になってやがる……暴発も辞さねえぞ……)
「くそ……」
揺れる炎。はためく風。ダルクがそれらを見定め、覚悟を決めたように前へ進む。
「なになにこっちにきて? 腹パン? 魔法使い族なのに魔法で戦闘しないで、リョナる方に思考が走るなんて野蛮人だねえ!?」
「……」
ダルクが力強く歩みライナと距離を詰め、その額に手をつける。
「……なに。熱でも出したんじゃねえかとか、言いたいの?」
「――《闇霊術-「欲」》!」
ライナの挑発を異に返さず、ダルクは魔法を発動する。
「『際立つ闇』なんだろ? だったらそんな闇属性――リリースさせてくれよ……」
《闇霊術-「欲」》は闇属性モンスターをリリースし、詠唱者が魔力を得る魔法。真にライナが闇属性だったなら、その時は――
「てめえは光属性だろ。こっちに来るなんて真似は――よせよ――」
一瞬でもライナが消えてしまうのではないかという思考が走った自分を、ダルクは戒める。
最後の方は細切れになった声色を抑え、ダルクがひざから崩れた。
「……」
ライナは無防備な背中と自身の杖を交互に見、大きく息を吐く。
「ダルクくん、ごめん。ちょっとあたまがゆだってました」
それは誰から見ても棒読みな一言。だからこそ、あえて棒読みにした様子が聞き取れる一言。
「ちょっと、どころじゃねえよ……」
「焦りもせず、そんなガチな反応されたら冷めちゃうよ」
その様子は悪びれない。しかし、
「やり方は悪かったかな、とは思う、うん」
弱弱しい声で吐かれるその言葉は、決して棒読みではなかった。
「……でも私は、本気で『今の状況』は良い物とは思ってない。私、ダルクくんのことは放っておけないし、納得してもらえる『何か』を見つけてくる」
俺はそのとき、そもそもライナが何に納得していなかったのか、何を見つけてこようとしてたのかを――考えてすらいなかった。
だけど、あいつは初めにそう言ったじゃないか。だから、出ていった。
そして、今。あいつは『それ』を見つけて――俺につきつけてきた。ああ、これ、必然だったんじゃねえか――。
「起きた?」
ダルクが気付いた時、彼はライナに抱えられていた。
「どういうことだよ」
「ふふん。お姫様だっこ」
「鼻息荒くして言うなよ」
「だってダルクくん眠ってたし仕方ないじゃん。華奢なライラちゃんにやらせるわけにはいかないしね」
「てめえが眠らせたんだろうが」
ダルクは特にその姿勢に抵抗せずあたりを見渡す。そこはほんの数時間前訪れた、AOJの主幹フィールド。
「……いい夢、見れた?」
「さいっあくの思い出が蘇ったさ」
その返答にライナは寸分考え、
「ふーん。じゃあ私はすごくその夢、見たかったね」
限りない満面の笑みでダルクを地面に下ろし、答える。
「言っとくが、何を見て、何を判断材料とするかは、俺が決めることだ」
「……知ってる。これが私の見つけてきた『何か』だから、あとは身をもってそれを感じて」
目の前にはジェインを肉塊にした、禍々しい機械。ダルク・ライナ・ライラの三人が距離を取り、機械に対峙する。
3:1による数的優位のバトルフェイズ。だが、ダルクとライラは先の爆散の光景がフラッシュバックし、距離が詰められないでいた。
「……」
ライナはそれを一瞥し、にこりと笑う。
「びびるまでもないよ。もう『あれ』はこっちのものだから」
一瞬ダルクはその言葉の意味を掴めなかった。だが、反芻するうち――ライナとの会話の内容が脳髄を駆け巡り――理解。
「随分用意周到じゃねえか……《月の書》で俺を眠らせた。結果、今俺はリバースした。そのことにより、あの機械は俺のコントロール下になったっていうことか」
「そういうこと。ダルクくん、心情的に『リバース』の概念を信じたくはなかったでしょ? だから身を持って、機械的に理解を求めたわけ」
「俺は、そんなの……求めてねえよ……!!」
ダルクがカタストルを見つめ、歯ぎしりをする。強く目を瞑り、杖を一閃。――瞬間、その『機械』の足がダルクの動きとシンクロするように一薙ぎする。ライナはその様子を微笑のまま見つめ、ダルクは自分の取ったアクションに『認めるもの』を感じ、渋い表情。
「殺人鬼を人の責任下に押しつけて、てめーは満足かよ」
「機械族のモンスターだから、殺人機って言う方が正確かもね」
「言葉遊びしてるんじゃねえよ! 人の話を」
「聞いてるよ」
ダルクの言葉を打ち切るような声色。ライナが語尾を強めたわけではない。だが、ダルクは反射的に自分の言葉を打ち切ってしまった。
「冷静になりなよダルクくん。私の言動も行動も、貴方を煽ったうちにも入らないようなかすかなものだよ。だって、私には理念がある。ライトロードを守りたいという確固たる行動理念がね。結果としてダルクくんの心を傷つける結果になってるのは謝るべきポイントだろうけど、でも私は謝らないよ」
「……」
「いい加減諦観しちゃおうよ。光と闇が並びたてるなんてことはありえないんだからさ」
「その、なんでも知ってますって態度が気に入らねえんだよ」
再びダルクが杖を構え、『機械』に意識を同調させる。多くは語らずとも、怒りの矛先の始点と終点は容易につかみとれる。
「ライナさん、あんまりダルクさんを煽らないで下さい! ここで内輪もめするのは有効ではないです!」
険悪な雰囲気に、だんまりを決め込んでいたライラが口を挟む。だがライナは、
「いいよ。それで気が晴れるなら、私のド真ん中……ブッ刺して。私はあらかじめ戦闘への保険として《ミスト・ボディ》をまとってある。軽度の戦闘なら受け止めきれる。折角だからそれ、威力を試しておきたいでしょ? 戒めと、理解してあげる」
その妙な饒舌に、その時のダルクは疑念を抱かなかった。所謂『一発殴らせろ』と同義の事を行うだけという軽はずみな考えだった。
「ライラ……あいつの言っていることは事実か。サンドバッグにして、いいんだな」
「本気で言ってるんですか……ダルクさん――事実ライナさんの纏うオーラには装備性のものが感じられます。でもそれって――」
本当にただの幼馴染の喧嘩なんですか、口元で言葉が止まる。
「……じゃあ、やらせろ」
迷うことなく、ダルクが呟き、じりと距離を詰める。ライナはほぅと力を抜いたと思うと視線を横にやる。何かを呟いたかのようにも、見えた。
「あああああああああああああ!!!!」
慟哭と同時に、『機械』が轟音とともにライナに向かい、心臓付近を一突き。
「かっ……はッ――!」
けぷ、と水濁音がライナの胸元から聞こえたかと思うと、豪快な吐血。だが、ライナは死なない。
「はァ――!」
ライナを纏うミストが肢体の周りをつつんだかと思うと、ものの数秒で何事も無かったかのように穴はふさがっていた。
「きっ……くぅ――よおしゃ、ないなあ……」
しかし、ライナは崩れた表情のまま力なく笑い、続ける。
「まあっったくぅ……あたしが気を遣えなきゃ、こんな結果じゃなくて『爆散』してたとこだったんだよ……!」
「どういう……!?」
「気付いた? 私も本来光属性なんだから、それに触れた瞬間……攻撃どころか『接触』するだけで爆散するとこだったんだよ? 普通ならね」
地面にぺたりと座りへへへと笑いつつ語る内容は、物騒極まりない物だったが――続ける。
「どういう意味、だよ……」
「やだなあ、なんとなく意味はわかってるはずなのにカマトトぶっちゃって。ダルクくんも魔法使いなんだし黒ミサくらい行くでしょ? ダルク君も光属性の遺伝子、もらっときゃいいのに」
「……ああいうのは、好かねえ」
「ウブだねー。どうせ減るもんじゃないしヤッときゃ役得なのに」
その口調には照れも恥ずかしさも、隠すべきものも、なにもなかった。彼と彼女の意識の違い。プライベートにかかるところまで、ねじれは深かった。 あえてライナは口にせず、ダルクも口にさせなかったが、それが遺伝子構造の真理。この世界の能力は遺伝子の交わりあい。ライナは現実、闇属性としての遺伝子を少なからず獲得しており、その手段は――。
けほ、とライナは口腔にまとわりついた血を吐き捨て、
「どうかな? 『たたかい』の前に一区切りはついたかな?」
「……」
「それじゃあ、ダルクくんのお願い。叶えてあげよっか。会いたいって言ってたんでしょ?」
そこに現れた言いようのない悪寒。ダルクは思わず唾を呑み、眼前のライナから目を離せない。
「よそ見してて、大丈夫?」
思わず立ち止り凍りついたダルクの視線をいなすように、ライナがたしなめる。その言葉にはっとしたようにダルクは辺りを見渡し――そこに、煌びやかな装飾鎧に身を固めた妙齢の女性の姿を見定めた。
「っ――!」
瞬間ダルクはその正体を理解した。自己紹介、名乗りなんて不要。そこに感じる威圧は先に紹介を受けた――
「お初に目にかかりますね、闇の御方。私の名はケルビム。ライトロードの名の元で審判職を仰せつかっております」
しかし彼女は名乗る。まるで自分が虫けらのように小さき存在であり、名乗らないとその存在がそこに無いとすら思わせるような自然さで。だが、ライナは元より、初対面のダルクですらそこに感じた威圧。そのうえで――、
「ダルク様。この状況について、説明を頂けますか? 場合によれば、いえ――場合によらなくとも、私は貴方に『審判』を下さなければいけないかもしれません」
ちゃき、とケルビムの持つ杖から軽やかな金属音。向けられた杖の切っ先はまごうことなき正義。
(都合が――悪すぎる――!)
確かに。確かに確かに! 激昂に任せライナを貫き、その結果血とライナの口元が殺人現場の形相すら漂わせる状況にある事実は完全に俺の逆上だった。その現場を見られたのなら結果として疑惑の目を向けられることは当然の帰結だ。だが――、
「ケルちゃんは、そんな些細な喧嘩を問題として無いよ」
案の定ライナは『それ』を見透かしたように台詞を吐く。
(問題としてるのは、この機械――その『機械』が俺のコントロール下にあることだ。ライトロード側からみれば、どう見積もっても『扇動者』として俺を勘定するしかなくなる――そして、そんな疑惑を払拭するのは無理な相談――事実俺はこいつをコントロールしてしまっているんだから!)
遠くない未来か過去か。ピケルはにこにこと自分の『趣味』を語っていた。
「すいりしょーせつ? ええ、好きですよ。一番好きなのは『《名推理》シリーズ』ですね。推理しているのが探偵と思ったら、実は容疑者とされていたバンダナの男だったっていう叙述トリックには胸が躍りました!」
人差し指をぴっと立て、畳みかけるように。対面する者への質問に軽やかな口調で返す。
「え? そうなんですよね。なんで容疑者になる人ってすべからく余計なことするんですかね? 例え自分が犯人じゃないと高らかに宣言しても、例え真犯人の策謀により仕組まれたとしても、殺人現場に落ちている血塗れの包丁を触ってしまえば、真犯人を見つけない限り自分の疑惑を晴らすのは難しいですよねー」
「け、ケルビム様。少々お待ちください」
その対峙の中、意外な角度――ライラからたしなめが入る。
「確かにダルク首領はライナ様に《ミスト・ボディ》がったとはいえ、喧嘩と称して破壊衝動を加えました。それは否定しようがない行動です。しかし、申し訳ありませんライナ様――ライナ様の行動に非が無かったかと言われると私は諸手を挙げて同調できない部分があります」
「おー。イエスマンになりきらないライラちゃん凄い素敵!」
振り絞るように俯き意見を述べるライラ。ライナはそれに逆上せず、頷きもせず、ただただ軽く茶化すだけ。
「……承知しておりますよ」
ケルビムはライラの目を見つめ、ついでライナの四肢を舐めるように一瞥し、そして、
「審判する身として、そこに『事実』があれば、動かざるをえないのですよ――!」
ぎゅっと握りしめた杖の尾はかすかに震える。
「ライナは……」
ダルクは紡いでいた口を重たげに開く。
「ライナは、これを想定して俺にその『機械』を投げたのか? 俺を犯人として『仕立て上げる』ことで事態の収束を狙うのが目的で?」
「……」
「いや、違う。てめーは善人ではなくとも、自分の正義には全力で取り組み、そのうえで結果を掴み取る奴だ。少なくとも、こんな『落とし所』で納得する奴じゃあないだろう。大体てめーは俺よりも大局を『知っている』。どう考えても、ここで落ち着くには余りにも尚早だろう……!」
俯きあげた表情はあまりにも悲しげで。敵を敵として捉えられないダルクの甘さが、そこに、
「尚早か焦燥か知らないけどさ、ダルクくんは本質を見誤ってる。なんで、ケルちゃんが来たからってもうライトロード編が終わったかのように観念してるの?」
「どういう、ことだよ」
「ケルちゃんもさ、楽ーにしててもいいんだよ。どーせ」
もう1人死なないと、召喚条件整わないでしょ?
「……ッ!」
ライナが吐いた傍目意味不明の言葉は空間を木霊し、ケルビムがその言葉にぴくりと反応する。
「ダルクくんもさ、まずは自衛努力しよう? その『機械』は自分のものじゃないんだったら、ケルちゃんに破壊してもらえばいいんだよ。ケルちゃんは審判長に足る実力は持ってるから、戦闘面で問題は無いよ」
「だが、光属性と接触すれば……」
「うん、そうだね。じゃあダルクくんに求められる解決方法って、一つでしょ?」
「くっ……」
ダルクは内心、誘導もここまで行けば詐欺ものだという思いを抱きつつも、ここまでたどり着くのに疑念を抱かなかった自分を戒める。
「さくっと作っちゃお? 《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》」
《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》を使えば――闇属性モンスターの『効果』が封殺されるに等しくなる。それは――
(俺は偽りなく只の人間になり下がる。それゆえ、それまでリバース効果で引っ張っていたその『機械』は、自我を取り戻す。そして、闇属性であろうその『機械』の、接触による戦闘回避効果も無効化され、只の機械になり下がる。いいこと、づくめじゃねえか――!)
あいつらにとってはな――!
(厄介なアンチ属性の上を生殺しにしたうえで、自分達の抱える問題の収束を図る。それほどまでに《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》の存在は偉大だ。ライラには、状況によれば作る余地があることをちらつかせていたとはいえ、このカードの切り方はあまりにも勝手が悪い――!)
「……わかった。だが……効力が及んだ瞬間、その『機械』は自我を取り戻す。きっと暴走を始めるが、その瞬間叩いてくれ――頼む」
「承知いたしました」
ケルビムはここまでの流れを最初から想定していたかのような涼やかで、滞りない返事。
「じゃあ、いくぞ……」
ダルクが静かに目を瞑り、気を貯め、集中を高める。どこからか具現化された鏡は禍々しい色をかもし、魔力は溢れんばかりに空間を包み込む。空間がAOJの元闇属性に染まっているのが幸運だったか、もしこれが通常の空間であればその違和感は相当なものであっただろうことがわかるようなもの。
「ほら、よ」
出来あがった魔鏡をダルクは忌々しげにケルビムに手渡す。ケルビムはそれを首肯し受け取り――その瞬間――
「~~!!」
その『機械』が清音とも金切り音ともつかない奇声を上げ――ライラに向かい飛びかかり――
「くっ!」
ライラが『覚悟』をした瞬間、ケルビムがその前に立ちふさがり、一撃をいなし返す杖が胴部を突く。
ケルビムの一撃の重さはダルクにも伝わる程度に響き、その『機械』は粉砕され、砕け散った部品が一帯に散らばる。
「……プレイング、甘いなあ」
ライナがそれら一巡したアクションを垣間見るも、まずは大きく溜息を吐き、発した一言は誰に向けたものか。
「ありがとう、ございます」
ケルビムが切れる息を整えつつダルクに向かい合い礼をする。そこには無力となったダルクを潰してしまおうなんていう邪心は全く感じられず、
「……ああ」
その反応にはダルクも塩らしく感謝を受け取るしかなかった。
「あんたには俺を出し抜こうなんていう邪心は感じられない。解決するまで……俺はこのままでいいさ。その方がこいつら――AOJを潰すのに好都合なんだろう?」
「ええ、誠に申し訳ありません。ご協力を頂けるのに、感謝し……」
Trrrr….
ケルビムが謝辞を述べていた合間、ダルクのローブのポケットから魔力通電機のアラーム音が響く。ダルクはケルビムに断りを入れ、通話に切り替える。
さあて、
「もしもし。俺だ……ああ、エリアか。どこに居るかって? 《ジャスティス・ワールド》辺境の、AOJの――」
そろそろライトロードなんかのちまちまとした紛争には、飽きてきたでしょ?
「!? ……ど、どういうことだよ!?」
『だから言ってるじゃない! 闇属性の魔法使いが暴動を起こしてる! ビンド爺にも協力は依頼してるけど、あくまでもトップは君なんだから! 鎮静のために至急帰国して! お願い!』
見えてきた? そろそろ見えてきた? 世界なんて理解しなくても、キャラクターなんて理解しなくても。
『じゃあ速やかに戻ってきて! お願い!』 プツッ
「……切れたか」
あまりにも性急に用件のみを伝える通話が切れ、ダルクは渋い表情を見せつつ、辺りを見渡す。
「――聞こえてたと思うが、一旦国に戻りたい。『俺の問題』も解決してない中戻るのは癪なんだが、これも責務だ――また改めて来させてもらう。ところでライナ。《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》だが、俺が《魔法都市エンディミオン》に戻ったら効果は……」
「切れるよ。そんなに捕球範囲は広くないから。ただ、こっちに戻ってきた時に失念さえしなければ、ね♪」
ライナがなびく髪の毛を弄りつつ答える。首をかしげつつ楽しげな声は、ショーを前にした子供のように。
「じゃあ、一度《強制転移》させてもらう。しばらく後に、な」
「ばーいばーい♪」
大局的に。マクロに。見つけられたくない物を隠すためには、技術より力技。探すべき範囲を広くしちゃえばいい。
ダルクが消えたフィールド、虚空を見つめる形でケルビムが呟く。
「……ライナさん、ご機嫌ですね。まさか《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》に関して」
「嘘はついてないよ。ほんとほんと。ただね、ようやくだなと思ってさ」
そして、ライナはどこに向けたかなとも思われる言葉を、意味深な笑顔を作り呟き――。
ここからが、ダルク君の腕の見せ所だよ。
「さあ、ちゃぷたー1.5!! らいとろーどへんの合間のシエスタってとこかな! 《魔法都市エンディミオン》での提起・解決編だよ!」
ずびし、と片指立てて、パフォーマーのように大袈裟に明後日の方向をライナは指差す。
その発言はきっとメタなもので、その佇まいはピエロのようで、見方を変えれば朗読者のようで。そしてそれゆえ――。
ほんの半日程度離れていただけなのに、そこはどこか懐かしかった。
(なんにも外見は変わっちゃいねえな)
エリアに緊急通達の名の元帰国を命じられたとはいえ、ダルクはそこに違和感を感じられなかった。《魔法都市エンディミオン》を守るバリアはあらゆる攻撃で揺らされていたが、エリアが焦りの元招集をかけるような特段の事情を見受けられない。
「……おかえり。気持ちも整理してないのに戻ってきてもらっちゃって、ごめんね」
その背後から、落ちた声が響く。声の主のエリア。先の通電機から感じた怒号のようなものは感じられず、落ち着き払いといえば聞こえはいいが、消沈ともとれる声色。
「一応俺も首領だ。私情だけで動いてはいられねえからな」
「そっか。たった一日でなんかダルク、変わったね。男子1ターン会わざれば刮目して見よ、ってとこかな」
へへ、と力ない調子でエリアは笑う。
「ま、玄関で立ち話もなんだしね。会議室、いこっか」
●
「やっぱり、俺のせいなのか」
会議机で二人は見合い、切りだしたのはダルク。
「……本人が自覚がないものを本人の責任にする気は無いよ。そもそも今の事態、なんで起きてるかすらわからないんだからね」
「――闇属性のモンスターが暴走……アンコントローラブルになってるんだよな。原因らしきものが全く思案できないと言えば、嘘になる」
ダルクはエリアを真摯に視界にとらえ、切りだす。エリアはその言葉に一瞬はっとした表情を見せるも、すぐに強く視線を戻し、
「教えて」
「つい数分前、俺は《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》を創造した。《ジャスティス・ワールド》下で作成して、俺はその中では効果を失っていたが――《魔法都市エンディミオン》でもその影響を失ったとみれば……」
「ちょっと待って。色々突っ込みたいところはあるけど、その考えに至ったってことは……ダルクくん。ライナちゃんに会ったね?」
ひときわエリアの瞳の色が強くなる。心なしかその目頭が震えているようにも見受けられる。
「『効果を失う』――リバース効果の概念。私はあの冷徹な思想……ルールを受け入れられない」
「俺もそうだ。出来ることなら俺達がそんなルールで縛られているなんて考えたくもねえ。でも、事実がそのルールを縛っている」
「ライナ様に会えた、いや、会ってしまったんですね」
部屋のドアをこんこんとノックし、数秒後ピケルが入室――うなだれたような表情。
「年を経た貴方達は決して邂逅してはいけなかった。心情的にはどうあれ、光と闇の首領は水と油と言う他ないんです」
強く足の歩を進め、ダルクから目をそらさずにピケルは話す。揺れる帽子の居心地の悪さに気付いたのか、軟い手つきで帽子を脱ぎ、右の手に抱える。
「それがわかっていたからこそ。ライナ様は外遊に出た。抑えきれない物が、きっとダルクさんを潰すと考えたから」
「……随分とあいつの肩を持つな。同じ光属性の狢、コントロールされているから当然といえば当然だろうな」
「はい。私は光属性ですからね。ライナ様のリバース効果に縛られてる……何と言われようとそれは事実です」
ピケルのよどみない回答にダルクは一つ舌を打つ。
「……確認したいんだが、本当に《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》の創造と現在の状況の関連性は無いんだな?」
「ええ、ありません。もしそれの関連性があれば私達は、光属性と闇属性のそれこそ『全て』を掌握しきれます」
会話の流れとしては不自然で、それこそ証明の過程を数個すっ飛ばしたかのような言葉。だが、ダルクはそれを理解する。
「ええ。ミラーが他フィールドまで影響を及ぼすような反則アイテムでないからこそ、私達は戦争の渦中にはいないわけです」
迸りすぎた文明は潰される対象になりうる。先端すぎる兵器は集中砲火の対象となりうる。しかし、エンディミオンは未だ『とばっちり』の攻撃を受けているのみ。隣国のジャスティス・ワールドにすらそのような攻撃を受けていないあたり、そのような事象は無い。
「なら、今のエンディミオンは何に晒されているの……?」
理屈を重ね、現実を見定めたエリアが結論を出しきれない自分に嫌気がさしたように髪をくしゃりと揉む。
「単純なことですよ」
即答するかのように、ピケルが冷たく一言を発する。
「この国で、《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》が同時タイミングでもう一枚発動されたにすぎません」
「ちょ、ちょっと待って。《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》ってそんな誰でも簡単に作れるものじゃないわよ!? 闇属性の中でも特に秀でた魔力を持つような……!」
「――私だって《閃光を吸い込むマジック・ミラー》を創造出来るんですよ。それを考えれば結論は一つしかありません」
エリアの反論に対し、ピケルが大きく息を吐き繋いでいく。ダルクはその会話を聞きながら、どこか遠い結論を考える。
(そんな、そんな事態は単純でいいのか? 何のために?)
「ピケルは、ビンドが《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》を発動したと考えているんだな?」
ビンド――《執念深き老魔術師》の長老であり、ダルクと共にエンディミオンの闇属性部分を一手に担うブレインともいえる存在。アウスの死に至っても冷静さを欠くこと無くダルクを諌めた闇属性の――影の――
「なんでビンドがそんなことをする必要が……!」
「そんなこと、知りませんよ。机上でどうこう言うより、ビンド卿のところまで走った方が早いですよ?」
わかってる。そんなことはとうにわかってる。責任を、現実を、結果を先延ばししたいだけだ。
「くそがッ……!」
「言わずとも良い。会議室できゃんきゃんと喚くな小童どもが」
その三人の会話を察したように――まるで初めからこの場に鎮座していたかのように、ビンドが座標転移し、現れる。
「どこまで聞いていた……!?」
「聞いてはおらん。だが、全てに通じておる」
ビンドの表情と佇まいには一切のゆがみが無い。対峙するダルクが思わず立ち上がり、杖をぎゅっと握りしめる。ピケルとエリアは、闇属性の二人を交互に流し見、そして――
「意味がわかんねえよ! ビンド! あんたが《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》を創造したのなら差し出してくれ! あんただってこの」
立ちあがったエリアが、据わった目で持つ杖をダルクに向け、詠唱無しで一撃を
「状況……が――」
飛ばす。
いいものなんかとは思ってないだろう、そうダルクは口にしようとしていた。だが、目の前で起きた行為に我を失いかけた。
状況は認めたく無くとも、ビンドは敵である。傾いだ心を立て直し、対話と――場合によればバトルも辞さないつもりでいた。それだけに、その方向を――想定していなかった。
「ど、どういう……!」
茫然自失のダルクに対峙するエリアは、自身の杖を見つめ顔をしかめる。その動きは、制御しきれなかった一撃に調子の悪さを戒めるように。眼前のダルクには興味を払わないように。
「逆に聞きたい。ダルク――何故この部屋の全てを疑わない」
ビンドの重みの聞いた一言に、ダルクが見渡し――三人を見据える。そして、その意味を考える。
鎮座し、この部屋の状況を背景音かのように聞き続けるピケル。机を間に対面で立ちあがり、攻撃的な面構えでダルクを見据えるエリア。会議室の扉最寄に、魔術的な構えも取らず無防備に話すビンド。
この部屋に、いまやダルクの味方は誰一人いない。
「まさか……」
状況を忖度し、思い描いた結論。
「エリア、ピケル。お前らは、俺を台本通りに仕組んで、この状況に俺を置いたのか」
何故か? ライナと邂逅させるため? じゃあ何故エリアは俺を『今』殺しにかかった? 俺が出国している間に準備が必要だったから? なんの準備を? ――ビンドが《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》を発動すること? 内乱を起こして何になる?
思考の枝葉が生えては折れる。だが、その中で一本が軋み、折れない。
(内乱が起きている。それを止めようと動かざるを得ない人物がこの部屋で俺一人)
闘争の創生(THE DUELIST GENESIS)
いつかライナが呟いた一言。そして、たたずむピケルが動かないたった一つの理由。
(ここまで全てがライナの掌の上ってことかよ!)
「ようやく気付いた『目』だね。うん、ごめんね。中立だと思ってたかもしれないけど、私も縄張り争いが起きることははっきり言って賛成なの」
エリアは笑う。決して邪悪ではない笑い。その考えを悪と感じておらず、さも当然に呑んだ騙らない表情。
「水属性は――いえ、私は、力を得た。なあなあで平和ボケしないで生きていける能力を」
ふつふつと語るエリア。その力は『リチュア』――水属性の魔法使いが得た儀式魔法で、相手の行動をコントロールすることにより戦局を操る手法。ダルクも魔法使いの端くれとして耳には挟んでいた固有能力であったが、まさかそれを用いて謀反を画策することは考えていなかった。
「さっきピケルは『ミラーが他フィールドまで影響を及ぼすような反則アイテムでないからこそ、私達は戦争の渦中にはいない』、そう言ったよね。半分合ってるけど半分間違い。私達闇属性や光属性でない魔法使いにとってミラーは十分に脅威たるアイテム。だからそれに抗うために、私達は戦う」
決意の瞳。もちろんダルクにはそういう支配の意思はない。だが、《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》の発動下、下級魔法使いが暴動を起こしている状況でその意思に説得力は無い。
ピケルの――光属性の意思については語るまでも無い。既に首領の姿勢が戦いに向いている。
「まあ……さ。さっきまでの私と同じと思いたくないでしょ? エリアの儀式リチュアル――戦闘モードの私は『エリアル』とでも呼んでよ。私としても、別個の人格として扱ってくれた方が嬉しいかな」
エリア――エリアルは首をかしげ、ゆったりと笑い――片手間で魔法を唱える。簡易魔法により杖の先端に帽子が現れ引っかかり、左手には首飾りとアンクレットが具現化される。
「お洒落だな、エリアル」
「ありがと。これらのアクセはエリアルとして頑張る時のルーティーンみたいなものなんだ。褒めてくれたなら着けるまで待……」
一撃。
「待たねえよ」
「ぬうんッ!」
ダルクが攻撃を放った瞬間、ビンドが服の間に潜ませた《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》をエリアルの方向へスナップし、ダルクの攻撃を吸収――ミラーは粉々に砕け散る。
その攻撃が防がれること無くエリアルに炸裂すれば、彼女の首筋はえぐられていた。
エリアルはきょとんとした表情で装着を止めるが、ふっと何かを覚悟したかのように笑い、首と太股にアクセサリーをつけ、最後に杖にかかった帽子に手をかけ――ゆったりと頭に乗せる。
「似合う?」
「似合うが、おまえはそういうのが似合う女にはなってほしくなかったってのが本音だな」
儚げで、どこかさみしげで。溌剌と自分を表現し、時にしなやかに揺れ動いていたエリアの面影を感じえない表情。
(そうは言っても、真正面から攻めればビンドに、搦め手を使えばエリアに――下手な思考はピケルに読心される。王道に奇策に精神に――全てが塞がれている。真面目に……やべえ――)
戦局を回顧し、ダルクは歯を軋ませる。思考が甘かった――ダルクは自分の想定の次元を戒め――
「1対3は卑怯だぜ、エリア」
声は、ダルクの後ろから聞こえた。《強制転移》のエフェクトともに現れたのはヒータとウィン。多少怒りを含んだような表情で憂うヒータと、萎れたようにヒータの後ろで揺らぐウィン。
「解せぬな。この周りで貴様らの気配は無かったが。どこで聞いていた? どうやって聞いていた?」
「ビンド卿、申し訳ありません。《ガスタの交信》で盗聴しました」
ウィンが弱弱しくも、はっきりと。
「ついでにいうと、盗聴元はダルクだから、ここでのやり取りはおろか『全て』把握してるぜ」
ヒータがウィンの頭をぽんぽんと叩きつつ、補足。
「ダルク!」
「……なんだ」
「思案してるのはわかった。だが、結論に納得してるのか? アウスが破壊された訳については棚上げされてないか?」
ヒータが高ぶりつつもなお、冷静に抑えつけ――ダルクに問う。
「正直……ダルク。初めはダルクの全ては信じていなかった。だからウィンに頼んで『交信』させてもらった。これがこんな形で実を結ぶとは思わなかったが――こうなった以上俺達はダルクの味方だ」
「……」
「正直裏切られ疲れて、俺達の事も信じるに値するかってところになってるだろう。それでもいい。俺達はただあいつらを敵とみなし、戦闘するだけだ。ダルクはそれを見て戦うか否かを選んでくれ」
ヒータは大きく一息つき、言葉を選ぶように放り出す。ダルクはそれを反論せず、呑みこまず、ただただ聞く。
「兵法には良い言葉があるじゃねえか。敵の敵は味方ってなァ!」
ヒータの叫びが部屋に響く。びり、とその甲高い声は五人の鼓膜を揺らすが、全員は一切ひるむことなく――、しかし、動けない。部屋の中はある種のスリーマンセルの均衡。その均衡を勝手に潰していいのか、むしろ潰すべきなのかの囚人のジレンマが部屋を支配する。ダルクが鼓動を拮抗させる中、その膠着を破ったのは、
「はァっ!!」
ウィン。束ねた髪が身体の速度に追いつけないように風を撫で、鋭敏に敵に向けられた瞳は『風』の申し子にふさわしい形相。向かう先は、エリアル。
「エリアル――、いえ、エリアああああ!」
ウィンは持つ杖を走りつつ豪快に横回転させる。風圧で巻き起こる竜巻をエリアルに向け飛ばしつくす。ひゅんひゅんと、鎌鼬が鳴き対象に向けられたエリアルが一瞬目をまたたくが、すぐに目を伏せる。
竜巻はエリアの首元と胴をぶった切るが、肌に傷は付かず、血も垂れない。
その一陣の風圧と同速で――ウィンがエリアルに迫り――杖をまるで鈍器のように構え、
「っ!」
振りおろす。がぁんと響く金属音。エリアルとウィンの杖はつばぜり合い、今にも瞳が涙ではち切れそうなウィンと、儚げに――しかし、奥が見えない瞳で杖に力を入れる。
「《一陣の風》ガストね。私を斬るより前にその後方の罠を気にするとか、一端の指揮官じゃない。ぽけっとした顔して、好きだよ。そういうの」
「エリア。私は貴方の事を『エリアル』なんて呼ばないよ。奥底はエリア――なんと言おうとそこを譲る気は無い」
「もはや私に奥底なんて、無いよ」
「嘘。今も、本気で貴方は堕ちてないでしょ? 色んな事象が重なってる。バトルに勝って、ふんじばって聞きだして見せる。話を聞けない状態になんて、絶対にしてやんないんだから!」
戦いは、分離する。ダルクは、その二人の交錯に並々ならぬものを感じ、視線を改めてピケルとビンドに向ける。二人の戦いには、援護なんて、不要だった。
「なんと言われようと。これが水属性の魔法使いとしての意思よ」
つばぜり合う二つの杖先――先端の水晶がかり、かりと高い音を響かせる。ウィンはその言葉に鋭い眼先は緩めず、言葉を紡ぐ。
「一つだけまず聞かせて。アウスを……アウスを破壊したのは、貴方じゃないわよね?」
「『はい』でも『いいえ』でも結果は同じなんでしょ? じゃああーだこーだ言わずに! やりにきなよ!」
エリアルの際立つ殺気が、音を為す。瞬間、対峙するウィンが強烈な吐き気に襲われる。
そう、それは――まるで――自身が生け贄として死の間際に誘われたかのような――
(ま、まずいっ!?)
「《緊急テレポート》!!」
ウィンが揺らぐ脳天をかばいつつ詠唱。短距離の瞬間移動でエリアルから距離を取るが、嘔吐感の混じる息が荒い。
「それが……噂に聞く《リチュアに伝わりし禁断の秘術》……! 他の領域から生け贄を捻出するっていう禁忌に手を染めた……!」
「貴方も人の事は言えないでしょ? ウィン。……いいえ、サイキッカーの腕を見込んで、別の名で呼んだ方がいいのかしら?」
エリアルが杖を肩で担ぎ、鼻で笑う表情。ウィンは息を整え、視線を死なさずに答え直す。
「私は貴方とは違う!」
「一緒よ。カーム? リーズ? 貴方の侍女だったかしら? 彼女達はサイキック族。そんなのを引き連れてるなんて、魔法使いとしての風土から言えばそっちこそが禁忌なんじゃないの?」
「彼女達をそんな風に言うな!」
「ええ、そうね。じゃあ言わない。ただその代わりに、彼女達への狼藉は主人たる貴方が受けるべきよね、ウィン。……いえ、ウィンダ」
にやりと口端を歪ませるエリアルの言葉。ウィンは声を荒げることなく額の汗を拭い――。
ウィン――ウィンダは回顧する。
ウィンダが今、エンディミオン内で風属性の地位を確固たるものとしたのは、紛れもなく、エンディミオン内風属性を一手に担う組織『ガスタ突風』を確立させたから。しかしその組織――組織員は魔法使いにとどまらない。ウィンが外遊を行っていた際に、飢餓に苦しんでいた者らを引き連れ、帰還。もちろんエンディミオン内部には一定の反対層はいたが、そのサイキック能力は魔法使いの能力にも運用が可能であるという「政治」を押しきり、隙を与えぬまま『居場所』を組織した。
事実、その能力は有効に作用した。だが、その一方魔法使いの枠にとらわれない観点から、ある種の『踏み出すべきではない領域』にも、風属性を――ウィンを誘うことになる。それは、裏切り者ユダと言い切っていいものなのか。
●
ウィンがエリアに飛びかかる瞬間。ダルクはその様子を見て、援護の考えを捨てた。
ダルクは改めてビンドとピケルに視界を向ける。ヒータも一切ウィンの方に視線を傾けず、思考の一致を感じ取る。それはビンドとピケルも同様であり、ある種の利害の一致。眼前にはとらえきれない間合いにピケルがゆらりと構えている。ダルクは、その様子を見定めて息を呑む。
(こいつ、場馴れしてやがる)
ピケルはダガーナイフサイズともとれる短い杖を前に構えた左手で揺らし、瞳孔をぶれさせない。それは集中の極致。少なくともこの戦時においての動揺は全く感じられなく、ダルクは内心捉えきれないでいた。
(やりづれえな)
年端もいかない少女に攻撃をしかけることが、ではない。肉体的筋力的な差が実力に影響しない魔法使い族同士の戦闘において影響となるのが、攻撃のレンジと、相手の的としてのサイズ。小さければ当然狙いにくいし、その点では十分な実力を持ちなお肉体的な成長が薄いピケルは高い水準の戦闘要員である。
こんな「内乱」が起きる前は、ライナがまだエンディミオンにいたときは、ライナにひょこひょこと笑顔でついていくピケルの様子をダルクは見たことがあった。内心、その様子をほほえましいと思いつつ見ていたのも事実だが――その裏で行われていたことは――。
ダルクの後ろで構えを取らず戦況を撫でていたヒータが、誰に視界を向けるまでもなく、
「《ファイヤー・ボール》!!」
仕掛ける。ダルクとの打ち合わせも、作戦も無い。後方から放たれた火の玉がダルクの耳元を掠め抜け、ビンドへ豪速に迫る。
ヒータは考えない。それは彼女の元々のスタンスが「速攻に拙攻無し」にあるからだ。常々『相手に考える隙さえ与えない』という思想の元の戦闘技術を鍛錬している彼女にとって、戦闘は戦術や戦略、謀略の介入する余地が無い。反射で体を動かし、経験で展開を操作する。
だから彼女は、ノータイムで、動く。
「《精霊の鏡》ィ!!」
奇襲、速攻。しかしビンドもその攻撃に一切の迷いなく反応。鏡は爆音を響かせ砕け散り、火の玉はいなされて拡散する。そのうちの一個が反射しヒータに迫るが、
「《火霊術-「紅」》!」
火の玉はヒータの杖に吸収されたかと思うと、ヒータの肉体から熱波が溢れだしエネルギー派として再びビンドに迫るが、
「《閃光弾》 」
横からピケルが視線を一切動かさず光弾を射出、炎と光のエネルギーを相殺させる。熱波を寒波で強引に中和するかのような互いのわだかまりの差。ヒータとピケルはにらみ合い、追撃のチャンスを伺いあう。
交差するように、ダルクは脚に力を入れ――距離を詰める。矛先はビンド。
「《闇霊術-「欲」》ゥ!!」
眼前で視線が重なった二人のうち、仕掛けたのはダルク。手から迸るエネルギーをかかげ、ビンドの胸元を狙う。瞬間、ダルクは視界の端で嫌な笑いを見せるピケルを見た。
「狙うと、思ってましたよ」
ぼそり、とピケルが呟いた。ビンドは、胸元に闇属性を一撃で破壊する攻撃が向けられていることを見据えたなお、怯まなかった。
「がっ!?」
まるで岩の壁に攻撃を反射されたかのように、『反発』。構えるビンドの――ダルクが攻撃を放った先には『円陣』。見覚えはあった。
(魔法陣――《ピケルの魔法陣》か!)
皮膚の表面を強引に光属性のオブラートに包み《闇霊術-「欲」》の効果を回避。そんなものが事前にされているとは――意味するものは一つ――周到な準備。そして、
「《闇霊術-「欲」》」
寸分の迷いもないビンドのカウンタースペル。
(……ッ、《闇霊術-「欲」》は俺の専売特許じゃねえ。だから、俺はあの魔法陣の上に立てなかった)
だから。
「そー簡単に諦めんなよ、ダルク。まだまだ戦いは1ターン目だぜ」
ビンドから放たれた一撃の前にヒータが立ちふさがる。魔力を伴う強烈な掌に一切避けるそぶりを見せないヒータが、受けきった。
「パンチとしては死ぬほどいてーが、炎属性のあたしを逝かせるわけにはいかねー技だよなァ!」
エリアとウィンの表情と言葉は、どこか達観しているような、結末が見えているような落ち着きだった。
「ウィンダ。ウィンとして、ユダとして……『エリアル』と同じ道を進ませたいってわけか」
「進ませたい? いいえ、もう貴方は進んでる」
「そっか。もう進んでるか、なら!」
ぞくり。目は、気持ちは死んでいない。エリアルは怒号に反射するように構え、次の一撃を待つ。
「《最古式念導》サイコキネシス!」
「直接心を狙ってくるってわけね! だけど、そおいうのは、効かない」
精神攻撃を仕掛けるウィンダに『直接』語りかけられる言葉。ウィンダは内心しくったかと舌を打ち、思考を切り替える。
(瞑想――《儀水鏡の瞑想術》を物にしている以上――もはやあのコに心を折らせる勝ち手は見えない。大風呂敷だったかも)
視線の先にはエリアの持つ杖――儀水鏡。
(闇属性も、光属性も――そして水属性も。鏡は戦術の核となる。まずはあれを狙ってみるか)
精神攻撃をばっさりと見きり、ウィンダは詠唱をやめ、
「《風霊術-「雅」》!」
流れる風をなだめ、美しく舞う。一言一言が空気を伝い、舞った魔力が狙うはエリアルの杖。
「それだから甘いって言ってるのよ!」
風霊術がエリアルの杖を撫でる。外見からは考えられない内圧が杖を砕くとウィンダは算段を立てるが、微塵も動かぬまま。
(鏡を割れない!?)
「ええそうよ! 固定観念も程ほどにしておくのよ! この鏡は――」
「永続装置じゃない!?」
「《水霊術-「葵」》!」
ウィンダの一撃を見切ったエリアルが、反詠唱。頬をなびくウォーターカッターは肌を切り裂き、鮮血が迸る。
「こんなの、アウスの痛みに比べたらァ!」
ウィンダの声は震えていた。状況に感きわまったわけではない。頬の血による恐怖がフラッシュバックしたわけではない。
「《ブローニング・パワー》ァァ!」
サイキック族の能力はほぼ全領域において身を切ることコ ス トを前提とする。それは生身の人間にとって、その能力はエグく、辛く、どこか効果の『腱』を斬らないとたどり着けない領域であったから。
(痛い……臓器が……ちぎれっ……る――!)
だが、ウィンはその腱をためらいなくちぎり、ウィンダと成った。
「ウィンダ! いいモノ持ってるじゃない! とても魔法使い族の戦術とは思えないね!」
その目的は、言わせる者に言わせれば『力を求めた末の結末』? だが――、
「うん……そうかもしれない。ちょっと彼らを理解しすぎちゃったかもしれない」
だが、ウィンダは彼らの持つべき物を――思想を理解するために踏み行った。その首領としての行動を、風属性の魔法使いは許さないか。
「そんな愚鈍で馬鹿な首領を下っ端のみんなと、ガスタは許してくれると思う!?」
念じることで起きる力サイキックも、一つの魔法だ。
ウィンダは努力していた。そして、たどり着いた。風属性の魔法使いは、そしてガスタは――それを見ていた。許すか許さないか? いや、彼女は『磔』にされたことすらない。
ウィンダは、思う。
「エリア。随分と追い込まれてたんだね。気付いてあげられなくて、ごめん」
「……」
ウィンダは、笑う。それは慈愛。邪気や皮肉は無い。瞳はうるみ、肌は震え、今にも崩れ落ちそうなはかなさを抱えていた。
エリアルは部屋を走り抜ける。抜けられた間合いを詰め、その表情を視界にとらえ、一瞬首を落とし、口を開く。
「同情なんて! 同情なんてっ……!」
杖を叩き下ろせば届く距離。エリアルは心を壊し、右手に持った杖を振り上げる。
ウィンダはその様子をしっかりと視界にとらえたまま離さず、防御の姿勢も取らない。
「はああああああ!」
ためらいなく振りおろされる一撃。ウィンダは、小さく口を開く。
「待ってた。その一撃を」
《念導力》!!
杖から無数の魔力の束が拡散したと思うと、影響範囲内の目標を捉え――距離を詰めた二人――エリアルとウィンダの体を黄色い魔力が包み、じわりじわりと体を締める。
「が、ぐっ……!」
「もう、抗えないよ」
「くそっ、頭……おかしいよ――ウィンダあ!」
「おかしいかもね。ほら、私サイキッカーだし」
自らに向けられた皮肉を咀嚼するようにウィンダは答える。その間にも黄色い魔力は二人を深く太く縛る。
「私を殺す気なんて……無かった癖に!」
「殺す気……? ああ、そういうことか。ふんじばる、なんて大風呂敷広げたもんね。ほら、ふんじばってるじゃん」
「ふざけないで! これだと……これだと――!」
「そうだね。二人とも逝っちゃうね。お話聞けないね。せっかくふんじばったのに」
「がっ……!」
「じゃあ続きは、『あっち』で聞くよ。エリア!」
「やっぱウィン、あんたはユダだ――!!」
圧力が限界を迎える。包み込んだ魔力は事切れた二人を優しく囲い、表情は、見えない。隙間からは鮮血が、滴り落ちる。
●
極限状況にあってなお、ダルクの頭は回っていた。それは戦闘によって生じる脳内麻薬状況かもしれない。だがダルクはそれをあえて飼いならそうとした。目の前の敵から注意をそらさない程度に――集中力を思考に分散し――考える。
(そもそも、この戦闘、おかしい。俺がここに戻ったのは《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》の創造による闇属性の暴動。だが、ビンドはそのミラーを一瞬で切り捨てた)
ダルクがエリアに初撃を加えた際に、それを防御するためにビンドは鏡を放出した。その際に《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》は粉砕された。そのため今は暴動していたモンスターも自我を取り戻し、言うなれば戦闘する理由が無い。
(内乱は、ビンドにとって目的ではなかったということか?)
だが、動き出した歯車はもう止まらない。止めるために必要なのは一方の降参リザイン。もはや、言語での解決を試みられる次元ではない。
(なら、何故そんなことをした? 『敵の思惑通りに乗ってしまった』ことを考えろ――)
――俺を、エンディミオンに戻らせるための理由を作るため?
ダルクの論理が、一つの仮定を導く。それは提示された条件による仮説であり、真実は闇。だが、ダルクは不思議とその結果に明確な自信を持っていた。
(だが、なら……そもそも俺が出国する際に何故引きとめられなかった? 呼び戻すために策を講じるより、そもそも出国させないのが方法としての道理――)
結果には、どこかに必ず理由がある。
(追い出して、その間に『何か』を準備する必要があった? いや、違う。逆だ。俺が『行った先に』理由があるってことか――?)
回顧したライナの表情が消えては浮かぶが、そこから先が繋がらない。
「ダルクぅ。悩んでんのが顔に煤けて出てるぜえ」
思考にしては数秒にも至らない。だが、ヒータは空気の変動を肌で感じ取り、一気に締める。
「……悪い」
「まずは動け。体動かさねーと、働く脳も働かねーぜ!」
ヒータが、強烈に笑い――射程距離にあるビンドの胸倉をつかみ取って、そのまま自分の眼前に。
「ぬぅっ!?」
杖の柄でビンドの顎を叩き、掌底。
「はあああっ!」
体幹の上下に一撃をくらわされたビンドが回転し、吹っ飛ぶ。今の一撃の流れを見れば、とても魔法使い族の繰り出された一撃とは見えない、流れるような攻撃。
(今のが、『炎車回し』。話には聞いていたが、流石に強烈だな)
『炎車回し』――ヒータの持ちうる、数ある攻撃の一つ。ヒータは魔法使いではなく魔法戦士として――あらゆる鍛錬を積んだ。感覚派の戦い手であるヒータにとって、鍛えるべきだったのはまず身体能力であり、それは異種の発想。しかしだからこそ、たどり着いた実力は、一つの信頼。
ヒータは続いてピケルを視界にとらえる。そこには一介の子供に対する慈愛や、母性は無い。あるのは明確な、敵意のみ。
「いいですね、ヒータさん。素晴らしい攻撃です」
だが、ピケルは怯まない。
「ヒータ、気をつけろ。ピケルは、相手の心が読める」
部下ができることが上司が出来ないと恥ずべきでしょ? もっと褒めてよ。
ほんの数時間前に、ライナがダルクに口にした言葉。ダルクはその意味を理解し、諫める。
「言っただろーが。アタシは考えるよりも先に体を動かす! 読心されようが、されまいが、関係ねえんだよ!」
ぎゅるりと足に力を入れ、猛烈な方向転換。ピケルに向かい一気に走るが、なお、ピケルは怯まない。
「違いますよ。ヒータさん」
「ッ」
「『何も考えず攻めてくる』という心が読めただけで、十分です」
ノーモーションの詠唱準備。これも、想定の範囲内にあったということの証明。
何も考えず攻める。鍛錬された戦士にとって、『何も考えずに攻める』は『最善の選択をする』と同義。ゆえに、言い換えれば、裏の掻きあいを自ら放棄しているということ。いくらヒータ以外の魔法使いは肉弾戦闘に秀でてないと言えども、理論としての肉弾戦闘処理は理解している。ゆえに選択は。
「愚直に対しては、『誠実(オネスト)』であれ、ってね」
ヒータの打撃が、『折れる』。ヒータは、そしてダルクは何が起きたのかがわからなかった。ただ、そこにあるのは、いなされた攻撃と、曲がってはいけない方向に曲がったヒータの腕という純然たる事実。
「ガキだからって油断してましたか? 頭脳派相手だからゴリ押せるとでも? いや、違いますね。貴方は自身の実力について自信過剰すぎる。ゆえに、危険牌が読めない」
爆撃音がヒータを掠める。ピケルの後ろには隆々しい肉体の男の天使が浮く。見ようによればそれは霊使いらの持つ精霊と同様のニュアンスをはらんでいるが――そう称するにはあまりにも無骨。
「オネストッ……! すっかり忘れてたぜ――だが、天使の力を借りるなんて――てんでバラバラな思想だよなあ!」
折れた左腕を抑えつけるようにヒータは呻く。
「ライナ様がライトロードを支援している中、もはや光属性に魔法属性単一で動こうという思想はありませんよ」
瞬間でピケルが返す言葉は真理。ヒータはその冷たい真実に言葉を紡げない。
「くそっ……杖さえ持てやしねえ――!」
痺れ、糸がちぎれた左腕を庇うように立ちあがった、その時だった。
「《念動力》!!」
横のフィールドで起きた相打ちスーサイド。《念導力》によって、そこに回復の魔力が生まれ――それは損傷したヒータの元へ駆け抜ける。
滴り落ちる赤と対照的な、緑色の、朗らかな魔力。それはヒータを優しく包み込み、ひしゃげた腕を再生する。
「う、うぃ……ッ――!!」
眼前の光景。自身を包み込んだ再生魔力。そして、ウィンの首領としての活動を知っているからこそ――全てが可能性としてつながる。
泣きそうになる。足から力が抜けそうになる。だが、それをぐっとこらえ――ただ一言。
「あああああァァァァァ!!!! ピケルゥゥゥ! ビンドォォォ!!!」
「いいですよォ! それじゃ、2ターン目に、いきましょうかァ!!」
「いいですよぉぉ! それじゃ、2ターン目に、いきましょうかァ!!」
言うなれば、それはピケルの怒号。外見からでは想像できない強烈なまでの殺気。しかし、ダルクとヒータは怯まない。それをビンドは揺らがず見据える。
流れる静寂。先の一連の戦闘があったからこそ、そして、一つ一つの挙動が戦況を揺るがせたからこそダルクはあえて落ち着き払い、心を殺す。
「《闇の護封剣》!!」
ダルクがふっと眼を見開き、詠唱。瞬間、禍々しく輝く剣が三本ざくりざくりとダルクの前方に現れては刺さり、かすかな防御膜が剣と剣の間に貼られていた。
「《光の護封剣》……」
その様子を見据えたピケルが興を削がれたような、嘆息したような表情で詠唱し、ピケルの元に白光の剣が現れて刺さる。その様子は、対極の色彩を除いてのシンメトリーの光景。ゆら、ゆらと揺れる魔力は安定しており、暴発することが思考の埒外になるほどの鍛錬の技。
「ヒータ、すまん。だが、頭を冷やしてくれ」
「……ッ、ダルク!!」
「俺だって、あいつらを一秒でも早くぶっつぶしてえ……! だがそれ以上に、何か、何か掴めそうなんだ――!」
ヒータが見据えたダルクの横顔は、影で落ちていた。だが、それでもなお、焦燥と冷静と怒号の混沌が絡まる――怪奇な表情が――。
(このシナリオに感じる違和感はなんだ……! 解決しておかなければならないものが――ある気が――!)
「ヒータ、一つ聞きたい。俺への盗聴――《ガスタの交信》はいつからしていた?」
「……ほぼ最初から。リリーに話を通じて、地図にエンチャントしてもらえるように――」
「!?」
がくりと心に沈み込む違和感の塊。ダルクはそれを口に出さず、思考の紐を手繰り寄せ結ぶように――慎重に語っていく。
「ちょ、ちょっと待てよ。俺がリリーに話を通じさせる前に地図に《ガスタの交信》をエンチャントしたってことか」
「あ、ああ。そうだ。エリアが先にリリーとあの時の議事の内容について話しておいて、後で議事録を持って向かわせるってことをアポイントしてたそうだ。――リリーはその伝聞から行き先を絞ったってことだったから、……ウィンはそれに応じてその地図に《ガスタの交信》をエンチャントした」
ヒータがたぎる頭を必死に抑えつけ、裏方で行われたことをゆっくりと語る。だが、ヒータもその内容が自分から口にすればするほど『違和感』あるものであることに気付いた。だからこそ、語気はあらがなかった。
「ヒータ。……自分で、それ。どういうことなのか、気付くよなァ――!!」
エリアは敵。それに議事録を持っていけと言われたシナリオ。《ジャスティス・ワールド》に向かわされたシナリオ。帰還したシナリオ。
「――くっそ、口にしないと気付かないなんて……お人よし過ぎるぜ――!」
ヒータは突き付けられた真実に動揺した表情を作りつつ、怒りを炎に揺るがせる。
「リリーも、あっち側の人間……!!」
ダルクは、ローブのポケットから魔力通電機を取りだし、震える手を抑えて番号を一つずつ押していく。何コールかの後、ぷつりという音と共に、リリーが通話をキャッチする声。瞬間。
「リリィィィィィィ!!」
『……何かと思えばダルクさんじゃないですか。その血管がはち切れそうな声。どうしたんですか、なんて聞くまでもないですね」
リリーはダルクの怒号を意に返さないように淡々とうそぶく。そこには一切のひるみは無い。心の底から、いずれ気付かれるであろうことを受け入れていたかのような声。
『そうはいっても、勘違いはしないで下さいよ? 私にアウス様を手にかけられるほどの能力はありません。一連の『シナリオ』の歯車となることが自らの利であったこと――ただ、それだけです』
「なんでだよ!? 俺と話してる時にそんな様子は……!」
『メンタル・カウンセラー、ですから。それとも、私が”机に伏し、肩を震わせ”てる様子でも見たっていうんですか? もしそれを見てたとしても、ただ笑いが抑えきれないで、机にふさぎこんで笑っていただけですよ?』
反省とか、良心の呵責とか。そういうのが全て吹っ飛ぶような軽々しい言葉。
「……何故、アウスがいなくなることを望んだ。政治的なものか。それとも、てめえが……首領の座を狙っているのか」
『どちらかといえば後者ですね。自分の手を汚さず、その座が空くなんて、ステキなことじゃないですか』
そこまでを聞いて、全ての思いを食いちぎらんばかりの力で、ダルクが歯を軋ませる。
「誰と、組んでいる。アウスを破壊した犯人も知っているってそぶりだな」
『共犯者に犯人の正体を聞くなんて野暮な真似はやめてほしいものですね』
「くそっ……!!」
万に一つも信じたくは無かった。例えリリーが共犯だとしても、彼女がシラを切って貫き通せば、一縷の希望はあった。だが、現実はどうだ。数秒で自分から自白した。その真意は、ダルクの性格を知った上であえて『叩き落とす』選択を取ったということ。
「はは、ははは」
しかし、ダルクは笑った。きっとこれが数時間前であれば、ダルクの心はここで折れていただろう。でも、ダルクは軋む心を矯正した。既に、ライナによって心は折られていたから。ダメージは少なかったから。
『……何がおかしいんです』
疑惑の声がリリーから返る。
「いや、な。見えてきた。現実問題、起きている事象の整合性は、取れない。全てが繋がっているようでいて繋がってない」
《闇の護封剣》がじじじと電磁音を掠めつつ、震える。ヒータはその様子とダルクの会話を交互に流し見、改めてピケルの方に視線を向ける。
「てめーは、地属性の転覆のために謀反に協力した。だが、そうすると色々見えてくるんだよ。まずエリアとビンドがてめーと噛んでいる時点で、霊使い上層部が絡んだスキャンダラスな状況。まっとうに考えて、ただの下っ端魔法使いであるリリーなんぞのために、首領どもが協力すると思うか?」
『……』
「やらねえだろうな。心情的に、プライド的に、立場的に。そこに足を突っ込むのは至難だろう。だから、『あいつら』は各々が持つ自分の計画があり、そのためにリリー。てめーを利用した。……アウスを破壊するという飴を与えて、な」
『……』
「なんとか言えよ、リリー。ピケル、ビンド。てめーらもだ」
ダルクが床に魔力通電機を叩きつける。一瞬にして粉々になったそれからはアーキテクチャーがむき出しとなり、黒い煙を上げる。表情は怒りを隠さない。対峙するピケルとビンドの表情はなおも変わらないが、ヒータは――その目を曇らせる。
「なあ……なんでみんな揃いも揃ってそんな空しい茶番に自分から飛び込んでるんだよ!? 政治!? 支配!? そんなつまんねえもんで殺し合ったり死んだり逝ったり!? おかしいだろ!?」
それは心からの沈痛な叫び。ダルクも時が違えば、心が違えばそう叫んでいただろう正義の象徴たる一言。だが、この場のにバランサーは既に、1人しかいなかった。
「黙れ、失われた黄金時代(THE LOST MILLENNIUM)」
「……ッ」
ピケルの重い一声は、ヒータの心を歪ませる。
「ヒータ」
「……ダルク」
「さっきのリリーとの話を聞いてたな。じゃあ、あいつらを『どう』すれば潰せるのか、わかるよな」
「わかる、わかるよっ……! だけど――そんな、そんなのって 正しいのかよ!?」
「んなもん、勝った奴が正義だろ。それが、決闘デュエルだろーが」
《光の護封剣》が、《闇の護封剣》が、力をはちきらせ、防御膜を破けさせる。それは、その場総勢の決意を象徴したかのように。大喧嘩を許可したかのような、一瞬。
「あああああああああああ!!」
ヒータが叫び――ノーモーションでその杖を天に掲げる。――その一秒後、落下してきたのは『業火』。
「《火炎地獄》ゥァァァァァァ!!」
ダルクが耽り、そしてヒータが選んだ戦術は個々を攻めること。タッグでの戦闘であるが、あえてコンボを放棄し、個々の戦闘に持ちこむことを選択した。それは、ビンドやピケルが『協力して』何かを成し遂げようとしている可能性が高くないという現在の事実。ビンド、ピケル、そしてリリーが『各々の計画のために』打算的な協力をしているというなら、個々を攻めると言うことは自身の防御に手いっぱいとなること。
「まあったく……!」
嘆いたのはピケル。ピケルは《ピケルの魔法陣》を下に敷き、ヒータの一撃を完全にいなす。
「どっちが悪役か判ったもんじゃありませんね!!」
だが、ピケルはビンドを一瞥すらしない。先のリリーとの会話が聞こえていたか否か、ピケルの表情には余裕が無く、目の前の敵と、自分の魔力制御に集中している感が見受けられる。
「馬鹿野郎……!」
ダルクは、ヒータの行動を見抜ききり、なお小さく懸念の声。ヒータが攻撃に《火炎地獄》を選択したのは、ビンドが鏡を使役する光景を見据えたこの度の戦闘から、単体攻撃を捨てたという思考。だが、単体攻撃を捨てるのは『個々は攻めない』ということではない。より広い範囲を攻め燃やす魔法である《火炎地獄》を選んだということ。だが、それは、
「ァァァァ!!」
《火炎地獄》はハイパワーハイリアクション。すなわち、自らへリバウンドする反動が大きな魔法。ヒータの掌が、杖が、上半身が燃える。
炎属性の魔法使いとして、化身として火のコントロールを得手としているのはあくまでも自分が発動した魔法の範囲であり――意図しないものまで扱いきれるほど――魔法は万能ではない。
ビンドの上半身はヒータの一撃で焼けただれていた。元々治癒方面を不得手とする闇属性――今の一撃で逝かなかったのはあらかじめ皮膚に纏っていた《ピケルの魔法陣》の恩恵があったからとも言える。
「ぬうっ……!」
だが、ビンドも歴戦の老練。力を入れ握った杖を振るう。矛先はヒータ――。
エネルギー弾が射出。えぐりゆく一撃がヒータの腹を『持っていく』。ダルクはあえて目を見開かない。瑞々しい音と、感触は――やっぱり、あの時と――アウスを『持っていった』それと同じ。
目を見開く。横たわるヒータをダルクは、見る。
(はっきり言って、わかってた。あいつを――アウスを破壊できる力があるのはビンドだけ。だけど、みんなが思っていたこと――なぜそのような必要性があったか――を証明できない限り、そんな風に追及することなんて不可能だ)
ダルクは、心を殺す。リバース効果を発動し隙ができたビンドに迫り、その顔面に掌を押しつける。
「さすがに、お化粧なんてしてねえだろ」
《闇霊術-「欲」》を詠唱。瞬間――その顔面が、あわせて胴体が――花火のように消し飛ぶ。
一瞬でのぼりつめた吐き気をぐっと抑えつけるが、体から一気に力が抜ける。足から蒸発するように抜ける力。ダルクは四つん這いを余儀なくされ、大きく、嘆息。隙あらばピケルにいつでも捕捉される隙。だが、ピケルは襲ってこなかった。
息が落ち着き、気持ちが落ち着き。改めてピケルに視線を向ける。そこには、
「ブラヴォー。素敵な殺陣を見せて頂きました」
まるで初めから『居た』かのように、ライナがいた。ピケルと並び立つ姿は、神聖性の象徴。
ぱち、ぱちと手を叩き、その破音が静寂を割る。
「アウスが破壊されたこと。ライナに会って現実を突きつけられたこと。そして今の殺し合い。――全部、繋げろってことなんだな。そんなに命を軽く考えろっていいたいのか」
「……何のことかな。あたしよくわかんないな」
ライナは首をぴょこぴょこと左右に揺らし、ダルクの次の一言を誘う。
「ようやく全てが――てめえの『掌の上』がわかった。乗っかって――潰してやろうじゃねえか!」
「いいよ! 『あの時』の続き、おっぱじめようじゃん!!」
ライナは、ダルクの据わった視線に臆せずむしろそれを期待するかのように叫び、笑う。
彼女は、人の心が読める。だから、突き詰めればダルクが一言も発せずともライナは思考を読み取り、それに正誤の評価を下すことができる。
「あああああ!!」
だからこそ、あえてダルクは頭で結論をまとめるという考えを捨てる。ライナもそれを理解するかのように、読心する考えを持たなかった。
ダルクが杖を鈍器のように構えライナに襲いかかる。鍔迫り合う二つの杖は、とても魔法使いの戦闘とは思えない。ピケルはその『続き』を見て、ライナに援護しない。だってそれは、ライナが望んだ喧嘩の続きであるから。主人の望んで得た結果を邪魔するほど空気を読まない部下ではない。
「はじまりはきっと、どいつでもよかったんだな」
「……」
「それでもなお、なぜ引き金になったかってのを考えれば、主査監督者……つまり外交を取り扱うリリーが内通者であり、そいつが地属性であったこと。だから、地属性の首領である《地霊使いアウス》を殺すための駒として与し易かった。その程度のことだったんだろうな」
命を軽く考えやがって、そんな愚痴をダルクは心のなかで留める。もっとも、それは「読まれている」だろうから、口に出そうが思おうが結局は一緒ではあった。
「そのうえで《メンタル・カウンセラーリリー》として天使族をもコネクションがある。先にピケルが《オネスト》を従えていたこと……その種も伺えるな。そして、アウスら四人で出来た属性の円環を一つ潰すことは……この通りだな。属性間のバランスを壊し、それぞれの首領の隠していた部分や本音を露呈させ、バトルフェイズを煽る。まさにライナの思う壺じゃねえか」
「あっは。おおむね正解。というか、涙目で違うよ馬鹿!とか言っても信じてくれないだろうしね」
「そして結果として『闘争を創生』する。望みは、それだ」
肉弾戦闘により近づいた二つの顔が睨み合う。ライナは声色や威勢を変えず、それでも淡々とつぶやく。
「でもさ」
次いに吐く言葉。ダルクは悪寒をわずらい、ぞくりと一つ身震い。
「なんでビンドを殺したの? ホントに殺す理由があったの?」
ぞぞ、ぞぞぞ。
「仮にも闇属性の仲間でしょ? 勝手に悪役認定してぶっ殺して? これで冤罪だったらどう償うつもりなの?」
ダルクの視界のなかでライナが大きくなる。その笑顔に奥底が見えるように。いや、故意にそれを見せつけて彼を揺らがせようとするような、そんな囲い込み。だが、
「……だったら、なんで俺がエリアに奇襲したときにビンドはあいつをかばった? 俺のあの攻撃は過剰防衛か? いや、違うだろう。ビンドとエリアは作戦上並び立っているから、あの画が出来た。そんな脅迫で、ブレて、たまるかよ」
だが、ダルクはぐらつかない。脳内で、心の中で広がるかすかな綻びを抑え、話す。
そこまでを嘆息し呟き、杖を持つ手に力を入れ、一度間合いを取る。ライナは鬼気迫るダルクの表情を見て、
「うん。いい精神武装だね。そう思考されると、心から攻めるのは無駄かな」
はあ、と大きく息をつく。それはため息と言うより、むしろ力を抜くような。
「!?」
集中。
(《魔力掌握》の構え!? 《精神統一》の上位技術か!)
ライナは杖を胸の前で構え、目を静かにつむり、体内に流れる魔力を研ぎ澄まさせる。だが、ダルクは目を瞑るライナ相手に攻撃を仕掛ける気力が起きなかった。
「悪いねーダルクくん。あたし、なんでもできちゃうオールラウンダーだし、鍛錬も欠かさない努力の権化だから」
「うっさんくせえこと言いやがってよお!!」
「いくよ、操り人形!」
ライナが杖を構えると、その手元にマリオネットが現れる。ダルクがそれに感想を抱く間もなく、そこから『魔力』が射出。
(くっそ! 魔力の精製から使用までが鍛錬過ぎる!)
魔力の塊がダルクの頬をかすめる。マリオネットの能力はモンスターの破壊。言い換えればビンドが持つ効果を条件付きでコンパクトにまとめたものである。
(こ、こいつ……)
「あ、いっとくけど」
ライナが攻撃の手を止めつぶやく。
「アウスを破壊したのはまごう事無きビンド。そんなマリオネットなんかに任せるなんてするわけないじゃん」
読心。いや、ダルクはまだそこまで思考をしていなかった。それはすなわち完全な戦場の総意。
「そんなんじゃ」
煽 れ な い で し ょ ?
「くっそやろぉぉぉぉぉぉがああああああああぁ!!!」
ダルクは叫ぶ。叫び倒す。
「あっははは!! いいよだるくくん! あたし濡れちゃう! もっともっと!!」
ライナはいかれたからくり人形のようにけたけたと笑い、ねだる。心底戦闘に陶酔した表情はダルクの精神に深く斬り込み、喧嘩はさらに加速する。
「てめえは絶対許さねえ! ぶっ潰して……」
「うん、ぶっ潰して? その後どうするの!?」
「ッ……!」
「見方によればあたしたちが並びたって『政治』する方が色々と賢明なんじゃないのかな!? 失われた黄金時代が潰し合って全滅し、貴方の右腕たるビンドも絶命し、そのうえであたしまで死んじゃったら……ダルクくん、『ひとりで』『この先』『やってける』のォ?」
その言葉にダルクの勢いがぴたりと止まる。杖を弾き距離を取り、はずむ息を整える。
「ん? どうしたの? 図星だった?」
「……それでも、やんなきゃいけねえ。俺は、おまえとは、並び立てない。あいつらの骨をうずめてから……俺は全て、背負ってかかる。それが霊使いとしての、責務だ」
「……」
ダルクがつぶやいた決意。ライナはその目を見据え、無表情に戻る。
「なにそれ。つっまんない」
「おまえにとっちゃそうだろうな。自棄になった俺を戦闘で掬い上げ、心を攫っていくことを狙っていたおまえにとってはな」
「並んでくれない、なら、潰すしかないじゃん」
冗談めいた口調ではなく、垂れ流すようなそれは。
間際のピケルをぶるりと、撫で舐める。
「考えて、なかった、わけじゃないよ」
「ライナ様!」
ピケルがか細い喉頭を奮い立たせるように叫ぶ。タガを外しかけた主を止めるように。
ライナはその様子をちらりと一瞥するとすぐにダルクに視線を戻す。
「だけど、そんな、脳筋プレイは……」
好 き じ ゃ な い ん だ よ ね ェ ェ ェ ェ ! !
「!!」
ごう、とダルクの全身に殺気が襲いかかる。瞬間、ダルクの左後方と右後方にケルビムとドラグーンが戦闘の構えをとっていた。
(ライトロード!?)
「当然だよね! 光属性のライトロードは当ッ然あたしの手駒だよね!」
狂い笑うライナが杖をダルクに構えた刹那、ドラグーンが口腔から光線を吐き出す。
(!?)
それは巨大なエネルギーの弾道としてダルクの正面を捉え、それは、
ダルクの前に現れた4匹の『羊』を弾き飛ばす。
四方の予知せぬ方向からピケルが杖を一閃していた。トレードマークであった羊の帽子は跡形もなく消滅し、ピンクのロールヘアがあらわとなる。
風でばたばたと震える髪を彼女は意に返さず、言葉を発しない。
「自分のエンチャントを犠牲にしてダルクくんを守るなんて。ピケルってそんな健気な子だっけ?」
「……」
茶化すような、皮肉るようなライナの言葉にピケルは言葉を返さない。
「ダルクさん」
「なんだ」
「光属性の……ライナ様の視点で見たら今の論理は概ね正解です。ただ、それでいいのですか。攻める理由を作るため、自分で自分を落とし込んでいませんか」
詩的というより、わざわざわかりにくくしてるかのようなピケルの表現。その意図をダルクは一瞬悩み、それに気づく。
(そうだ。それにしてもアウスがその攻撃を『受け入れた』理由にはならない)
「だが、それでも」
「んん?」
「それは、この戦闘を終わらせてから考えることだ」
「……」
心をスイッチするダルクの様子を見てピケルは意を決したように、
「そうです。その疑問が解決しない限り、あたしは、ライナ様は、ダルクさんは笑ってこの世界を去れません。全てを終わらせたあとに、真実をその手で手懐けてください」
呟く。その遠まわしは、きっとライナへのささやかなる抵抗。操作されてる以上敵視できる行動は取らせてもらえない。かすかに動く本能を必死に自分でコントロールし、迫れる限界の台詞を話しているかのように。
「さて」
ピケルが微笑し詠った瞬間。それを待ち望んでいたか、それとも偶然か。
けぷり。
ピケルの心の臓を『杖』が貫いていた。ピケルの真後ろに構える人影は、ライナ。
「か……っ……!」
「おしまい。もういいでしょ。霊使いでもないモブが出しゃばるのはこんなもんでいいよね」
息の残るピケルから躊躇いなくライナは杖を引き抜くと、全体にまぶされた血しぶきを振り落とす。
「これ以上調子に乗せてると要らないことまでしゃべりかねないからね」
「だからって……!」
「ああもう! 友達思いとか超反吐だから!! 心配するならまず自分の身を案じるべきだよね!!」
横たわるピケルの肢体を尻目に、ライナは赤く染まった杖をダルクに向ける。ケルビムが、ドラグーンが隠しきれない敵愾心をダルクに向ける。
ダルクは前を向く。あくまでライナを見据え、視線は絡む。
「終わらせる。終わらせてやるよ……!!」
「終わらせる。終わらせてやるよ……!!」
「うん。終わらせましょう」
ダルクの搾り出すような声色に対し、ライナはまるで意に返さないように杖を構える。それはまるで死を日常として飼い慣らしている戦士のような自然さであり、だからこそそのギャップにダルクは悪寒を覚える。
(落ち着いて考えろ……!)
ライナは初め、俺を取り込もうと思っていた。ということは、俺に少なからずの『未練』がある。なら怖いのは『破壊』狙いじゃなく『コントロール奪取』。墓地に送られることより、心を掠め取られて自意識を持てなくなることに警戒する――。
ダルクはあえて思考を垂れ流した。もちろん本心で思うこともあろうが、思考の果てにライナの行動を縛る目的もあったからだ。
「へえ。死線くぐってない割には、なかなかどうして」
「……」
「いい思考じゃん!!」
叫び出すと同時、ライナの手元には一つの『巻物』が現れた。同時に、全身を駆け巡る、それは。
(リバース効果!? ライナの! 光属性のコントロール奪取を行うリバース効果を俺に向けるってことは、あの巻物は……!)
「ごめーとう! 《幻惑の巻物》だよ!!」
(属性を変更して無理やり光属性のコントロール奪取効果をねじ込もうとは、とんだゴリ押しじゃねえか! だがそれは、)
「考えてなかったわけじゃねえ!」
ライナが巻物を構えると同時に、ダルクは《月の書》を構えた。それは、くしくもライナと同じ戦術を――ライナを対象に取り、リバース効果をぶつけるというもの。だが、違うのは……
(ライナ。てめーはさっき、『闇属性の遺伝子を取り込んでる』って言ってたよな。そうだとすると、《幻惑の巻物》なんて搦め手を挟むまでもなく、てめーはリバース効果に苛まれることになる!)
ダルクは《月の書》と《太陽の書》を同時詠唱し、一気に脳内に襲い掛かる昏倒感を強引に抑えつける。対象に向けるはライナ。だが、
「……」
ライナは動じない。そして、ダルクから放たれた『効果』を体の正面で受ける。しかし、彼女は破壊されない。
「な、なんでだ……」
「あらダルクくん。もう忘れちゃったあ?」
茶化すように放たれたライナの左手に、鏡が握られていた。それは、あの時に作った、ダルクが一番知ってるはずのもの。
「あたしがエンディミオンに飛んできたからには、このフィールドでダルク君からもらった《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》は発動された。従って、ダルクくんのリバース効果は出ない」
「くっ……」
「惜しかったね。狙いが被るってのは癪だけど、あたしも持っている闇属性という観点を狙うのなら上策だったとは思うよ」
それは図らずとも、ライナの光属性の首領としての立場を垣間見る一コマだった。戦闘慣れ、指揮官としての思考。それらは着飾っていても、本物。
「目の前で人が死ぬのを見たくないってのはよくわかるよ。あたしもそりゃ、できることなら回避したいもの。だけどね」
「……」
「そう思うなら思うで、切り札の切り方が流石に甘い。もうわかってるよね、ダルクくんを《ジャスティス・ワールド》に呼んだのは、紆余曲折の流れで《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》を作ってもらうため」
「よくできた、脚本だな。おかげでこんな展開を不自然に思うことなく《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》を作っちまった。それにしても、随分《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》の扱いに手馴れてんじゃねえか。ただ闇属性の遺伝子を持っているからって扱いじゃあねえな」
ダルクに、《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》の存在を直前まで匂わせない発動技術。それにダルクは一番驚いていた。《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》を受託したといえど、あくまでライナの根本は光属性。《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》を『使い慣れる』ことはないからだ。だが、彼女はそれをやってのける。
「……《閃光を吸い込むマジック・ミラー》と《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》はある種の爆弾。属性間のバランスを考えたら、扱いには精通しておかなくてはならないわけ。それは、光属性だから、闇属性だからっていう単純な理由じゃない。兵器を扱うものの責務だよ」
一瞬、ダルクはその言語に揺れた。本心なのか、綺麗事なのか、揺さぶりなのか。それすら、見えない。
「どうやら、エリアもウィンと戦う中『鏡』、使ってたようだね」
ライナが足元にふと目を向け、落ちていた儀水鏡を拾い上げる。滴っていた血をさっとふき取ると、
「水属性も鏡を取り扱う中、私達のミラーのように能力を先鋭する可能性もあった。だけど属性の色かな。そういうことにはならなかった。だけど、これも使い方は学ばせてもらってるよ。鏡の力は全て、わかってる」
「『ライナ』を潰すのが癪というなら、いっそのこと思い出を強引に塗りつぶしてあげる。Lyna , Lynna … myra … ミラ。うん、私の名前は、ミラだ」
考える素振りを数秒見せ、何かに気づいたように呟く。
「私の名前は魔術師ミラ。《久遠の魔術師ミラ》!!」
ライナが――ミラが口上を高らかに宣言すると、ケルビムが杖を構え猛烈なスピードでダルクに距離をつめている。
これまで、ケルビムとドラグーンは言葉を全く発していない。その瞳は、沈んでいたように、見えた。
(あいつらの自我は今、残っているんだろうか)
だが、そこまで他人に構う余裕が無い命のつばぜり合い。
「《マジカルシルクハット》!!」
ケルビムの杖を捌き、勢いを受け流し防御魔術の詠唱。ライトロードと、ミラと距離を取り体制を整える。
(戦況はあまりにきつい。1:3なんて悪い夢だと思いたい。だから、守って守って勝機を伺うしかない)
『攻めない』ダルクの様子をミラは黙って見つめ、唐突に口を開く。
「いま、《マジック・クロニクル》の発動を想ってるよね」
「ん、なっ!?」
ダルクが驚いたのは思考を読まれたからではない。もっと奥底の発想を『攫われた』からだ。
ダルクがこれまでライナに読まれていた思考というのはそれこそ完全に考えている思考だった。前頭葉のハッキング。ライナが行う読心術はそれで、灯火がついては消えるひらめき――海馬で行われている脳活動まではハッキングされていない。そう思っていた。
「これは読心したとかじゃない。『見える』んだよ」
だが、ミラはそこまで踏み込んできた。違和感と畏怖と、警戒。それらが全身を右往左往する。
「もう私は心を読まないから、臆せず考えて。ただ」
その種は考えてしまった一つの可能性。
「これから、本能を読んであげるから」
「くそっ!」
「そして、『わかっていても止められない』! それが、ミラの効果!」
その背後に感じるおぞましいまでの殺気。ダルクは反射で、防御の構えを整えようとした。だが、
「見えるよ! びびってるよねぇ! 《リチュアの儀水鏡》!!」
ミラが甲高く笑う。叫びきれるような魔法の詠唱。そこから紡がれるシナリオは、
「ど、どういう……!」
ダルクを、狂わせる。
「あは、あはは」
《リチュアの儀水鏡》の詠唱が終わった瞬間、ケルビムの胴体が中からはじけ飛ぶ。臓器が、肉片が厳かな絨毯にへばりつく。
「な、なんだよそれ」
「なんだよ、って《リチュアの儀水鏡》。儀式魔法じゃん。儀式のためにはモンスターのリリースが必要なんてこと、基本中の基本だよね?」
「そうじゃねえ! なんでケルビムを!」
「なんでって……? だってケルちゃん、フィールドにいちゃう限りはただ力の強いでくのぼーなんだよ? 既に老害。ゴミクズなの」
それは、なんでそんなこと聞くの?という瞳。だからこそ、ダルクは光景を信じたくなかった。
ケルビムの肉塊を踏みつぶし現れたのは《イビリチュア・マインドオーガス》。本来ならば水属性を統べるエリアルの護衛として統治を担うモンスター。
だが、主はマインドオーガスの上で遺体となっていた。それは先の戦闘の結果。事実は覆らなく、マインドオーガスも主の不在に混迷をしているのか、落ち着きのない挙動を見せる。
「エリア! エリアァ!」
「無駄。エリアルはもう、死んじゃってる」
(ライトロードも、リチュアも、敵か)
三種族からの敵愾心を一心に向けられながら、ダルクは途方にくれる。
(パワー的に力で制圧するのも至難の業、大降りになるコントロール奪取はできない……チェック、メイトかよ)
汗をぬぐい、可能性を探りながらも、心のエンジンが切れかかっているのも自覚しかかっていた。
(コントロール奪取は……でき、え? いや、『奪取する』必要なんて……!)
切れかかった細い糸。だが、そこに、可能性があった。
(その『手段』! あとは俺が詠唱できる範囲で可能かを探すだけだ!)
ダルクは堂々と思考する。ミラはその様子を怪訝に感じながらもその実を読めない。なぜなら、ダルクの本能ですらまだ、『解答』にたどり着いてないから。
「魔法、魔術、マジカル、マジック……」
ダルクはぶつぶつと呟く。脳内の検索。持ちうる知識を全て洗いなおすかのように。
「護符……印章、――これだっ……!」
解答に、たどり着く。
「!? まさか、そんなのっ!?」
瞬間、ライナがそれを読み取るが――
「《所有者の刻印》オーナーズ・シール!」
詠唱が、間に合う。シール(Seal)――印章は魔術的な図形。ダルクも魔法使いとして《六芒星の呪縛》や《五稜星の呪縛》を会得しており、印章も、その発展的魔術。そして《所有者の刻印》の刻印は、自我を奪われたモンスターの目を覚ます魔術。従って、ドラグーンは、決してダルクの配下になりはしないが、敵愾心はしぼむ。マインドオーガスも元々エリアルの配下。儀式魔法を唱えたのはミラではあるが、そのコントロールはミラから引き剥がされる。
「竜の御仁! 確かジャッジメント・オブ・ドラグーンとかっつったよな!」
ダルクは叫ぶ。
「決して俺はあんたらの味方じゃあない! だが敵でもねえ! 乗り込んだ船、必ずAOJの問題は片付けてやる! だから、つくべき『主』を選んでくれ!」
ミラはその様子を怪訝な表情で、睨んでいた。
「私は、間違っていたのか」
ドラグーンが、地を震わす声で呟く。
「ケルビムは、葬られる必要があったのか。私は、ライトロードは、ライナ女史の教えに従い、事態解決の道を模索していた。だが、ライナ女史の教えが正しいとして、ケルビムが葬られるような教えは、全て従って後悔のないものと言い切れるのか」
「決してライナを裏切らなくていい! だから、この戦いを黙って見届けろ! 勝った方につけばいい!」
ダルクは慟哭し、改めてミラを見る。
「……《裁きの龍》を手懐けていたからこその戦況だった。それをひっくり返された。ダルクくんをこっちに引き込むことも、できなかった」
「ミラ、いや、ライナ」
「引導、かな。糸が、千切れちゃった」
ライナは、目前に迫るマインドオーガスを捌き、ダルクの元に距離を詰める。
「すまねえが、終わりだ。《魔法の筒》!!」
《魔法の筒》の詠唱と同時、ミラが勢いを止める。攻撃を行えば《魔法の筒》のトリガーが誘発し、反射魔力が彼女を襲う。それを十二分に理解するミラは寸での所で攻撃をせきとめる。
「なにが、終わりなのかな。そんな大振りな魔術、私がくらうわけが」
「あるんだよ」
ダルクは、にやりと笑う。彼の右で鎮座するコミカルの物体が、相手の攻撃を吸収して反射する仕組みのアーティファクトが。
ドォォォォン!!!!!
『ミラの攻撃を受けてもいないのに』砲撃する。
「!? ど、どうし――」
エネルギー体が豪速でミラに迫り、胴体に直撃し――ぶち抜く。
ダルクはその様子を切れる息と脈動を必死に抑えつつ、呟いた。
「《ジャスティス・ワールド》の玄関先で貰った一撃だ。返してやろうじゃねえか!!」
それは、測れる定理から外れた一撃。あるはずの無い一撃。
「……ッ」
これまで仮面で着飾っていたミラが、取り繕っていたミラが、その仮面を引きはがされる。他所で行った戦闘により発生したエネルギーをぶち込む。『理』や『常識』から外れた一撃は、想定をゆがませるに十分だった。脊髄反射で恐怖に歪む表情。自我と本能の狭間にある意志が、それでもミラに防衛の意識を呼び覚まし、ミラは自身の胸の前で腕を交差する。図らずして《魔法の筒》による一撃がミラに豪速で迫り、接触。衝撃波を発生させつつ、ぶち抜かれた一撃はミラを部屋の壁まで吹っ飛ばす。
「くっ、はあ……!」
ミラは、息を残していた。ただ、弩級のエネルギーを一身に受けたミラの腹部の服装は熱量により消失、体躯の所々から血が流れていた。寸でのところで攻撃を受け流し、周辺の壁をえぐるほどには自身へのダメージはなかったが、ぐったりした様子は隠しきれない。
「手を抜いたつもりは、なかったんだがな」
ダルクは大きく負担をかけた先の戦闘のリバウンドで、大きく肩で息をする。数秒の間の後、一つ大きく息を整えると《裁きの龍》を一瞥し、ミラに向かいゆっくりと歩を進める。
「……」
「なあに?」
ともすれば一撃を秒で浴びせられる距離。ダルクは見下ろすようにミラを見つめ、手に持つ杖を強く握りしめる。
「く、そっ……ッ!」
先の戦闘の勢いそのままでいけば、ダルクは躊躇なくミラの急所に杖を差し向けたいただろう。だが、手が動かない。
「ほら、早くやりなよ」
ミラが満身創痍の全身を鞭打つように両手を、立つダルクに向ける。
それは場が許せば抱擁を求めるようであり、立ちあがる自分に助力を求めるようであり。だが、今はそういうシーンではない。
「まあったく。ホント、ダルクくんは甘いよね」
ミラは持ちあげた腕をぽとりと落とすと、肩を震わせて笑う。
「ここで私を殺しておかないと、ほんとにほんとに、後悔するよ」
その言葉にダルクの眉間は揺れるが、ミラにつきつけた首元の杖は震えるだけ。
「……いいでしょう。じゃあ、私の持ってる知識は全部流してあげるから。だから、気持ちよく墓地に送ってよ」
そう言いながら、ミラはダルクに一枚の鏡を差し出す。それは先ほど《イビリチュア・マインドオーガス》の召喚に使用した儀水鏡。ダルクは差し出されたそれを黙って受け取る。
「さっきウィンが《ガスタの交信》してたよね。あれは本来盗聴なんてコスいことに使うための技術じゃないんだよ?」
「どういうことだよ」
「本来《ガスタの交信》はシャーマニズムのために生み出されたもの。っ……イタコ……って知ってる?」
ミラが脇腹から走る痛みに一瞬顔をしかめつつ、続ける。
「死せるものとの交信技術――いわゆる口寄せってやつね。だから、交信によりチャンネリングができる以上、フィールドと墓地は決して遠い物じゃない。その気になれば混線できるんだからね」
「そ、それはなんか、違う……だろ…!!」
「うん、違うね。そうであっても、死者と気軽に関わりを持っていいとは決してあたしは言わないよ。でも、そんな個人の思想とは別に世界の理は出来あがってる。それがその《リチュアの儀水鏡》」
ミラは、手渡したその鏡をぴっと指さし、続ける。
「決してリチュアが魔法をひん曲げたわけではない。それでもその《リチュアの儀水鏡》は生まれ出でしときから墓地に干渉する魔力があった。死者を蘇生するような禁忌たる技術ではなくとも、それはリチュアの種族の感情に訴えかけるには十分すぎた」
だからこそ、だったのかな。そんな遠い表情を作りミラは続ける。
「リチュアはガスタと組んで、墓地干渉を突き詰めようとした。《ガスタの交信》はイタコの域にとどまっていたから、うがった見方をすればホットリーディングとも取れる。勿論ウィンダは《ガスタの巫女 ウィンダ》として正当に仕事をしていたはずだけど、生真面目さかな。どうすればいいか悩んで悩んで、そしてその解答として――死者を視覚情報として得られるように出来ればいい、そう至ったわけなんだと思う。でも、その末起きたエリアルとウィンダの戦闘は皮肉な結果かな」
そんなの、正常な思考なはずねえじゃねえか。そんな言葉がダルクの口から紡がれかけるが、それはぐっとせきとめられる。だってそれは。
「視覚情報を得るためによりしろとして使われたのが儀水鏡。そして、《儀水鏡との交信》は為された」
苦しんだ末に生まれる思考が外す箍の重みを誰よりも彼は知っていたから。だから、口に出せなかった。
「だから、私を殺してくれていい。それで、寂しくなったらその鏡で《儀水鏡との交信》してくれたらいいから。もっとも、その鏡から見える私が、正視に耐えうるものかは保証しないけどね」
やっぱり。ダルクが想定していたことは、ずれていなかった。例え墓地との対話が可能といっても、既に墓地に行くモンスターはなんらかの外傷を与えられて『破壊』されている。その後どういった手段を取って埋葬されるかは別にしても、最終的に死体と会話する技術。まともな造形の者と会話できるはずが無い。
「いたい、痛いんだよダルクくん。さっさと殺してよ。あたしはのうのうと延命させてもらえるような善人なんかじゃないんだから」
えへへと、痛々しくミラは笑う。
「……私が、何人殺してるか。ダルクくんは知ってる?」
「いきなり、なにを」
「もっと言えば、ダルクくんが見ていないところで何人殺したか。だね」
それは、心の底から同情を嫌うように。吐露する。膿を出す。扼殺する。
「ヒントはいくらでもあるんだよ? リリーが電話口のダルクくんにあまりにも流暢に裏を話したこと。そのリリーが急に、糸が切れたように応答をしなくなったこと」
「ま、まさかっ!?」
「リリーに喋らすこと喋らして、サクッとね。あのとき私はリリーの横で椅子を借りていた。最期の顔は、爽快だったね」
思えばあの時のリリーの声色や台詞は妙に観念的、諦観的だった。実が頭の中で一本の線につながる。
「あと、ライトロードの『設定』。《裁きの龍》による放射の一撃。あんなもんがノーリスクで打てるはずがない。《裁きの龍》がその起動効果を発揮するには、ライトロードモンスター4体の死が必要不可欠」
「な、何を言ってるんだ? 起動効果? 4体の死?」
「私達霊使いがリバースにより効果を発揮するように、ある種のモンスターは効果を起動するために手順を踏む必要があるの。《裁きの龍》であれば、その召喚設定はライトロードモンスターの死を4体必要とする」
ケルちゃんもさ、楽ーにしててもいいんだよ。どーせ、もう1人死なないと、召喚条件整わないでしょ?
いつかライナが吐いた、その時はよくわからなかった台詞。ケルビムが眉間をゆがめた台詞。
そういう意味か、ダルクは呟くがその言葉から生じる矛盾点が口をつく。
「ちょ、ちょっと待て。ライトロードのうち殉職したのはガロス・ウォルフ・ジェインのみ。3体……」
口をつくが、ミラの意図せんところが一瞬で脳を駆け巡る。
「殺したってことか……!!」
ダルクの頭に会議を繰り広げたライトロードの精鋭たちの表情がリフレインする。
誰を、いや、聞くまでもない。ダルクがエリアの招集を受け《強制転移》した瞬間、そこには献身的でなお文武を従える優秀な魔術師がいたじゃあないか――。
「これで、理屈と理性の堰を壊してあげた。それでなお、殺さないなんて決意が取れるのならきっとダルクくんは聖人だよ。罠を張っているとか警戒してるのならお門違い。私はただ、お役御免を悟っただけ。世界と、ライトロードの手綱を切るのはダルクくんなのさ」
ミラが弱弱しい瞳と指先をぴっとダルクに。向けられた人差し指はかすかに震え、きっと放っておいても事切れるだろう、そう感じさせる。
「なあんてね」
だが、それで幕切れでいいのか。それで自分はライトロードに向き合えるのか、疑念が脳内を駆け巡る。
「……。卑怯ですよ、ライナ――いえ、ミラ様」
その静寂を、ダルクの後方から突き破ったのはピケル。
「ぴ、ピケル……安静にッ……!」
その様子は痛々しいと称するに余りあるもの。つきぬかれた胴体を包むローブには血が滲み、まともに見ればとても直立すらできない状況。
「大丈夫です。重傷ではありますが重体ではあり、ません。内臓損傷程度です。唾つけて治癒魔法かけておきゃ勝手に治ります」
その暴論には流石に無理があるだろう、ダルクは口を挟もうとするが、ピケルの畳みかけるような台詞に気押される。
「ここでダルクさんにトドメを求めるのはあまりにも酷すぎます。もっともそこまでがミラ様の揺さぶりと言うことであれば、口を挟めませんけども」
「ピケルも言うようになったね」
「私も驚いています。……。きっと、《久遠の魔術師ミラ》様として効果を発揮するにあたって従来の《光霊使いライナ》様としての属性影響力が薄まったのかもしれませんね」
ピケルはよろ、よろとミラに向かって歩を進める。足元にはぽたりと血が滴るが、そこには不思議と悲壮感を感じさせない。
「それでも私は一生涯《光霊使いライナ》様にお仕えします。これは、コントロール云々なんかじゃなく、私の意思です」
「……そっかあ」
それは、《久遠の魔術師ミラ》に語りかけるからこそ意味あり、説得力のある一言だっただろう。ミラはその力強い一言を噛みしめるように一つ大きくまたたき、一瞬だけ――ほんの一瞬だけ悔恨の表情。
「それじゃ、ピケルに頼もうかな」
「はい。謹んで、お受けします」
何を? それは聞くまでもない。もはや、場の全ての共通認識。
よたよたと近づくピケルは、ふと足を止めミラの首元に杖の切っ先を。
躊躇することなく洗練された魔力が、ミラの首元を貫通する。
最小限で、だがしかし死を確信できる一撃。最期の表情は、優しい笑いだった。
ピケルはその死に顔をじっと見つめると、しゃがみ込んでその瞼を易しく手のひらで包み、瞼を閉じさせる。
「疲れました」
それだけを終えたピケルがぱたと沈み込み、そのまま床に寝そべる。
「む、無茶しやがるから!」
「勘違いしないでくださいよ? 役目を終えたピケルはそのまま息を引き取った――なんて感傷的な死なんて決してしてやりません。これから私は光属性を背負わなくちゃいけないんですから」
だから、そうピケルは小さく呟いて。
「ちょっとだけ、休ませてください。私はここで治癒魔法をかぶせて、すやすや眠っておきます。今度起きた時に、全てが終わっていることを信じています」
「ああ、ゆっくり休め」
「はい、ダルクさん。おやすみなさい、それと……ごめんなさい」
ピケルの瞳は涙に溢れ、横たわる顔からこめかみにそれは伝っていく。
ダルクはピケルの顔元にしゃがみ込み、その涙を人差し指でぬぐう。
「全部終わったら。みんなのわだかまり、解きに行こう。この部屋の後片付けも、一緒にやろう。だから今は、眠っておけばいい」
それは、ダルクが珍しく見せる朗らかで、思いやる表情。ピケルは一つだけ頷き、赤らんだ顔を頭上のフードで隠そうとして――先の戦闘で『使った』ことに気付き、行き場の無い手を握り、ちょっとだけ笑った。
「まったく、情けないもんです」
ピケルは、寝転がった体制で、涙で赤みがかった頬を隠さずに呟く。
「ミラ様の腹心としてダルクさんを陥れる模索を行い、結果デレるだなんて。とんだピエロです」
「デレる、っつーのも違うだろ」
「この戦闘の結果私を殺さなかった時点で、フラグは立っているようなもんですよ」
ピケルは力なく笑う。それは照れるというより、諦観したような表情でもあった。
「ダルクさんはこの戦闘に力勝負という意味では勝利しました。あのライナ様と正面切って向かい合い勝利をおさめるなんて大したものだと思います。しかし」
ピケルは握りこぶしを解き、続ける。
「六属性の首領が入り乱れたバトルになった時点でライナ様の勝利は確定してたんですよ」
「DUELIST GENESIS……闘争の創生、か」
「はい。元々その『闘争の創生』をするためには、エリアさんの闘争本能を揺り起こすことが必要不可欠でした。エリアさんは儀水鏡という後ろ立てがあったからこそ、光属性と闇属性のマジックミラーの能力に焦燥していました。いえ、嫉妬というべきかもしれません。結果エリアさんがこちらに回り、傾いてたバランスが均衡になった。そして決戦の火蓋が切って落とされたというわけです」
「ちょ、ちょっと待て。ということは……」
「はい。結果として『闘争の創生』された理由は《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》が作成されたからです」
その言語はダルクの視界を歪ませる。
「だけどあれは避けられない判断だったと思います」
「『あれ』って……ピケル、俺がミラーをライナに渡したことを……」
「ええ。知ってましたよ。ちなみに、当の発端であった闇属性の暴動はビンドさんが造った《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》による影響です。ダルクさんがミラーを作るのと同じタイミングでライナ様とビンドさんが口裏を合わせて、《魔法都市エンディミオン》でもミラーを造った。そのことでダルクさんが造ったミラーが《魔法都市エンディミオン》に影響を与えたというミスリードを誘発させ、ダルクさんを帰還させやすくなる。暴動が起きた段階で《ジャスティス・ワールド》もしくはAOJのフィールドにいたダルクさんが所持していたミラーによるものではありません。罪悪感など、持たないでくださいよ?」
「……」
「その意味では、導火線に火をつけることはいつでも可能だった。それを単に、ダルクさんのミラーの創生に重ねて、罪を全部押し付けた。5属性もの首領が死した段階で、ライナ様の目的は十分に達成されているといえます。自身の死は流石に想定していなかった、はずですけれども」
「だったら……」
「だったら?」
「俺が全部、担ってやる。闇属性の首領じゃなく、霊使いとして……魔法使いとして、引っ張ってやる」
「……。……はい、当然です。そうなってもらわなくちゃ、困ります」
ピケルは笑った。
「そのためにも。まずは《ジャスティス・ワールド》の問題を片付けてきてください。真の解決編はそれが終わってからでも十分なんじゃないですか?」
「俺がその時まで、生きていればいいがな」
「あはは」
ピケルが屈託なく笑う。それまでに流していた涙は通り過ぎた先だけを残し綺麗に消えていて。
「ダルクさんは、殺しても死ぬようなタマじゃありませんよ」
ダルクは、《ジャスティス・ワールド》へ《強制転移》した。手には《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》《閃光を吸い込むマジック・ミラー》《リチュアの儀水鏡》が持たれていた。それはある種の属性間のバランスの象徴。ダルクのモラルハザードが疑われていれば、一気に《魔法都市エンディミオン》が陥落しかねないほどのアイテムの集約である。急戦派が見れば、戦争学者から見れば、暴動を渦中へと誘うプロパガンダとも取られかねない物。だが、ダルクはそのような考えをほんの一欠片さえ持たず、明鏡止水のような精神状態を保つ。
「何が正しいのかなんて、進んでみなくちゃわかんねえもんだろうがな。カードゲームじゃ、あるまいし」
「何か申したか。ダルクよ」
《コート・オブ・ジャスティス》で、ダルクとドラグーンが並び立っていた。ぼそりとつぶやいたダルクの言葉はか細くドラグーンの耳に届いていない。
「いいや。独り言だ」
ダルクは自身の呟いたそれを特に補足せず、宙に投げ捨てる。
「ドラグーン、いや、竜の御仁」
「……なにか」
「この度のあんたの国への壊滅的な被害。直接的な原因は俺達の国のライナにあった。認めなくてはいけない、贖罪だ。謝罪の意を口にした瞬間その足で踏み潰されても仕方ないとは思うがそれでも言わせてもらう。すまなかった!!」
しん、とした空間に鋭く声が響く。
(この、人間は)
もちろんドラグーンはその言葉に反抗的な目を向けなかった。大きく見れば確かに魔法使いの責任だが、その見方はあまりに曲解で大局すぎる。それに対し謝罪の意を表明できるダルクに、ドラグーンはいっそのこと敬意さえ感じていた。
(もちろん、政治的な意図や今後の駆け引きなんて俗な視点で口にしてはいないのだろうな……)
「根本はライナ女史に舵を取らせた私と、亡きケルビムの責任だ。貴殿が気にやむことは何も無い」
「そこ、だ」
ダルクが何かを思いついたかのように呟く。
「そもそも当初、何故ライトロード陣営はライナをそんなに陶酔してたんだ? それだけをさせる『理由』があったとしか思えないんだが」
「鋭い、な」
ドラグーンは一瞬言いあぐねるが、しかし一つ大きく瞬いて口を開く。
「AOJを駆逐する決戦兵器をライナ女史から戦術構想として紹介されていた。前線から持って帰ってきたパーツを元に機械戦闘へ特化することを視野に入れ、もうしばらくでそれは実戦に移されるところだった。その名は光神機ライトニングギア」
「敵の鱗を剥ぎとって戦機を見出す。ったく……あいつらしい発想だな」
「今となっては、使えない一手となろうがな。前線だけでなく、ケルビムを、ライラを失った。そんな血濡れの兵器を使うのは道に反しよう」
「いや、それは違うだろう」
ダルクは両手に合わせて持つ3枚の鏡を慎重にドラグーンの前に掲げ、続ける。
「この戦闘の結果俺達の仲間が、あんたらの仲間が何人死んだ? 確かにライナの行いは償いきれないだろうが、少なくともあんたらを……ライトロードを救おうとした気持ちは本当だったんじゃねえのか? その『結果』を思考無しに切り捨てちゃ、ライナだけじゃなく、それこそみんな無駄死になっちまうんじゃねえか!?」
それは幾重にも目前で死を見てきたダルクの心の叫び。
「もちろんライナの行動を全部許すわけじゃ断じてない。だが、だからこそ取捨選択だ。そうでないと……浮かばれねえよ」
その言葉の主語は誰だったのだろうか。全ての歯車を動かした彼女か。歯車に身を委ねた彼女か。それとも、そこに気持ちを置いてきた自分に対してかもしれなかった。
「だから、見せてくれよ。その光神機ってやつをよ」
その光景は圧巻の一言だった。
「なる、ほどな」
《ジャスティス・ワールド》の工場一角の倉庫に彼らはいた。目の前にはダルクの身長の数倍もの大きさの、ほぼドラグーンと同じ大きさの機械が3つ並んでいた。
「ライナ女史は暇を見つけては当該機械の調整をしていた。機械の名はコード上、左から、閃空・桜花・轟龍」
「天使に機械に他属性……全くあいつにはプライドとかポリシーがあったもんじゃ……」
いや、あったからこそ、か。喉から止めどなく溢れる言葉をせき止め、考える。
(あったからこそ、それが届かない領域に手をつけたんだろうな)
「彼女は言っていた。まだこれらの兵器は未完成だと。瞬発力はあれども、持続力がない。エネルギーの消費効率が悪いのが難点だと」
「……」
ダルクは悩んでいた。これらのシナリオの、整合性に。
(ライナが目的の一つとして、俺の《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》を得ることを考えていたとしたら……)
「なあ、そもそもこの機械でAOJを相手することは可能なのか? AOJは光属性を駆逐する能力を持っているだろう? 根本的な解決手段とは考えにくいんだが」
「その点については解決済みだ。ライナ女史の手により、任意に属性を切り替える……セーフモードで起動することが可能となっている」
(やっぱり。つくづく、皮肉めいてるな。ライナはそもそも他属性を取り込むことに一切抵抗心がない奴だった。自身に組み込んだ《DNA移植手術》のルーチンを応用すれば可能ではある、か)
「そうすると、ライナが目指していたところが見えてきた。その短期決戦仕様の高出力ってのは『効果』だよな。AOJ用に改良された闇属性への変化。そしてライナが《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》を手にしたかったことを考えるときっと、《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》で、そのセーフモードの出力能力切れを強引に無効化することを考えていたんだろう」
その瞳には、信念を携える。
「それは正着だ。強引に俺からミラーをむしりとろうとしていたことだけを除けばな」
「……敵いそうか?」
「やる価値は、ある。ライナが用意したクリティカルな一手だ。存分に利用してやろうじゃねえか」
「貴殿らの関係は、複雑なものだな」
ドラグーンが含み笑って呟いた言葉に、ダルクはたった一言、よく言われる、とだけ返した。
「ライナは? その闇属性としてのセーフモードにコードは付けていたのか?」
「うむ。呼んでいた名は獄炎。邪神機ダークネスギアの獄炎だ」
「……あいつらしいノリノリな名前じゃねえか。いいぜ、斬り込んでやる! この戦いをぶった切って終結させるのが、俺の贖罪だ!」
ダルクは三枚の鏡を腰元に携え、叫ぶ。語気にそれは揺れ、若干の反射光を施設内に呼び込んだ。 「光神機」。仰々しい名前だが、その実は目には目を、機械には機械をという発想のもと用意されたライナの一手。
(きっとライナは、その一手を繰り出すことを、禁忌とすら思ってなかったんだろうな)
それは、チェスの板上に別面の駒を置いて相手のクイーンの通路を閉ざすこと。碁に置いて自分の地一マスに19路盤を彫り作り、361目ものアドバンテージを得ようとすること。負けそうな対人ゲームの最中に中断し、相手が餓死するまで中断を解除しないこと。そんなことをしてはいけないなんてルールブックには書いてない。
根幹は「ルールブックに書いてないことを勝手に反則だなんて解釈して、ためらう理由なんてない」ということだ。
(【トランス】戦術、か。事実、自身への……種族へのプライドを捨てられるのなら、有効な一手。相手が光属性を敵視する効果を持っているのなら、その効果を封殺すればいい。そうすれば……)
ダルクとドラグーンは、再びAOJの戦場へ。《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》を発動し、邪神機の燃費粗悪デメリットを解消。かつ、AOJの効果を封殺。襲ってくる低級AOJは邪神機のパワーで排除する。晴れてドラグーンを戦場に送れる状況を構築させていた。
「ドラグーン」
「なにか」
「あんたがライナにコントロールされていた状況下、ピケルが作り出したトークンを一斉に排除するような効果を発動したよな。あれは、切り札と見ていいのか」
「切り札と言うには、もろいものさ。発動回数も限られている上に、見境のない一撃。自我のある中、使う余地もないだろう」
「ケルビムの、部下のできることは上司もできないと。それがライナの心情だったからな。破壊の、能力か」
ダルクは暗闇がかった空間を見渡し、気を張りつつも説く。
「発動回数は、私の生命力が続けば……おおよそ7回と見込んでいる。しかし、それは」
「それは、自身に与えられた傷によっていかようにもブレるんだろ」
「察しのいい。その通りだ」
ドラグーンがいたく感心したかのように語尾を細め呟いた。
「いわゆる、ライフポイントをコストとして使う能力。《魔法都市エンディミオン》にもそういうのに長けた奴がいて……いや、いた。耳タコなくらい聞かされたさ」
思い返すのはウィンの姿。にこにこと笑ってご高説を賜った思い返す日々を噛み締めて、悲しげに吐く。
「すなわち、生命力の消耗がそのまま戦闘能力の低下に直結する。なんのひねりもないが、自分を大切にしてくれよ」
(懸念は大きく解消された……ただ、これらは眼前の問題を解消しようとしているだけに過ぎない。真に問題なのは……)
果たして、この「正義同盟」のリーダーは何か。そして、交戦状態になっている原因は何か。それがわからない限り交渉のテーブルも、実力行使も出来やしない。
このままでは勝利条件のわからないカードゲームをプレイし続けるのと同義。いくら雑魚敵を蹴散らしたとしても、勝利条件が相手のリーダーを粉砕することであれば浪費を重ねることであるからだ。
すなわち、必要なのは「理解」。データを集めることだけでなく、ライトロードとAOJの関係性・共通点・反目点、それらを勘案して「糸」を見つけることが課題。
(それに……)
ダルクが考えていた『悪い仮定』が眼前に。それは、これまでのAOJの機械とは違う大きな威圧。
(マザーシステム級。物理的なサイズも、傍目から感じる精密性もケタ違いってところだな。あれだけの数の機械を運用していることを考えたら、コアとなるサーバがあるってことは想像ついてたが、思ったより早い出陣だな……!)
巨躯なる図体は金色に輝き、アクセントのように碧みがかる。中心に備えた大きな砲艦に、足回りに光る刺々しいアクセント。どこをどうとっても戦闘用のデザイン。
ダルクがちらりと胴体に彫られているレリーフの文字を見ると、そこに書かれたのは ”Desicive Arms”の、流暢な筆記体。
「決戦兵器、か。いい虚仮威しじゃねえかよ!」
その巨体は、ドラグーンと比較しても引けを取らない。踏み潰されたら臓器の一欠片すら残らなさそうな威圧感すら感じる。
「ドラグーン。見積もってどうだ、肉弾戦は可能そうか」
「……厳しい所があるな。おそらくは、わずかながら相手のほうが自力は勝る」
「いい見積だ。俺もそう思ってる」
時と場合によればそれはとても失礼で、慇懃無礼な一言。だが、二人共そんなことは微塵も考えていない。そこにはあるのは歴戦の戦士共の忌憚なき戦力の計測の結果。
「ならまずはっ……!」
ダルクが力を抜き、杖を邪神機へつきつける。
邪神機のセーフコードを解除。光属性へ――『光神機』へ戻ったその機械を――
「ふんぬあああああ!!」
ドラグーンの咆哮。光神機の指示権を受け取ったドラグーンが、バトルフェイズへ。光神機の攻撃対象を《A・O・J ディサイシブ・アームズ》へ。
(突貫にしては作戦が通じ合ったな!!)
「ァァァァァァァァ!」
《A・O・J ディサイシブ・アームズ》の奇声。というより、バグ音。
音波域まで届くようなつんざく金属音を響かせる。ドラグーンは一切ひるまないが、ダルクは思わず耳を塞ぐ。
《光神機-桜火》が《A・O・J ディサイシブ・アームズ》へ駆け寄り、一撃をくらわすが、
ガッ、キィン!!
攻撃が弾かれ、《光神機-桜火》が爆発。
(やはり、ポテンシャルは高ェ!!)
ダルクと、ドラグーンが思考したのは、相手のポテンシャルの確認。《光神機-桜火》をぶつけることにより、相手の攻撃力のスペックを確認すると共に、光属性をそもそも戦闘で寄せ付けない効果があるかどうかを確認しておくため。そもそもジェインが爆散した時のような効果を持つ相手であれば、同一戦闘上にドラグーンを配置していることがまず不味いからだ。
(だが、あれはアンチ光属性ってのでやられた感触じゃない! 単に力負けしただけだ!)
「ドラグーン!」
「任せろ!」
ならば。ライトロード陣営の中でもトップクラスのパワーを誇るドラグーンを戦線に送ることに支障はないということ。
「《ライトロード・レイピア》!!」
ドラグーンが装備魔法を詠唱し、自身に装備。彼の中で、肉弾戦闘において考えるならば眼前の《A・O・J ディサイシブ・アームズ》を排除できるだろうという、歴戦の勘が働いていた。
「……」
懸念があるとすれば……。
「!?」
突然、ドラグーンの掲げていた《ライトロード・レイピア》が砕き割れた。それを目の前で見た二人は感じる。これは、物理的損傷ではない、と。
(効果……! 装備魔法を叩き割る能力だと……!!)
レイピアの割れ方はいわゆる経年劣化なんていう生易しいものではなかった。
まるでレイピアの原子構造を解体するように、内面から消失したような不自然かつ美しい崩壊。
つながる、ように。《A・O・J ディサイシブ・アームズ》がセンターに構える物々しい砲弾が、スタンバイ体制に入り。
その間二秒も経たず、軌道に乗せた豪速のレーザーレールガンを吐き出、
「《ライトロード・バリア》ァ!」
した、が、ドラグーンが適切に防御体制。声の威厳は変わらずまま、瞳の色は落ちぬまま。ドラグーンの前に拡がる透明の膜がレーザーを明後日の方向に受け流す。
「さすが、だな。力のほどが窺える」
「力はむやみに振り回すものではない。守るためのものだ。……《ライトロード・バリア》は永続的にライトロードに防御の加護を与える物。私のことを懸念せず、思うように戦ってほしい」
ダルクは一つ息を整え、そうか、と呟こうとしドラグーンの方を見た。その瞬間。
バリアが、割れた。それは先程の《ライトロード・レイピア》と同じような崩壊。
(装備魔法だけじゃ、ない!?)
二人は声には出さぬが戦慄し、ほんの寸分の間に脳内を一気に加速させる。
(装備魔法だけでなく永続罠も割る力がある……! となると永続魔法も戦力として計算できない!)
ダルクが思い立った思考は論理としては正確で、現状に即したものだっただろう。対峙する難敵に対しての打開策を模索する最中、たった一つの罅を除いて。
「ならばっ……!」
(迎撃してみせる!)
永続的能力に頼れない以上、手段は限られる。ダルクは思い至り、《魔法の筒》を構える。《A・O・J ディサイシブ・アームズ》が先ほどのようにレールガンを放てば、それはそのまま跳弾し、自身の力に溺れる。
そう考えた。だが、それは罅。
からん。ころん。
「なっ……!」
ダルクが言葉を失ったのも無理はなかった。何故なら、ダルクの後ろで《魔法の筒》が具現化し、風に流されたゴミ箱のように転がっていたからだ
それは、『発動すらできずにアーティファクトが排除されたとき』に起きる光景。《ライトロード・レイピア》《ライトロード・バリア》に続いて、3つ目の光景。
罅。それは認識が甘かったこと。勝手に対峙する相手の能力を『絞り』、その想定で動いたこと。
たった一つの謬り――それは――。
驕りがあったかもしれない。ともすれば、焦りだったかもしれない。だが、
「っ……!?」
だがそれは、ダルクの全身を震え上がらせるのに十分な衝撃だった。
(レスポンス型の反撃を予知して破壊してくる能力があるとか、リスクの高い防御ができねえじゃねえか!)
《魔法の筒》はまさに一撃必殺の防御。ぶち当てれば相手の戦意を大いに削ぐことができるし、その逆もしかり。ダルクがしくったと考えたのは、先のライナとの戦闘で充てんされていたエネルギーを放出してしまったこと。それが無ければこちらの戦闘に活かせたのかもしれないが、無い物ねだり。
(いや、逆だ! 逆に考えろ!)
「ドラグーン! 焦るな! この状況は、言い換えれば相手は直接俺達をコンバットできないってことだ!」
既にダルクとドラグーンが《A・O・J ディサイシブ・アームズ》の前に姿をさらして1分は経っていたが、一向に死を感じるような感触は無かった。種類関係無く魔法&罠を破壊し尽くした効果を相手にし一瞬、ターゲットとしたものを全て破壊できるのではないかという最悪の仮定が頭をよぎったが、どうやらその可能性は無い。
そこまでをダルクは考える。考えたうえで、の発言だったが、
「くそっ……」
考えるからこそ、状況の悪質さに答えを見いだせないでいた。
(伏せられないとなると、通常魔法くらいしか使えない。防御はどうしても手薄になる、攻めるしかねえってことか)
「いや、さっきの……! ドラグーン! さっき言ってた除去効果! あれであいつだけをぶっぱなすことは……!」
「さっきもいったが、それを行うと己以外のモンスターは全て排除される。貴殿もその例外ではない!」
「なら、俺が魔法を唱えて退却バウンスする! フィールド上で発動する効果の影響が及ばない場所に!」
ダルクが食い気味にドラグーンの言葉に返答する。相手が機械ということもあろうが、作戦は声色に流して、包み隠さない。だが、
「いけない!」
その言葉に口を挟んだのは全く別の方向。ダルクとドラグーンの後ろに、ルミナスが現れていた。その表情はいたく憔悴しており、エネルギーを多量に放出した後か、息も荒かった。
光の援軍。戦闘シーンにライトロードを招集・集合させる技術。ルミナスはその意味と、危険を顧みず、あえて死線に飛び込んだ。
「ドラグーン様! ダルクさん! ここで自身をバウンスすることは考えてはいけません! あの機械は帰還先てふだに干渉して破壊を行って来る効果も持っています!」
「るみ、なす……なんでここに! こんなとこに来るとあぶねえだろうが!」
「私みたいな一兵卒の命より貴重な命はいくらでもあります! 少なくともダル……いえ、そんなことを言いに来たのではありません! お聞きください!」
「っ!」
そう叫ぶルミナスの表情は寄せ付けぬ意思の塊のように、ダルクの反論を喉元で抑えつける。
「あのモンスター、《A・O・J ディサイシブ・アームズ》は一度ターゲットとして認識したモンスターであれば、その認識下から外れても破壊されます!」
「どうしてそんな事がわかる!」
「今、ドラグーン様とダルクさんがかけあった戦闘で、解明不明であった戦闘データが解明できたからです! 数日前にガロスから貰っていたデータ……そう、ダルクさんが《ジャスティス・ワールド》に来られたあの日です! ガロスは当の《A・O・J ディサイシブ・アームズ》と戦闘を行っていたのですが、その時はあまりにも大きな力の差に退却を試みたんです。しかし、大きく距離を離し、もう《A・O・J ディサイシブ・アームズ》のいるフィールドからは離れたと思ったら……!」
「あの、時か……!」
ジェイン・ライラとAOJのフィールドに踏み込んで間もなかったあの時、ガロスは”外傷なく”破壊されていた。その時、そして今この瞬間までその原因を、《A・O・J カタストル》と思っていたが、違った。
「ガロスからの最後の通信はそれでした。まさかの、フィールド外からの破壊。けれども、《ジャスティス・ワールド》にいる諜報担当は被害を受けていません。それらから考えると……」
「なるほど。一度視認されちまえば逃げられねえ。自然な考えだな!」
ルミナスの言うことが真実なら、もう逃亡は図れない。防御も出来ず、逃亡もできない。取れる手は、前進。
(手が、思いつかねえ!)
ダルクがじりじりと重圧に、胸を焼く。がっちりと噛み締めた歯は自身の力で歯茎を鬱血させていたが、本人はそれすら気づいていない。
(《A・O・J ディサイシブ・アームズ》は闇属性。だから《暗闇を吸い込むマジック・ミラー》を使えば除去効果は封殺できる。だが、それは危険な賭けだ。この場に及んで切り札となるコントロール奪取効果を切り捨てることにもなる。戦術としてそれは正しいのか……どう、すればいい……!?)
一発目のレールガンから20秒も経っていない。《A・O・J ディサイシブ・アームズ》は感傷に浸る3人を黙って見ているわけではない。単に、機械的に、次弾の充てんを進めていただけ。
(まず……)
ダルクの意識は外に向いていた。それは、戦場においての自殺行為。
「やられっ 「《光の護封剣》!!」
音もなく放たれた一撃にほんの数コンマ間に合ったように、ルミナスが防御の詠唱。弾かれた一撃は明後日の方向に飛んでいくが、一秒も経たず《光の護封剣》は破壊される。
「すまねえ、油断してた!」
「はい! 油断しないでください! 私は光ルミナスの魔法使い! だからこそ、たまたま《光の護封剣》は詠唱できますが、そうそうそんな都合いい防御ができるなんて思わないでください!」
ルミナスは、一瞬で消失した自分の防御魔法について全く怯まず悪態をつく。むしろ、覚悟があったからこそ割り切っていたような腹でもあった。
(くそやろうが……!)
手に持つマジックミラーを発動すれば効果を無効にした肉弾戦が可能になる。だが、ドラグーンは地の能力で《A・O・J ディサイシブ・アームズ》より攻撃能力は下回っていると解答した。《ライトロード・レイピア》の二度目の創生は容易ではない。ここで思考放棄するのは得策じゃない。
そこまでダルクは考えてマジックミラーをローブの奥にしまい込み、その際視界に入った《魔法の筒》に目をやり、
(!?)
その抜け殻に、感じた違和感。
(あいつらは機械。ということは誰かしらの創造主がいないと道理が立たない。それも、防御魔法の破壊能力を創造の時点で仕込めるくらいだ、自身がその能力を持ってないと完成はおぼつかないだろう。俺の知りうる限りそこまでの能力を持つ手練と言えばビンドだが、もしその仮定が成り立ったとしても、俺がこの場にいる理由はライトロードとAOJの闘争。そうだとするとライナとビンドが喧嘩していることになる)
思い返すのは、血みどろの会議室。
(だが、ビンドが《A・O・J ディサイシブ・アームズ》の創生に関与した可能性は濃厚。なら、帰還先てふだを狙って破壊する能力ってもしかして……)
「竜の御仁」
「……」
「可能性の話ではあるが、《A・O・J ディサイシブ・アームズ》の視認外からの破壊。あれに、俺達闇属性魔法使い族は対象にならない可能性が高い」
「そう、至ったのは」
ドラグーンが、噛み締めるように。言葉を選ぶように。
「そう至ったのは、ライナ女史の一件が関与しているのか」
「さあな。……、もしその目論見が外れて《A・O・J ディサイシブ・アームズ》に射ぬかれても、なんも後悔はねえ。むしろ墓地であいつらに、首根っこを掴んででも理由を吐かせたいくらいだ。だから」
ダルクの背の何倍もの体格を誇るドラグーンは、その瞳を大きく捉えていた。それは覚悟を決めたものの見せる揺るぎ無き表情。
「だから、お望みならこの場から退却できる。ただ……ルミナス。あんたは」
「わ、私はドラグーン様が効果を発動なされるということであれば、受けるつもりでここに来ました。命を散らす、つもりです」
「そうじゃ、ねえだろ!」
ルミナスの悲壮な決意に、ダルクは食って掛かる。ルミナスの方を見ず、叫び倒すように。
「なんでそうどいつもこいつも死にたがるんだよ! てめえのヒロイックな覚悟とやらで散り終わった奴らはさぞ彼の世で満足に過ごせるだろうよ! だがな、残された奴らのことを考えろよ! ドラグーンがその結果に満足すると思ってんのか!?」
ルミナスの肢体がびくりと震える。震えと、風圧でルミナスの首元にかかるマフラーがたなびき、するりと外れて地面に落ちる。
「あ、あたしも生きたい! いや、生きてみせます!」
「それでいい!!」
「ドラグーン様の効果の範囲外に退避しなきゃいけない。ただ私は光属性、《A・O・J ディサイシブ・アームズ》の手に掛けられる可能性は濃厚なので『外』にはいけません。だから、私は墓地に行きます」
ともすればそれは自殺宣言。だが、そこからは一切の悲しさとか、皮肉とか、諦めはない。
「私は召喚師(サモナー)。死線と生線の扱いは心得ています!」
ルミナスの肩書きである召喚師(サモナー)。その扱う技術である『召喚』は死占術(ネクロマンシー)であり、死者蘇生技術を彼女は会得している。だが、彼女はその能力を発動したことがない。死は自然の理であり、それをねじ曲げるのは道に反すると考えていたからだ。
そのため、普段その能力を使うのは僧侶として、生ける者に慰みを与えるためのものだった。だからこそ、抵抗もあっただろう。自分を殺し、自分を蘇生すること。元々死ぬはずのない運命だった。彼女は正当と飲み込み、墓地へ飛び込む決意をした。
その決意を、ダルクは表情を緩めず見つめる。
「……」
手元には一本の羽根ペン。ローブの裏にしまい込んでいたそれを手に持ち、じっと見る。その羽根は翡翠色に輝き、なんらかの魔法の効力があるのかオーラが透けていた。
「《ガルドスの羽根ペン》。ウィンからもらった帰還用アイテムだ。これを使えば俺は一瞬で退却できる」
「わ、わたしは。死ねるのは10秒くらいです。あまり引っ張りすぎると、多分戻ってこれません」
仮死も過ぎれば壊死になる。魔法とか、効果とかそんな小手先の話ではなく、それが生物の摂理だ。
「ということは、一度決めたらドラグーン。あんたには腹を据えてもらわなきゃいけない」
ダルクの言葉に、ドラグーンは一つ首を鳴らし唸るのみ。
「行けるな?じゃなくて、行ってくれ。俺もルミナスも、あんたに命を預ける。俺とルミナスは別々の場所から戻るが、その時に『終わってる』ことを期待してる」
「お願いします、ドラグーン様!」
ドラグーンは、足元を大きくかち鳴らす。
「うぬら、行けえええええええ!」
瞬間、ダルクは羽根ペンを撫で上げ、瞬間、ルミナスは手元に集めたエネルギーを自身の胸元に押し付ける。
二人は別々の場所に消え、取り残されるはドラグーン。一秒も経たず、行われたのはLIGHT OF DESTRUCTION(破壊の光)。
白さと熱さと爆音が、世界を包み込んだ。
ドラグーンはぶち撒け、ダルクは飛び、ルミナスは死んでいく。
くすくす、くすくす。ようこそ、ようこそ。
ようこそ《アンデットワールド》へ。あたしたちは、死人を受け入れる。
戻るのもご自由に。いくらでも、戻れる手段はあるじゃない。
「!?」
ルミナスが自身の効果を発動した瞬間、彼女は《虚無空間》にいた。全方位全てが暗く、東西南北どころか上下すらわからない空間。体の奥から生じる倦怠感は自分が今立っているのか寝ているのかすら判断を迷わせる。
「だ、誰ですか!?」
ルミナスは自身の体躯に何も損傷がないことを確認すると、聞こえてくる不気味な声に反応する。
前からか、後ろからか。どこから聞こえてるかのかすらわからない声。たった一つわかるのは、それが女性の声であるということだけ。
あたしが誰だって? そうねえ、名前はないけど、生きてた世界より《アンデットワールド》こっちの方に適応している不埒なモンスターかな。
でも、貴方だって墓地を墓地とも思ってない罰当たりなやつでしょ? ね、ライトロードの、ルミナスちゃん。
ルミナスはその声にぞくりと体を震わせる。
(あ、あたしは悪くない)
「す、すぐに私は戻ります。あっちの、世界に」
すぐに戻る? そんな買い物に行ったみたいに言いやがって。
それが「墓地を墓地とも思ってない」って言ってんの。
(く、う……)
胸が焼ける。頭がただれる。元々反魂的な措置だ。自分が今「死んでいる」という認識が脳に届いてしまえば、あとは死へ一直線だ。だから、長くは持たない。
ああ、ごめんごめん。引き止めるつもりはないから。勝手にお帰りなさいな。
……どうして貴方がこっちにきたのか、私はフィールドを観測できないからよくわからないけど、
「え? いま、なんて……?」
既にルミナスの意識は電波の届かない通信機器のように途切れ途切れにその「声」を捉えていた。 薄れゆく意識の中、最後に聞こえた声は。
あた……は、もう《ゾン … ター》になっち…… ど、ダルクに よ ね。
みんな、こっちに居る ら。きっと全てが終 …き、選択することが、きっと ……
「ん、うう……」
ルミナスが次に視界を開いた時、目の前に映ったのはどんよりとした、曇天。
倦怠感に抵抗するようにルミナスは顔を横に傾けると、そこには片膝を立て彼女の方を揺するダルクがいた。
「ここは……」
「あんたがさっき、効果を使った場所だ。……しかし驚いたな。外傷は全くないが、痛々しさが全身から満ち溢れてる。途切れてた意識の間、一体どんなことをしてきたんだ」
「そ、それが……ッ」
びり、と体の内から溢れる生命の危険信号。ルミナスはそれに抗えず、立ち上がろうとする気力が一気に体から抜けていくのを感じた。
「無理すんな。戦闘は終わってるから、ゆっくり休め。AOJはサーバと目されるモンスターを失ったことにより、機能を停止している。気を張らずに、休んでから……戻ろう」
ダルクのその言葉はルミナスにかけることは元より、自身に言い聞かせ落ち着かせるためのような声色だった。大きく息を吐き、呆れるような一言。
「……」
ダルクは、意識の戻ったルミナスから手を離すと、立ち上がり、動かなくなった《A・O・J ディサイシブ・アームズ》の元へ。倒れてもなお猛々しさが残るそれの外壁をこん、と叩くと、彫られているシリアルに改めて目を向ける。
(結局、原因ってのはなんだったんだろうか)
ここまできてもなお、わかっているのはAOJがライトロードを駆逐する姿勢を取っているという当初からわかっている情報のみ。戦線上の進展はしていれども、情報の進展は全くない。
(闇属性……破壊の能力……。魔法使いの中で創造主を考えるならビンド一択だが、他の種族にそういった能力に長ける奴がいる可能性も高い。この世界、そういった知能を持つのは俺達魔法使い族以外には戦士族と天使族、悪魔族とサイキック族くらい。そのうえ人間の話す言語を備えているとなれば相当限られるだろうな……)
「ダルクさん。何やら思索に耽っている感じですが、聞きたいことが」
「なんだ」
ルミナスが横になった姿勢のまま、目を閉じて思い返すように呟く。
「ちょうど『こっち』に戻る間もなく、混線していく意識の中で、『あっち』の世界の『誰か』に声をかけられました。そしてその声の主は、ダルクさんのことを見知った風でした」
「……。姿は、見れたか」
「いえ、あの世界の中は、自分が眼を閉じているか開いているかすら理解ができない漆黒の世界でした」
ルミナスの回答にダルクは思い馳せる。その候補はいくらでもいる。取っ掛かりもないのに思い返すのは、辛いだけ。
「その声は、『ダルクが全てを』『終わる』……『選択する』……とか、言ってました」
「意味深というか、知った風だな。……、その候補に当てはまりそうな死人には、数人心当たりがある」
「《魔法都市エンディミオン》に及ぶ闘争で、失われた命でしょうか。ご冥福をお祈りします」
「……」
ダルクはその誤った解釈をあえて訂正しなかった。外遊のうち帰還した数刻で失われた首領の命はいまだ世界が認識していない情報。わざわざ世界を引っ掻き回す必要もない。
「まあ……十中八九その声の主はエリアだろうな」
「え? でも、私姿は……」
「……俺のことを呼び捨てする女はエリアとヒータしかいねえんだよ。だが、ヒータはそんな遠回しな言い方をするタイプじゃねえ。自然と候補はエリアに絞られる」
「え、ていうことは……エリア首領もお亡くなりに……」
ああしまった。黙っておくって、ほんの数秒前に決めたばかりじゃねえか。
「というか、その言い振りだとヒータ首領も……!?」
え?え?と、ルミナスが再起動しつつ頭を整理するように呟きつつ、ダルクの口から漏れた綻びから真実を開いていく。
「当初ダルクさんは、アウス首領の死の事実を解明しに《ジャスティス・ワールド》に来た、と聞いています。でも、今話を聞いた限りではエリア首領とヒータ首領の死も確認され、そのうえ……そのうえ!!」
「ライナ女史も死に絶えている」
その『現場』を直視したドラグーンが躊躇わず、一言。
「まさか、ウィン首領も亡くなっているなんてことは言いませんよね!? ねえ、答えてくださいよ!!」
「……」
ルミナスがよたよたとダルクの元に歩を進め、すがりつくようにその半身を揺らす。
「いったい、魔法使いは何を背負っているんですか!?」
背中から煤ける闇を振り払うかのような願望の込められた声。
「なんも、背負ってなんざいねえよ。背負ってねえから、このザマなんだ」
「……」
「竜の御仁。……これで、俺は、贖罪できた、のかな」
ダルクの語尾はいつになく柔らかく、だからこそ茶化せるようなものではなかった。その言葉に対して、触れようを間違えれば崩れてしまいそうな、そんな脆さ。
それでもダルクは『真実』を二人の前で吐かない。いっそぶちまけてしまえば楽にもなれただろう。だが、ぶちまけて楽になるということは『それ』を押し付けるということ。彼にはそれが、できなかった。
「…って」
ダルクのその様子を見て、ルミナスが伏し目がちに呟く。
「戻って!!」
「……え」
「戻ってって言ってるんです! 一刻も早く! 貴方は! 今! こんなとこでしょげてる場合じゃないんでしょう!?」
ルミナスが、涙で顔をくしゃくしゃに腫らしつつ。
「『あれ』はエリア首領なんですね!? その前提で話します! 彼女は悲愴的でした! 悲観的でした! 絶望的でした! どこをどうすればあんな風になれるのかってくらいに! でもそれ以上に……」
待ってるんですよ! あなたを! ダルクさんを!!
それはまごうことのない慟哭。
「貴方達がどんな闇を抱えているのかあたし達みたいな端役に同情されたくはないでしょう!? だから、あるべき場所に戻って!」
ダルクはルミナスのその言葉に一瞬だけ後悔したような表情を見せ、
「……俺は、エンディミオンに戻りたい。そうしないと、終われない」
「はい。思うがままにしてください。元々通りがかりに助けてもらった命。ダルクさんには十分、助けてもらいました」
ダルクはその言葉を聞き、静かに《強制転移》の詠唱に入る。ドラグーンの姿を一瞥するが、何も語らない。それは、語るべきことはルミナスが全部言った、そんな風にも見え取れた。
「じゃあな。さよならだ」
「その慌ただしさ。嫌いじゃないです」
ルミナスの頬は赤みがかっていた。それは、泣きはらした後遺症か。それとも。
エンディミオン。戻ってきたのは、見慣れた会議室。
血濡れの会議室はまるで何事もなかったかのように片付けられ、一時前の惨状を全く感じさせない。
「……ううん」
長机にピケルは伏せ、寝ており、それこそその様子には戦鬼としての様子は微塵も感じられない。
ダルクはピケルの肩をゆさゆさと揺すると、間もなく彼女は起き上がる。
「あら、本当に殺しても死ぬタマじゃなかったですね。……おかえりなさい」
寝ぼけなまこをこすりつつも、悪態は変わらない。
「……さっきの、その、もう体は大丈夫か」
「ちょっと貧血気味ですけどね。ま、私は生きる救急箱ですから」
肩をくるくると回し、笑いかけるピケルの様子にダルクはひとまず安心する。
「ただ、エンディミオンは予断を許しません」
「どういうことだ」
「元々4人の失われた黄金時代(THE LOST MILLENNIUM)が生まれることにより、世界は戦禍に巻き込まれると思われていた。だが、平和主義に徹底した彼女達は起爆剤とはならなかった。だからこそ世界は好戦的な属性であるダルクさん(THE DUELIST GENESIS)とライナ様(SHINING DARKNESS)を世に生んだ。ここまではお分かりですね?」
「な、なにを突然」
「しかし、今度は……光と闇の霊使いの出現は六属性の調和をもたらしてしまった。やはり世界は平和主義の姿勢を譲らなかった」
ピケルが語りつつ、肘を立てた人差し指をくるくると回す。円環、を意味するように。
「そしてこの度、アウスさんが葬られることにより均衡が取れなくなった。立て続けの首領の死により、均衡は木っ端微塵になった」
「まさか……」
「ええ。首領の死は《魔法都市エンディミオン》に住む全てのモンスターと自然環境のバランスに影響を及ぼします。マジックミラーで効果を封じられるだけで属性の統率が乱れるんです。その存在が消失した時の影響は推して知るべしですね」
「今、生きている首領は俺だけ。逆に俺だけが残ったからこそ、混乱しているってことか……」
「そ、そういう意味で言ったわけではないですよ!? 大体ダルクさん、あたしに『おれがになうー』とかかっくいー台詞吐いて出ていったじゃないですか! それにさっきも『ヒロイックがなんとかかんとかー』ってのたまいつつ戦ってきたんですよね!?」
ピケルががた、と椅子から立ち上がり強く叫ぶ。その瞳からは、死ぬなという意思が全力で伝わる。
「なんでそれ知ってんだよ、ですか? 読心術読心術。……人に言うなら自分から。確かに『それ』は均衡を取り戻すのに明快な手段かもしれません。しかしそれを選ぶなら、むしろ死した霊使い5人の影響力を取り戻す方に腐心すべきです」
それもまた正論。ダルクが戦禍の中心にあるからといって、それを潰して戦場を均そうという発想は、自分からも他人からも決して進めてはならない自滅思考。
「霊使いが死したからといって、世界は霊使いが生まれる前に戻るわけではない。一度彼女達によって引き上げられた世界の水準は、押し下げられることで致命的な軋みを生じさせます」
ピケルの言うことは、例えを変えれば『ラチェット効果』。経済において、所得が低下しても生活水準は低下しないことを説明しているそれに同じ。霊使いの消失により影響力が失われても下々はその影響力を前提とした生活を行うし、影響力を失ったことを理解してもそうそう水準を戻せない。しかし、それは環境に軋みを生じさせ、いずれ破綻への引き金となる。
「だからこそ、生き残った貴方はヒーローでありヒロインでありラスボスであるんです」
ヒーロー。ライトロードを救った救世主であり。
ヒロイン。霊使いの中で唯一残った、守るべき存在。
ラスボス。しかし、その「守るべき存在」を潰せば、世界は均される。
「どう行動を取るのが正しいのかわからない。だからこそダルクさんの一挙一動に、世界は敏感になっています。だから……」
ピケルは改めてすとんと座り、扉の方に流し目を送る。そこには。
「ほうら。そこに意味ありげに少女が倒れていますよ。いっちょ、『担って』いきましょう? 少なくとも、行き倒れを見捨てる『ヒーロー』はいないでしょう?」
「考え無しに人助けをする『ラスボス』もどうかと思うがな」
「あはは、それでこそダルクさんです」
二人の視線の先には碧の長髪を振り乱したように倒れる女性の姿があった。周りには辿ってきた道のりを示すかのように血痕が残り、倒れざまの勢いを物語るかのように所持品であろう杖の先端がひしゃげていた。
ダルクは、倒れている少女の首元に手をやり脈を確認。いっぱしですね、なんていうピケルの茶化しを無視しつつ一つ息を吐く。
「生きてるな。ピケル、治癒を頼めるか」
「それはいいですけど、この方がどこかからの斥候で、意識を取り戻した瞬間襲ってくるなんてことは考えないんですか?」
「考えねーよ。第一、敵の本陣で倒れてるなんて斥候聞いたことねえ」
それもそうですね、とピケルが舌を出して答える。その人背負って椅子まで運んでください、というピケルからの指示にダルクは無言で従う。
おぶった彼女を会議室の椅子に掛けさせ、碧の髪の合間から見える額にピケルは手を当てる。じとりと、汗が伝っていた額をやさしく拭い、詠唱。
「……」
その様子をダルクは黙って眺めていたが、突如口を開く。
「ピケル、随分余裕そうだが、おまえその女の事、」
「ええ、見知ってますよ。ダルクさんが属性間折衝してない間、私は何をしてたと思いですか。ライナ様の代わりに外交してたんですから」
目線は変えず、誇らしげにピケルが呟く。
「彼女はカーム。ウィンダさんの手元にあった魔法使いではない勢力、サイキックのガスタ(突風)の一員です」
いきなり増えた情報。だが、ガスタという存在は既に世界に根付いている。
ウィンが戦時の村落から滅びかけの一族を拾ってきたと言われたときは霊使い一同が思わず失笑したものだが、ウィンの懸命さに押されガスタはエンディミオンにその立ち位置を得ることとなる。
ガスタは魔法とは違う「サイキック」という能力を使い、ウィンの、そして魔法使いの文明を補助していた。しかし、保守的な思考を持つ老練たる魔法使いはその「わけのわからない」力に不信があったのも事実。決して表沙汰にはしないながらも、そこには誰もが気づいていた冷戦があった。
因循たる老魔術師が気に食わなかったのが、彼らガスタの一員が人間としての体(てい)を成していなかったこと。ガスタのうち一部は《メンタルマスター》や《マジカル・アンドロイド》のようにもはや機械ともいえる形相。しかしその一方、一般的にコミュニケーションを取ることができる「人間」もいる。そのうえウィンやサイキック族の人間は「機械のような」者達とコミュニケーションを取れていた。
それが、傍目から見て気持ち悪かった。誰しも、自分が理解出来ない範疇で理解出来ないやり取りが行われることは生理的に受け付けないからだ。そのはけ口は、「人間の」サイキック族である者達に向けられていた。
「巫女」ウィンダ。彼女は、ウィンの名の下、風属性魔法使い族を統括しながら、その口寄せの能力を利用し、魔法使い族としては踏み込むことがグレーである領域を扱っていた。
「賢者」ウィンダール。ウィンダが魔法使いの業務の下ガスタから離れる時にに統括を行う、実質的首領。
「静寂」カーム。一説では詠唱なしにスペルを詠唱できるとも言われる、寡黙な戦闘要員。
「希望」カムイ。御姿は子供ながらも、神の生き写しとも讃えられる崇拝を受けている男児。その理由はウィン以外の霊使いには知らされていない。
のような、上層部員は顕著にその罵声を受け止めていたといえる。しかし、彼らはその冷遇に対し反抗の態度を見せなかった。ただただ、ウィンに、ウィンダに恩赦の忠誠を見せていたのみ。だからこそ、やはり「気持ち悪かった」。魔法使いは彼らにアンドロイドの人間じゃないような、居心地の悪さを思っていた。
「どうだ、そいつは意識を取り戻しそうか」
「ええ、大丈夫そうですよ。外傷は派手ですが、意識が飛んでいる原因は失血より精神的、内面的なものですね。なんらかの事情で、体がぷちっとブレーカーを切ったと見るべきでしょう」
ピケルが細い人差し指を折り曲げて、ジェスチャーでそれを表現する。ダルクはその様子を見てなるほどな、と一言。
(こいつの服は確かに土埃や血に塗れているが、血が滲んじゃあいない。自分の身体にダメージは少ないか。だが、それを考えると随分と物々しい状態だな……)
下手に触るとピケルが騒ぎ立てるだろうな、とどうでもいいような感想も持ちつつある程度の予測を立てる。
「ん……」
それから2分も立たないうちに、カームの口元から息と声が漏れる。
「お。思ったより早いお目覚めだな」
その時、確かに、油断していた。だが、その叱責としては厳しすぎやなかったか。
ダルクがカームに歩み寄る。カームはまだ自体を掴みきれてない脳をくるりと揺り起こし、その瞬間。
ひゅん、と、風が切れた音がした。
「……!」
(鎌……!?)
瞬間、ダルクはカームの手元から自分の首元に襲いかかる『鎌』を確かに見た。
首元への手刀。その速度は、ダルクが攻撃を認識できないほどのものだった。それこそ、その風の切れ筋を視界と脳が『鎌』そのものと認識するほどに。
(鎌鼬……じゃねえ、鎌、そのものっ……!!)
その手刀はダルクの首元すんでで止まる。というより、カームが直前でブレーキをかけて止めた。
その対局でカームの治療をしていたピケルも唖然としていたが、目の前の事象を咀嚼できないのか回復活動を止めていなかった。
「……。……。間違えました、ごめんなさい」
第一声は、それだった。
理解できないカームの行動はダルクとピケルの脳を硬直させる。
「ごめんなさい って言ってるのに、許すか許さないかくらい答えてくれてもいいじゃないですか……」
目に見えてしゅんとした態度を見せる様子を見てピケルが口を開く。
「え、ええと。正直事態を飲みこんでいないのですが、私は貴方の性格と立ち位置を知っているからここで貴方をどうこうするとか言いません。しかし……」
ちらりと見るのはダルクの方向。ほんの数秒前に命のチキンレースをその身で体験した者へ『根は良い人なんですよ』なんて戯言が通じるとは思えない。ピケルは不安でもやもやとした感情を持って、ダルクに視線を向ける。
「……」
案の定ダルクは硬直していた。しかしその一方、特異な状況にある今、神経が過敏になっている『モンスター』に対してへの猜疑心は不思議と出なかった。だってそれは、とうの数時間前ダルクがライトロードに向けた『それ』と同じものであるから。だから。
「カームっつったな!」
ダルクはカームの横の椅子に豪快に腰掛け、そして。
「目的を、事情を聞かせろ! 殴るか殺すか味方になるかはそっからだ!」
◆
「すいません 攻撃を止める瞬間まで戦場にいた意識が強すぎて、反射的に体が……」
カームがしゅんとした表情でダルクとピケルに頭を下げる。
カームの羽織るローブは土埃と血痕にまみれている。それは、ここに来るまでの道のりによって生じたものだと容易に推測できる。そして、その原因がここ数刻で引き起こされた殺戮によるものであることも心の内気付いていた。
「戦場に……? エンディミオン内の、あんたらのいる地域も暴動に?」
「いいえ そうではありません。私の指す『戦場』は旧領域。霞の谷(ミストバレー)のことです」
「ミストバレー……?」
「妙ですね」
その返答に口を挟んだのはピケル。声色も、視線もじっくりと前を見据え、凍りつくような色。
「ミストバレーの法律的領土はウィンさんによる補助が合って以降、エンディミオンに統括されています。そこはエンディミオンのように外殻が無いため、私達にとってもアキレス腱。外部干渉を受けないようにデリケートな戦力配備をしています。したがって、そこに攻撃があれば光属性首領代行である私やダルクさんに報告が来るはず。しかし、そんな兆候は感じられない」
こつ、こつと歩みつつピケルは論じる。
「そんな兆候は無い。しかし、貴方の衣服一つとってみても、貴方の言っていることは嘘とは思えない。となると……解答は……」
「ええ 内乱です」
「内乱……」
思っていた解答ではあった。だが、ダルクはそこに腑に落ちない点を感じていた。
「内乱と言っても派閥とか、領土争いといった理由によるものではありません。そちらの意味が『内乱』という単語では強いと思いますが、もっと根源的な意味です」
「国内の混乱、って意味ですか」
「理解がお早くて助かります」
カームがピケルに対して軽く会釈。口元には微かな笑みを浮かべている。
「その原因ですが、この数時間の間に霞の谷を襲い始めた原因不明の《猛毒の風》によるものです」
「《猛毒の風》……」
「いえ、原因不明というのは語弊があります。原因はわかっています。……ウィンダ様が生を全うしたことによるものです」
その言葉に、二人はぴくりと眉間を震わせる。そして、たゆたうカームの視線を強く見つめて押し黙った。
(ああ、そうか)
それは。
(わかったうえで、言ってるんだな)
「ウィンダ様がお亡くなりになられてから急のことです。地平が揺れ、火山性のガスが私達の居住地域を脅かしました。まるで、見えない圧力から解放されたように」
「はっきり言えば」
ピケルが覚悟を決めたように、カームの対面の椅子に腰かける。羊を装った帽子を取り、それを自分の脇へ。
「いずれ、地学的な影響が出ることは私も理解していました。ただ……これほどまでに早いとは予想外でしたね」
「地学的?」
「ええ。先にも言いましたよね、霊使いの世界に与える影響は何の比喩も無くただただ大きい。霊使いの死は、地学や化学、生物学的な観点においてもバランスを崩します。そのため厳密に言えば一次被害はアウスさんの死により《山》のホットスポットが限界を迎えたこと、波状するようにそこより噴出した火山性ガスの大気構成がウィンさんによりコントロールされずミストバレーを覆ったことが二次被害となります」
厳密に言えば、そこにはヒータとエリアの死も絡んでいるだろう。火山活動、ヒータは言わずもがな影響があり、エリアも火山活動のフロントラインである海溝をコントロールできる立場にあった。言うなれば、自然の摂理が元素レベルからかき乱されている状況。予断を許さないことは決して比喩ではなかった。
「なるほどな。……で、カーム」
「やーですね ダルクさん。そんなにさっきの出会い頭の未遂をお怒りですか?」
カームは首をかしげてダルクの方を座ったまま向く。怒りか何かを感じ取ったかのような、リアクション。
「ウィンの命を失ったことの理由に俺がいるのがそんなに不服か。殺意が煤けて感じられるぞ」
「なんの ことでしょう?」
カームの口端は上がり、包みこむような笑いが感じられる。
「なんで、出会い頭に頭ァはねなかった。あの『鎌』は受けられる気しなかったぞ」
「……キイテタヨリ、タニンノ機微二 ビンカンナンデスネ」
その声に抑揚はあった。だが、脇で聞くピケルはその声に硬質で尖鋭な、超音波を声色に乗せたような悪寒を汲み取っていた。
「答えろ、カーム」
ダルクは杖を構えず、詠唱の準備もせず、無防備に佇む。
「せめて 話だけでも聞かないと まるで私が殺人狂みたいじゃないですか。私は、合理的な理由がないと そういったことはしませんよ。だから」
ウィンダ様を返しなさい この世界の癌。××××野郎。
笑顔でカームは立ち上がり、杖を構え、額に掛る輝いた髪をはらう。血は既に乾いており、先につきつけられた悲壮感は見られない。
ダルクはそれを見て一つ呟いた。
「ピケル、話し聞かなくてわる、かった」
「言わんこっちゃ、ないですよ」
ダルクのカームの間に距離はない。ダルクは杖を構えカームの射程距離からじり、と離れるがピケルが浮かない表情をしていた。
「どうしたピケル。さっきの発言、まだ気にしてるのか」
「……さっきの発言。くしくも予想を当ててしまったことについてですか? ええ。……はっきり言って、当たると思っていませんでしたから」
そこまでの言葉でダルクは多くを察した。ピケルはライナの代わりの外交担当として、カームのことを敵対関係のない対話をしたことがあった。全く見知らぬ他人ならともかく、既に数度対話して性格も態度も見知ってる相手の突然の豹変。それが演技だったんだろうという発想はダルクもピケルも百も承知。
だからこそ、腑に落ちない。あのピケルが、「取り入ろう」とするような演技を見透かせなかったのかということを。
「一つ想定があります。ダルクさん」
「なんだ あいつに聞こえて、いいことなのか」
そんなダルクの言葉にピケルが、小細工整えてる時間なんて有りませんよ、そう返した瞬間だった。
びゅおお、と耳をつんざく轟音がダルクの正面と背後をかすめていった。ダルクの体躯にダメージはない。だがそれは《サイクロン》。背後にある罠を掠め剥ぎ取ろうとする意志がキンキンに感じられる一撃。カームはノーモーションでそれを繰り出し、なおもダルクを睨みつけたまま。
「ダルクさん! 今のカームさんの豹変は裏切りとかそういうのとは思えません! 二重人格とかコントロール奪取とか、そういった類のものだと推測します! そうだとしたら、対処すべきはカームさん本人でなくて……!」
「その背後にあるトリガーなり黒幕ってことだな!」
もはや一刻の猶予もない。そう判断したピケルは大声で、包み隠さない予測を口に出す。
「ええ!」
語るが同じ、ピケルが《光の護封剣》を詠唱。ダルクがその発動を包みとったと同時に《闇の護封剣》を詠唱。カームの四方を6本の剣が覆い尽くす。
ダルクは踵を返し、部屋の外へ向かい駆ける。カームはその様子を見て、手なりで護封剣を杖で叩く。手首に響く鈍い感触に舌を鳴らし、
「《ハリケーン》!!」
風を操るサイキッカーが得手とする、大型の魔法除去詠唱。それすらも、ノーモーションで起動する。だが、
「《対抗魔術》!!」
ピケルもその魔法を一瞬で打ち消す。ここは《魔法都市エンディミオン》。打ち消すのに使うエネルギーはいくらでも捻出できる。そう言いたげに、口端は上がっていた。
「ダルクさん! ご武運を!」
ピケルの言葉に、疾駆するダルクは振り向かず声も返さず、スピードを落とさずかけていく。
ダルクは会議室を飛び出し、廊下をぐるりと見渡すと、向かって右手に踵を返す。
(ピケルの考えに反論はないが、それでも確証はねえ! そもそも、何がトリガーなのかすらわかん……)
ダルクが駆けつつ、思いを馳せる。踵を返した数秒後、思考が止まるような光景を目にする。
廊下に普段見慣れない二つの影。しかしそれは、侵入者という雰囲気でもなかった。
二つの影は子供と青年。一方は先に見たカームのように碧の髪をした子供。衣装もマントや短めのパンツを着用しており、カームの同類であることが容易に察することができる出で立ち。対峙する青年に対しどこか焦ったようにまくし立てたように見えた。相向かう黒髪の青年は藍色の上着、両手に金色のブレスレットをつけており、装飾過多の感じも見受けられていた風貌。
ダルクは、青年の正体を推測出来なかった。だが、少年があまりにもカームに似ていた。今抱えている問題と無関係とは思えなかった。
(予感がハマればいいんだが……!)
「おい! そこの二人! ちょっと話を聞かせてくれないか!」
ダルクは走る速度を落としつつ、慇懃でもなく、威圧的にでもない態度で接したつもりであった。
「え、はい……あ、貴方は確か、ダルクさんでしたよね!」
若干の焦りがありつつも明るい声で返した少年と、
「あんたが……ダルクか。言いたいことはあるんだが、まずは別件を解決させてくれ……」
消沈したかのように、頭を掻きつつイライラとした表情で答える青年。
二人の態度は対称的だったが、感じたのは、そこに一致する問題があることだった。
「えと、僕、名前はカムイと言います。ガスタのことはご存知でしょうか?」
年端もいかない少年ながら、ぶれない敬語でぺこりと頭を下げた少年の名はカムイ。ダルクも、直接の接触はないが、その存在は心得ていた『ガスタの希望』。
「ああ、知っている。カムイ……か。よくわかんねえうちに神の生き写しに仕立て上げられて大変だな」
「そこまでご存知でしたか。光栄です……っと、ごめんなさい。正式なご挨拶は後とさせてください。差し当たって火急を要する問題がありまして」
「……ひょっととして、カームのことか」
確証はない。鎌をかけただけだった。だが、カムイの表情の変化はそれを雄弁に物語っていた。
「ビンゴ、だな」
「どうして……?」
「俺が走ってきた理由がそれだからだ。カーム。おそらくカムイ、お前と一緒にエンディミオンに来たんだな」
「ええそうです。ただ、途中ではぐれて……いえ、厳密に言えば気を失って、再び気づいた時にはお姉……すいません、カームは姿をくらましていまして……」
「おねえ、ちゃん。姉さんか」
「すいません。ちょっと動転してまして……」
カムイは顔を赤らめ、対外的な所で呼称を間違えた自分を戒める。
「親族なら、普段のカームの様子も知ってる……よな」
「質問の意図を、はかりかねます」
ダルクの質問に対し、カムイは強い口調で返す。
「カムイ、正直に答えてくれ。カームが俺達の対話中、額面通り『人が変わったように』なった。これについて、全く何も知らないってことはないな」
その質問に対して答えたのはカムイではなく、その対面にいた青年。
「それだ。ダルク、やっぱりその事情を知ってるな」
「あんたは……?」
「俺はヴァニティ。エリアル様から儀式関係の研究を担わせてもらっていた。……俺も挨拶はあとでさせてもらうが、」
黒く長い髪はともすれば中性的なものを感じさせるが、声から伝わる力強さは紛れもなく男性のものであった。
「それでだ。『事情』。こいつ--カムイと俺がエンディミオンで出会って、あんたに用があるから一緒に行こうとしてたんだが……その途中、いきなりこいつも『人が変わった』」
「……」
その話をカムイはしゅんとした様子で聞いていた。そして、二人の言葉からダルクが紡いだ一つの発想。
「気を失った、ね。厳密に言えば『なにか』に体を乗っ取られた。んだろ」
「察しがいいな」
ヴァニティと自分を称した青年が目を細めて感心したような表情を作るのを、ダルクは鼻頭を揉みながら言葉を返す。
「単純なことじゃねえか。ヴァニティ、あんたは『いきなり』『人が変わった』と言った。本当に気を失ってるのならそこは『いきなり倒れた』とかそういった事を言うだろう。だから、カムイの言う『気を失った』は、あんたの言う『人が変わった』と同義だ。深く考えるまでもねえよ」
「もっとも子供の腕力だ。殺気を見せた途端制圧したら、元に戻ったわけだがな」
「まいり、ましたね」
返す返すの言葉に、カムイはバツの悪そうな表情を作る。ダルクはさらに、続ける。
「先に聞くが、カムイ。ガスタは全員二重人格を持つだなんてことを言わねえよな」
「……はい。そんなことは、ありません」
偽りのない道理だ。ガスタを統括するウィンは、ダルクにそんなことを一言も漏らしてなかったし、深く付き合いがあったウィンがいきなり暴虐的な態度に豹変したことなんてなかったからだ。
「じゃあ、カームやカムイ。なんであんたらは『そんなこと』になってるんだ」
その言葉にカムイは数秒黙りこくると、覚悟したように口を開いた。
「それを解決するために、エンディミオンに伺いました。『ガスタの希望』として。」
一方、会議室。ピケルとカームの、バトルフェイズ。
「はぁっ……はぁっ」
風の魔法除去魔法を立て続けに唱えるカームに対し、ピケルは精神的に疲労していた。《サイクロン》《トルネード》《ハリケーン》《ツイスター》と矢継ぎ早に唱えられる風属性の魔法に対し、ピケルはキャンセライズを差し込むだけ。なにせこの戦闘の至上命題はダルクが原因を見つけるまでの時間稼ぎ。『殺さず』『傷つけず』『制圧する』こと。
普段が命の削り合いをしている戦闘をこなしていただけに、言わば使っている筋肉が違う戦いだった。
(真面目に、そう長くは持たないですよ……! 魔法なら《対抗魔術》で根性比べに持ち込めますけど……!)
ピケルは『仮定』を頭に思い描いていた。その『仮定』とは。
(ほうら来た……!)
相手が、魔法を捨て、違う手段に切り替えてくること。
「XXXXX!!」
カームが、単語にならない叫びを上げて、ピケルへ一気に距離を詰める。
選択したのは、愚直なる攻撃。ひねりもない、小細工もない、力任せのダメージステップ。
(そう来ますか……! あたしは基本後衛だから、こういうピュアな攻め口は逆にやりづらいんですよ……!!)
カームの振り落とした杖がピケルの左脇腹を一閃と捉え、伝わったダメージは重力任せにピケルを右手にぶっ飛ばす。
「か、っはっ……!」
ピケルは腹からひり出された呻きに意識を飛ばされそうになるが、反射で受身を取り、すぐさま立ち上がる。
(まだですかダルクさん……! あたし、この人を殺したくは無いですよ……!)
心が折れそうな瞬間だった。朦朧とする視界に、映ったのは。
「待たせたなピケル!!」
「お姉ちゃん!」
「……」
会議室に駆けつけた三人の姿。ピケルはその姿をほっとした表情で見つめるが、カームは一切視線を揺るがさなかった。
その様子を見て、カムイが悲しそうに、
ひゅん。
駆ける。
(早……!?)
ダルクはその一瞬の行動を頭で理解するのに遅れを生じさせた。
カムイがその小さな体躯をカームの脇元にねじ込み、くるりと腕を回転させる。
瞬間行われたのは、合気投げ。触れられてもないカームの体が見えない風車に押し込まれたように空中で一回転し、地面へ緩衝なく叩きつけられる。
「凶暴化を止めたければ気絶させることで、これで次に起き上がったときは本来の意識を取り戻します。僕達の抱えている問題、『ヴェルズ化』。対処療法は力ずくで簡単ですが、その根本的な解決方法を探りにエンディミオンに伺ったわけです」
カムイは地面に叩きつけた姉の顔元にしゃがみ、首に手を当てて脈拍を確認しつつ、ダルクに強い視線を向ける。
矢継ぎ早にヴァニティが、
「そして幸か不幸か、俺も根っこが同じ問題でここに来た」
穏やかとは言えない笑顔でダルクの方を向いて話す。その手には、コルク栓で抑えられ、中には無色透明な水が入っている小さな瓶が持たれていた。ダルクから見える角度で、そのビンには “Virus(ヴェルズ)” と書かれたシールが貼られていた。
ヴァニティはさらに、淀みなく呟いた。
「ダルク。あんたは俺だけでなく、こいつらの拠り所も奪い取ったんだ。罪滅ぼしとして解決してもらうぜ」
ヴァニティのその言葉にダルクは怒りもせず、反論もしなかった。
責任を重く感じていることは隣のピケルもわかっており、だからこそ容易に口を挟めなかった。ダルクは軽く頭をかき、返す言葉に困ったように考え倦ねて、やがて、
「……ほら、そいつ。カーム背負って医務室行くぞ。いつまでも地べたに寝かせてられねえだろ」
困ったように話題を逸らして、答えなかった。それは回答から逃げたのか、あるいは――
「ううん……」
カームは30分もしないうちに気を取り戻し、隣にはダルクとピケル、カムイとヴァニティも椅子に腰掛けて陣取っていた。
「気、取り戻したな」
「お姉ちゃん、ごめんなさい」
「ここは……?」
カームは一面真っ白な部屋の内装を目をこすりながら舐めるように見て、呟く。
カムイは一言、ダルクさんに背負われて医務室に運ばれたんだよ、と返す。そして、それ以上は語らない。
そっか、とカームが一言。そして、背中から感じる痛みに一瞬顔を歪め、反射的に寝た体制から横に転がる。しかし、彼女はなんで、とか、どうして、とか呟かなかった。ただただ後悔したような悲しげな表情になっただけ。
「そのリアクション。どうやら、『慣れてる』ようだな」
「またあたし、やっちゃったんですよね。もうこの背中の痛みも慣れっこです。カムイにもほんと、迷惑かけっぱなしで……」
カームはそのまま体制をうつぶせに。数秒もしないうちに体が震え、明らかに泣くじゃくるすすり声が部屋に響いていた。ダルクはその肩に手を乗せようとしたが、ピケルが近づきそれを静止する。
「カームさん。ご傷心のところ済みませんが、二三聞かせてください」
「……はい」
ピケルの顔は明らかに厳しかった。ダルクはそれに若干の不信を仰ぎつつも特に言葉を返さない。
「カームさん。本当に貴方の『アレ』、二重人格ですか?」
おい、ちょっと待てよ。それが、大前提じゃねえのかよ。
「どうにも私、不審に思ってるんです。あれを二重人格と言い切るにはいささか変貌がナチュラルに過ぎる。洗脳ってのはもっとこう……気の利いた言い方はできないですが、もっと自然なものなんじゃあないですか?」
それが、何を指してるか。ピケルならわかっているはずだろう……!?
「貴方と私の仲だから単刀直入に言います。あれは二重人格に見せかけた演技だったのではないですか?」
「!?」
その言葉にカームとカムイの二人が揺らぐ。
「どうにも先ほどの件が納得行ってないのですよ。二重人格というには対峙した相手への行動が理性的過ぎる。ダルクさんへは殺す気満々な戦闘を、私に対してはガチンコの戦闘に見せかけて《サイクロン》とか《ハリケーン》とか、私にダメージが行かないような脅しだけ。上手く繕いましたが、私に対しては制圧する気が無かったのが見え見えでした。……納得する答えが聞けるまで聞きますよ? あれは、演技なのですか?」
「い、いいえ。そんなことはありません」
「どうにも、弁明がしづらいですね」
単に首をふるふると振って否定したカームとは対称的に、カムイの口調は曇っていた。
「悪意のなさを証明するのにかなり分が悪いですね……それならいっそのこと、本当のことを話すべきかもしれません」
「カムイ!?」
「大丈夫。僕に任せて」
カムイはカームの肩をぽんと叩き、強い視線をピケルに向ける。そして決意の塊を話し始めた。
「二重人格ではありません。ただし、自分の意識が乗っ取られるのは事実です」
「……?」
何も情報が増えていないカムイの言葉に疑問じみた表情を作るダルクに対し、ピケルは眉間を抑え何かを思う表情。ヴァニティは変わらず目を瞑ったまま壁にもたれかかり、一切口を挟まない。
「あの、私、すごい残酷なこと言いますよ?」
そして数秒後、何かを思いついたようなピケルが姿勢をただし、カームの方を向いて言う。
「はい」
カームはその言葉に、意図を察したかのように強く短い返事を返した。
「その『ヴェルズ化』ってのは、心の深層にある衝動とかを行動に移すような、野生化みたいなものなんじゃないですか?」
「……。驚きましたね、ビンゴです」
カムイが敬意を見せるような表情で目を見開き、ピケルの答えへ返答する。だが、だからこそダルクは。
「ちょ、ちょっと待てよ。ってことは……」
「ええ。私が言う『残酷なこと』ってのはカームさんへ向けてのことじゃありません。ダルクさんへです」
「カームは、俺に、殺意衝動があるってことか」
途切れ途切れのダルクの言葉に、カームはゆっくりと起き上がり数秒悩むように眉を曲げ、そして口を開いた。
「私が『あのとき』何を言ったかは覚えてないですが、貴方に恨みがないとははっきり言って、そんなことは言えません」
カームの瞳は燃えて、強い。透明さを見せる眼は、言質を伴うように本音を物語るようにも見えた。
「……カームさん、もっと本音言ってもいいんですよ?」
ピケルが数秒も経たず呟いた。ピケルの表情は一瞬苦虫を噛み潰したように歪められたが、ふっと視線を逸らしてぼそぼそと。
「ああ、そうでした……。ピケルさんは心が読めるん……でしたね……」
その意に気づいたカームが苦笑って前髪をくしゃりと握りつぶす。
「姉さん、いっそのこと口に出したほうがいい。姉さんが言わずとも、いずれピケルさんから伝わる『事実』。それなら正々堂々と話すほうがいい。裏側から恨まれるより、正面から恨まれたほうがいくらか清々しいんだから」
「そう、だね」
箍は、外れた。立て続けに、カームの口から棘が飛ぶ。
意志は明確な殺意。それはまさに、先ほどのカームの変貌を『真っ当な意識』で語ればそうなるであろうというような言葉の連続だった。
ダルクはそこでようやく『心の深層にある衝動とかを行動に移す』という意味を理解した。会議室で放たれた言葉と、医務室で産み落とされる言葉に差異はない。そこにある差異は、意思なき暴力が介在するか否かのみである。だからこそ、ダルクは、時折見せるカームの笑顔の表情に恐怖心を抱かずにはいられなかった。コルロフォビア。道化恐怖症。笑顔はときに自覚なき恐怖を伝える。
「はっ、はっ……」
すべてを吐き出した後、カームの息は切れていた。呼吸もままならないほど怒号の濁流を淡々と吐き出した結果。起き上がり背中を上下させるカームを、カムイが後ろからぎゅっと抱きしめていた。
その様子を見てピケルが呆れたように息を吐き、
「ええ。概ね、ダルクさんへのうらみつらみはそんなもんですよ」
カームの方を見つめつつ呟く。
「まったく、こんなあられもない怨恨の感情を肌で感じたのも久しぶりですよ。私の読心はスイッチをオンオフできるものではないんですから、こういう瘡蓋すらかかっていない、じゅくじゅくの傷口のような感情はさらけ出さないで欲しいんですけどね」
もっとも、それが八つ当たりであることは当然ピケルも承知していた。ダルクへのささやかなフォロー、ガスタへのささやかな抵抗の意味があったかもしれない。
カームから放たれた言葉はダルクの心で棘となり浸透していったが、その中の一つの言葉が事態を、加速する。
「殺す気はありませんよ! あたし達も野生生物じゃない! でも、のうのうと生きるな! 償え!」
ウィンダ様を墓地から連れ出せ! 連れだしてよおおおお!!
「あるぜ、その手段」
それは、待ってたとばかりの返答だった。返答の主はヴァニティ。ガスタとダルクの口喧嘩に一切口を挟まなかったヴァニティだった。
「俺も、究極的な望みはそこなんだ。エリア様……いや、この場合エリアル様か、の墓地からの奪還、それを望んでる。あんたらガスタは《猛毒の風》による事態の深刻化、怒りの衝動でここにやってきたんだろうが、俺は違う。建設的な解決手段を持って、それを叶えに来たんだ」
「急に口を挟んで、回りくどいな」
ダルクは額の汗を拭って答える。
「その答えが、これだよ」
ヴァニティは口端を上げ、手に持つ小さな瓶を掲げる。
「ガスタは、これらによる凶暴化を『ヴェルズ化』って呼んでいたようだが、俺達リチュアは体内感染……『イビル(InVirus)』って呼んでいる。イビル、リチュア、『墓地から連れ出す』。これらのセンテンスを、繋げられないか?」
「……」
ピケルがヴァニティの言葉にしまったというような表情を作る。
「しまった……ヴァニティさんのおっしゃる通りです……。答えは既に提示されてたんじゃないですか……!!」
「ど、どういうことだよピケル!?」
「まだわかりませんか。《イビリチュア・マインドオーガス》。ライナ様がダルクさんとの戦闘で、《ライトロード・エンジェル ケルビム》をリリースして召喚した儀式モンスターです」
もっとも私、背後からぶっ刺されて意識朦朧だったんですけどね、なんて捨て台詞も忘れない。
「《イビリチュア・マインドオーガス》……? それがなんで……?」
「戦闘を映像イメージで思い返してください。あのとき、マインドオーガスの体躯に乗っかる形で、エリアさんは、どうなっていましたか?」
ピケルは一言一言を噛み締めるように解答を待つ。ダルクは鮮明に戦闘を回顧し、一つ歯ぎしりする。
「なんであいつ……マインドオーガスの上で死んでたんだよ……!!」
「ええ。戦局を見させてもらってましたが、エリアさんはウィンさんとの戦闘の結果《念導力》に包まれ、文字通り肉塊になりました。外からは確認できなかったんですが、エリアさんを構成する『パーツ』は《念導力》の中にあるわけなんです」
それがどういう意味かわかりますか、ピケルは続ける。
「それがマインドオーガスの召喚時、エリアさんが視認できる遺体の状態でマインドオーガスの上部に配置された。例えばマインドオーガスという儀式体系がエリアさんとマインドオーガスのツーマンセルであることを指すとしても、その上に乗るエリアさんの遺体がぐちゃぐちゃのどろんどろんじゃないってのはおかしくないですか?」
「……確かに。確かにそうだ……! マインドオーガスは巨体だ、エリアの状態を全部確認できなかったのは痛いが、そもそもあれはエリアだった。ただの肉片とかじゃ、断じて無かった」
「仮に、ですよ。どんな死に様にも関わらず、そこから引きずりだしたときの状態は生前に統一されるとしたら? マインドオーガスのように、霊使いとモンスターによるツーマンセルの儀式モンスターで遺体を墓地から引きずり出すことができたとしたら?」
「ま、待て! 確かにエリアの遺体は引き摺り出された! だが生き返っちゃいない!」
「ええ。確かにそうです。生き返らない以上、そんな方法で遺体を引きずりだしてもただの冒涜です」
ダルクとピケルの対話をヴァニティは時折頷きながら聞き、カームとカムイは口を挟めずにいた。
「そうだ。墓地から戻れる手段はある。だが、死んだものを引きずりだすわけにはいかない。裏返せば、生きた状態で墓地に行くことは、戻れる以上ただの外遊と何ら変わらない」
「詭弁だ! 第一俺が戻れる保証はなんにもない!」
ヴァニティの言うことは『すぐ生き返らせてやるから、進んで死ね』。道義的にそれが簡単に飲み込めないことは場にいる全員がわかっていた。
「だったら……」
沈黙を破ったのは、これまで議論に大きく口を挟まなかったカムイだった。
「だったら僕が、生きて墓地に飛び込みます。ヴァニティさんの手段が安全であることを立証してきますよ」
カムイが頭の後ろで手を組み、笑顔で毅然と思いの丈を吐く。碧のつやめく髪を縛った髪飾りを所在なげにいじりつつ、弱いところを見せずに呟いた。
「否定はできない! だが、安全である理屈は完全じゃねえんだぞ!?」
「じゃあ、やるしかないじゃないですか。猫はさっさと逃がしてしまったほうが楽なもんです」
さあ。さあさあ。生かさず殺さず、僕を墓地に送ってください!!
……どいつもこいつも狂ってる。いや、狂ってるのは俺達……もしくは、始めっから全部――
「僕を墓地に送ってください!!」
煽りではない。トラッシュトークでもない。カムイの眼は見開かれ、ぎらぎらと光る瞳の奥には弛まぬ熱さがある。
本気で彼は死線を潜ろうとしていた。真剣だからこそダルクは茶化したり罵声を浴びせたりできなかった。その本気の言葉に返す手立てを見失っていた。
「ちょっと待ってくださいカムイさん。それにヴァニティさんもあんまり煽らないでください。お聞きしますが、貴方の理論で死線をくぐるとしてその手段はあるのですか? まともな死に様じゃ戻ってくることなんてできないんですよ?」
ピケルが場をいさめてそれぞれの来客に声をかける。それは正論。暴力的な手段で死に至ることはもちろん、細胞的な死ですら安全策とは言えない。命を賭けて試すには危険な賭けと言わざるを得なかった。
「妙案は、無いさ。だからこそエンディミオンにこさせてもらったもらったわけだからな」
ヴァニティの失意のこもった言葉にピケルは、そりゃそうですね、と一言だけ返す。ダルクは部屋のそれぞれを一瞥し、
「カーム。あんたはどうなんだ。弟の決意を聞いてどう思う」
「笑顔で手を振れるわけ……あるわけないですよ! 心情的には貴方にその役回りをやってもらわなきゃ気が済みません! だけどそんなの!」
「できるわけないですよ。今や世界のバランスはデリケートです。万が一『失敗』したときの世界への影響は計り知れません」
カームの文句を遮るようにピケルがすっぱりと事実を語る。
「なので、恨みつらみでダルクさんを墓地に放り込むわけにはいきません。裏返せば、私なら……全然いいんです。もう失うものなんて、ありませんから」
続けて語るピケルの笑顔は悲痛なほど輝いていた。
「でも、私には私なりの理念があります。ちょっと私についてきてくれませんか。ヴァニティさんの考えをどう見るか、確かめてみたい人がいます」
◆
「ようこそ、魔導図書館へ」
エンディミオンの外れにある図書館。そのまた奥深く、関係者以外を拒絶する趣の暗闇をさもありなんと通りぬけたどり着いたもう一つの図書館。
ピケルを初めとする一行の気配に気づくと、高い声色の男の声が本棚の脇から聞こえる。 「あ、ダルクさんにピケル。それに……ガスタとリチュアのお方たちですかね」
ひょこりと顔を出した少年は青のローブに帽子と眼鏡を携え、白く透き通るような肌はいかにも学術を生業とする佇まいを醸し出していた。左手には自身の顔より大きな魔導書を携え、視線を一行に向けると一礼する。
「こんなとこにご来客なんて久しぶり。僕の名前はバテル。魔導書士ライブラリアンのバテルです。ささ、お茶をお出ししますのでお掛けください」
バテルと名乗った少年は用件も聞かず笑顔で、部屋の隅にある応接間に5人を案内した。
「はい、おいしいオレンジティーですよ。皆さんお疲れのようですから、リラックスなさってください」
バテルは毒気のない態度で5人の前にカップを置くと、自分の机にあったカップを運んで持ってきて、応接スペースの空いた椅子に腰掛ける。
「……バテルは相変わらず緊張感がないですね」
「あっは、そうかな。むしろピケルこそそのお年でめんどくさい役職任されちゃって緊張感しかないじゃない」
ピケルが眉を曲げてバテルに冗談めいた嫌味を吐くが、バテルは飄々とした態度で手を振って言葉を返す。
「バテル……って言ったか。申し訳ない、気持ちはありがたいんだが、俺達、急ぎ用件があってここに……」
「あー、ストップ。ストップです。どの道一刻一秒争うようなことじゃありません。光属性首領代行に闇属性首領、それに首領を失ったギルドの構成員が三人。ろくでもない用件ってことくらい想像付きますよ。それならまずは話し合いの場を持ちましょうよ」
「なるほど。死した首領を取り戻したい」
倒れているカームを介抱してからのい一連の流れを聞いたバテルがまずは一言呟く。
「……驚かないんだな」
「ええ。私のような学術サイドの人間は、方法があるならそれを理論的に追究するのが生業です。もちろんそこには倫理とか野暮ったいものもありますが、考えてみることはタダでしょう?」
バテルはダルクらの話に眉を潜めることもなく、驚くこともなく、ただただ取り込むように頷くだけだった。そのうえでダルクからの言葉に返した一言には自虐的な態度とかもなく、ただただ理念を語るだけ。
「ここに来たということは、その手段を模索している……ってことと解釈していいんですか?」
バテルはピケルの方に顔を向け、あまりにも答えにくい質問を臆せず呟く。確たる返答がないその質問から数秒後、バテルは一つ息をつく。
「不可能ではないと思うんですよ。誰もが変にモラルを敷き詰めて踏み込んでいないだけで」
「……」
「例えば《ライトロード・サモナー ルミナス》。ダルクさんも最近会ってるはずですが、彼女のスペックはご存知で?」
「あいつスキルは確か、ネクロマンシー……」
「ええ、ええ。例のAOJ戦のことについては聞き及んでいます。その中でルミナスは効果を発動したとか」
「ドラグーンの効果発動の時にその場にいたら巻き込まれるからって奴だったな……」
「はい。あの効果は本質的には代償を支払うことによってライトロードモンスターを蘇生する技術。それを発展することによって、自身をコストとして自身を生き返らせたにすぎません。言い換えれば一度死に、墓地から引っ張り出された」
その会話になるほど、とピケルが呟く。
「ルミナスさんは『戻ってきてからも』ご健在でした? 五体満足ですか?」
「……健在だ。もっとも、戻ってきた時、精神的には痛々しかったがな」
ダルクの口調が曇りがちなのは、理論が実在する結果に武装されていくから。逃げ道をハンマーで砕かれているような圧迫感が背後から迫る。
「あれは数秒間の脳死とか心肺停止とかいった生易しいものではないんです。それこそ何の比喩もなくこの世界からほんの数秒だけですが体と精神が消失し、墓地に飛ばされているんです。そのような次元移動が行きと帰りで2回行われている……そりゃ痛々しくもなるでしょう」
バテルは机に肩肘を付き視線を落として答える。そして続けざまに、
「もはや机上の空論じゃありません。戦闘として経験してきたダルクさんならお判りでしょう。もはや僕達は異なる次元から戻ること(ディファレント・ディメンション・リバイバル)の可能性は立証されているわけなんです」
楽しげに語る。バテルは清濁織りまぜた意味で学者である。幼い頃から世界の仕組みに興味を持ち、世界を自身に与えられたおもちゃ箱のように突き詰めていった。彼にはそのことについての善悪の判断はない。摂理は摂理でありそれ以上ではないと感じていた。
しかし、彼は周りの人間の感覚を察知する。彼自身は、今回の問題に対して倫理で箍をかけることは是としていないが、対峙する者には決して押し付けない。
「僕達学者は、ダルクさんを後押ししますよ。『戻れる』『死に方』を模索しているなら、手を差し出すつもりです」
結果的にバテルはダルクを試すこととなる。
「……」
それは、ほんの数秒で返答しろというのにはあまりにも酷な問題であった。
「なあピケル」
「……なんです?」
「おまえはこうなることを、」
「ええ。バテルはこういう人間ですからね、大体こういう流れになるってことは想像ついてました。……私は何もハッタリで墓地に行くのもやぶさかじゃないとか言っているわけではないんですよ。でも、私が言って解決できる問題か?って言われたら、頑張っても、ノーなんですよ、きっと」
途切れ途切れになる言葉は、自分の無力さを噛み締めるような歯切れだった。
ピケルの言葉の裏には、『解決の選択肢はダルクが墓地に行くことしかない』というニュアンスが含まれていた。それには感情でダルクの墓地行きを求めたカームですら同調の言葉を乗せられなかった。感情的にも、理論的にもこの次元からの一時追放を求められる存在。ある意味では『この世』から存在を疎まれることは、余りある辛さだった。
「あんたも残酷だな、ピケル」
ヴァニティがくっくと口端を上げ、肩を震わせる。
「カームの感情論に乗っかるのはいくらなんでも立場上おかしいからな。きちっと理論固めをするように見せかけて、実際のところ結果は見えてる。まったくいい性格だな」
「随分な言い振りですねえヴァニティさん」
ピケルはヴァニティの皮肉に対し反論を吐かなかった。苦笑するように部屋を見渡して、続けざまに、
「でも信じてほしい。私がダルクさんに言ったことばは、全部本心ですよ?」
「え? なに? ピケル、ダルクさんに何を」
「バテル茶化さないで。死なないで欲しい、生きて世界を担ってほしい。それをヒールになりきって騙しすかして言えるほど、私は出来た演者じゃありません」
ピケルは胸に手を当て、ダルクの眼をしっかりと見据えてはっきりとした口調で語る。
「でもその一方、死した霊使いの皆さんを救えるのはダルクさんなんです。私は全力でバックアップします。だからお願いします」
ライナ様を、そして皆さんを、救ってもらえませんか。
それは、無視してそっぽを向くにはあまりにも切ない嘆願だった。
「救う、ってのは……」
「もちろん、蘇生してほしいっていう意味ではありません。そんなことをしてしまえば……」
してしまえば、これまでの戦いの意味が問われることとなる。裏切りがあり、暴走があり、その結果「正義が生き残った」。それをノーサイドとして蘇生を許してしまえば、決意と判断が無に帰す。
「……大丈夫です。死んだ者は生き返られない。それは不変です」
ピケルの詰まる返答に言いよどんだようにバテルが付け加える。
「死因は全て聞き及んでいます。アウスさんは脳損傷、ヒータさんは焼死、ウィンさんとエリアさんは圧迫死。ライナさんは首……最終的な死因は窒息死ってところですか。こう並べると皆さんいい死に方してますよ、全く」
もちろんバテルの言葉は皮肉交じりである。
「『戻して』『支障ない』『墓地への行き方』は死に際の状態……いうなれば死因によります。大丈夫なのは、身体には傷のない死に方。裏返せば身体的な裂傷が激しい状態の死んだ者を揺り戻したとしても、その人は間もなく再死します。体という入れ物が生きるために必要な精神のキャパを支えきれませんからね」
その解説を聞き、ダルクはルミナスの効果発動を思い返す。あれも、『死』というよりは一種のワープである。それさえ踏み違えなければあれは『死』なぞではなく、同じ発想で考えれば、死なずに墓地に踏み込むことができるだろう。
「言い換えれば、霊使いの皆さんは決して生き返ることはない。それでもなおピケルは何を望んでるの? 考えようによれば、君はダルクさんにとてつもなく残酷な役目を背負わせようとしてるんだよ?」
バテルが踏み込み、論じる。いつも毅然とした態度で思いの丈を表現していたピケルが、この場では正論と感情の合間に揺られている。ダルクはぶれる態度のピケルを見るが何も語らず、バテルは真剣な表情を崩さず言葉を待つ。
「それでも、死んだ皆さんと、ダルクさんの安寧を求めるなら、」
途切れ途切れに。
「『振り出し』を、『アウスさんの死を』解きほぐして、この度の闘争に決着をつけてきてほしい。今の状態は、解決したように見えて何も解決してないから」
「……」
「それを突き詰めて帰ってきて、生き続けて欲しいです」
悲壮なまでな決意と、願いだった。
「俺も、『振り出し』が宙ぶらりんになってることについてはあいつらに聞きたいことがいくらでもある。そのうえに場の全員が墓地行きを望んでる……か。ある意味ウィンウィンだが、」
ダルクは改めてテーブルの周りに陣取る全員を見渡す。
「僕達が、口を挟めることではないかもしれません」
沈黙をカムイが破り、隣のカームの肩を叩き、続ける。
「はじまりは、復讐心でした。でも、聞けば聞くほどその淀みは霧散していきました。だから、僕達の望みと皆さんの望みが同じなのなら、頭を下げます。お願いします」
カムイが頭を下げ、カームはちょっとだけ複雑な表情を作り、続けて頭を下げた。
「全くどいつもこいつも調子いいこと言いやがって……。わかったよ! バテル! 話を聞いてやる! せいぜい良い死に方を教えてくれよ!?」
「りょーかいです! その言葉をお待ちしておりました!!」
ダルクの決意にバテルが爛々とした表情で立ち上がる。瞬間、何かの詠唱があったかのようにバテルの頭上に魔導書が数冊現れ、引力に任せ落下する。バテルはそれを器用に両手でキャッチし、意気揚々と話し放つ。
「まるで曲芸だな」
ダルクは、両手で器用に自由落下する魔導書をキャッチするバテルを見てそう呟いた。
そうダルクに思わせたのは何もキャッチが上手かったという理由だけではない。バテルの表情が心からわくわくしているように見受けられたからだ。体全体と、アクション全体の躍動で明るさを表現するバテルはまるでピエロのようだ、とダルクに思わせる。
「僕には、ダルクさんの考えていることがなんとなく伝わりますよ」
バテルは、ダルクの表情から暗に何かを読み取ったように言葉を返す。
「人の生き死にを取り扱うのに、そんなファンキーな態度は不謹慎なんじゃないかって。戦争に快楽を見出して何人もの首領を死に誘ったライナさんと何が違うんだって。そう、思ってるでしょう?」
「……あんたが俺の態度からそう読み取ったのなら、そうなんだろうな」
ダルクは、バテルの挑発めいた言葉に対し嫌悪感を隠さず否定しなかった。
「……。この世界はですね、思った以上に『システム』に縛られてるんですよ」
「おまえ、なにを」
「『次元の飛び交い方』。ダルクさんに信じて頂けるかどうかわからないですけど、この世界は多重構造なんですよ」
バテルが話しだすその持論に、誰もが口を挟まない。部屋はしんと音が落ち切り、壁にかけられた時計だけがちっちっと空間を裂いていた。
「霊使いの皆さんを含め死人が『い』るのが墓地、そして私達生者が『い』るのがフィールド。そこまではおわかりですね?」
それは誰しもが、それこそ子供から大人まで生きとし生けていれば本能が理解していることであり、ダルクも否定するところは全くなかった。
「世界はそれだけじゃありません。墓地とフィールド以外に『異次元』という世界があります」
「いじ、げん……?」
「ええ、そこは生きているとも死んでいるとも別の空間。ねえ、ダルクさん。『例えば』『抹殺とかされて』『異次元に魂が除外されたら』。それって死んだってこと、なんでしょうかね?」
「お、おまえが今行ったじゃねえか。抹殺って。それって死んで……!!」
「死んでないですよ。少なくとも世界の定義上異次元に行っただけ。墓地に送られていない。ってことは死んでいない」
「そんな言葉遊びで……!」
「言葉だけ、ですか? 一回フィールドから魂が離れてしまえば死人と? なら貴方は、ルミナスの正面で『てめーはゾンビだ』って啖呵を切りますか? ルミナスの覚悟を、そうやって戒めることができますか?」
「……」
「現に、私達のような魔導を取り扱うものには、中に異次元で活動をしている者もいます。《魔導教士 システィ》。《異次元からの帰還》はご希望であればいつでも可能ですよ?」
ダルクは、バテルの言葉を聞いて釈然としない所を思いつつも、明らかな反論ができなかった。
「要は私は、気持ちの持ちようだと考えています。例えば外傷激しく五臓六腑がでんでろりんになっているような状況では、それを流石に『死んではない』という気はありません。それはただの現実逃避です。ただ、意識を失ったり、故意に意識を飛ばしている……そんな形で『意識が干渉できない』ような場所、それを『死』と表現するべきではない。それが我ら魔導のコンセンサスです」
「……ダルクさん。正論でしょう。だから私は、嫌だったんです。最後まで頼りたくなかったんです。聞いてしまえば引き返せない気がしたから」
ピケルの声色は震えていた。怒りとか、悲しみとか、そういう表層的な感情を通り越して……本質が深層を突き抜ける。心に空いた穴に冷風を突きつけるようなロジックに、気持ちの整理が追いついていないかのように。
ダルクも曲がりなりにも首領だ。同調性がなくとも、政治的対話は多少なりとも経験してきた。だからこそ、対話の中で相手が何を求めているか……そのことを察することもできる。バテルの称する世界構造の説明、倫理的な死の回避、場のダルクに『異次元に行ってほしい』という感情の醸成。
ダルクの頭は冷えていた。回答にもたどり着いていた。
「《抹殺の聖刻印》。これでまっさらな体で異次元に行け、ってことか」
「イエス。流石に頭の回転がお早い。」
皮肉でもなんでもない。側頭で導き出された回答に、バテルは素直に称賛していた。
ダルクがその回答に気づいたことは完全な偶然というわけではなかった。先のライナとの戦闘において勝敗を分ける分水嶺となった《所有者の刻印》。ひりつく戦闘の中で刻印(Seal)の可能性に気づいた経験が、ここでの可能性の発現に至ることとなった。
「そして、《異次元からの埋葬》を行うことによって異次元から墓地に『戻せば』いい。このバイパス移動においてモンスターは『破壊』は行われていないため、従って、ダルクさんが危惧されている『死』という概念は絡んでこない。まっ更な体で墓地に行くことは可能です」
(ライナが言ってたな……ガスタは死者とのチャネリングが出来る。俺が墓地に行ったとして、《ガスタの交信》は容易いか)
「……」
「刻印なんてマイナーなマジックアイテム、よく思い描くに至りましたね」
「それにはちょっと、世話になってな」
深い返答をしないダルクに、ピケルは口を挟まない。
「《抹殺の聖刻印》は対象となった『相手』を異次元に送り込む魔術。……自分で自分を送り込めないんですよね」
バテルが次いで発言した言葉、それが意味することは場の全員が理解していたことであり。
「くくっ。つくづくアンタ、性格悪いな」
それをあえて口に出したヴァニティと、
「よく言われます」
皮肉を正当に咀嚼したバテルがいたずらっぽく笑う。
「ホント馬鹿ですよ、バテル。そんなの、そんなの」
感傷的にならないわけないじゃないですか、ピケルがうつむいて呟いた言葉は皆の耳に届かなかった。
先の数時間前まで身を賭して刈り取りたかったダルクの命が、こんなに軽く天秤に賭けられるなんて。そして、その儀式は他人によって行わなければならないということ。ピケルは目を瞑り、部屋の屋根を見上げ何かを考えあぐねるように眉頭をつまむ。
「……ピケル」
「ピケルさん」
カームとカムイが二者二様にピケルの様子を憂う。考えがまとまったのか、ピケルははぁ、と大きく息を吐きダルクの方を向く。
「よりにもよって、それですか」
「そう。それなの」
ピケルの意図不明の嘆きに乗っかる形に即答したのはバテル。飲みかけのティーカップに再度口をつけ、ピケルの方を一瞥する。
「……そうですね。私が説明しないといけないですね、私が」
「……?」
「抹殺の聖刻印。名前を見返せば……何か思うところがあるんじゃないですかね、ダルクさん」
「抹殺の……聖……刻印。聖……まさか……!」
「私が思わせぶりに喋ってること。そして戦いの中から見出される因果性。察しの通りです。《抹殺の聖刻印》も《光霊術-「聖」》の同種技術。聖なる刻印、ですから光属性である私やライナ様が得手としていたのは自明の理です。サイキック族であるカームさんやカムイさんに任せるのはもっての外ですし、ヴァニティさん。貴方も魔法使い族に見せかけて、実はそうじゃないでしょう?」
「……ご名答。よくわかったな」
「乙女の勘です」
ピケルはくすりと笑い舌を出すが、鎌をかけた部分でもあった。元々水属性の魔法使いにそのような役回りを願う考えもなかったし、その意味ではハッタリが効いたと言えた。
「遅かれ早かれ、そうなる因果だったんですね」
「ピケル……」
「もうお分かりですよね、ダルクさん。この場のねがいは、私が貴方に《抹殺の聖刻印》を放ち、異次元、そして墓地を経由して、逝去された五人の霊使いの方々から『一連の真意』を突き止めてきてほしいということです」
「……」
「それはとてもとても残酷な要望だと思っています。とりようによれば、私の邪な策謀にて、対ライナ様との戦闘で葬りきれなかった貴方をそれらしい理由をつけて潰してやろうという意図が垣間見えるかもしれません。だけど……」
「信じるよ」
遮るようにダルクが透き通った声を出す。
「…えっ、だる、く、さん」
その即答が信じられないかのように目をぱちくりとして、ピケルが辺りを見渡す。それはまれに見るピケルの年齢に似合った仕草であり、ダルクはその様子を純粋に滑稽に、微笑ましく思えた。
「あーこれオチたなー。ピケルオチたなー」
バテルがその様子を見てにひひと笑い、続ける。
「もちろん、私がピケルと組んで虚偽の理論を提出し、貴方の死を謀っている……なんて線は捨ててください。そんなアンフェアを行わないのは学者としてのポリシーライン。それを行えば『人として』のバテルが死ぬ前に、『学者としての』バテルが死んでしまいます。私は、学を裏切りたくありません」
本来ならばその優先順位の等号は逆なのではないだろうか、そんな考えがよぎりもしたが、ダルクはその思考を無粋と考え、口には出さなかった。
「……いずれ通らなくちゃいけなかった道だ。それが早かったか遅かったか。たまたま『今』だっただけだ」
そう言いながらダルクは隣の席に座っていたピケルの手を取り、自分のローブの胸元に突きつける。
「ちょっ、うわっ!?」
ピケルのてのひらにはダルクの心音が規則正しくとくんとくんと響き、突然のダルクのアクションに頭がついていなかった。
ただそれも一秒以内のこと。つきつけられた意味、そのことについて何も言わないダルク。ピケルは意図をしっかりと掴み、
(ここで何か感傷的に言ってしまうと、きっと聖刻印の発動に躊躇ってしまう。だから)
ただしっかりと、無邪気に、可愛らしく、悲しそうに笑い、
「《抹殺の聖刻印》!!」
解き放つ。
瞬間、ダルクの姿はぽつねんと消失し、図書館の一つの椅子はぽっかりと空いた。まだ、その椅子には人のぬくもりは残っていた。
(ここから先の執筆は行っておりません……! ダルクたちの戦いはここからだ!!)
いいなと思ったら応援しよう!

