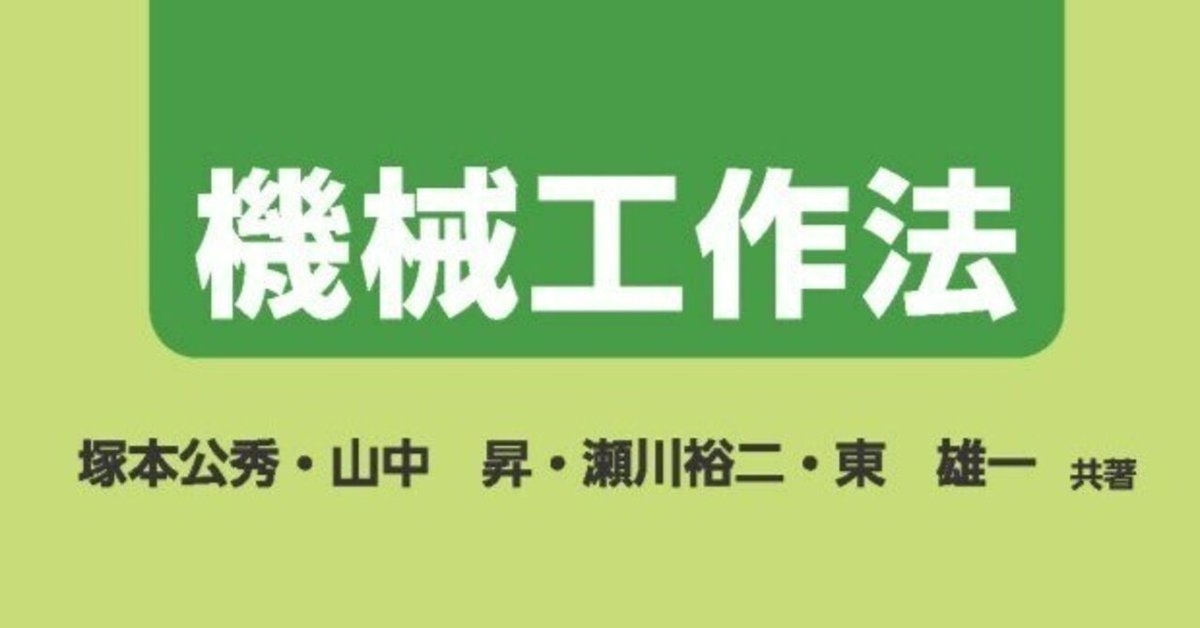
【内容一部公開】ものづくりに必要な基礎知識を身につける――近刊『機械工作法』
2024年11月下旬発行の新刊書籍、『機械工作法』のご紹介です。
同書の一部を、発行に先駆けて公開します。

***
はじめに
今世紀になって日本のものづくりは大きく変化した。従来は大量生産による安価な製品製造が中心であったが、中量生産や多様な消費者のニーズに応じた多品種少量生産が拡大している。このため、製品設計と製造との連携が重要となり、製品のアイデア創出の段階で加工の知識が必要となっている。また、情報・制御技術の導入により、加工機械は高度化し、積層造形法などまったく新しい加工法も生まれた。このように移り変わっていくものづくりだが、その進歩は機械工作法の歴史でもある。各々の加工法は独自に進化しつつ、ほかの加工法や新しい技術を導入して高精度で高効率の加工法へと進歩している。
本書の構成は、従来からの機械工作法の基本である、鋳造、溶接、塑性加工、切削加工、砥粒加工、特殊な加工法である。これらの加工法のなかでは、固相接合、プラスチック加工、アディティブ・マニュファクチャリングなどの新しい加工法についても説明する。
機械工作法は、機械工学から生まれたが、ほかの工学との融合で新規分野が生まれたことで、いまや機械系の学生だけでなく、ものづくりを学ぶ学生の基礎科目として位置づけられている。そのため、本書は大学・高専でものづくりを学習しようとする学生を対象として、ものづくりをする際に知っておきたい各加工法の特徴がよくわかるように配慮した。初めて学ぶ際だけでなく、実際に設計や加工をする際の参考としても活用いただければと思う。
(後略)
***
鹿児島高専 名誉教授 塚本公秀(共著)
都城高専 名誉教授 山中昇(共著)
都城高専 瀬川裕二(共著)
鹿児島高専 東雄一(共著)
ものづくりにおける加工技術について、スタンダードな手法から新しい手法まで、丁寧に解説した入門テキスト。
<本書の特長>
●鋳造、溶接、塑性加工、切削加工、砥粒加工、特殊な加工などはもちろん、固相接合、プラスチック加工、アディティブ・マニュファクチャリングなどの新しい加工法についてもしっかり解説しています。
●各手法のメリット・デメリットをわかりやすく解説しています。
●豊富な図や機械の現物写真などが理解の一助となります。
初学者の入門書としてはもちろん、設計や加工に携わる方の参考書としても役立つ1冊です。
【目次】
第1章 ものづくりと機械工作法
1.1 もの(製品)づくりの流れ
1.1.1 開発工程
1.1.2 製造工程
1.2 “もの”の価値を決めるものづくりの3要素
1.3 さまざまな加工法
第2章 鋳造
2.1 鋳造の基礎
2.2 砂型鋳造
2.2.1 作業工程
2.2.2 模型
2.2.3 鋳型
2.2.4 砂型鋳造の種類と造型法
2.2.5 鋳造用金属材料
2.2.6 溶解炉
2.2.7 特殊砂型鋳造
2.3 金型鋳造
2.3.1 重力金型鋳造法
2.3.2 低圧鋳造法
2.3.3 スクイーズキャスティング
2.3.4 ダイカスト
2.4 特殊鋳造
2.4.1 連続鋳造法
2.4.2 遠心鋳造法
2.4.3 真空脱ガス法
2.4.4 真空鋳造法
2.5 鋳物の欠陥とその検査方法
2.5.1 欠陥
2.5.2 検査方法
演習問題
第3章 溶接
3.1 溶接の基礎
3.1.1 溶接の特徴
3.1.2 溶接の種類
3.1.3 開先
3.1.4 溶接継手の形式と溶接の種類
3.1.5 溶接姿勢
3.2 溶接部の性質
3.2.1 溶接部の組織と機械特性
3.2.2 溶接残留応力と溶接変形の発生メカニズム
3.2.3 溶接残留応力の影響と除去
3.2.4 溶接変形とその軽減
3.2.5 溶接欠陥と対策
3.3 金属材料の溶接性
3.4 各種の溶接法
3.4.1 ガス溶接
3.4.2 アーク溶接
3.4.3 抵抗溶接
3.4.4 固相接合
3.4.5 ろう接
3.5 マルチマテリアル化
演習問題
Column 「応力」
Column 「熱処理」
第4章 塑性加工
4.1 塑性加工の基礎
4.1.1 塑性加工の特徴
4.1.2 塑性加工の種類
4.1.3 加工温度
4.2 圧延
4.2.1 圧延とその特徴
4.2.2 圧延機
4.2.3 一次加工と各素材の圧延方法
4.2.4 材料の変形
4.2.5 ロールの変形とクラウン制御
4.3 鍛造
4.3.1 鍛造とその特徴
4.3.2 熱間鍛造と冷間鍛造
4.3.3 自由鍛造
4.3.4 型鍛造
4.3.5 鍛造用機械
4.3.6 鍛造用加熱炉
4.3.7 転造
4.3.8 鍛造欠陥
4.4 押出しと引抜き
4.4.1 押出し
4.4.2 引抜き
4.5 プレス加工
4.5.1 せん断加工
4.5.2 曲げ加工
4.5.3 絞り加工
4.5.4 プレス機械
演習問題
第5章 切削加工
5.1 切削加工の基礎
5.1.1 工作機械とは
5.1.2 工作機械の種類
5.1.3 工作機械の特徴
5.1.4 切削工具の材種
5.2 数値制御工作機械
5.2.1 マシニングセンタの構造
5.2.2 NC工作機械と座標系
5.2.3 NC工作機械の加工点の制御
5.2.4 NC工作機械のプログラミング
5.3 切削のメカニズム
5.3.1 切りくずの形態
5.3.2 切削抵抗
5.3.3 切削熱と工具温度
5.3.4 構成刃先
5.3.5 工具の損傷と寿命
5.3.6 表面粗さ
5.4 切削油剤
演習問題
第6章 砥粒加工
6.1 研削加工
6.1.1 研削作業と工作機械
6.1.2 研削砥石
6.1.3 ツルーイングとドレッシング
6.1.4 砥石の自生作用
6.1.5 研削仕上げ面に与える要因
6.1.6 研削液
6.1.7 研削機構
6.1.8 そのほかの固定砥粒による加工
6.2 遊離砥粒による加工
6.2.1 ラッピング
6.2.2 バフ研磨
6.2.3 噴射加工
6.2.4 超音波加工
演習問題
第7章 特殊な加工法
7.1 熱エネルギーによる加工
7.1.1 放電加工
7.1.2 電子ビーム加工
7.1.3 レーザ加工
7.1.4 プラズマ加工
7.2 化学反応・電気化学反応による加工
7.2.1 化学的除去加工
7.2.2 電気化学的除去加工
7.3 プラスチック加工
7.3.1 プラスチックの種類
7.3.2 プラスチックの加工法
7.4 アディティブ・マニュファクチャリング
演習問題
参考文献
索引
