
執筆者の声を大公開!――近刊『高専数学の参考書 基礎数学』
2025年2月下旬発行の新刊書籍、『高専数学の参考書 基礎数学』のご紹介です。
本記事では、著者の中村先生のコメントや執筆・校正に参加した高専生の生の声をお届けします。
※「はじめに」や目次はこちら。
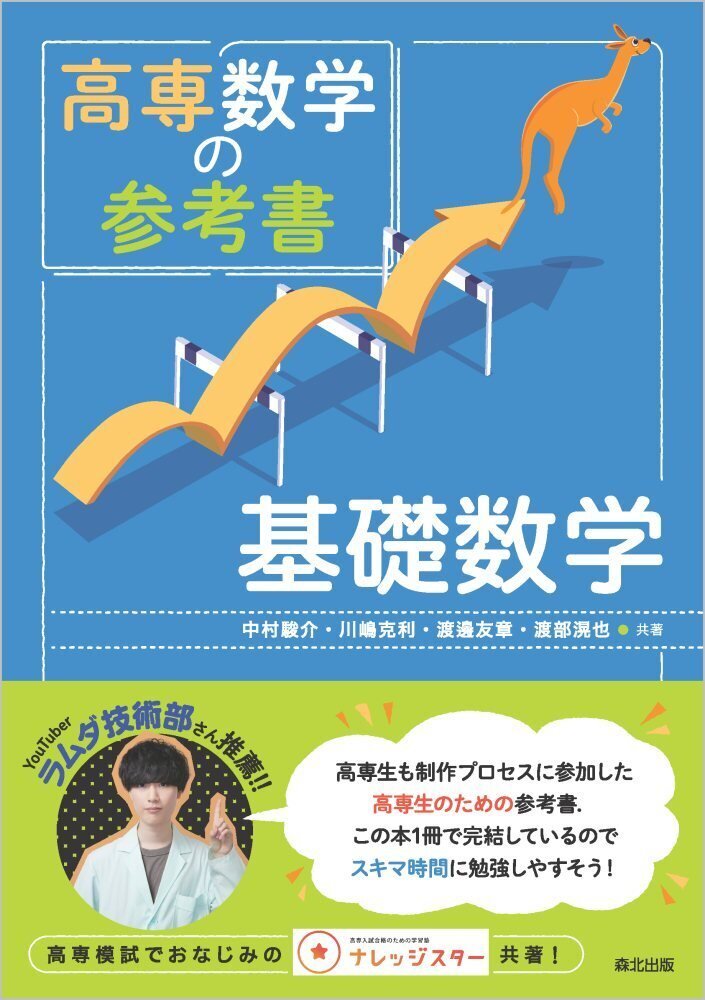
***
著者・中村先生より
「基礎数学」は、高専数学を学ぶ上で土台になる部分です。基礎数学の先では、微分積分学、線形代数学、応用数学、確率統計といった科目を学習していきます。本書の第1章から第3章の内容を基礎として、第4章から第7章の内容を学習します。第4章「指数関数と対数関数」、第5章「三角関数」の内容は、これから学ぶ数学で頻繁に登場します。第6章「図形と式」は、特に微分積分学や線形代数学を学習するときに、第7章「個数の処理と数列」は、特に確率統計を学習するときに利用します。このように、基礎数学はこれから学習する高専数学で必須の内容です。本書1冊を学習すれば、「基礎数学」の内容を十分に身につけることができるようになっています。
本書は、例えば次のことに工夫して執筆をしています。
途中式を出来る限り省かずに丁寧に解説する。
電車に乗っているときなどの隙間時間に読めるように、複雑な計算の筆算を空きスペースに書く。
国公立大に編入学をする学生と、1年次入試試験を突破してきた学生との間に、数学的思考力の差が出ないよう適切な発展問題を取り入れる。
数学は使わないと忘れていきます。学年が進んでからでないと、あまり使わない基礎数学の内容もある為に、忘れてしまう基礎数学の分野も出てくると思います。本書1冊があれば、忘れた基礎数学の分野も容易に思い出せます。このように、辞書代わりに本書を持っておくこともよいでしょう。
本書が、基礎数学を学習するみなさんの一助となり、将来にわたって必要とされる基礎数学の力を身につけてもらえたら、これほどうれしいことはありません。
***
執筆・校正に参加した高専生の生の声!
――数学を学ぶ目的はなんなのでしょうか?工学のための道具でしょうか。確かにそうです。しかし、数学が好きになると人生の幸福度ΔHが増加し、豊かさが広がります。本書でそのきっかけを見出してみてください。
――高専から大学編入を経験した上で、最も大切だと感じることは「基礎」をしっかり身につけることです。何冊も参考書を解きましたが、基礎がある分野とない分野では、一発目の理解度が大違いです。
――高専生活で勉強に困らないために、数学の先取り学習をしておくと5年間楽に過ごすことができます。数学を勉強するときは、1行1行を人に噛み砕いて説明できるくらいにまでなってください。わからなかったら積極的に質問に行ってください。その姿勢がいつか実を結びます。
――「皆さんは、数学者・新井紀子さんの著書『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』をご存じですか?この本では、現代の子どもたちが教科書を「見る」ことはできても、その内容を実際には理解できていない、つまり「読めていない」という問題について述べられています。この参考書を手に取る方の多くは高専生だと思いますが、おそらく皆さんはすでに『高専の数学』を持っていることでしょう。先程述べたようにこの参考書を使うにあたって「見る」だけなら『高専の数学』があるので十分なはずです。私は、この参考書をしっかりと読み、『高専の数学』では得られない新たな知識や視点を身につけてほしいと考えています。
――高専の「数学」という科目は、基礎数学から始まりたくさんの範囲を学習します。基礎数学ができないとその後の科目も理解できません。本書で基礎数学の苦手を克服し、今後の高専生活を楽しみましょう。
――この内容はこれから学ぶ全ての土台になっていきます。基礎=簡単という意味ではありません。「基礎だから簡単だし余裕」と思っていると(僕のように)後々痛い目を見ます。
――勉強はサボろうと思えばサボれますが、今やっている勉強は今後役に立ちます。挫けず頑張ってください。
――私は、問題を解く際に解説をしっかり読み、類題を繰り返し解くことで理解が深まりました。定期的に復習し、苦手分野を重点的に学ぶことが大切です。是非、本書を手にして新しい知識を身につけて欲しいです。
――この本は、初めて「高専数学」という大きな壁に対面する高専生のために、全国の先輩高専生の叡智を結集して作り上げた本です。ぜひボロボロになるまで使い込んで、マスターしてください。そうすれば赤点回避は確実!
――数学は、問題に取り組み自分で考えることが大切です。高学年の難しい数学も、基礎ができていればきっと大丈夫。数学の壁を感じてる?それ、実はドアです。この本で鍵をゲットして5年間のドアをこじ開けよう!
――高専で学んだ基礎は、次のステージでも大きな力になります。苦手分野も挑戦することで、必ず成長につながります!
――これから中学の数学とはまた違った数学を学んでいく皆さんにとって、つまずきやすいポイント、わかりづらいポイントを、自分の経験も生かしながらまとめました。ぜひ読んでみてください!
――早いうちに「わからない」を潰して、「困らない」高専生活を送りましょう。苦手を潰すにはたくさんの訓練が必要です。
――解説が省略されがちな高専の数学。私も当時はモヤモヤしていました。あの時この参考書があれば……と少し羨ましい気もしますが、力強い味方を手に今から学習されるみなさん、今後の活躍を楽しみにしています!
――数学において、大切なのは本質を捉えることだと僕は考えます。この参考書を通して、公式の丸暗記ではなく、なぜその解き方で解けるのか、またその解き方はどのように応用できるかを掴み、数学の楽しさを知って欲しいです。
――勉強は質か量か、という永遠の問いがあります。私は質より圧倒的量派です。講義で使っている教科書や問題集、先生が配るプリントに満足せず、圧倒的量をこなしましょう。あなたの力が開放されることを約束します。
――本書は、高専で頑張りたい方にも、編入しようとしている方にも、編入が差し迫っている方にもお勧めです。大学進学で科学の基礎である数学は、習得すべきだからです。本書は網羅的に解説されていると思います。
――普通科高校の数学は、どうしても受験のためのツールとなってしまうことが多いです。対して高専数学は、純粋に工学のツールとして学ぶので、とても有意義だと感じます。高専生だからこそ、数学を楽しんでください!
――1年生で習う対数関数や三角関数などは、2年生以降で学ぶ物理や専門科目でたくさん登場します。この本はやさしく丁寧に解説されています。専門の授業では数学的知識の解説はもちろんありますが、専門科目でつまずかないようしっかり勉強しましょう!
――高専→大学→欧州物理M2の先輩です。高専数学は理工学に欠かせない力で、もっと勉強しておけば、と後悔していて今でも勉強し直しています。高専は勉強の量が多くて大変ですが、この本を使って数学力をつけてください!
先生、先輩、そして森北出版は、がんばる高専生のみなさんを応援しています!
