
反、反、反、復、復、復、
日記を書く。
10時に縦になった。11時にまいばすでにらを買った。12時にニラ玉を作った。13時に落合さんから電話がかかってきた。14時にシャワーを浴びた。15時に学校に行った。
どうしてもだらだらと過ごしてしまう。早く立ち上がって、早く歩き出さなくては。なんか夏休みに無職になってしまったので、アルバイトも探さなくてはいけない。
研究室に居たら、先輩にコンペに誘われた。CLTを使った図書館のコンペ。なんだかんだで初めてのコンペになる。ずっとやりたいと思っていたけど、なんとなくやれていなかったので嬉しいな。やりますよ。
昨日福島さんに言われたことを思い返してみる。2m26の建築を紹介された。
フランス人の夫婦による設計事務所。日本で廃屋をリノベーションしている。
馬を近所の人にもらって、馬小屋を作る。羊をもらって、門だと言い張りながら羊小屋を作る。犬を飼って、犬小屋を作る。人間の家はほとんど手がついていない。犬小屋のほうが立派だ。
バイソンギャラリーの施工として、西村組という組織がある。どうも普通の工務店ではないなと思って調べてみるとやはり、変な施工者だった。是非ホームページを見てほしい。
紹介ページにはこうある。
廃屋ジャンキー/ほぼ自然物を愛でる/あるものでつくる/土に還す/有機的な建築集団/神戸
廃屋ジャンキー。すごい言葉だ。廃屋を「ほぼ自然物」と見ている。
廃屋はある意味自然物かも知れない。自分が生まれる遥か前からそこにあるであろう廃屋。人間がものを見たときに、前後関係を知らなかったらそれが自然物かどうかは見分けがつかないだろう。明治神宮の森を原生林だと言う人間がいるように。
閑話休題。西村組のメンバー紹介を見てみる。

親方。よし。

ネオ大工。ネオ?

ネバダ・リュウイチ(納豆研究科)。ネバダ?納豆研究科?ない職業かも知れない。

人間ブルドーザー。食っていけない職業だけど、たくさん食べそうな肩書だ。

風狂士。風狂な風貌が風景から見える。
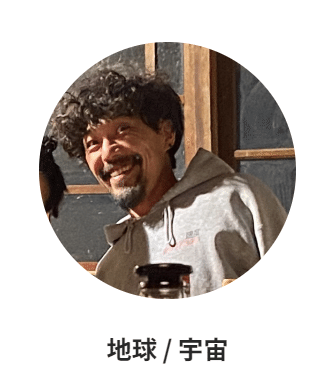
名は地球。肩書は宇宙。
これは有機的な建築集団だ。ここまでフランクに建築を行ってもいいのか。建築って素晴らしいな。
福島さんが取材したと言っていた場所。施工前の写真から、施工中の写真まで載っている。
施工前の廃屋はもはや、建築とは呼べないだろうというものだ。柱を1本ずつ入れ替え、セメントを手運びして土間を作る。ガラスは廃ガラスを再利用。
廃屋への愛を感じざるを得ない。美しくなって廃屋の喜びの声が画面越しに聞こえてくる。
話は2m26へと戻る。生活の一つ一つに見えてくるものが作品として紹介されている。
犬小屋、鶏小屋、鶏の餌場、屋台、馬小屋、屋根裏、サウナ。全てに日本建築のディティールが凝縮されている。これは外国人という視点があるのかも知れない。
我々、日本人がいわゆる日本建築を見たとき、それは日常の延長線上にあるものだ。下見張りの外壁の民家を見たとて、それらは古い家として目が滑る。ただ、海外旅行に行って、例えばパリの風景を見たとき、それはとても新鮮なものとして目に映る。
ディティールに注目したとき、日本の建築は非常に面白みがあるだろう。組積造の場合、ほとんど勉強をしていないのでなんとも言えないが、そこまでディティールというものが存在しないだろうと思う。あったとしてもそれは意匠的に発達したものが多いのではないだろうか。
日本の木造建築の場合、先人たちは長い時間をかけてたくさんのディティールを作り上げてきた。それは工学的であり、意匠的である。工学、実用に基づいたディティールたちは、異様と言える反復を以て現れてくる。瓦、障子、茅葺き、畳、格子窓、石垣。日本の伝統建築は反復をすることをデザインとし、美しさを培ってきたのかもしれない。
福島さんは、こんなことも言っていた。過剰な参照をしろ。
2m26が行っていることは、正に日本伝統建築の過剰な参照だろう。馬小屋の窓に蔀戸を使う。鶏小屋は木皮葺き。建築と言えるのか、微妙なものにさえ、わざわざ、日本伝統建築のディティールを写している。
昨日強く取り上げた日本の民家の写真を見ても、日本伝統建築の最も強く目に見えるものは、反復だ。小屋と倉を見てもすべてのページと言ってもよいほどに見えてくる。木を小さく割り、大量に並べることで強さと美しさを作り上げてきたことがわかる。
僕は小屋を作る。小さな小屋。
反復するということは、なんなのか。反復が強調になるとして、何が強調たらしめるのか。強調とは。美しさとは。日本人が反復する日本伝統建築を美しいと思うのはなぜなのか。なにが、どうやって、日本人のDNAのようなものに植え付けたのか。何もわからない。
