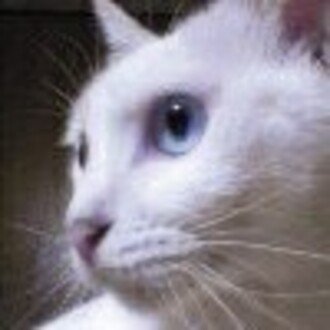DTM用語:オーディオレベルメーターとは
■はじめに
オーディオレベルメーターとは、音や信号の大きさを視覚的に表示するメーターです。オーディオメーターと略すこともありますが、オーディオメーターには聴力を測定する器具や視聴率を調査する装置などの意味があるため、どちらかと言うとレベルメーターと略されることが多い気がします。
■オーディオレベルメーターの種類
オーディオレベルメーターには様々な種類があります。最も一般的なのはアナログ時代に作られたVUメーターですが、DTMなどデジタルオーディオの時代になってからはピークメーターやRMSメーターが、今後はラウドネスメーターが主流となりそうです。
1.VUメーター:信号レベルの平均値を表示するメーターです。聴感上のレベルを把握する目的で使用されます。
2.ピークメーター:信号レベルそのものを表示するメーターです。瞬間的な最大値を監視する目的で使用されます。
3.RMSメーター:信号レベルの実効値を表示するメーターです。聴感上のレベルを把握する目的で使用されます。
4.ラウドネスメーター:信号レベルのラウドネス値を表示するメーターです。聴感上のレベルを把握する目的で使用されます。
かなり簡素にまとめましたが、見ての通りピークメーター以外は聴感上のレベルを把握するという目的が同じであり、なかでもVUメーターとRMSメーターはどちらも一定時間間隔の平均音量を表示するためか同一視される場面が多々あります。
しかしながら、VUメーターとRMSメーターは似て非なるものであり、様々な理由からどちらが優れているという議論は皆無、よもや好みで選択している人が多いように思えます。
■VUメーターとRMSメーター
そもそも、VUメーターはアナログでありRMSメーターはデジタルです。その違いから、なにより音量を表す単位dBに大きな違いが生じます。
まず、デジタル信号は最大音量を0dBとした0dBFSが使用され、0dBFSを越えないよう常にマイナス値で表されます。対してアナログ時代にはdBuと呼ばれる単位が使用されており、電圧変化を数値化したものであるため根本的に比較が出来ません。
VUメーター:dBu
RMSメーター:0dBFS
また、RMSメーターが0dBFSに対する絶対値で表されるのに対して、VUメーターは0dBuを任意に指定する必要があることから相対値で表されるという違いも大きいです。
VUメーター:相対値で表される
RMSメーター:絶対値で表される
さらに、RMSメーターには数学的に正しいRMS値を表示するものとそうでなりものが混在しており、そこには±3dBの誤差が発生するというなんとも困った問題をはらんでいます。
正弦波の音圧を0dbとしたRMS=True RMS
矩形波の音圧を0dbとしたRMS
True RMS+3dB=RMS
そうした違いがあるうえでVUメーターは平均値、RMSメーターは実効値(二乗平均平方根)を導き出しているのですから、これを同じものと考える方がいささか乱暴とも言えます。
とは言え、どちらを使用するかと判断に迫られた場合、個人の多くはRMSメーターを選択するのではないかと思われます。理由は単純に多くのDAWに標準搭載されているからと、正確な数値を表示するVUメーターは手軽に手が出せない程にお高いからだと推測します。
ちなみに、プラグインとしてデジタル化されたVUメーターもありますが、正確性に欠けるものが多く、当然ながら正確なものほどお高くなるため敬遠されがちです。なにより電圧の平均値を取っているVUメーターをデジタル化した時点でエミュレートでしかなく、それをVUメーターと呼べるのかもまた甚だ疑問です。
では、詰まるところどちらが正しく聴感上のレベルを表示しているかと言うと――実のところ聴感上のレベルという意味ではどちらも正しいとは言えません。むしろ、VUメーターとRMSメーターのいいとこ取りをしたうえでさらに人間の聴覚特性を取り入れたものこそがラウドネスメーターとなります。
■ラウドネスメーター
ラウドネスメーターとは、等ラウドネス曲線などを考慮した人間が感じる音量感を測定するメーターです。
ラウドネスメーター:人間が感じる音量感を測定するメーター
VUメーターやRMSメーターは、一定時間間隔の平均音量を示すことで人間の聴感上のレベルを表していましたが、ラウドネスメーターではそれに加えて音が小さくなるほど低音や高音が聞こえにくくなるといった周波数特性や、大きな音に埋もれた音は聞こえにくいといったマスキング特性、瞬間的な大きな音より持続した音の方が大きく聞こえるといった時間特性などを加味しており、より人間の聴感に近い音量感を導き出します。
周波数特性:音が小さくなるほど低音や高音が聞こえにくくなる
マスキング特性:大きな音に埋もれた音は聞こえにくい
時間特性:瞬間的な大きな音より持続した音の方が大きく聞こえる
そのため、ラウドネスメーターの値は単純に音の大きさを表すdBでは表現出来ず、ラウドネス値としてLUFS(Loudness Units relative to Full Scale)というまったく異なる単位で表すことになります。
ラウドネス値:LUFS(Loudness Units relative to Full Scale)
では、実際にそのLUFSがどうなればいいかというと、すべてはラウドネスターゲットレベルに準じます。ラウドネスターゲットレベルとはいわゆる目標基準値であり、例えばテレビ放送なら-24LKFS、YouTubeならば-14LUFSと言った具合にターゲットによりその値は異なります。
ラウドネスターゲットレベル:目標基準値
ただし、ラウドネスターゲットレベルを越えると、多くは強制的にその値へと揃えられてしまうことに注意が必要です。これをラウドネスノーマライズと呼び、ユーザにとっては自動で音量が揃うため曲によってボリューム調整する必要がなくなるという利点がありますが、制作側からすれば意図して作り上げていたダイナミクスが失われ、音楽的な強弱や迫力などが犠牲になるというデメリットをはらみます。
ラウドネスノーマライズ:音圧が強制的に目標基準値へと揃えられる
とは言え、今後このラウドネス値が音量感を表す指標であり標準となるのは間違いなく、それを測るラウドネスメーターが必須となってくるのもまた間違いないでしょう。
■ピークメーター
ピークメーターは、信号レベルそのものを表示するメーターです。瞬間的な最大値(ピークレベル)を監視する目的で使用されます。その用途は単純明快、ピークレベルが0dBFSを越えないようにするものです。0dBFSを越えるとピーク部分が飽和し音が潰れてしまいます。これをクリップと呼び、クリップした音は歪みが発生していわゆる割れた音になります。
ピークメーター:瞬間的な最大値が0dBFSを越えないよう監視する
ちなみに、VUメーターやRMSメーターは平均値を表すものであるためピークレベルを見ることが出来ません。言い換えればピークレベルを見るにはピークメーターでしか見れないとも言えます。
VUメーターやRMSメーターではピークレベルを確認することが出来ない
そのためマスタリング作業では、VUメーターかRMSメーターもしくはラウドネスメーターとこのピークメーターを併用するのが一般的です。
■おわりに
最後まで読んで頂き有り難うございました。あくまで個人的備忘録ですが、何かしらの参考になれば幸いです。
いいなと思ったら応援しよう!