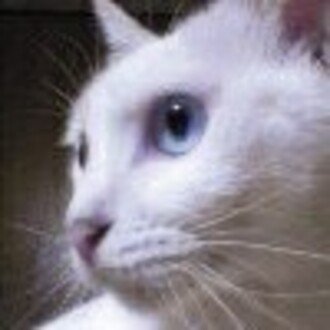DTM用語:ダイナミックレンジとは
■はじめに
そもそもダイナミックレンジとは、信号の最小値と最大値の比率またはその範囲を意味します。映像機器やデジタルカメラの指標としても用いられますが、ここではもちろん音声信号におけるダイナミックレンジを指します。
■ダイナミックレンジとは
音声信号の最小値と最大値の比率またはその範囲を意味します。ノイズが発生しない最も小さな音と、歪みが発生しない最も大きな音の差をデシベルで表します。
ダイナミックレンジ:最小音量と最大音量の比率をデシベルで表したもの
最小音量:ノイズが発生しない音量
最大音量:歪みが発生しない音量
また、ダイナミックレンジは最小音から最大音までの範囲つまり音量幅でもあるため、その差が小さいと狭い、大きいと広いで表されます。
ダイナミックレンジが狭い:音量幅(最小音と最大音の差)が小さい
ダイナミックレンジが広い:音量幅(最小音と最大音の差)が大きい
1.最小音量
電子回路には常にそれ自身が発生するノイズが含まれています。この領域をノイズフロアと呼び、ダイナミックレンジにおける最小音量とは厳密にはこのノイズフロアから抜けた直後を指します。
最小音量:ノイズフロアから抜けた直後
2.最大音量
サンプリング間隔における瞬間的な音量の最大値をピークレベルと呼び、ダイナミックレンジにおける最大音量とはこのピークレベルを指します。
最大音量:ピークレベル
つまるところ、ダイナミックレンジとはノイズフロアを抜けた直後からピークレベルに達するまでの音量幅とも言い換えられます。
ダイナミックレンジ:ノイズフロアを抜けた直後からピークレベルに達するまでの音量幅
■ダイナミックレンジの最適値
ダイナミックレンジが狭いと音楽的には抑揚のない楽曲となり、飽きやすくつまらないものとなります。また、全体的に音が潰れた感じに聞こえ、耳が疲れやすいというデメリットもあります。
対してダイナミックレンジが広いと音楽的には抑揚のある楽曲となり、ドラマチックで魅力的なものとなります。反面、小さな音が聞き取りづらく、音量をあげると突然の大きな音に不快感を抱くというデメリットがあります。
ダイナミックレンジが狭い:抑揚ない楽曲=飽きやすくつまらない
ダイナミックレンジが広い:抑揚のある楽曲=ドラマチックで魅力的
そう考えると、音楽的にはダイナミックレンジが広い方が良さそうにも思えますが、ことはそう単純ではなく、なにより人間の耳は音圧が高いほど迫力のある良い音に聞こえるという特性がさらに状況を複雑化しています。
人間の耳は音圧が高いほど迫力のある良い音に聞こえる
例えばマスタリング時、迫力ある良い音で聞かせようとつい音圧を上げがちですが、音圧を上げれば上げるほど最小音もまた大きくなり、結果としてダイナミックレンジが狭く抑揚のない楽曲へと成り下がります。
音圧を上げれば上げるほどダイナミックレンジは狭くなる
かと言って、ダイナミックレンジが広すぎると小さい音が聞き取りづらく、抑揚はあるが迫力のない楽曲になるばかりか、そもそもどれくらいの音量で聴くかは聞き手に委ねられるため、もはやイタチごっこでしかありません。
ダイナミックレンジが広い楽曲は抑揚はあるが迫力がない
つまるところ、ダイナミックレンジの最適値というものは存在せず、むしろどのような楽曲として聞かせたいかによって適宜広げたり狭めたりする他ありません。
ダイナミックレンジの最適値などない
ちなみに、楽曲のダイナミックレンジとして最も狭いのはEDMで6dB前後、次いでポップスやロックで10dB前後、ジャズやクラシックは20~32db前後と言われています。
EDM:6dB前後
ポップスやロック:10dB前後
ジャズやクラシック:20~32db前後
■おわりに
最後まで読んで頂き有り難うございました。あくまで個人的備忘録ですが、何かしらの参考になれば幸いです。
いいなと思ったら応援しよう!