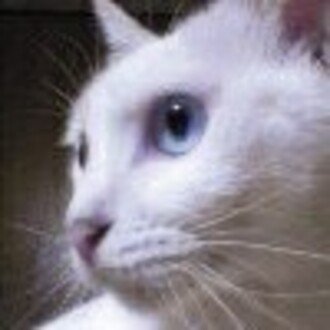DTM用語:サンプリングとは
■はじめに
そもそもサンプリングとは、対象の中から何らかの基準に基いて一部を取り出すこと(標本化)です。ここではアナログ信号をデジタルデータへと変換する際に行われる処理のひとつを指します。
標本化:対象の中から何らかの基準に基いて一部を取り出すこと
■サンプリングとは
アナログ信号をデジタルデータへと変換する際、時間方向に対して離散的に抽出する処理です。離散的に抽出とは、連続的ではなくある一定の間隔で抽出するという意味であり、この間隔をサンプリング周期と言います。
サンプリング:時間方向に対して離散的に抽出する処理
サンプリング周期:サンプリングする間隔
また、1秒間にサンプリングする回数をサンプリング周波数と呼び、サンプリング周波数が大きいほどサンプリング周期が短くなるため、より原音に忠実なものとなります。
サンプリング周波数:1秒間にサンプリングする回数
サンプリング周波数はヘルツ(Hz)で表現されます。例えば48kHzの場合、1秒間を48,000回の精度で表現出来ることを意味しています。
サンプリング周波数はヘルツ(Hz)で表現される
ちなみにサンプリング周波数は、サンプリングする割合を示すことからサンプルレートまたはサンプリングレートとも呼ばれます。
サンプリング周波数=サンプルレート=サンプリングレート
■サンプリングレート
サンプリングレートは、その値により音高を表現します。音高とは音の高さであり、サンプリングレートが大きいほどより高い音域(高周波数帯)を表現出来ます。
サンプリングレートが大きい:より高い音域(高周波数帯)を表現
一般的に音域の可聴範囲は20Hz~20kHzとされていますが、アナログ信号を正確にサンプリングするには最大周波数の2倍を超える周波数が必要とされているため、可聴範囲を補うには少なくとも40kHz以上のサンプリングレートが必要となります。
そのため、CD-DAでは最大周波数を22.05kHzとした44.1kHzのサンプリングレートが採用されています。
CDのサンプリングレート:44.1kHz(最大周波数22.05kHz)
とは言え、可聴範囲を超えた高周波数帯がまったくの無意味というわけでもありません。サンプリングレートを大きくすることで数字では現せない空気感や遠近感を得られる可能性があります。実際、44.1kHzのCDと48kHzのDVDでは明らかにDVDの方がより良い音に聞こえます。
44.1kHzと48kHzでは明らかに48kHzの方がより良い音に聞こえる
しかしながら、48kHzと96kHzではそこまで違いを感じないのもまた事実であり、必ずしもサンプリングレートが大きいほど良いというわけでもありません。どころか、サンプリングレートが大きいほどデータ容量も増加するため、場合によってはデメリットになることもあります。
48kHzと96kHzではそこまで違いを感じない
そのため、個人的にサンプリングレートは48kHzにするのが無難であり、現状それが私にとっての適正値だと思っています。
サンプリングレートの適正値:48kHz(最大周波数24kHz)
■おわりに
最後まで読んで頂き有り難うございました。あくまで個人的備忘録ですが、何かしらの参考になれば幸いです。
いいなと思ったら応援しよう!