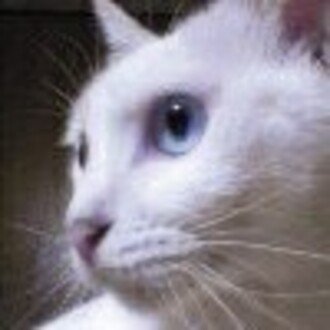DTM用語:ラウドネスとは
■はじめに
そもそもラウドネスとは、人間が耳で聞いて感じる主観的な音の大きさのことです。物理的な音量とは異なり、あくまで感覚的に捉えた音量であることから音量感などとも呼ばれます。
ラウドネス:人間が耳で聞いて感じる主観的な音の大きさ(音量感)
■聴覚の特性
例えば音楽を聴く際、音量を絞るとボーカルの音は聞き取れるのにベースやシンバルの音がやたら聞き取りづらくなります。これは、人間の耳が小音量の時は中音域に比べて低音域と高音域が小さく聞こえる(大音量の時は低音域と高音域が大きく聞こえる)という特性を持っているからであり、人間の耳が音量差と周波数特性を分けて考えられないことを意味しています。
人間の耳は音量差と周波数特性を分けて考えられない
つまり、人間の耳には聞こえやすい周波数と聞こえにくい周波数があり、周波数によって聞こえる音の大きさが変わると言えます。
人間の耳は周波数によって聞こえる音の大きさが変わる
この、人間の聞こえやすい周波数と聞こえにくい周波数をグラフに表したものを等ラウドネス曲線といい、主観的な音量感であるラウドネスを客観的に判断する指標とされています。
等ラウドネス曲線:人間の耳の周波数特性をグラフにしたもの
■等ラウドネス曲線

等ラウドネス曲線は、基準とする1000Hzと同じ大きさに聞こえる音圧レベルを周波数ごとに結んだものです。赤い線がラウドネス曲線であり、音の聴覚的な強さ(ラウドネスレベル)をフォン(Phon)という単位で表します。
等ラウドネス曲線:基準とする1000Hzと同じ大きさに聞こえる音圧レベルを周波数ごとに結んだもの
例えばラウドネスレベルが20Phonの場合、基準とする1000Hzと同じ大きさに聞こえる音圧レベルは20dBとなり、ラウドネスレベルは音圧レベルに等しいということが分かります。
基準となる1000Hzのラウドネスレベルはその音圧レベルに等しい
しかしながら、60Hzでは60dBの音圧レベルが必要となっており、同じラウドネスレベルでも低い周波数ではより大きな音圧レベルが必要となるのがわかります。
同じラウドネスレベルでも低い周波数ではより大きな音圧レベルが必要
言い換えると、人間の耳は同じ音圧レベルでも低い周波数は聞き取りづらいとも言えます。
人間の耳は低い周波数が聞き取りづらい
逆に最も音圧レベルが低いのが3000~4000Hzであり、いわゆる中域と呼ばれる周波数帯は人間の耳で最も聞き取りやすいということがわかります。
人間の耳は3000~4000Hzの周波数が最も聞き取りやすい
しかしながら、4000Hz以上はまた音圧レベルが上がっており、低い周波数同様、高い周波数もまた人間の耳は聞き取りづらいと言えます。
人間の耳は高い周波数も聞き取りづらい
■オーディオにおけるラウドネス
放送業界や音楽業界では、ラウドネスメーターと呼ばれる等ラウドネス曲線などを考慮した人間が感じる音量感を測定するメーターにてラウドネスの値を計測します。その単位はLUFS(Loudness Units, relative to Full Scale)であり、1LUFSは1dBに相当します。
LUFS:Loudness Units, relative to Full Scale
1LUFS=1db
そもそもラウドネスという言葉が一般的になったのは、欧米の放送業界が番組コンテンツとCMの音量を出来る限り近づけようと人間の体感音量に基準値を設けたことにはじまります。具体的に言うとその値は-24.0LUFSであり、現在日本の番組やCMもまたこの数値を超えないようにすることで体感音量が均一になるよう整えられています。
こうしたコンテンツの再生音量を決められた値に落とし込む仕組みまたは機能をラウドネスノーマライゼーションと呼び、現在では放送業界だけでなく音楽、特にストリーミング業界で多くのサービスが活用しています。
ラウドネスノーマライゼーション:コンテンツの再生音量を決められた値に落とし込む仕組みまたは機能
例えばApple Musicは-16.0LUFS、YouTubeやAmazon Musicは-14.0LUFSがその基準値とされており、ラウドネスノーマライゼーション機能によりすべての曲の音量はこの値へと強制的に揃えられます。
これにより、異なる音圧で録音されていた楽曲がすべて均一化され、曲変更のたびにユーザが音量調節をする必要がなくなりましたが、反面、制作側が意図して作り上げていたダイナミクスが失われ、音楽的な強弱や迫力などが犠牲になるといったデメリットもあります。
ラウドネスノーマライゼーションにより音圧が均一化されると制作側が意図して作り上げていたダイナミクスが失われる
これを回避するために、ユーザ側がラウドネスノーマライゼーション機能をOFFにするといった方法もありますが、制作側は強制的に音圧を変えられるくらいなら最初からその音圧つまりラウドネスノーマライゼーションの基準値にあわせた楽曲作りをするといった動きが一般的になってきました。
具体的に言うと、ミキシング時やマスタリング時に音圧を上げすぎず、ピークメーターやRMSメーターだけでなく、今後はラウドネスメーターにもしっかり目を向ける必要が出て来たということになります。
強制的に音圧を変えられるくらいなら最初からラウドネスノーマライゼーションの基準値にあわせた楽曲作りをする
■おわりに
ちなみに、その昔のオーディオ機器には音量を下げても迫力ある音で聞けるラウドネスコントロールという機能が搭載されていました。これは人間の耳が音量が小さいと低い周波数と高い周波数が聞き取りづらくなるという特性を逆手に取り、音量を下げると同時に低い周波数と高い周波数を持ち上げるというものでしたが、音量を上げると逆に音質が崩れてしまうためか昨今の機器にはほとんど見られなくなりました。今思うとこの機能こそが現在のラウドネスノーマライズの始まりだったのかもしれません。
最後まで読んで頂き有り難うございました。あくまで個人的備忘録ですが、何かしらの参考になれば幸いです。
いいなと思ったら応援しよう!