
『ケアを紡いで』のカメラマンのはなし
テロップのないことが新鮮なドキュメンタリー
語り手☘️田中圭さん
聞き手🌙朝山実(写真撮影も)
カメラマンではあるが、田中さんはジブンが専門職だ、という意識がつよくあるわけでもない、らしい。
なんで?
「カメラがよかったねえ」
と、最新作『ケアを紡いで』(大宮浩一監督)の評判は高く、監督の大宮さん(『夜間もやっている保育園』など)は取材を受けるたび、カメラのことをイイね、イイねと言われるものだから、もうスネてしまっているという(といっても監督自身が見込んだ選択眼の正しさを確認できた嬉しさ混じりのそぶりだろうが。たぶん)。
はじめて会った田中さんは、ほわあん、としている。
話を聞いていくうち、なんで?の事情が理解できてきた。
日本映画学校(現・日本映画大学)の学生時代、撮影も編集も映画制作の現場で必要なことは学んでいるので一通りのことはできる。
ただ、どれをとってもやれている自信があるわけではない。
だから『ケアを紡いで』の企画の話が監督からあったときも「助手くらい、、」の立場で入るつもりでいた。
そしてどうも自分が撮るらしいとわかり、あわててカメラを購入した。それまでは仕事のたびレンタルでやりくりしてきた。
自分のカメラはナシなん?
「自分がカメラマンという意識が薄いんですよね」

撮影©️朝山実
インタビューのこの日、彼女が持参してきたのはポケットに入るムービーカメラだった。
「これを買ったのは、母親がガンとわかったときなんです」
え!?
その話はおいおい聞いていく。

ドキュメンタリー
©️大宮映像製作所(場面写真も)
映画『ケアを紡いで』で印象に残るのは、テロップがないことだ。試写で観終わった最初のときにはゼロだと思ったくらい。
もう一回、インタビューするので見なおしてみると、わずかに部分的についてはいた。
二度観て「いい映画やなあ」あらためてそうおもった。
あっちいったりこっちいったり、まとまりきらないところはあるけれど、主人公の看護師さん、このひと前に会ったことがあるみたいに思えた。
主人公の「ゆずなさん」は舌がんの手術で舌の左半分を切除し、太腿の筋肉を移植している。撮影しはじめたのは手術から日数が過ぎ、トレーニング(すごい頑張り屋さんなのだろう)により発声できるまでになっていた。けれどすこしモゴモゴとしている。
ゆずなさんは、朗らかにゆっくりと話す。テレビだとぜったいテロップで補足するだろうというところに、それがない。だからスクリーンに対して、こころもち前傾になる。
聞こうというふうな姿勢にさせる。
そこがこの映画全体の空気をかたちづくっているように思えた。カメラの距離感も、とてもしぜんに見えた。
今回そのカメラマンである田中圭さんに話をきいた。
🌙まず聞きたいなぁと思ったのは、カメラを向けながら田中さんは何を思っていたのだろうか。
撮影中には話しかけたりされていたんですか?
☘️今回はカメラマンとして呼ばれていたので、できるだけ話しかけないように心がけてはいたんです。だから自分から話しかけるということは少なく、ゆずなさんから話しかけられたら返すという。
🌙田中さんが話している部分は、映画の中ではカットされている?
☘️ちょっとだけ、わたしの笑い声が入っていたりしますね。
🌙きょう同席されている映画配給会社「東風」のMさんが話していたことですが。ゆずなさんが結婚式をされた際のプランについて話しているとき、「女性だったらこうしたいというイメージがありますよねえ」と話しかけ、「いえ、わたしはないです」という返答が聞こえる。で、ゆずなさんが笑う。
このやりとりをMさんが面白いと言っていて。わたしも印象に残っていた場面で、「いい映画だなあ」とおもったシーンのひとつです。それでカメラマンにインタビューしてみたいとおもったんですね。
☘️ああ、そうなんですか。でもわたしはないなあと思ったので、そのまま言葉にしたんですよね。
🌙そういうのも含めてやりとりが自然ですよね。とても。
☘️わたし、今回が初めてなんです。全編、撮影を担当したのは。
『島にて』(2019)という前作は大宮監督との共同監督で、カメラマンは前田大和さん。わたしは、カメラはぜんぜん回していなかったですし。『桜の樹の下』(2015)という初監督作品のときも半分くらい。前田さんがカメラマンで、半分を撮ってくれている。
今回、大宮監督に呼ばれたときには、わたしの役割は助監督とか録音かなと。
カメラと言われはしたんです。でも、きっと誰かを呼ぶにちがいないと。
ええ。自己評価が低いんです。
ずっと自信がないままやってきたので。ふだんメイキングとか、ちょっとした記録撮影の仕事はするんですけど。
最初、この企画で大宮監督に呼ばれたときには、もうひとり編集マンの方がいて。三人で会ったときに誰がどの役職とは決まっていなくて。もうひとりの方は撮影もできる人だったので、ふたりでどっちが撮影するか決めてというような。だから、まさか自分がという。
何となく補助的な立場を想像していたら「次はカメラ持ってきて」と言われ。もうひとりの方はスケジュールが合わず、だったんですよね。
東風のMさん🐢ちなみに監督の取材日に、記者のみなさんが「カメラがいい、いい」というので、ちょっと監督がすねて見せていたんですよね。もちろん本心じゃなく、嬉しそうにですけど。
☘️ああ、そうなんですか。
それで一回目の撮影のときも、このあと別のカメラマンが撮るんだろうなぁと思いながら。これはわたしが撮るんだと腹をくくったのは、二回目からで。
そうなんです。しかも一回目の撮影は、使われる可能性が高いんですよね。ドキュメンタリーは。
これはヘンなカメラでは行けないというので、レンタル屋さんでSONYのZ150というデカいのを借りていったんです。これだと癖もないし、ほかの人が撮るとなっても(色調を)合わせられるだろうと。
それで次も撮るとなったときに、初めてカメラを買ったんです。NX80というのを。
大丈夫ですかね、こんな話していて。
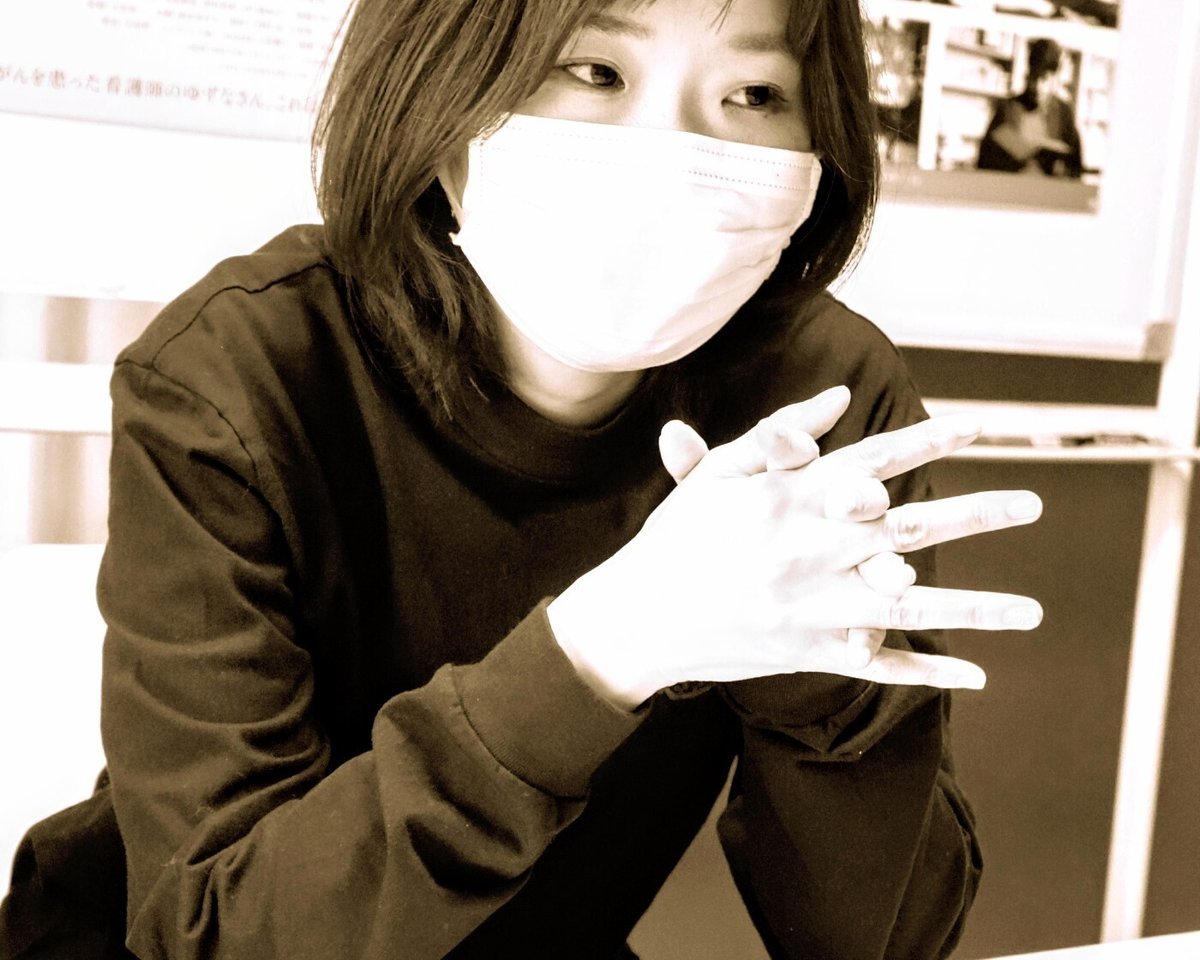
田中さんはしきりに「わたしより上手い人はたくさんいるから」という。
インタビューの最初に、ポジションがわかっていなかったということが不思議におもえたが、これは日本の映画の制作現場を表しているエピソードでもあるようだ。
とくにドキュメンタリー映画は予算がないため、現場は2人体制がめずらしくない。
ディレクターがマイクを持ち、カメラを回しながら照明も考える。制作コストの問題とは別にカメラが小型化、高性能化した結果、そういうことができてしまうようになったことも大きい。
そういえば同じ東風配給のドキュメンタリー『私のはなし 部落のはなし』の満若勇咲監督に話をインタビューした際、彼はカメラマンだけど監督に専念するために撮影は師匠にあたる辻智彦さんに頼んだという。
そのときはカメラマンが監督をするということをかなりイレギュラーなことだと捉えていた。そして今回、田中さんの話をきいてようやく、そんなに不思議なことでもないというのが掴めてきた。
☘️スタートとストップのボタンを押せるのは、カメラマンだけなんですよね。
現場で監督が「回して」と言えないときもあって、あとで「なんで回してなかったの」と怒られることもあるんですよ。察するものなんだと。
劇映画だと、監督の「よーい、スタート」がないと始まらないんですけど。ドキュメンタリーは、カメラマンが監督のエリアに足を踏み入れていることがあるんですよね。
はい。今回、大宮監督はカメラは回してないです。次の新作映画の企画に入っているんですが、そこではけっこう回しているんですけど。はじめてじゃないですかね。
Mさん🐢大宮監督とは東風の初期の頃からご一緒していますが、大宮さんがカメラを回しているのはなかったんじゃないかなあ。
🌙ゆずなさんに初めてカメラを向けたのは、いつからになるんですか?
☘️映画の最初のほうに出てくる、病院に行くクルマの中だったと思います。
撮影期間じたいはすごく短かったんですよね。二か月はなかった。撮影回数も16日。
そのうちゆずなさんがいるのは7日間。彼女が入院したあとは、彼女が通っていたナノ(「地域で共に生きるナノ」:ゆずなさんが暮らす埼玉県三郷市で、ハンディをもった人たちを支援するNPO施設)の人たち、まわりの人たちをインタビューに行ったりしていました。

🌙結婚式の映像とかを中に挟んでいるのは、なるほど、そういうことなんですね。
☘️そうですね。
🌙ところで、彼女のことばが聴きづらいからテロップを入れよう、というのではないところが作品としてよかったです。無いことが新鮮にも思えました。
☘️テロップは、わたしも今回はなくても大丈夫かなあと思っていたんですが。どっちかというと『島にて』(高齢化が進む山形県酒田市の離島「飛島」で唯一の男子中学生と教師。老人ばかりでなく新たに島に移住、Uターンしてきた若者たちを映したドキュメンタリー)のときにそれは思いましたね。方言が伝わりづらいかなあというのは。あれもテロップが無いですよね。
それで、ゆずなさんの話している、ボイスレコーダの音のところだけはテロップが入っていると思うんですが。わたしがカメラを回しているときは、ピンマイクをつけてもらっているんですね。

舌がん手術について説明する
ゆずなさん。
「ケアを紡いで」より
🌙聞き取りにくいこともあるということでは、日常よくあることだというか。あと、最後のラストカット。彼女のはちきれるようないい写真で終わっているのがよかった。カメラを向けながら、田中さんはどんなことをおもっていました?
☘️はじめに大宮監督からこの企画の話を聞いたときに、「いまの自分を見てもらいたい」と彼女が言っているというのを聞いて、わたしの母ががんで亡くなっているんですけど、その闘病中一緒に生活していたので、まず母のことを考えたというか。
このひとが何か残そうとしていることを応援したいなと思って。
そんな想いはありましたね。
母が52のときです。2009年に亡くなっているので、14年前。わたしが21歳。
闘病生活も、年齢が上だったので長かったんですよね。ゆずなさんのように若いとがんの進行は速いんですけど。
そういう想い入れもあって、カメラを買ってしまったんですよね。
ええ。買っちゃいました。
それで、きょう何を話せばいいんだろうと考えていたら、初めてわたしがカメラを買った、母の闘病を撮るために買ったのをきょう持ってきたんですけど。
そうなんです。こんなに小さい。ザクティといって、これを。
いま見たら画像がすごい粗いんですけど。母が亡くなる一週間くらい前に買ったんです。
探しだしたら保証書も出てきて。購入が2009年5月。母の命日が5月8日だから、そんなに撮れてなかったんですね。
その後はぜんぜん使ってないです。画像はいまのケータイのほうがきれいですし。これは1000万画素ですから。
バイト代で買ったから、2万とかじゃなかったかなあ。

🌙映画を観た、ゆずなさんの印象ですが。彼女一見ほわっとしているけど、しっかりしたひとだなあとおもいました。
☘️ゆずなさんはすごく気をつかわれるひとで。ひとの前ではシャキッとしていたいというのはあったのかなあ。
わたしも、この映画は「つよい人の映画」なんだろうなあというイメージがあって。
わたしが母を撮ろうと思ったときも、人はこんなにつよいんだと思うことが何度かあったんですよね。
それは、母は「ガン友仲間が言うんだけどさあ」と話していたんですけど。そう。「ガン友」って。笑っちゃいますよね。
そのとき(母が)クチにしていたのは「頑固な人しかガンにはならない」って。
その後もわたしは、バイト先で仲良くなったひとがガンになったりして。そのたび、頑固なひとがなるんだなぁという印象があって。
悲劇のヒロインになるようなタイプの人じゃない。
残された時間にアレをする、コレをしたいとプランを練っていく人が多かったりして。ゆずなさんも身体がつらいだろうに、富士山に登ったりするし。
生きようとするエネルギーがすごいなあというのを母のときに感じていたのと、今回話があったときに、きっとこれを残したいというのは、このひとの意地というか、力強い映像になればいいなあと思っていました。
🌙彼女はカメラを向けられている間、「病人」ではあるのだけど映画を観ている側に病気を忘れさせるところがあります。不思議なほど自然体で。印象的なのが、申請していた障害者認定が下りたという報告をスマホで受けたときの、笑顔。はじけるような。やったあ!という。
たしかに医療費負担が軽減するので安堵したということですが、すごく前向きで明るいひとだと驚かされる。
☘️そうですね。あと、ゆずなさんとは会ったときに、なんとなく波長があいそうというのはありましたね。
どういうあたり?
、、、話していて、前から友達だったような。年齢がちかいというのもあったのと、ゆずなさんも、「田中さんは話しやすいです」と大宮監督にも言ってくれていたみたいで。ふたりきりの時間をつくってもらって、部屋で撮影しているところがあるんですね。
🌙ノートに、ゆずなさんが「やりたいことリスト」を書いてあるのを映しているときですか?
☘️ああ、そうです。
🌙スカイダイビングとか書いてあって。病人じゃないみたい。
☘️そうです、そうです。あのときは大宮監督が「話してきてもいいよ、1時間くらい外で待っているから女子会してきなよ」と言ってもらって。
あの日はナノから帰ったときで。結局、監督はクルマで2時間くらい待っていたんですけどね。

「ケアを紡いで」より
気球に乗りたいというのは、あのノートには書いてなかったですね。でも「わたし、気球に乗りたいんですよ」とは話してました。
最後に出てくるあの気球は、ええ、ホンモノです。
あれは、ゆずなさんが乗ろうとして予約していたんですよね。翔太(夫)さんとゆずなさんとで。二泊三日でホテルも予約して。
でも、入院してしまったので、翔太さんは日帰りで友人と見にいったんです。
あの気球には、人も乗ってます。(宣伝の)デザインしてくれた成瀬さんも、素材だと思っていたと言われたんですよね。

「ケアを紡いで」より
🌙後半、ゆずなさんが障害者認定を受け、ナノに通いはじめます。そこからの彼女は「ナノの利用者のひとり」として脇役っぽくなります。
☘️ゆずなさんは観察するというか。ナノのひとたちを見ているのが面白いということを言っていたんですよね。
ふたりで話していたときに、認知症のおばあちゃんとスタッフのかかわり方だとか、通っているひと同士のやりとりが面白いと言っていて。
ゆずなさんは、看護師の目であそこの人たちを観ているんだなぁと。
🌙歩行が難しいおばあちゃんに、スタッフが「365歩のマーチ」を歌いながらスッと立ち上がらせ、ゆっくり一歩ずつ歩かせる。それを見ていたゆずなさんが、ああこうすればいいんだ。これを後輩に教えたいとつぶやく。いい場面ですよね。
☘️そうですね。
この映画の撮影中に印象深かったことですか?
うーん、、、撮っていて興味があったのが、谷口さん(ナノの発起人)の息子さんが高次脳機能障害でナノにいて、ゆずなさんがナノにかかわったことでどういう変化が起きるのか。そこは個人的な興味もあってカメラを向けていました。
ゆずなさんがあそこにいることで微妙に、言葉にはしにくい変化があるのかなぁというのは、そのあとも見ていかないといけないのかもしれないと考えながら。
あれだけいろんな人が入っているナノという場所には、たぶん出会いと別れは頻繁にあると思うんです。それが、どんな変化をもたらしていくのかなぁという。
実感としては、あるように思うんですけど。それは自分の期待がそう思わせるのか、ちょっといまは、、、
そういうのは気になっていた部分ですね。
あと、印象深かったのは、谷口さんがこの映画はゆずなさんのお母さんに見せたいと言っておられて。谷口さんも大宮監督も、ゆずなさんの親の世代でもあるので。親のことが気になるというか。
この映画を見ることで、ゆずなさんがどんなふうにナノで暮らしていたのか。そういうものを知ってもらえるんじゃないのか。谷口さんが、そう語っていたのが印象に残っています。


谷口正幸さんが描いたイラスト
「ケアを紡いで」より
🌙お母さんにインタビューするというのは案としてなかった?
☘️それは大宮監督の判断で、インタビューはしませんでした。
🌙なるほど。たしかにまあ、誰しも家族に話を聞かれるというのは嫌かな。
田中さんが監督した『桜の樹の下』も、そういえば老朽化した団地に暮らすお年寄りたちを撮ったドキュメンタリーですが、現時点にしかカメラを向けていない。いま、ここにいる人たちにだけ絞ってカメラを向けるということでは共通していますね。
ゆずなさんという、ひとりの人間を描くのに集中して「いま、ここ」を撮るという方法論もあるなあと、観ておもいました。
生い立ちや家族のことはわからずとも、それはそれというか。生い立ちや学校時代に遡るのを必須とする人物ドキュメンタリーとは逆の描き方になるけれど。
あと何か聞かれなかったけど言っておかなきゃ、ということがあれば?
☘️ええっ、、
Mさん🐢AYA世代(医療や介護制度のサポートのない若いがん患者)とか、がん患者と家族の話というふうに映画を分かりやすく説明は出来るんです。ただ、この作品に限らず、テーマやイシューでなく、「いい映画だった」というのがいちばん伝えづらい。宣伝もしづらいんですよね。
大宮監督の取材で立ち会っていたときに印象的だったのが、
「ケアという言葉は看護や介護だけでなく、(監督がナノで感じたこととして)黙って見守っているということ。隣ではなく、ちょっと離れたところから気にかけているということもケアなんだよね」というふうに話されていて。ああ、そういう関係性っていいなあ。
わたしはナノ、楽しそうでいいなあと思いながら見ていたんですよね。そういうことも伝えられたら。
🌙楽しそうでいうと、ナノのみんなで道路の向かいにあるスーパーにお昼の買い出しに行くところ。思いおもいに総菜など買って帰るだけなんだけど、ゆずなさんをまじえ「何買ったの?」「アジフライがあったかい」とか、遠足みたいなかんじがよかったですね。
☘️ああ、あれ。そうですね。
🌙わたし、ひとン家にいったら、玄関の靴の様子が気になるんですよね。きちんと整列されていたり、ごちゃごちゃっとしていたり。いい悪いでなく、その家の空気が感じとれる。カメラマンも、たぶんそういうふうに見たりしていることが多いんじゃないですか?
☘️そうだ、と、思います。わたしは、あの日、横断歩道のないところを身体の不自由なひとが渡るんだということにびっくりしました。えっ!?と。撮っていいのかなあとかヒヤヒヤしながら。
🌙ちなみに、田中さんはおばあちゃん子ですか?
☘️あ、そうです。何かに書いてありました?
🌙いえ、そうかなぁと。過去の作品なんかを見ていて。
☘️むちゃくちゃおじいちゃん、おばあちゃん子でした。一緒に住んでいて。祖父は20年前、わたしが中学生のころ、祖母は3年前に亡くなりましたけど。祖母が大正12年生まれで。92歳。
祖父は材木屋さんで。静岡でやっていたんですけど、戦争で燃えてしまって、そのあと民宿をやっていたんです。静岡駅から徒歩圏内だったこともあり。
わたしが4歳くらいのころに一緒に住むようになって、静岡からこっちに出てきたんですね。それまではわたしが風邪とか日いたりすると、そっちに送られるんですよね。祖父はヘビースモーカで、よく競輪や競馬、競艇に連れていってくれては、帰りの電車賃まで使いはたしてました。
きょうだいは姉がいて、ふたり姉妹ですね。
家では、ケイ。呼び捨てです。
ゆずなさんも、おばあちゃん子で、ふたりでよくおばあちゃんトークをしていました。ナノにTさんというおばあちゃんがいて、あのおばあちゃんカワイイよねえ。ぜったいあのひとお嬢様だったんだろうね、と言ったりして。
そうそう。片付けをしていたら、母のカメラが出てきたんですよね。母は写真部で、フィルムのカメラ。FUJIの太陽電池式です。日光に照らしているとバッテリーが充電される。それが出てきたので、たまに旅行なんかするときに持っていって撮ったりしています。

おばあちゃんといえば、おばあちゃんたちの野球を撮っていたんです。
いま(そのひとは野球を)もうやめちゃってて、若い、女子プロ野球の選手だったひとを撮っているんですが。撮ろうと思ったのは、戦後まもなく女子プロ野球ができて、二年くらいで消滅するんですけど。そのときの選手たちがご存命で話を聞けるというので。
わたしも野球をやっていたので。
ええ。硬式野球です。
ポジションはセンター、ああでも、ぜんぜんうまくないのでレギュラーじゃなかったんですけど。
それで、撮影をはじめたときにはまだおばあちゃんたちも、キャッチボールとかやっていたんですよね。それを大阪まで撮りにいっていて。
1950年にできたときに、13歳だったのかな。そのひとは。だからもう90代かなあ。
でも、キャッチボールしていたんですよお。
グランドに来るまでは、杖をついてヨロヨロしているんですけど、ボールを握るとちゃんと投げてるんです。すごいなあ、と。
でも、そのおばあちゃんたちも何年か前にやめてしまって。あまり映像も撮れていなくて。
その後、女子野球の本を書かれている谷岡雅樹さんという方から、こういう人がいるから行ってみたらと教えてもらったのが、最近まで女子プロ野球の選手だったひとで。けがでやめた人なんですけど、そのひとを撮っています。
完成したらぜひ観てください。

【後記 : これは余談だけれども。戦後まもない頃にあったという女子プロ野球のはなし。へえー、と驚きとともに、うちの姉に子供のころキャッチボールの相手をしてもらったのを、あとあと思いだした。
父とボール遊びをした記憶はないが、しゃがんでキャッチャーの姿勢で受けてくれた姉には、甲子園の高校野球にも水筒持参で何度か連れていってもらった。姉とは干支が同じで「子供さん?」と聞かれるたび彼女はまたやとムッとしていたけど。
世代的に女子プロの選手だったひとたちと重ねる。なぜ姉とキャッチボールが出来たのか。存命なら、なんで?と聞けただろうが。ユニホーム姿の姉を想像した。そういえば彼女もそうとうに頑固なひとだった。
『ケアを紡いで』は4/1より東京・ポレポレ東中野、4/8より大阪・第七藝術劇場、4/14より京都シネマはかで順次公開(配給=東風)
いいなと思ったら応援しよう!

