
「市井の人たち」を描きつづける上原隆さんにノンフィクションの取材について聞きました。
たえがたき「ある一日」を紡ぎつづける作家の話「後編」ですなんてヒドいことを聞いてしまったのか?
長いインタビューの間に、質問したあと自身で「ああ…」とうなだれることがあるという。
読者としても、このひとは、すごいことを聞くんだなぁと思う。
しかし、そのヒドい質問ナシには人物記は芯を欠いたものになる。
そうしたスリリングなやりとりが、上原さんの短編コラムの魅力でもある。
聞き手・文=朝山実
写真=山本倫子
ツライときに支えとなるゲンカイ哲学って?
上原さんに聞いた。前回の「前編」から読みたい👉こちら

上原さん(以下同)「私がいう限界哲学は、まず哲学者の鶴見俊輔さんが『限界芸術』という言葉をつくったものからきています。鶴見さん自身はマージナルアートと言っていたんだけど。限界芸術というのは、たとえば羽子板やカルタのようなものを美しいと感じる土台があり、その上にポスターとかの『大衆芸術』、さらにその上に絵画などの『純粋芸術』がある。
鶴見さんは、美意識というのは羽子板が楽しいというような日常生活に根ざしたものを土台にして養われるんだという。それにならって私は、困ったときの占いだとか何々頼みといった生活の根底にあるもの、その人を支えるものを『限界哲学』と呼んで肯定するようにしています」
──上原さんの考える「限界哲学」は、ツライとき、究極の判断を迫られたときに、生きる支えとなるものということなんでしょうか?
関連するかどうかわかりませんが、上原さんにとって、「市井の人たち」を取材して書くということは、相手を支えるものであるとともに、ご自身を支えるものになっているということはありますか。
「うーん、どうかなぁ。今回『恋し川さんの川柳』という話(新聞に川柳を投稿するのを生きがいにしているひとり暮らしの男性)を書いたんですが、最後に『川柳のどこがいいんですか?』と聞いたら、人をオッ!といわせるのが楽しいんだという。それを聞いたときに、この人は私だと思った。
もの静かなんだけど、川柳の話になると急に急に言葉数が増える。彼は夕方スーパーで惣菜を買い、近くの銭湯に行き、アパートに帰宅するとリュックからメモ帳を取り出し、大学ノートに書き写し、そこから葉書に五句を選んで鉛筆を走らせる。見ていて、喜ぶポイントが自分も同じだ、と(笑)。
よく読者から『ここには人生がある』とか褒めてもらうんだけど、私としては『彼と彼女と私』を読んで、これは村上春樹のことかと、どこで気づくかなぁと思っている」
──えっ、そうなんだ(笑)。未読のひとにはネタバレになってしまうけど、「彼と彼女と私」は、いまは世界的に有名な作家と若い頃に親しくしていた国分寺駅近くの本屋さんの半生を綴った話で、最後まで作家の名前は出てこないけれど、読者が彼が誰なのか気づいたとたん、場の色合いが変わってみえる。でも、そこを気づいてほしいと思っているというのをうかがって、そうか上原さんもそうなんだと安心しました。すごい俗物っけがあるんだと。
「俗物なんです。『あんた何様?』。ブッシュ(元米国大統領)にインタビュー許可をとるのに苦労する女性の話は、じつはもっと面白い話がいっぱいあったんだけど、これは『プラダを着た悪魔』だと思った。
映画ではメリル・ストリープからアン・ハサウェイがいじめぬかれるんだけど、ハサウェイの主観で描かれた原作も面白くて、そう思った瞬間から、真似をしたいと思い、話を一点に絞り、ああいう構成にした。40年以上も昔の日記をもとにした『定時制グラフティ』は、『アメリカン・グラフティ』のマネだし」
──なるほど。構成を練るところを、書き手としてはひそかに楽しんでいる。しかも今回の本は、話によって書き方が一様ではない。定点観察記や同行するルポがあるいっぽうで、いま言われた『あなた何様?』のようにモノローグを軸にしたものなど、たしかに手が込んでいる。これまでの本と違って、「どうだ、俺はこんな球も投げられるんだぞ」といわんばかり、ミラクルピッチャーぶりを印象づけられました。
「ミラクル。うふふふふ」

──異色といえば「有名人」という一編は、「有名であることは気持ちがいいんだろうか?」という好奇心の一点で、芸能人などの発言を収集していく。まったく誰にも直接インタビューせずにまとめたものだけど、これが面白い。もともと著名な人を取材対象にして来なかった上原さんが「有名人」を書くとこうなるのかと。
「まだ若い頃『上野千鶴子なんかこわくない』という本を出したときに、自分には有名になりたいという欲望があると思った。同時に、有名になりたいというのはどういうことだろうとひっかかっていたんです」
──一度、過去の本で政界を引退された政治家をとりあげられたことがありましたよね。編集者のリクエストで。テレビにもよく出ていた人物だけど、上原さんはその人のことをよく知らなかった。それで一計を案じ、散歩しながら話を聞こうとする。
上原さんらしいのは、そうして「現場」をつくりながら、周囲のひとが彼に気づくかどうか、彼がどう反応するのを探っていく。見方によっては取材者として、すこし意地が悪い。結局、誰も目をとめず、彼もまた自然なこととして受け入れている。わたしは、そこでこの人物に対して好印象を抱きました。

本と映画の検索カードを作成している。
収納空間は限られ、読みおえた本は一度処分する。
「必要になれば探せばいい」
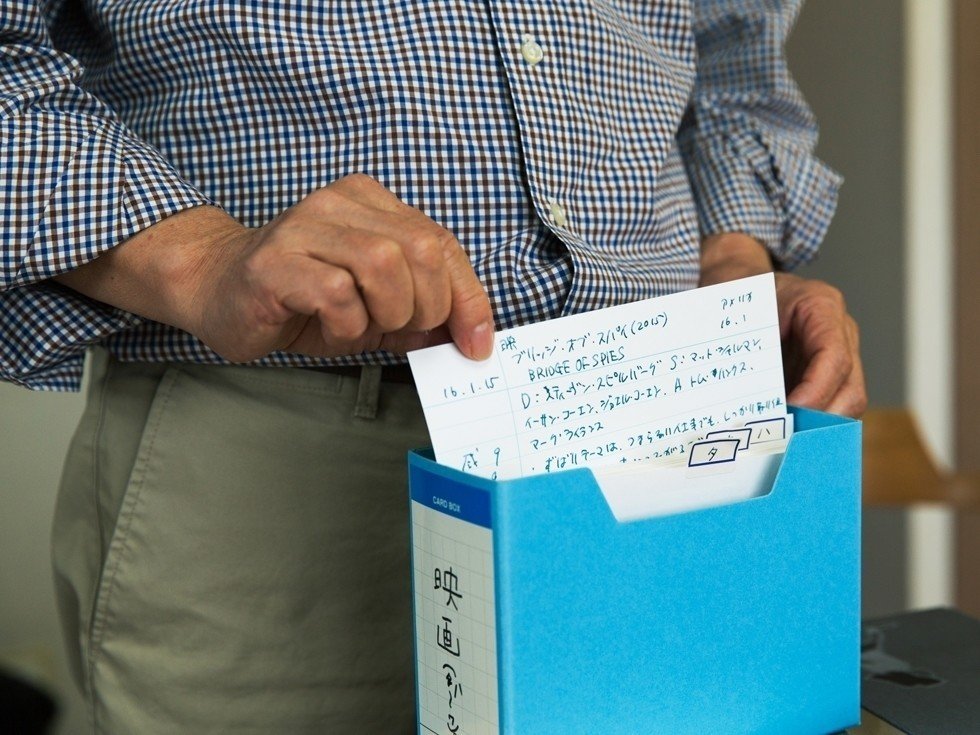
「私には依頼は来ないけど、たとえば『AERA』の『現代の肖像』のようなものを書かないかという話がきても、自分には書けないだろうなと思う。挫折したところを書きたい。だけど、そういうのは書いてはいけないように思えるからだけど……」
──あの頁をやっていたことがあったんですが、著名な人物であることが必須で。挫折がありバネにしていまがある。そういうまとめ方を求められる。Ⅴ字回復のドラマですね。
「それが嫌なんだな。回復していない。まだどうなるのかわからない。その渦中にあるというのではダメなんでしょう? 『まいったなぁ』という瞬間をいつも切り取ってきているんだけど、これが永遠に続くのかもしれない。そう思うとやりきれなくなる。そういうのを書きたい」
──取り上げる意味がない、と言われそうだなぁ(笑)。
話は異なりますが、取材者の「私」がときおり出てこられますよね。自然なかたちで登場する。
「出るか出ないかは、構成のときに決めているかなぁ。出すのは『私』がないと間が持たないときだとか、この質問が大事だというときですね。さっきの村上春樹の話だと『お知り合いの人がノーベル賞候補になっていますが、どう思われていますか?』といった質問をする」
──読んでいて、ドキッとするようなことをストレートに訊かれますよね。実際にあのように質問されている?
「実際に聞いています。そう。よくよく考えたら、ひどい質問だったりするんだけど。ひどいといえば、重い障害をかかえた子供を育てられている作家の打海文三さんにも、『子供が死んでホッとされていますか?』と聞いたことがあったな」
ここから先は
¥ 200
最後までお読みいただき、ありがとうございます。 爪楊枝をくわえ大竹まことのラジオを聴いている自営ライターです🐧 投げ銭、ご褒美の本代にあてさせていただきます。
