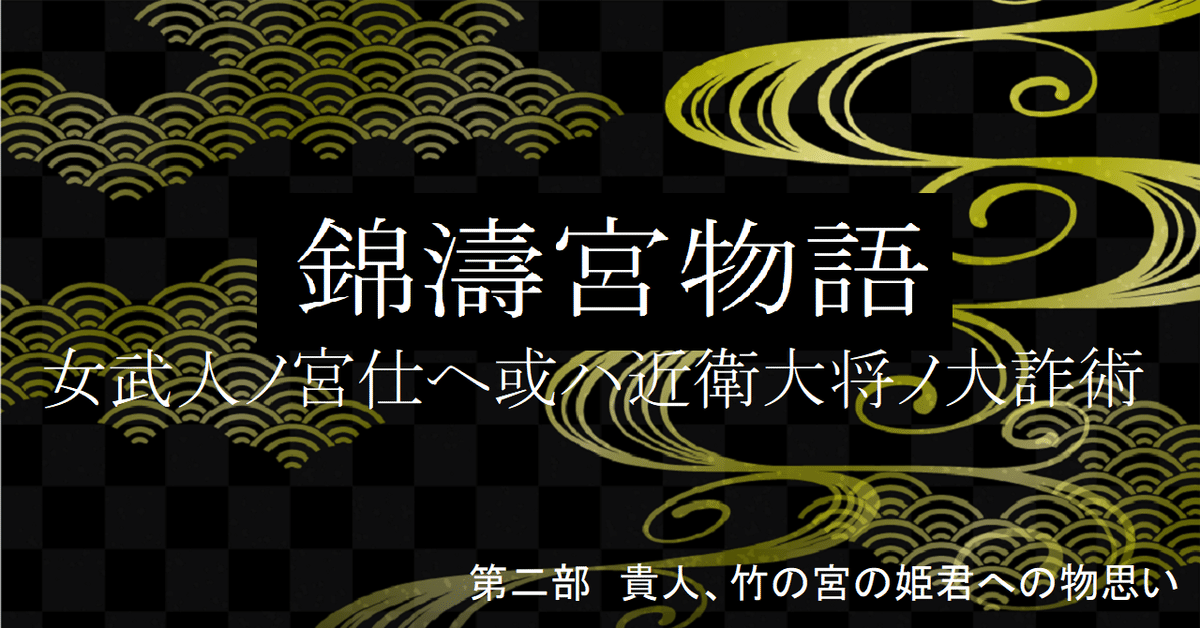
四十二 白狼、字を習う
暦の上では梅雨も半ばを過ぎている頃だった。早い年ならそろそろ明けてもいい頃だ。
だが、ここの所ずっと雨がしとしとと降り続くばかりで終わりが見えない。邸内に倦み疲れた空気が漂っている。
姫君もこの天気を鬱陶しく思うのか、夜になるまで御簾から出て来て白狼と話すことが多かった。
庭の木の葉を水滴がぽつぽつと叩く。その音に耳を傾けていた姫君が、ふと傍に立っていた白狼を見上げた。白狼の手には、真名の学び書がある。
「白狼、真名の勉強は進んでいますか?」
白狼は肩を竦めた。
「元から知ってる字はあるが、知らない字が多いな。覚えようとしているが、ごちゃごちゃしてる字は頭に入りにくい」
「ごちゃごちゃした、とは画数の多い字のことですか?」
「そうだ」
「元から知っていた文字とはどのようなものですか?」
「物の名前だな。米、金、衣……」
「そう……」
「わりとごちゃごちゃした字も知ってるぞ。酢、塩、鏡、角盥、燭台……」
姫君が首を傾げているのは、そこに何の共通性があるのか分からないからだろう。白狼の説明は単純だった。
「つまり、貴族の家から盗んだら、後で市場で売れる物だ」
姫君は複雑な顔で息を吐くよりない。
「そうですか……」
「これくらいの真名なら書くこともできる。手元にどんな品があるのか記録を付けておく必要があるからな」
姫君が微笑んだ。
「白狼の手蹟を見てみたいわ。ここに文台と硯箱を持ってこさせますから、書いてごらんなさい」
白狼は書き物を始めたが……。姫君が慌ててその手を止めさせた。
「ちょっと待って、白狼。いつもそんな風に筆を持っているのですか?」
鷲掴みした筆を白狼が目の高さまで持ち上げて首を傾げる。
「……? 特に意識したことはないが? これで書けるぞ」
「単純な字は書けるでしょうけれど……。画数の多い字はその持ち方では書き辛いでしょう?」
「ごちゃごちゃした字はあまり書かないな。書く必要に迫られれば仮名で書く」
姫君はこめかみに指を当てた。
「白狼はここで真名を習得するのですよね? 真名を書ける筆の持ち方を教えましょう。書くことで覚えやすくなります」
いいですか、と姫君は教え始める。
白くて細い自分の指の先を、白狼の太くて無骨な指に添えた。そうして筆の持ち方から矯正していく。
白狼は不思議なものを見ている気分で自分の手を眺めた。姫君の指は、ひやりと冷たいが決して不快ではない。そして、自分が盗み出したどの宝玉よりも輝かしく、どんな高級な布よりも滑らかな感触がする。
姫君は幼子に諭すように声を掛ける。
「筆は横から握るのではなく、上からそっと指を立てて持って。手首はまっすぐにして動かしてはなりません。筆先は紙に触れるか触れないかくらいで……」
「面倒だな……」
「慣れれば苦になりません。まずは書いてみましょう。この本の中でどの字を知らないのか教えてください」
「『天地』……この字は知ってるし書ける。『宇宙』……ってのは知らないな。ええと、『雲騰』?」
「雲がおこるという意味です」
「ここら辺の、このごちゃごちゃしたのは何だ?」
「『曠遠緜邈』? 簡単に言えば風景の様子ですが……。あまり日常生活で使う言葉ではありませんね。白狼には馴染みが無いのも仕方がない……」
白狼は手習い用の見本の文字列から、一つ文字を指さした。
「あ、この字なら分かるぞ。意味は”貴族の気まぐれ”だ」
「……え?」
姫君は白狼の指先を見た。そこには「仁」の文字があった。
白狼は皮肉気な顔をする。
「朝廷に円偉って奴がいるだろう? そいつがときどき貧民街で粥を振る舞う。その時に役人たちが書きつけを振りかざすからそれで覚えた。『円偉様が仁に基づいて施すから有難く思え』って意味の文章を読まされるからな」
「仁というのは思いやりとかそういう意味です。円偉は貧しい民に粥を食べさせているのでしょう?」
「確かに粥を食ったその時は腹が膨れて助かるが。だが、腹ってのは時間が経てばまた空くものだ。なのに、その仁の粥が次にいつ貰えるのか分からない。円偉の気まぐれで決まるから」
白狼は鼻を鳴らした。
「その円偉より俺の方が役に立ってるぞ。皆の食べるものが無くなったら盗みに出かけるから。みんな円偉の粥より俺の腕の方をあてにしてるさ」
「……」
「円偉ってのは佳卓に並ぶほど偉いんだって? だが、佳卓のやり方が理にかなってる。あいつは食べていく手段である仕事を与えるから。こっちの方がずっと助かる。誰だって仕事さえあれば自分で自分を養える」
姫君は不意を衝かれた顔をし、少し黙って考え込んだ。
「前から一つ聞きたいと思っていたのですが……」
「何だ?」
「白狼は何もできない者をどう思いますか?」
「……?」
「白狼は恩を返すことを重視し、情けを受けることを厭います。でも、誰もが皆、恩を返せるわけではありません。武芸や商売、農作業の仕事に耐えられる健康があるとも限らないのです」
──何が言いたい?
白狼は姫君をじっと見つめ、彼女が悲しく、寂しそうな表情を浮かべているのを見て気づいた。
──そうか。自分の出した何気ない話題は、彼女を傷つけてしまったのだ。
佳卓が職を与えたことで白狼の手下は暮らしていく──暮らすことができる。だが、この女は、いつ健康を取り戻せるかも分からないのだ……。
「白狼はわたくしに逃げていればいいと言いましたね。ですが、逃げても逃げても、わたくしが弱いままで、誰にも何もしてやれない人間であり続けることもあるかもしれません……何もできないままであれば、白狼はわたくしを軽蔑しますか?」
「いや……。そんなことはない」
そんなことはないと白狼は思う。その理由について説明が必要だとも思う。ただ、言葉が出てこない。それでも、違うのだということは伝えたい。
「……俺が嫌いなのは、最初から人からの情けを当然だとして人から何かを毟り取っているような奴だ。結果として恩を返せないのとはわけが違うだろう……」
彼女のように、生きてあること、ただそれだけで日々精一杯な人間を鞭打とうなど白狼は全く思っていない
ええと……。白狼は首を捻りながら言葉を探す。
「恩を返せる返せないというより……。誰かから何か毟り取っているのに、毟り取られた側の痛みや思いを考えない奴らが俺は嫌いなんだ。民から取り立てた税で贅沢三昧しているような奴らだな。俺は多分……何かを返して欲しいというより、こちらを気遣って欲しいんだろう……」
姫君は「わたくしは……」と言いかけたのを、白狼が遮った。姫君が尋ねたいことは分かっていた。
「その点、あんたはいい主公だ。この前は俺が眠りやすいよう灯火を消そうとしてくれたじゃないか。今だってこうやって字を教えてくれる。あんたはちゃんと他人を思いやれる人間だ」
そうだ、この女は本来なら心優しいのだ。俺の方こそ……。
「俺が『恩を返せ』と口にするのが、あんたに重圧になったのかもしれないな。だが、俺はただ……あんたに気概を持っていて欲しかったんだ。あんたは、折角いいものを持っているから」
「そうですか……」
「俺も悪かった。俺が恩の遣り取りにこだわるのは、それは俺の料簡が狭いからだ。本当に偉いのは、恩を受けたから返す奴じゃなくて、先に恩を与える人間だ。報われるかどうかにかかわらず、人に恩を差し出せる人間の方が偉い。佳卓がそうだな。俺を捕らえるだけで、あいつは十分手柄を立てた。だが、あいつは俺の手下全員の職を用意してくれた」
それから、と白狼は続けた。
「俺があんたに話した人間なら、翠令という女武人もそうだ」
「錦濤の御方の従者の?」
「ああ、あいつが嬢ちゃんを主公と定めた時には、嬢ちゃんはただの流罪人の子だった。先行きの分からない幼子を守ると決めて、実際刀で守ってきた。あの嬢ちゃんに仕えたところで栄達が見込めるわけではなかったが、そんな損得勘定抜きで嬢ちゃんを守ってきた翠令は大した女だと思う」
「錦濤の御方は幼くして両親と死に別れています。翠令はその方の母親のような存在なのでしょうか?」
「まあ、その例えが近いかな。翠令の情の濃さは世間が『母性』と呼んでるものに近いんだろう。俺はその言葉が嫌いだが」
「何が何故嫌いなのです?」
「『母性』という言葉が嫌いだ。無償の愛情を女親の特性のように言うのが嫌なんだ。俺を生んだ女は別に母性なんてすばらしい愛情を持ち合わせてはいなかったから」
姫君はふっと顔を白狼からそむけ、しばらく無言で庭を見た。その悲しそうな瞳に、白狼はまた何か自分が彼女を傷つけるようなことを言ってしまったのかと慌てる。
「おい、あんた……。何を考えてるんだ?」
姫君は少し躊躇い、そして恐る恐るといった様子で白狼に顔を戻した。
「白狼が自分の母親を嫌うなら、わたくしのことはもっと厭わしく思うでしょう……」
「なんでだ?」
姫君は眉根を寄せてぎゅっと瞳を閉じる。袖の中で拳も握りしめたようだ。
「わたくしは我が子を殺すような母ですから」
白狼は思いがけない話題に顎を引く。
「殺す? あんたが?」
わたくしは……と続けようとした姫君の声は震えていた。
「わたくしは……あの子を産んでやれませんでした……わたくしの腹に宿った子を……。生きていれば錦濤の御方と同じくらいの年齢でしたでしょうに……」
「……」
佳卓から聞いた話では、姫君は自分を襲った先帝の子を身籠ったが出産には至らなかったという。それが錯乱の直接の原因だとも。
「あの子は……半分はあの豺虎の子でしたが半分はわたくしの子。いえ、あの子はあの子で親とは別の命です。なのに、わたくしは産みたいとは……心の底から産みたいとは思えなかった……」
「……」
「望んで身籠った子ではありません。産んでも愛情を掛けて育てる自信がありませんでした。だから、お産の時に力を出し切れなかったのではないかと悔いています。あの子が生きて生まれなかったのはわたくしのせい……」
姫君は唇をきつく噛んだ。これ以上自分の唇に歯を立ててしまうと、紅ではなく自分の血で赤く染まってしまいそうなほどに。
「よせ。あんたのせいじゃない」
「でも……。あの子は……」
白狼は頭をぼりぼりと掻きながら言葉を探した。
「俺は男で妊娠したこともないが……。お産はよく見た」
姫君が怪訝そうな声で問うた。
「白狼が?」
「庶民てのは、こんな大邸宅には住んじゃいないからな。壁一枚隔てた家の中で妊婦のうめき声はしょっちゅう聞いた。あんたは他人のお産を見たことないんじゃないか」
姫君は小さく首を振る。
「……ありません」
「だろうな。これまでいっぱい見て来たが、お産に上手い下手はない。どんな女も始まってしまえば全力でのたうち回る。唸り声を上げながらな」
「ええ……わたくしも苦しかった……その苦しみに挫けてしまって……」
「挫けるも何も……。途中で止めたいからって止められるもんじゃない。身体が自然と産み出そうとする。俺も何度も妊婦が痛くて痛くて『もう嫌だ』『産みたくない、止めたい』って泣き喚くのを聞いたもんだ。だが、そう叫んだからって止められるもんじゃない」
姫君は目を見開いた。
「そんなことを口にする女君もいるのですか? わたくしだけかと思っていました……」
白狼はからからと笑った。
「いっぱいいるさ、そんなの」
笑い飛ばされた姫君は、少しばかり呆気にとられた風に呟く。
「そう……そうなの……」
「身体の弱い妊婦だと途中で力尽きることがあるな。そしたら産婆が腹の上に乗って出すこともある。周囲が妊婦の周りで手伝うのはそのためだ。あんたは身分が高いんだから助けだって大勢いたんだろう?」
「ええ……」
「それから、腹の子だって自分で産まれようとするもんだ。俺の周囲は娼婦ばかりだったからな。望んで妊娠することの方がまれだ。妊娠が分かるやいなや何とかして堕胎できないかと試みることも当たり前だった」
「……」
「母親が堕胎しようとしても産まれる子は産まれる。俺がそうだ。反対に、身ごもっているうちに胎の子に愛情が芽生えて産みたいと願う女もいるが、それでも産まれないときは産まれない」
白狼はしっかりと姫君の目を見て断言した。
「どうにもならないことというのは、人の世にどうしてもある──ただ、それだけだ」
「それだけ……」
「俺があんたを厭うかって? それはないな。あんたは、産んだ後に愛情をかけられなかったらどうしようと案じる殊勝さがあるじゃないか。俺の母親は堕胎を何度も試みたし、産まれた俺をさっさと捨てた。まあ、仕方ない。出て来たのがこんな妖のような容姿で、赤子の頃から普通の子じゃなけりゃあ、ますます育てる気をなくしたんだろう。……ああ、別にあんたがそんな顔をすることはない」
姫君は我がことのように辛そうな顔をしていた。
「俺のことは気にするな。生れて来たからには俺の人生だ。俺は俺が納得行くように生きてきたし、結構楽しんでる」
「親の愛がなくても?」
「娼婦街の子ってのは親の愛とは縁が薄い。まず、父親ってのがいない。母子だけだ。その母から捨てられても、なんとなく育つもんだ。屋根があるところで過ごして、娼館のまかないの余りを食って、娼婦の誰かや妓楼の主人、下男たちが構ってくれてりゃいつの間にか大人になってる」
「……」
「あんたは、もし産んだ子に愛情を持てなかったとしても、屋根や食事の手配はしてやっただろう。それから……明るくて眠り辛そうなら灯火を消してやったり、文字を教えたりはする……だろう?」
姫君は淡く笑んだ。
「……そうですね……」
「それだけできれば十分だ。別に愛情不足じゃない。愛情なんて子どもが育つのに必要十分あればそれでいいんだ」
姫君は聞いた言葉をかみしめるように、しばし目を瞑った。黒く長い睫毛がふるふると震えていた。
しばらくしてから、そっと瞼を上げて白狼を見た。小さく、それでいて真情の籠った声で囁くように礼を言う。
「ありがとう……」
「いや……」
正面切って礼を言われると居心地が悪い気がした。こちらの方こそ、この生真面目な女に荷が重いことを言っていたのだろうに。
「俺の方こそ……。さっきも言ったが、恩を返すことをあまり思い詰めないでくれ。俺が恩を返すことを大事にしているのは、返した方が気楽になれるからだ。誰かのためというより、きっちり返す自分が好きだからそうしてるだけだ」
だから、この女が必ずしも恩を返せなくても白狼は軽蔑などする気はない。
ただ、この女は、できれば誰かに恩を返したという実績があった方が本人のためにいいのではないだろうか。
「あんたも俺に似ているんじゃないかと思った」
「わたくしと白狼がですか?」
「あんたも健康ならそういう性格なんじゃないか。『感謝はしても見下されたくない』って意地があるところが、俺に似ているような気がした。だから、その意地を活かして生きる方が、あんたに向いているんじゃないかと思ったんだ。ま、なんだ……そもそも、あんた自身のためだから俺にどう思われるかなんか気にするな」
「ありがとう……」と言いかけて、姫君は止めた。つい先ほど姫君の礼に白狼は気まずそうな顔をしたばかりだ。だから姫君も、正面から礼を言ったところで白狼が素直に受け取らないと気づいたのだろう。そこで、少し違った方向から白狼を褒める。
「白狼のような男君であれば、妻になる女君は幸せでしょうね」
「なんだ?」
「不安を和らげてくれますし、哀しいことや辛いことも白狼は慰めるのが上手です。きっとよい夫になるでしょう」
「へえ……」
白狼はこそばゆい思いでそれを聞いていた。照れ臭いが、この女にそのように評価されるのは、心のどこかが痺れるように心地いい。
しかし、姫君は思いがけないことを言いだした。
「そう言えば、白狼にはそういう相手はいないのですか? 翠令という女武人を褒めていましたけれど、その女君が白狼にとっての特別な女君なのですか?」
白狼は浮かび上がっていた気持ちが一気に地に叩き落されたような衝撃を受けた。目の前が暗くなる。ただ、なぜ自分がそのように感じるのか、その理由が分からない──。
