
『かなめ石』上巻 七 清水の石塔 并 祇園の石の鳥井倒事
寛文二年五月一日(1662年6月16日)に近畿地方北部で起きた地震「寛文近江・若狭地震」の様子を記したものです。著者は仮名草子作者の浅井了意。地震発生直後から余震や避難先での様子など、京都市中の人々の姿が細かく記されています。マガジンはこちら→【 艱難目異志(かなめ石)】
七章では、清水寺と祇園社の様子が伝えられています。
📖
七 清水の石塔 并 祇園の石の鳥井 倒事

清水の石の塔は、上二重をゆりおとす。瀧まうでのもの、其外さんけいのともがらきもをけし、色をうしなひ、あまの命をたすかりよみがへりたる心地して、下向の道のおそろしさ、いふばかりなし。
※ 「清水の石の塔」は、清水寺の十一重石層塔のことと思われます。
※ 「瀧まうで」は、瀧詣で。
※ 「さんけいのともがら」は、参詣の輩。
※ 「きもをけし」は、肝を消し。非常に驚くこと。
※ 「あまの命」は、天の命。天からの授かり物の命。
※ 「下向」は、高い所から低い所へおりて行くこと。
※ 「いふばかりなし」は、言ふばかり無し。言葉で言い尽くせないの意。

ぎおん
祇園の南門に立られし石の鳥居は、津の国天王寺の鳥居になぞらへ、笠木たかくそびえ、二ばしらふとしく立ならび、額はこれ青蓮院の 御門跡あらはされ給ひ、筆畫ゆたかにめでたくおはせしを、たちまちにゆりくづされ、立や鳥居のふたばしら、地をひゞかしてどうどたをれ段々にうちをれて、額もおなじくくだけたり。
※ 「ふとしく」は、太敷く。ここでは、鳥居をしっかりと立ててあること。
※ 「段々」は、段段。物を細かく切り刻むさま、ずたずたの意味。

八坂の茶屋どもは、鳥居のたをるゝ音にいよ/\肝をけしさればこそ、地の底がぬけて、泥の海になるぞやとて、建仁寺のうしろなる野原をくだりにかけ出たり。

おやは子をすて、兄はおとゝをわすれ、あるひは、わが妻の女房かとおもひて人とめ女の手をひきてにげいで、あるひは、わが子とおもひて 茶つぼをいだきてはしりいで、ふみたをされ、うちまろび、夢ぢをたどる心地して、目くらみ、たましゐきえて、をこがましきありさまどもなり。
※ 「おとゝ」は、弟。
※ 「人とめ女」は、人留女。宿屋の客引きの女のこと。
※ 「茶《ちや》つぼをいだきて」は、茶壷を抱きて。
※ 「うちまろび」は、うち転び。
※ 「夢ぢ」は、夢路。
※ 「たましゐきえて」は、魂消えて。
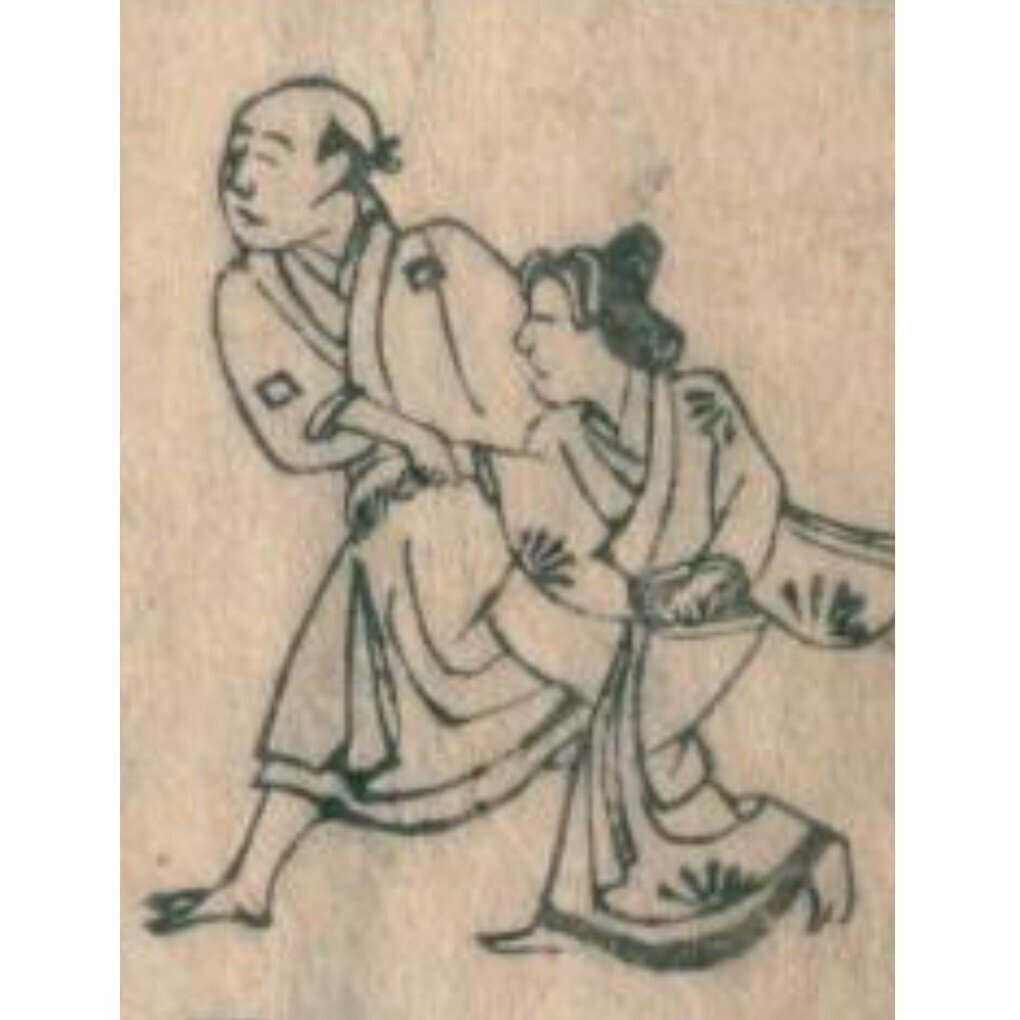
人とめ女の手をひきてにげいで

茶つぼをいだきてはしりいで
茶やにあそび居るわかきものどもは、あわてふためき、あみ笠を手にもち、草履・席駄 かた/\しはき、わきざしをとりわすれ、みだれ足になりてかけいづるもあり。
その中に井づゝ屋のなにがしとかや、年のころ八十四五なるおとこ、はう/\にぐるを見て、ある人かくよみてわらひけり。
としたけて まだ生べしと おもひきや
いのちなりけり 茶屋のながにげ

※ 「席駄」は、せきだ。雪駄のこと。
※ 「わきざし」は、脇差。
※ 「かけいづる」は、駆け出る。
※ 「にぐる」は、逃ぐる。
筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。
新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖
