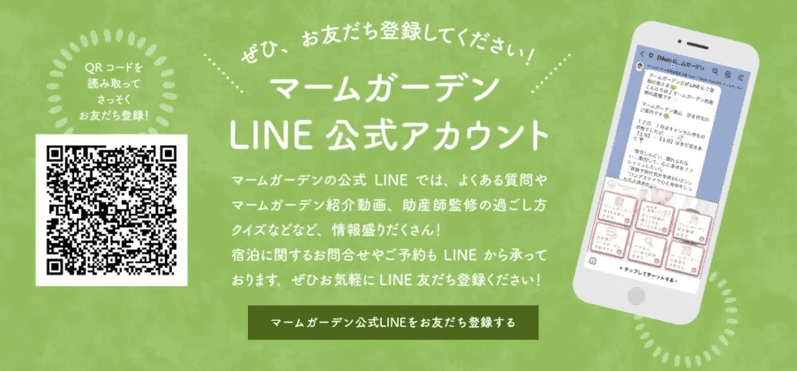マームガーデンスタッフ紹介Vol.4「ママと赤ちゃんが笑顔で安心できる日本で一番満足度の高いサービスを提供したい」
こんにちは!
産後ケアホテル 「マームガーデン葉山」の山口です。
ご好評いただいている、「マームガーデンで働くスタッフ紹介」。
過去には台湾の産後ケア施設でも勤務経験のあるベビールーム担当、簡をご紹介!
日本と台湾の産後ケアの違いや、これからの日本の産後ケアにかける想いをインタビューしました。

簡 麗真(カン レイジン)
プロフィール
資格:保育士、ベビーシッター(台湾の国家資格)
経歴:大学卒業後、台湾の幼稚園(3歳児 〜15人)、児童養護施設(〜18歳)、産後ケア施設に勤務。来日後、マームガーデンの立ち上げから参画。ベビールーム所属。台湾出身。
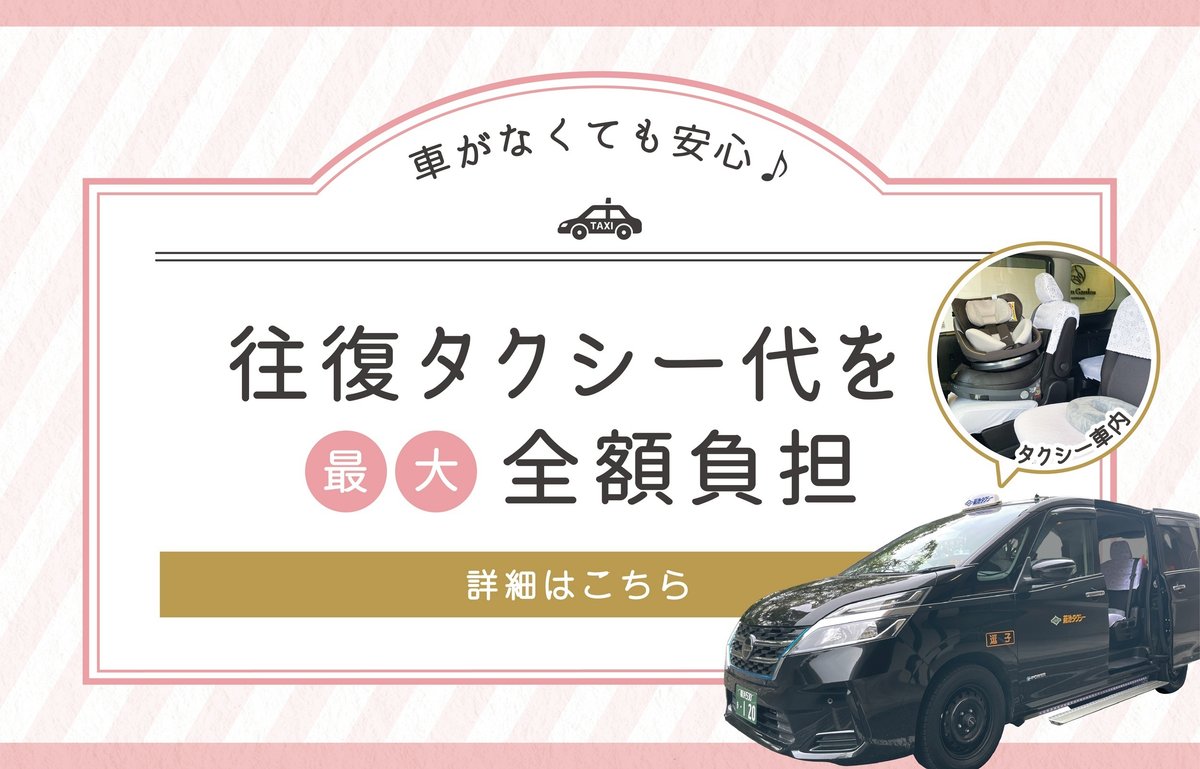
台湾ではどんな仕事をしていましたか

台湾では幼稚園、養護施設、産後ケア施設で働いてきました。
とにかく子どもが好きなので、どの職場もとてもやりがいがありました。
来日の直前まで働いていた産後ケア施設では、赤ちゃんのケアを担当していました。
業務内容はマームガーデンのベビールームと同じで、授乳・おむつ替え、沐浴など赤ちゃんのお世話がメインの仕事です。
その仕事を選んだ理由
実は高校時代、理系の学校で電子を学んでいました。
ですが、ずっと子どもが好きだったので子どもに関わる仕事をしたいという気持ちが強くなり、大学は思い切って保育系に進むことにしました。
大学進学後は希望通りに保育を専攻し、とても学びがいを感じました。
大学卒業後は、幼稚園・養護施設・産後ケア施設と子どもに関わる仕事に従事してきました。
子どもは純粋です。だから話していてとても楽しいですし、辛いことがあっても赤ちゃんや子どもたちの顔をみるととても癒されて頑張ろうという気持ちになります。
子どもに関わる仕事を選択してとてもよかったと思っています。
台湾の産後ケアへの意識
出産後はとにかく体を休ませなければいけないという共通意識が国民にあり、子どもが生まれるたびに産後ケア施設を利用してママは産後の体を回復させます。
特に徹底しているのが、産後1ヶ月程度は外出も控えるよう指導されることです。
体を冷やすこともよくないので、昔は髪を洗うことも自粛する人が多かったです。夏でも冷たい飲み物や食べ物は控える。母乳の栄養のために薬膳スープをとることも台湾や韓国の文化のひとつですね。
そして「産後のママをケアすること」は当たり前の意識です。
産後ケア施設を利用する際は、必ずパートナーも一緒に宿泊してママのサポートをします。
パートナーは無料で宿泊できますし(食事は別途準備が必要)、ほとんどの人は家から近い施設を選び、パートナーは施設から仕事に通います。
台湾の産後ケア施設側の体制

台湾の産後ケア施設は医療施設という位置付けです。
週に1〜2回は、医師が回診にきたり医療面での体制も整っています。
赤ちゃんの命に関わる仕事なので、働いているスタッフは年に1回必ず国の心肺蘇生法研修を受けます。そのほかにも、1ヶ月に1度は各施設単位で看護師長による産後ケア研修を受けます。
ここで知識の補充や共有をおこないます。
また台湾では産後ケア施設で働くためにはベビーシッター資格が必須です。
ベビーシッターは国家資格で条件が年々厳しくなっています。
資格取得には離乳食の作り方、救急対応、衛生面、遊び方など子どもに関わる知識全般が必要です。
孫の面倒を見るためにベビーシッター資格を取得する人もいますし、男性のベビーシッターも割と多いです。
国の制度として、ベビーシッターを利用する場合、申請すると補助金を受けることができます。そういった制度を利用してベビーシッターを雇い、復職される方がとても多いです。
台湾では、ママひとりが担うのではなく、さまざまなサービス、家族からの協力など、子育てをしていくための制度や意識が根付いています。
マームガーデンで働くことの面白さ、やりがい

日本が好きなので、日本の保育士として働いてみたいと思い来日しました。
しかしビザの都合で保育園に就職することは叶わず、ホテルで働いていました。
縁があり、マームガーデン事業責任者の斎藤さんとお話しする機会がありました。まだマームガーデンが開業することが表向きになるよりも前のことです。
斎藤さんから、日本で民間の産後ケア施設を葉山にオープンすること、開業に向けて動き出そうとしているという話を聞きました。
「ぜひ働きたい!」そう思い、立ち上げメンバーとして参画させていただき開業準備から携わり今に至ります。
開業までに、さまざまな想定をして運用ルールを考えてきました。
それでも、開業してからは想定外の事案も数えきれないほどありました。
うまくいっていることでもママや赤ちゃんにとって過ごしやすい場所にしたいという想いから、何度もルールや運営方法を見直して改善してきました。
そういう中で、ご宿泊されているママやご家族の方から「ありがとう」「助かった」という言葉をいただけるのはとても嬉しいです。
そして何よりも、ママや赤ちゃんが笑顔になってくれることが一番のやりがいです。
また、私は台湾人なので中国語が話せます。
マームガーデンには中国人のお客様もご利用されますが、母国語で会話ができて相談できるのはお互い安心感があると思いますし、中国語が話せることが私の強みの一つだとも思っています。
日本の産後のサポート、産後ケア界の課題と今後の展望
台湾では産後ケアを受けることは当たり前ですが、日本でも同じくらい当たり前にしていきたいです。
産後は心身が辛い時期。それでもママは頑張り、辛くても赤ちゃんの面倒をみていきます。産後の赤ちゃんのケアはママもパパも一緒にやっていけるような文化になるといいなと思います。外部からのサポートが増えることもママの安心につながると思うので、産後ケアが広く普及して欲しいと思います。
マームガーデンは、2022年12月で開業から1年が経ち、開業から多くの人にご利用いただきました。
もっともっとサービスをよいものにしていきたいし、ママと赤ちゃんが安心して過ごせる日本で一番満足度の高い産後ケアサービスを提供していきたいと思っています。