
世界で一番好きな(のかもしれない)音楽⑪/The Smiths Complete
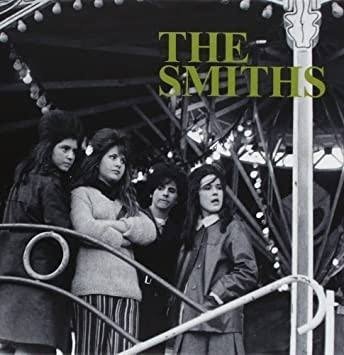
10代の頃に聴いておくべき音楽…と言うと大袈裟だけど思春期の頃に触れる方がしっくりくる音楽は少なからず存在すると思ってる。それはただ単に若者向けな若い演者や子供向けという意味じゃなくて、10代の頃に抱える感情の不安定さや日々の退屈さに訴えかけるものを抱え込んだ音楽であると。
じゃあ一体どんな音楽がそれに当てはまるだろうと考えた時、僕の中で真っ先に浮かび上がるのがスミスというバンドだったりする。もし自分がこのバンドを10代ではなく30代、40代になってから初めて触れたとしたら、彼らの音楽が心に響くかと考えると多分響かないような気がする。自分の中に彼らが存在しなかったらと想像するのもちょっと難しいのだけれど、恐らくひたすら単調で退屈なものと感じるか、もしくはギターがカッコいいバンドくらいにしか思わないんじゃないかな。
もちろんサウンドだけでも十分カッコいいバンドなのは間違いないのだけど、そこだけに惹かれたかといえばちょっと違う。Heaven knows I’m miserable nowを15歳の頃に聴くのと、30歳を過ぎてから聴くのとでは音楽の受け取り方は同じじゃないはず。Don’t trust over 30。スミスというバンドに限らないとは思うけど、若い時期にもたらされる鬱屈した気持ちと、彼らの音と歌詞の世界が紡ぐある種の閉塞感(と絶望感)を感じ取れるかがこのバンドに対する接し方とも言える。80年代イギリスといえばフォークランド紛争移行のサッチャー政権によるネオリベの台頭と失業問題が露呈した時代。失業保険で食い繋ぐ若者の生活と言えば「トレインスポッティング」(時代は90年代ですが…)を観ればどの様な状況だったのか分かると思うけど、所謂英国病と言われるあらゆる産業の民営化による経済停滞の時代に現れたのがスミスというバンドだった。閉塞した時代の代弁者であり、マイノリティの視点が普遍性を持っているからこそ時代を超えても受け入れられてるのでは無いだろか。スミスのトリビュート盤のジャケットにイギリスの貧困をテーマに撮り続けるケン・ローチ監督の「ケス」が使われていたのも、彼らのエスプリが後の世代にも受け継がれている。
この10年くらい若い世代のアメリカのインディーズシーンを追っていくと、親世代が聴いていたカレッジチャートの音楽が浸透しているのがインタビューなどを読んでいると見えてくる。たとえばクレイロが親の影響でコクトーツインズを聴いていたり、80年代当時アメリカではメジャーにはならなかったけれど、インディーチャートでは受け入れられていたと思われるものが顕著に影響元として存在感を増している。スミスもそのひとつで、決定的だったのが映画「500日のサマー」で男女が出会うきっかけとしてスミスが登場していたのも印象深い。スミスの音楽は全ての層に行き渡る音楽ではないけれど、カルトとレッテルを貼るには間口の広い人々による共有財産としての存在感を増しているのが、10年代のアメリカを見ていて感じた。そこにはヨーロッパに対する劣等感も含まれた過剰な自意識の裏返しでもあるように思うのだけれど、多分それは日本での受け取られ方も似たようなものなのかもしれない。
僕が10代だった90年代はスミスの影響下にあるバンドが多く、オアシスがデビューアルバムをレコーディングするにあたり、ジョニー・マーが自前のレスポールを貸与していたり、スウェードのバーナード・バトラーがジョニー・マーと同じギブソンのES345を使用していたり、ブラーがスミスのプロデューサーだったスティーブン・ストリートを起用していたりと、多くのバンドにとってスミスという存在が依代になっていた。90年代のイギリスのシーンを追えば必ず行き当たるのがスミスだった。
僕も自然とスミスのCDを手に取ったのだけれど、収録曲を見比べて買ったHatful of hollowを最初に聴いた時は正直全くピンと来なかった。それまで聴いていた60年代や90年代のイギリスのポップミュージックとも感触が異なり、異物感を強く感じた。ハードな音楽でもないし、ブリットポップの様なバブルガムなポップス性も希薄で取っ掛かりになるものが見出せずにいた。その後にレンタルで借りたベスト盤に収録されていたThe Headmaster ritualを耳にして、やっと良さに気付いた。
その後に各アルバムを追っていったのだけれど、キャリアを俯瞰できる様になると彼らの魅力はアルバムではなくシングル曲だというのが分かってきた。当然オリジナルアルバムの方がスミスというバンドの在り方を指し示してるとも思うのだけれど、曲の並びに今でも違和感を感じる。特にファーストアルバムとQueen is deadのA面の緩さが取っ掛かりとしては弱く、両盤の怒涛のB面に比べると冗長さがある。それこそがスミスといえばそれまでなのだけれど、個人的には彼らの魅力が初見でストレートに伝わるかというと難しい。Meat is murderとStrengeways,here we come(アルバムとしてはこれが個人的にはベスト)は先の二枚に比べて纏まりがあるが、バンドのキャッチーさが存分に伝わるかというとこれも疑問が過ぎる。
スミスというバンドの魅力がストレートに伝わるのは、シングルなどをコンピレーションしたThe World won’t listenやLouder then bombの方がキャッチーで取っ掛かりとしては食いつきやすいと思う。しかし、この二枚だけだとStill illやThe Headmaster ritual、Cemetery gates、Last night I dreamt that somebody loved meなどの曲が漏れてしまうため悩ましい。
こういった逡巡からアルバム一枚でなくボックスセットを選んだのは、余す事なく彼らの魅力を掴むには全部聴くしかないのかなと思い至ったからに他ならない。どれか一枚と言うならLouder than bomb辺りから入って、それぞれのアルバムを順に聴くのが一番の近道だと思う。
最後にスミスがユニークだと思うのが、パンク以降のイギリスの音楽シーンで貧困やマイノリティなどをテーマにしつつ、彼らが奏でた音楽ががなりたてたりディストーションの歪んだサウンドを使わずに、リリカルな表現に徹した点だと思う。サウンドがラウドにならざるを得ないアメリカのラジオやMTVを中心としたシーンとは違った表現を追求していたものとは明らかに手触りが異なる。90年代に入るとイギリスのシーンもアメリカのラウドな音楽に飲み込まれていくのだけれど、それだけではない部分はスミスという先達がいた事も少なからず影響していた。他者を圧倒するようなラウドなサウンドに依存せずに、繊細かつ大胆な彼らの世界観は唯一無二だと思うし、二度と生まれることがないものとして未だに君臨している。大きく変わることがない日々の単著さが生み出す鬱屈さを表現した事がスミスの大きな魅力だと聴き始めてから四半世紀過ぎた今でも感じている。
JMXさんによる「The Smiths入門に『Queen Is Dead』がふさわしくない理由。」が面白かったので併せて読んで欲しい。
