
分析型AIは小学校の学級会なのか?
みなさんこんにちは。
このブログは、私が自分自身でゆらゆらと試したり考えたりしたことについて記載しております。
なぜこの記事を書くことにしたのか
昨日この記事を書きながら、覚えた違和感がきっかけでした。
分析型AIが提示してきた記事への違和感
九段理江さんの「悪い音楽」という小説の記事を書いた
準備段階で。分析型AI Perplexityにまとめ記事を書いてもらった
そのまとめ記事に違和感を感じた
自分の視点を中心に記事を書いたが、違和感の原因はわからないまま
「分析型AI」とは?
Perplexityによる、分析型AIの説明
分析型AIの主な特徴は、膨大なデータを高速かつ正確に処理し、複雑な ーンを認識して高精度の予測や推論を行う能力です。具体的には以下 な特徴があります:
1. データ処理の自動化:
人間が処理するのに何時間もかかるような大量のデータを、AIは数分で分析できます。
2. 高度な予測能力:
過去のデータから学習し、将来の傾向を高い精度で予測します。
3. 多様なデータの統合:
テキスト、音声、画像などさまざまな形式のデータを統合して分析できます。
4. パターン認識:
人間が見逃しがちな複雑なパターンやルールを発見する能力に優れています。
5. 継続的学習:
新しいデータを取り込むたびに学習を重ね、精度を向上さ ていきます。
6. バイアスの最小化:
適切に設計されたAIモデルは、人間の主観や先入観によるバイアスを最小限に抑えることができます。
これらの特徴により、分析型AIは企業の意思決定支援、業務効率化、リス 管理など、幅広い分野で活用されています。
Perplexityが書いた記事を評価してみます
1.「悪い音楽」についてPerplexityが書いたまとめ記事

九段理江の『悪い音楽』は、第126回文學界新人賞を受賞した印象的な小説作品です[1]。この小説は、音楽を通して人間性を描いており、主人公は音楽の才能はあるものの、人の心がわからないという設定になっています[1]。
作品の特徴:
1. タイトルの秀逸さ: 「悪い音楽」という言葉は、読者の好奇心をくすぐり、様々な解釈を可能にします[1]。
2. 人間描写の深さ: 主人公は中学校の音楽教師で、人の気持ちがわからない性格の持ち主として描かれています。この描写を通じて、人間のリアルな感情や弱さが表現されています[1]。
3. 独特の文体: 軽やかでありながら、どこか不気味さを感じさせる九段理江特有の文体が特徴的です[1]。
4. 社会への問いかけ: 「人と芸術作品は切り離されるべきか」など、読者に考えさせる問題を提起しています[1]。
九段理江自身は、小説を書くことと音楽を聴くことを生活の一部として捉えており、文字と音楽が共感覚で結びつくことが多いと語っています[2]。彼女にとって、日常で一番感情が動くのは音楽を聴いている時であり、小説においてもそういった感情を喚起させることを意識しているそうです[2]。
『悪い音楽』は、人間の複雑さや社会の問題について深く考えさせられる作品であり、九段理江の才能が光る小説として評価されています[1]。
Citations:
[1] https://miteno.hatenablog.jp/entry/warui-ongaku
[2] https://brutus.jp/riekudan-music/
[3] https://note.com/yoshi_1095/n/n87f669569d07
[4] https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14300507494
[5] https://www.tokyo-np.co.jp/article/300461
2.Perplexityのまとめ記事への、Claude3の所見
なるほど。今拝見させていただいた内容から、確かにいくつか気になる点があります:
1. 作品の本質的な部分よりも、表層的な特徴(「タイトルの秀逸さ」など)が前面に出ている印象を受けます。
2. 引用されているソースの質的なばらつきが気になります。特に知恵袋(Yahoo!知恵袋)のような一般的な質問サイトと、文芸誌や批評家による専門的な批評が同列に扱われています。
3. 「人と芸術作品は切り離されるべきか」という問題提起は確かに重要かもしれませんが、これが本当にこの作品の中心的なテーマなのかどうか、十分な根拠が示されていないように思えます。
Perplexityの回答は、おそらくウェブ上で目立つキーワードや頻出する表現を優先的に拾い上げた結果なのではないでしょうか。文学作品の場合、特に:
- より静かな、しかし深い洞察を含む批評
- 作品の細部に注目した丁寧な読解
- 時間をかけて形成された評価
といったものが、アルゴリズムによる情報収集では見落とされがちかもしれません。
この作品について、あなたご自身はどのような読後感や解釈をお持ちでしょうか?
Claude3さん、なかなか鋭い指摘ですね。
この時点で、Claude3は「悪い音楽」という小説を知らない可能性が大きいです。この所見は、Perplexityの記事から受けた印象のみから作成されていることにも注目しましょう。
Claude3は私にも意見を求めてきました。では、述べさせていただきます。
3.私がこの小説で注目した部分
1.この主人公には、人の行動や発言を受け止めるときに独特な癖がある
・言葉遣いの細かな間違いを気にしてしまう
・相手の発言自体よりも、話し方やそれに伴う体の動きが気になる
・何かをきっかけに、妄想や没頭に陥り、判断を誤ることがある
2.中学校の教師の職責との兼ね合い
いろいろな個性や要望を持つ個々の生徒、父兄、他の職員と良好なコミュニケーションをとることを求められる教師という職業に就くには、この主人公の特性は妨げになるのでは?と心配になりました。
今感じているのはこういうことですね。
分析型AIには、視点の提示と事後のチェックが必要
1.「児童たちの学級会」に陥りがちな分析型AI
その後もClaude3との意見交換は続いたのですが、分析型AIに記事を書いてもらう際には「視点の提示」と「記事の対象について十分な知識を持つ人のチェック」が必要なのではないか、という点で意見が一致しました。
漠然と「○○という作品について述べてください」という指示の出し方だと、集めた記事を漫然と集約し、目立つ表現をあたかも代表的な意見であるかのように表示しただけの記事になってしまいます。
それでは、自意識のコントロールが難しい年代の児童たちの「学級会」と似たようなものではないかと思うのです。
2.比較対象を与えて考察させることで内容が深まります
作品の特徴をいくつかピックアップし、それぞれ似た傾向を持つ作品と比較させる、という方向で書かせる。この方法をとることでPerplexityの強みが生かされます。
小説「越境」について書いたこの記事は、そのような書き方をしています。
3.十分な知識や見識を持つ人のチェックが必要
また、提示された記事を「対話の起点」として活用する。十分な知識や見解を持つ人がチェックを行う。そんなバランスの取れたアプローチが、よい記事を書いてもらうには必要ですね。
もう一つの分析型AI「Genspark」のお手柄
分析型として有名なAIには、Perplexityの他に「Genspark」が挙げられます。詳細な性能や機能 の説明は機会を改めて行いますが、今回は特徴的な機能について説明します。
1.与えた題材について素早くレポートを作成するのが特技
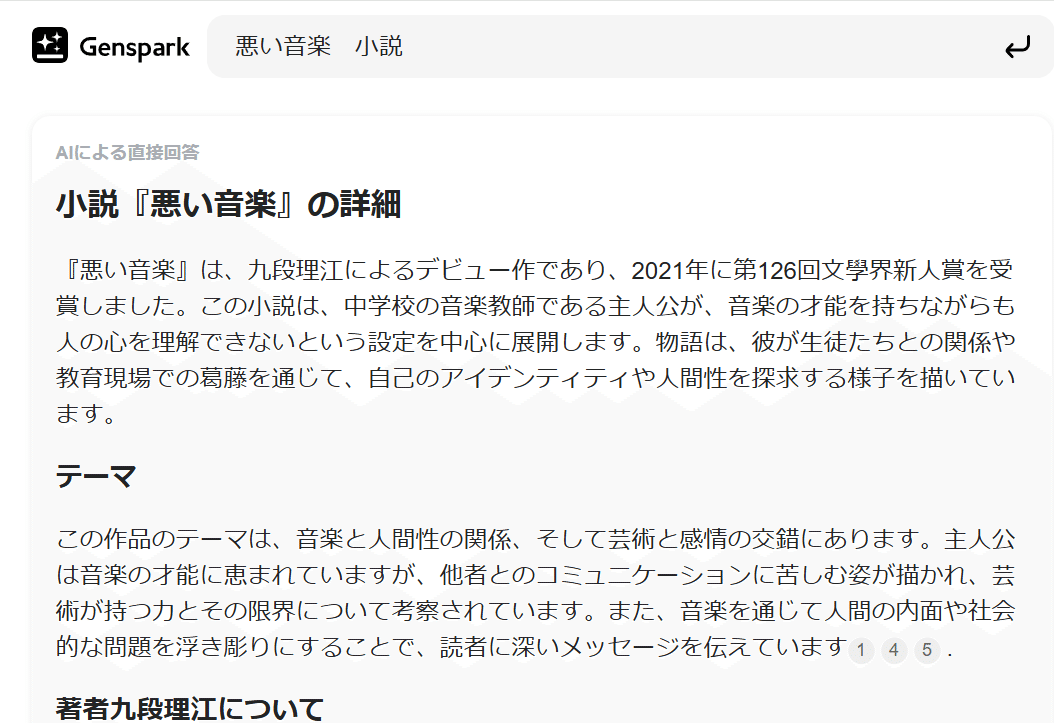
2.まとめ記事に影響を与えている資料の特定を的確にできる

この、noteの短い記事がほかの記事を差し置いて強いインパクトを与えていました。
おわりに
AIに振り回されないよう、思考の軸を鍛えましょう。
分析型AIにはこれまでのAI以上に便利な部分もあるのは間違いありません。 しかし、その挙動によく目を光らせておかないと、意図せぬ方向に議論や思考が流されてしまう危険性もあるように思われました。
AIをめぐる、私たちの学びはまだまだ続きそうですね。
今回も、最後までお読みいただきありがとうございました。
