
源氏物語 夕顔の巻 概略12(惟光の悔い~柔らかな女に更に溺れる)
・ 忠義な惟光
惟光が居所を突き止めて軽食など差し入れに来ました。
五条の家では車の行先どころか女主人が拉致されたこと自体知らなかったので、朝になって大騒ぎしているのですが、源氏の忠実な乳母子である惟光には、主の考えそうなことぐらい、すぐに見当がついたのでしょう。
五条の家の内情の偵察の為に女房の情人として通っていたことが、右近にバレて騒がれては面倒なので、源氏と女君のいる居間の近くには寄りません。
「ここまで御執心とは、あの夕顔の女とはどんなにいい女なのだろう」
「その気になれば、俺が手籠めにしちゃってもよかったんだがなあ」
「俺の女にできたものをお譲りしちゃうとはなあ」
「寛大というのか何というのか、バカなことをしちまったもんだなあ」
と不謹慎なことを思ってしまいます。

・ 夕映えを見交わす
源氏は立ち上がって、たとえようもなく静かな夕べの空を眺めています。
女が庭の奥の方は暗くて気味が悪いと言うので、
御簾の端だけ少し残して、後は下げてやって、また床に戻って怖がる女を抱いてやります。

夕映えを一緒に見ている褥で、
この思いがけない旅寝をまだ不安がってはいるものの、飽くことない源氏の愛撫につれて、そんなことも少しずつ忘れて快楽に没入していくような女の様子が可愛くてたまりません。
自分の施す悪戯が快楽に変わり果てしなく女に沁み込んでいくような柔らかさは、源氏の今までに見知らぬものでした。

そうかと思うとまた、何かをとても恐ろしがって、ひしと源氏にしがみついて離れないでいます。
自分だけを頼りにして離れない女が子供っぽくも見えて、それがまたひどく可憐だと思ってしまいます。
・ 夜が下りてくる
女が闇を恐れるので、格子を早々と下ろして灯りをつけさせます。
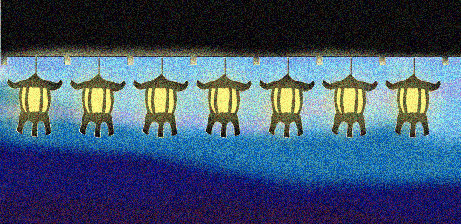
源氏にはまだ歯痒い思いがあり、「こんな風にすっかり残る隈なく契り合ったのに、まだ何か隠されているようで私は辛いのだよ」と恨みを言います。
・ 六条御息所と比較して嘆く
「帝はどんなにか私をお探しだろうか」「皆はどこを探しているのだろう」と案じる余裕もできてきました。
帝の御宸憂ばかりでなく六条御息所のことも気にかかります。
「我ながら不思議な仕儀となってしまった」「六条の人はどんなに思い悩んでおられるだろう」「恨まれるのは辛いが、こんな風に不義理している私が悪いのだからなあ」
いたわしい人として真っ先に脳裏に浮かんだのは六条の貴婦人でした。

翻って、向かい合っている市井の女を見れば、無心で愛らしくて気楽で居心地が良いので、
「あまり思慮深くご立派過ぎる女性は見る者も息苦しくなってしまうのだなあ」「あの方もそういうところを少しなくしてくれればなあ」
と、つい何もかも完璧な六条御息所と比較してしまう源氏です。

Cf.『夕顔の巻』柔らかな女に更に溺れる
眞斗通つぐ美
