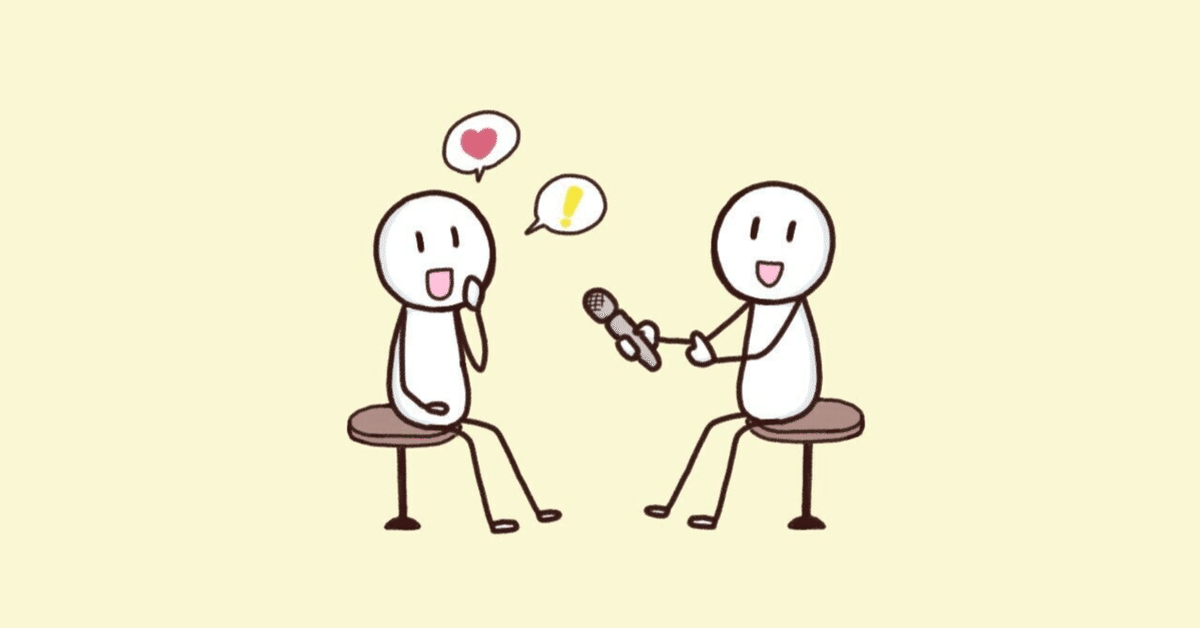
インタビューの極意は「たいこもち」にあり?
相手を怒らせたら取材は失敗
国際政治ジャーナリストの落合信彦さん(いまなら「落合陽一のお父さん」と言ったほうが通りがいいか)は、初期作品『男たちのバラード』(集英社文庫)の巻末インタビューで、「インタビューのコツは相手を怒らせることだ」と語っている。わざと怒らせることによって隠されたホンネを引き出すのだ、と……。
だが、ライター諸氏はこんな言葉を真に受けてはいけない。
相手を怒らせることでホンネを引き出すなどという手法が通用するのは、反体制派ジャーナリストが国家権力のイヌ(笑)を取材する場合など、ごく限られたケースであろう。
ライターがやるような普通のインタビューの場合、相手を怒らせてしまったら、その時点でもう失敗なのである。
むしろ、ライターのインタビューは、「いかに相手に気分よく話をさせるか」が勝負である。ライターはそのために、あの手この手で相手の心をこちら側に向けようとする。
たとえば、相手に著書がある場合、事前にそれを読んでおくのは当然だが、その著書に山ほど付箋を貼ったものをわざわざ持っていったりする。「私はあなたの著書をこんなにしっかり読んで取材に臨みましたよ」というさりげないアピールである。
また、私がよく使う手として、相手がマスコミに登場した記事のうち、ごく早い時期のものをスクラップ・ブックから探し出し、それを持っていったりする。「私はこんなにも前から先生に注目していましたよ」というさりげない(さりげなくもないか)アピールである。
「(黄ばんだ新聞の切り抜きを取り出して)先生は、85年のこの『〇〇新聞』のエッセイの中でこんなふうに言われていますが……」
「お、キミぃ、そんな古い記事、よく持っていたねえ」(と、急に機嫌がよくなる)
こんなふうに書くと、世のライターの中には「たいこもちじゃないんだから、そこまで相手のご機嫌をうかがうことはない」と反発を覚える向きもあろう。
しかし私は、インタビューをする間、ライターはたいこもちに徹してよいと考えている。そこが、社会正義の旗を掲げて仕事をするジャーナリストとは違うところだ。中立公正を旨とすべきジャーナリストは、取材相手のたんなる代弁者になってはならない。が、ライターはむしろ取材相手の「よき代弁者」になることこそが仕事なのだ。
取材を終え、まとめたインタビュー記事を取材相手が読んだとき、「私の言いたいことを、こんなにうまくまとめてくれたライターさんはあなたが初めてです」と言われることこそ、ライターの勲章である。
そのためには取材相手との関係を良好に保ち、気分よく話をしてもらわなければならない。だからこそ、ライターにとっては「相手を怒らせたら取材は失敗」なのだ。
取材相手を論破してはならない
では、そういう私は取材相手を怒らせたことがないのかといえば、じつは何度もある。
失敗例の1つを紹介しよう。
某人気女流作家をインタビューしたときのこと。談たまたまマンガの話になり、彼女が「シバカドふみさんのマンガって、面白いわよね」とのたまった。もちろん、柴門ふみのことである。ただし、いまのように柴門ふみが超売れっ子になる前の話だ。
私は、よせばいいのに「あれは『さいもん』と読むんです」と指摘してしまった。すると、彼女は顔を赤らめ、急に不機嫌になってしまった。そこまではいい感じで進んでいたインタビューが、私の不用意な一言で台無しになってしまったのである。
相手の間違いは、必要があれば原稿の中で直しておけばよいこと。けっしてインタビュー中に指摘してはならない――私は、この失敗でそんな教訓を得た。
同様に、取材相手が自分の意見にそぐわないことを言ったとしても、ライターはインタビュー中に反論してはいけない。
そういう場合は、「でも、先生のご意見とは反対に、『〇〇だ』と言っている人もいますよね?」と別の人の意見という形で反論を言い、インタビューイの再反論を促せばよい。
ましてや、取材相手を論破してはならない。論破すればその場は溜飲が下がるだろうが、その時点でインタビューは失敗に終わるのである。
作家の筒井康隆さんが、エッセイ集『笑犬樓よりの眺望』の中で「インタヴューアー十ヶ条」なるものを披露したことがある。
これがなかなかよくできていて、ライターおよびその卵にはぜひ一度読んでもらいたいのだが、その中にこういう一条がある。
相手の地位や教養が自分より下だと思っても、絶対に表情、言動に示してはならない。インタヴューイの地位は教養、学歴に関係なく、常にインタヴューアーより上
これは、とくにライターにとって肝に銘じるべき言葉である。インタビュアーとインタビューイの関係はけっして対等ではなく、ましてやインタビュアーが上ではないのだ。
ライターの側に「取材してやっている」という傲慢な気持ちがわずかでもあれば、必ず態度や表情、言葉の端々ににじみ出て、取材に悪影響を与える。「取材させていただいている」という気持ちで臨むことが大切である。
