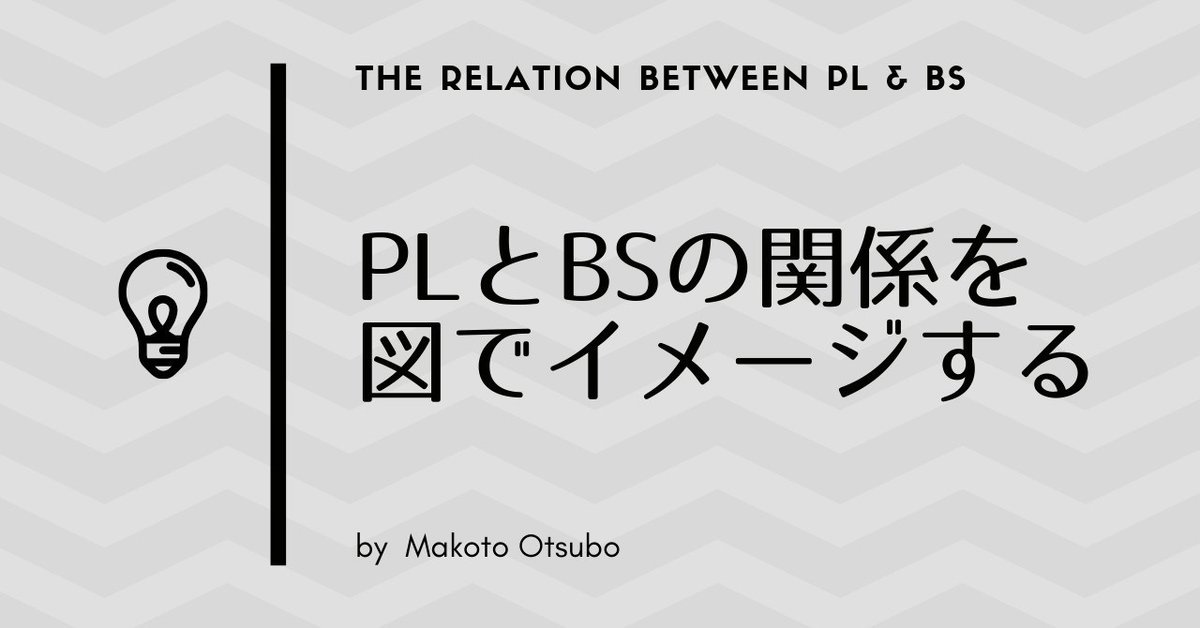
PLとBSの関係を図でイメージする
日本の会計基準では、以下の3つの表を財務三表という。
・損益計算書(PL:Profit and Loss statement)
・貸借対照表(BS:Balance Sheet)
・キャッシュフロー計算書(CF:Cash Flow statement)
これらの表はそれぞれ連動していて、ただ個別に見るだけでは不十分だ。
「PL・BSを読む」というのは、決算書に書かれている言葉や数字の意味を理解するということではなく、
会社のお金の「流れ」を読み、どんな事業がどうやって行われているかを推測するということなのだ。
今回は、PLとBSがどのような関係で繋がっているのかを、ぐっと単純化してイメージしてみよう。
PL(損益計算書)とは
PLは、「ある一定期間の間に得られた収益(≒売上)から、かかった費用を引いた差から、損益を計算する表」だ。

これだけのこと。 とてもシンプル。
当然、収益が費用よりも大きければ、その差は「利益」になるし、
収益よりも費用の方が大きければ「損失」(またはマイナスの利益)になる。
BS(貸借対照表)とは
対してBSは、「ある時点で、持っている財産の状態を、資産・負債、その差額である純資産に分けて表した表」だ。

自分が持っているお金(またはお金に換算できるもの)を、どういう形で持っているのか(資産)を左側に、
それが、いずれ誰かに返さないといけないお金(負債=他人資本)なのか、誰かに返さなくてもいい自分達のお金(純資産=自己資本)なのかを右側に表している。
BSでは、必ず右側と左側の合計金額が同じになる(一般に「バランスする」という)。
CFの話は今回は割愛するが、「ある一定期間の間の現金の増減を計算した表」のことで、PLとBSがあれば作ることができる。
つまり、財務三表で必要なのは、大きく分けると収益・費用・資産・負債・純資産の5つしかない。
はい、これテストに出ます。
PLとBSの間のお金の流れ
このPLとBS、2つの上で、お金をぐるぐると回すイメージをしてみよう。
例えば、銀行から100円借りたとすると、
①借金(負債)が100円増えて、②現金(資産)が100円手に入る。
この現金(資産)のうち80円を使って、売るためのりんごを買うと、
③80円の現金(資産)は、80円の仕入れ(費用)によって、④80円分の商品(資産)に変わる。

そのりんごを100円で売ると、
⑤100円の収益を得られて、⑥現金(資産)が100円増える。
このときの利益は、100円(収益)−80円(費用)=20円だ。
現金(資産)が120円になるから、⑦このときの資産と負債の差額の20円が自分のお金、つまり純資産だ。

⑧20円の純資産から、利子(費用)10円を足して、⑨借金を全額返済しよう。
⑩銀行に110円払った結果、自分のお金(純資産)が、現金という形で10円残る。

ビジネスは、この繰り返し。
負債や純資産を資産に変えて、資産を使って資産を増やして、その繰り返し。
このPLとBSの間のお金の流れをイメージするのが、会計的な視点で考えるということ。
会計の基礎中の基礎中の基礎の基礎。
図を並べて分かったと思うが、ある時点を切り取ったBSを時間ごとに並べると、会社の動きがなんとなく見えてくると思う。
今回の例はあまりにも単純化しすぎていているが、実際のビジネスでも基本のポイントは変わらない。
しかしながら、利益、つまりPLしか見えていないビジネスパーソンがほとんどであるというのも事実だ。
PLとBSを繋ぐお金の「流れ」のサイクルをイメージして、
両方を連動させながら、持続的に事業を拡大し続ける「仕組み」を目指さなければならない。
▼基礎的な会計的視点を身に付けるのにおすすめの本はこちら▼
いいなと思ったら応援しよう!

