
#ギーンおのみは視察する レポVol.1 ―泉南市子どもの権利に関する条例(大阪府泉南市)
※全体的にお堅め、長文注意⚠
※視察ってなあに?って人は、とりまこちらのIG投稿をチェックしてね↓
*****
視察の実施概要
実施日:2024年8月5日(月) PM
視察先:大阪府泉南市(於:市民交流センター)
視察目的:「泉南市子どもの権利に関する条例」の特徴、条例の下で実施されている具体的施策について学ぶ
大阪府泉南市では、2012年に制定された「泉南市子どもの権利に関する条例」の下で実施されている各種施策について、担当所管課(子ども部子ども政策課(※今年より新設)ほか)、小学校長、条例委員会市民委員の皆さんからそれぞれお話を伺いました。具体的な施策として、「せんなん子ども会議」の実施、権利学習をはじめとする子どもの権利を基盤とした公立小学校での取組み、そして、条例の実施に関する検証と公表のシステム等が紹介されました。特に三点目に関しては、子ども条例を制定する複数の自治体(※制定自治体は2023年5月時点で、全国64自治体と決して多くない)においてその形骸化が指摘・懸念される中、条例の実効性を担保するための実施・運用を検証する仕組みが極めて重要との認識から、個人的にも大変関心のある事項でした。

視察レポ
以下、視察を通して得た視点や課題等について大きく三点にまとめたいと思います。
(1) 条例の実施・運用を検証するシステム
「泉南市子どもの権利に関する条例」では第3章第16条において、条例の実施に関する検証と公表に関する事項が定められています。具体的には、条例検証の基本的な視点は「子どもの最善の利益を第一に考慮する」ことにあるとし、
市が条例の運営状況と条例に基づく事業の実施状況を検証すること;
有識者等から構成される「子どもの権利条例委員会」や、子ども及び市民等から意見・提案を募る「子どもの権利条例市民モニター制度」を設けること;
条例委員会及び市民モニターは、相互に協力及び連携して、この条例の運営状況を検証するための活動を行い、条例委員会は市長に対して必要な報告等を行うこと;
市長は、この報告等を広く市民等に公表するとともに、その内容を検討し、これを市の子ども施策等に活かすこと(子どもの権利に関する推進本部)
・・・等が規定されています。
※条例全文はこちら
この条文だけ見ると、大変素晴らしい仕組みのように思えます。しかし、泉南市では条例制定から10年を迎えた2022年に、中学1年生の子どもが自死するという大変痛ましい事件が起こってしまいました。これを受けて提出された子どもの権利条例委員会報告に目を通すと、条例の形骸化をめぐる様々な課題が見えてきます。
視察の際に、条例制定時から10年以上にわたって関わってこられた市民委員の方が、まず課題として指摘されたのは、検証の主体はあくまで「市」であり、市が課題として設定しないものは報告としてあがってこないという点です。市民委員は条例委員会に所属しますが、条例委員会はあくまで市が行う検証に資する活動を担うとの位置づけであり、市民モニターとも交流しつつ、それぞれの場で子どもの権利について学びながら、毎年報告をまとめています。
実際に公表されている最新の「第12次泉南市子どもの権利条例委員会報告」を見てみると、報告事項は三本立ての構成となっており、報告事項Ⅰは条例委員会による条例運営の最も重点的な課題について、報告事項Ⅱは市の実施機関による条例に基づく事業等の自己評価を含む概況について、報告事項Ⅲは市民モニターによる条例運営に対する意見表明として、それぞれ報告する形になっています。条例検証の中核となる報告事項Ⅱで報告される事業は、市が「条例に基づく事業」として独自に設定したものであり、必ずしも子ども関連事業がすべて網羅されているわけではなく、選定基準も公表されていません。この点に関して、市民からの疑念が払拭されないのは当然です。「条例検証のプロセスに、市民の意見・市民的感覚をより具体的に入れ込んでいく」ことは、大変重要な指摘であると思いました。
市民委員の方が強調されたもう一つの点は、子どもの権利擁護を担う大人側の理解がもっと必要であること、そして条例をつくっただけで終わらせない仕組みが必要ということです。これに関連して、子どもの権利条例に求められる5つの機能が紹介されました。
▼子どもの権利条例に求められる機能
①人々が子どもの権利と出会うことができる。
②深刻な現実や課題から目をそらさず、向き合うことができる。
③子どもに優しい街へ向かう道しるべとなる。
④子どもの最善の利益を目指す「市民的対話」が育てられる。
⑤子どもの権利を基盤とする社会モデルアプローチを子ども参加で拓いていける。
上記のうち、①③④は泉南市ではこれまで取組みが進んできた一方、②⑤には依然として課題があるとの認識が示されました。②⑤は特に、権利の主体たる子どもたちではなく、積極的に権利擁護を推進すべきわたしたち大人側の意識の抜本的転換と覚悟が求められる部分であり、「つくっただけで終わらせない仕組み」には不可欠といえます。
なお、泉南市には現状、子どもや市民からの直接申し立て機能が無いため、問題が発生しても議論の俎上にあがらない可能性があることを受け、今まさに子どもの権利侵害にかかる相談・救済システムを新たにつくる(子どもオンブズの導入等)方向で検討が進んでいるそうです。
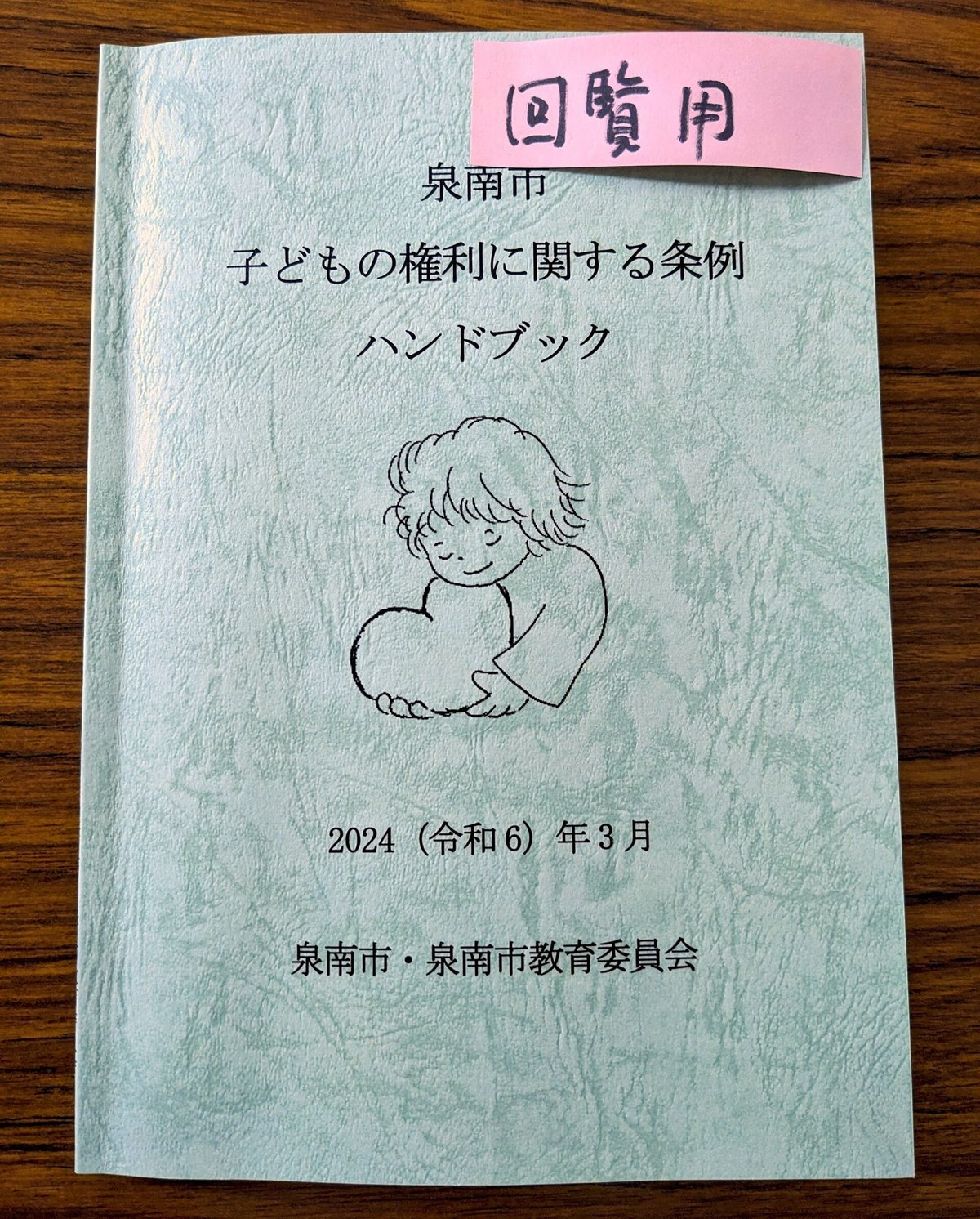
(2) 条例を活用した「子どもの権利」の主流化アプローチ
条例の実施・運用を検証するシステムに加え、もう一つ参考になるのではと思われたのは、泉南市における子どもの権利の「主流化アプローチ」ともいえる取組みです。上述の通り、泉南市では条例検証にかかる取組みの一環として、条例に基づく実施事業を設定しており、各条文との関連性を明確にして一覧化しています(※注:一覧表は第11次子どもの権利条例委員会報告の中で、条例委員会によって試行的に作成された)。
報告対象となった条例に基づく実施事業に目を通したところ、事業所管は教育部(生涯学習課、文化振興課、人権国際教育課等)が最も多く、次いで健康子ども部(家庭支援課、保育子ども課)、行政経営部(人権推進課、危機管理課)となっています。事業内容は、「8条 子どもの権利に関する学習と教育」に関する事業が圧倒的に多いのに対し、例えば「12条 施設等における子どもの安全」「13条 災害時における子どもの安全」等は1-2個しか報告されていないといったバラつきも見られます。
条例を活用した主流化アプローチは、子どもの権利に関わる施策はもちろん、他の政策領域にも応用可能ではないか?との観点から、上記点について、庁内でどのように対象事業を選定しているのか伺ってみました。
子ども政策課の古藤さんによると、条例所管課としても、条例との紐付けを全庁的に拡張していく必要は感じているが、まだそこまで追いついていないのが現状とのことで、実態としては、条例所管の3部署の担当事業を優先的に報告対象としており、それ以外の部署が実施する子ども関連事業については庁内で情報を得たら随時声掛けしているようです。
一方、条例委員会市民委員の青木さんは、『報告対象の一覧表に載っているのは、条例所管が実施する子ども関連事業のごく一部に過ぎない。事業の選定基準(何のために、どのように選定しているのか?)そのものがまだ曖昧で、ブラックボックスであることが問題。条例検証における今後の課題である』との旨、お話しくださいました。
すなわち、上述の通り、条例検証プロセスで報告される事業は、市が「条例に基づく事業」として独自に設定したものであり、必ずしも子ども関連事業がすべて網羅されているわけではなく、選定基準も公表されていない、ということです。
真の意味で子どもの権利を基盤とする行政運営を進めるのであれば、条例を活用した主流化アプローチには一定の効果があると考えられます。しかし、そのためには、条例に紐づけ、報告対象とする事業の選定基準の明確化、および選定プロセスの透明化は必須条件といえるのではないでしょうか。
(3) ハイティーンの子どもたちを対象とする施策の欠如
民法改正による成人年齢引き下げにより、現状は「18歳に満たない者」を“子ども”として定義するケースが多いと思います。しかし、実際には泉南市の施策もその多くが小中学生をターゲットにしており、高校生以上の子どもたちを対象にした施策・参加機会がとても限られている現状があります。例えば、「せんなん子ども会議」の参加者は小学生が最も多く、また市民モニターの子どもは、各学校を通じて生徒会で活動する子へ個別に声掛けを行っているそうです。この点については、市民委員の前田さんも『中学校を出てしまうと、子どもの権利に関する情報がなかなか入ってこない。施策や機会自体も少ない。』とお話しされていました。
しかし、「泉南市子どもの権利に関する条例」の認知度に関する調査結果(2019)を見てみると、認知度は年齢が上がるごとに高くなる傾向にあり、高校生はなんと半数以上(57.6%)が認知しているのです。これは、小中学校における権利学習の成果ともいえるのではないかと思う反面、条例を知っていても、自らの権利を積極的に行使できる場や機会を社会が十分に提供できていない状況にあるとも考えられます。
ハイティーンの子どもたちは、児童相談所等の公的支援につながりにくく、特に女の子たちは性的搾取の構造に容易に絡めとられるリスクもあることから、彼らへのアプローチ強化は社会全体で取り組むべき喫緊の課題です。
世田谷区への提案として参考になりそうなこと
世田谷区は2001年12月に、都内で初めて「世田谷区子ども条例」を制定しました。まだ「子どもの権利」が一般にも知られていなかった当時、生活者ネットの先輩議員が大変尽力したと聞いています(なんとかして「権利」を条例名に入れたかったが、この言葉を削除すれば条例案に賛成してやる、と某党が主張するので泣く泣くこれを飲んだとか…)。
今改めて読んでみると、謎の上から目線が鼻につく、どうにも古臭さが否めない条例ですが、それでも他自治体に先駆けて早々に「子ども条例」をつくったからこそ、その後の数々の子ども・若者施策が生まれていったのだと思います。偉大なる先輩のおねいさまたちには感謝カンゲキ雨嵐です。
さて、世田谷区では現在、この古臭い「子ども条例」を「子どもの権利条例」に大幅アップデートすべく、来年度制定を目指して検討が進められています。新テーマは「子どもの権利が保障されるまちを文化として築いていく」。大層な目標ではありますが、これはまさに、『子どもの権利を基盤とする社会モデルアプローチ』に相当するものであると思います。ただし、肝となるのは、これを子ども参加で拓いていける道筋をつけられるかどうかです。
また、区は権利救済制度として「せたホッと」(子どもオンブズ)を設置している一方、区の施策・事業において子どもの権利が保障されているかを調査・評価・検証し、政策提言を行う独立機関が存在していません。今回の視察を通して学ばせていただいた、泉南市の条例の実施・運用を検証するシステムは、その課題も含めて大変参考になるものでした。(ジェンダー平等など他の政策領域も視野に入れた)条例活用による主流化アプローチの実践とあわせて、積極的に政策立案に活かしていきたいと思います。
最後に、泉南市と世田谷区の子どもたちの条例認知度の差を紹介します。
▼泉南市(2019年調査より)
小学生:23.3%(名前だけ);36%(内容も知っているとの回答含む)
中学生:37.4%(名前だけ);43.7%(内容も知っているとの回答含む)
▼世田谷区(2023年調査より)※以下はいずれも、条例を知っているかどうかだけ聞いたそう。
小学生(高学年):19.5% ※低学年には聞いていない
中学生:15.3%
泉南市より10年以上も前に「子ども条例」を制定しているのに、この認知度の差はいったいどういうことなのか・・・子ども会議や権利学習など、その他の取組みに関しても学ぶべき部分は積極的に取り入れていくように、議会でも提案していきたいです。

一つひとつの言葉が胸にぶっ刺さる
