
奴隷制とブラジル・日本移民
国連・奴隷制度廃止国際デー(12月2日)を前にまとめます。「奴隷制はあまり関係がない遠い話」と思っていましたが意外と身近でした。
搾取されないために。
知っておいて損は無い話です。
◇◆◇
1888年のブラジルを最後に
奴隷制は違法となりました。

Image:Hồ Ngọc Hải on unsplash
なぜ奴隷制は違法になったのでしょうか?
「人間の良心が許さなかった」
「自由な社会を実現するため」
現在のわれわれが共有する人権感覚。
しかし単なる後付けかもしれません。

Image:Markus Spiske on unsplash
奴隷制が廃止された理由とは?
きっかけはインフレが進んだ19世紀初頭
英国資本家たちの闘争。
労働者の賃上げ要求に悩んだ工場経営者
VS
植民地のサトウキビ農園経営者(奴隷主)

Image:Robert Anderson on unsplash
「砂糖の値段を下げたい」
工場経営者たちが議会に対してロビー活動。
それが功を奏し、英国の奴隷制は廃止に。

Image:Shot by Cerqueira on unsplash
1822年ブラジルはポルトガルから独立し
英国に従属する国となりました。
修道院も奴隷を使役するほど
奴隷制に依存していたブラジル。

Image:ElevenPhotographs on unsplash
単に奴隷制をやめようという世界的な風潮
はありました。
が同時に経済的な理由も。
「奴隷を使うよりも移民を雇用するほうが
生産性が高いという認識」
(増田2000. pp.294-295)
1888年、ブラジルの奴隷制は廃止されました。

Image:Anastasiia Chepinska on unsplash
奴隷が去り労働力が不足したプランテーション。補ったのは日本などからの「出稼ぎ民」でした。

「とにかく労働者がほしい」サンパウロ州は
日本からの渡航費を半分負担したほどです。

ブラジルを「舞楽而留(楽しく舞い留まる)」「コーヒーは金を稼げる」と喧伝した起業家。
【モデルケース】
一日の収入目安(一人当たり):
1円20銭〜1円50銭
内訳:
コーヒー袋1つ(約50リットル)の労賃が30銭。一人で一日平均5-6袋の収穫見込み。
生活費が30銭。

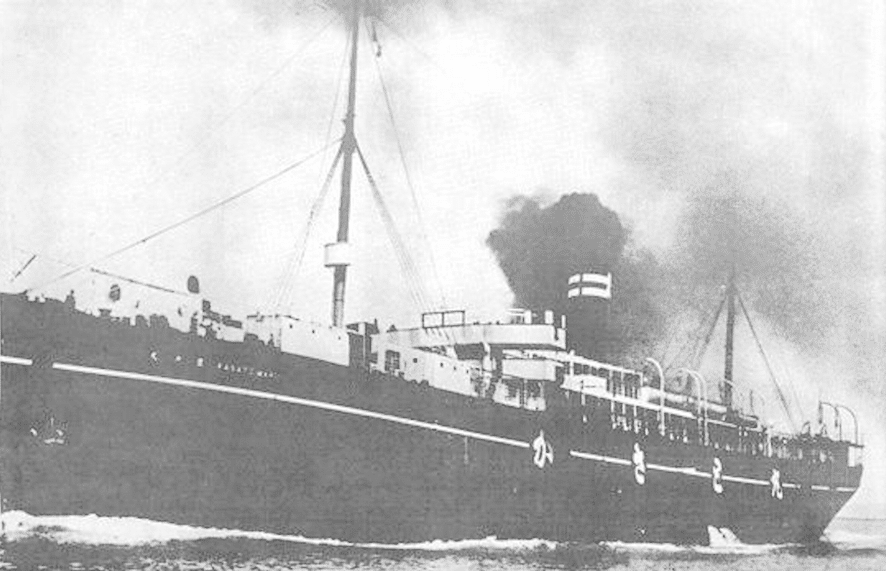
Image:Wikipedia
1908年、781人の契約労働移民が渡伯。
多くは数年だけ滞在するつもりだったそう。
大人一人あたりの渡航費用は約130円でした。
1円:現在の約4,000円
(基準:小学校教員の初任給50円)

Image:Markus Spiske on unsplash

Image:Masaaki Komori on unsplash
はたして投資は回収できたのでしょうか?
「借金はかさむ一方」
奴隷のような厳しい住環境に過酷な労働。
コーヒー価格の不況。異なる風土。不作。
過剰供給による薄利。日用品の法外な価格
(搾取の構造:販売元は農場主の関係者)

Image:Hennie Stander on unsplash
複合的な理由から農場を後にする日本人
後を絶ちませんでした。
とはいえ
「稼がず日本に帰るわけにいかない」
コーヒー農場
→鉄道敷設の作業員
→スモールビジネス
◇◆◇
ブラジルに日本人が渡った約80年後
ブラジルから日本への「移民」が起こりました。
【在日ブラジル国籍者数】
1990年 → 2007年
56,429 名 → 316,967 名
物価高なのに所得が増えないブラジル。
「日本にデカセギ、ブラジルで起業(進学)」

◇◆◇
デカセギから30年目、2020年。
【在日ブラジル国籍者数】
2020年12月末 208,538 名
「今さらブラジルには帰れない」という人たち
◇◆◇
今から約200年前
賃上げを嫌った起業家たちが
奴隷制を廃止に追いやりました。
「油や小麦粉の値段が上がった」
物価が上がっても所得は増えない現代日本。
我々が歴史から学べることは何でしょうか?
▼参考文献
増田義郎・編著『ラテン・アメリカ史 II』山川出版社, 2000.
丸山浩明・編著『ブラジル日本移民百年の軌跡』明石書店, 2010.
国立国会図書館「ブラジル移民の100年」
(おわり)
表紙:Tim Mossholder on unsplash
リオのガイドします✋
▼DMお待ちしています(Instagram or Twitter)
