
【連載企画2016】山激動~県産材復権へ
70年前の戦後復興元年は山の荒廃から始まる。軍用資材を求めた乱伐で災害が頻発し、植える山の再生が復興のシンボルだった。そして今、森林資源が熟し、山を守ってきた時代がようやく花開こうとしている。
日本一の丸太生産量だけにとどまらず、大型製材工場、バイオマス発電施設、丸太輸出といったあらゆる木材を受け入れる出口が用意されるようになった。林野庁幹部は明かす。「宮崎県は日本の先頭を走っている。林業の成長産業化を大きく左右する潜在力がある」。林業を切り口に山の息吹を取り戻せないか、激動する山をどう次へつなぐか、林業の今を追った。
このコンテンツ「山激動~県産材復権へ」は2016年の連載企画として、宮崎日日新聞社・本紙1面に2016年1月1日付から1月9日付まで連載。今回はまとめとして本稿に関連する記事を追加しました。登場される方の団体・職業・年齢等は掲載時のものです。ご了承ください。
首都圏進出が試金石
【宮崎大農学部(森林経済学)藤掛一郎教授に聞く】
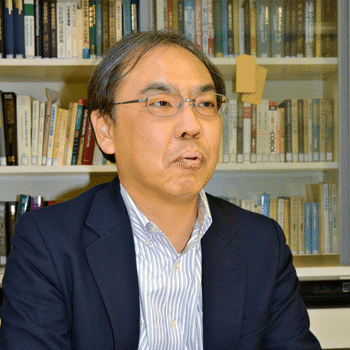
バランス良い需要大切
連載「山激動」では、平成に入って最も多い主伐伐採量となった山側から、急激に需要を広げる木材関連産業を追った。林業の成長産業化を目指し、いかに潜在力を発揮するか。宮崎大農学部・藤掛一郎教授(森林経済学)に展望と課題を聞いた。(聞き手 本紙報道部)
-中国木材日向工場の丸太消費量(年32万立方メートル)はインパクトが大きい。
「国内の国産材製材工場は大型化が進んでいるが、大手でも十数万立方メートルの処理能力。欧米に比べて生産力は劣る。世界と競う木材にとって、国内有数の森林資源、木材供給力がある本県で大型工場が動きだした意義は大きい」
「スギの建築材は九州で使われているが、首都圏は外国産材にやられている。それをどう置き換えていくか、中国木材の取り組みの成否が宮崎の林業を占う試金石になる」
-林地残材や低質材を燃料とするバイオマス発電施設の稼働とも重なった。
「需要量が急増し供給する山側は苦慮した面はあるが、膨大な低質材を求めるバイオマス施設だけが稼働しても、直材などの良質材の行き場がなく木材価格は下がっていたはずだ。大型製材から地元製材、バイオマス施設とバランス良く需要が生まれ、直材、曲がり材、低質材が山から安定的に搬出される環境が重要」
-資源目的に山を買う動きが加速している。
「県内のバイオマス発電施設はここ2~3年で数百ヘクタール、中国木材は本県を除く九州で5千ヘクタールを取得し、さらに4倍へ広げようとしている。投資目的に持たれた山が、資源の安定供給を担保するために産業へ集積していく流れは進む」
-伐採量が増え、人材対策が急務だ。
「宮崎大は鹿児島大と合同で林業・木材産業に特化した就職説明会を3年前から開催。15年は宮崎大で5人が採用につながるなど効果が現れている。拡大する産業にとって事業管理能力がある人材が必要になってくる」
「林業従事者の賃金をどれだけ上げられるかも人材確保のポイント。山村に残る、移住を選択しやすくなるために稼げる環境へ改善を求めたい」
-再造林率の低迷が課題。
「国の造林補助金が減額されるとの情報があり、さらに状況が悪化しかねない。再造林ができなければ生産量はいずれ減らさなければならない。再造林の低コスト化を真剣に考える時期に来ている」
1.森熟し目覚めの時
成長産業へ好機到来
山あいの小さな学校に大学生8人が集まった。「じいちゃんが捕ってきたシシ汁、ばあちゃんの煮しめ、漬物をどうぞ。おいしいですよ」。昼食のメニューを小学6年の「はるちゃん」が紹介する。スギの伐採現場にも学生を案内した。2015年末にあった「林業アピールツアー」は諸塚村・荒谷小(13人)の松村春菜さん(11)が企画した。

アピールツアーを企画した松村春菜さん(左から3
人目)=2015年12月、諸塚村
林業をテーマ学習に取り入れている同校で担い手不足を知った。「山や林業がなくなってしまうのが怖かった。だったら若い人に山師の仕事を知ってもらえれば」。家族や村観光協会から助言を聞きながらツアープランを練った。
祖父晃三さん(71)から教えられた山の営みが根底にある。食糧難の時代に苦労して道を通し、苗を植え、育ててきたこと。子や孫の代はより幸せな生活であってほしいという願いも込められた森。「山が大好きよ」と語る祖父の顔がいつも浮かんだ。
ツアーの学生は森林研究で村とつながりがある宮崎大、九州大から参加。同校のPTA会長だった地元の丸太生産業者が協力し、伐採現場で倒すごう音に拍手が上がった。「かっこいい。感動した」との声も。伐採作業から引退していた晃三さんはその場で「孫がいるから記念に見せたい」と久しぶりにチェーンソーを鳴らした。誇らしげな顔に春菜さんもうれしそうだ。
「15の春」になると子供たちは高校入学のため村を出る。晃三さんは「中学卒業記念で子供にスギの苗を植えさせてきた。『山を忘れないで』『ふるさとに帰ってきてほしい』という気持ちから。次ははるちゃんの番」と語る。
親から子、孫へ命の連なりとともに森を慈しむ心は受け継がれていく。春菜さんの夢は村で保育士になること。「山を守り育てる人がいて諸塚が輝き続けることが未来の子供たちにとって大切だから」。村全体の願いでもある。
村人口(約1700人)はこの10年で2割近く減った。憂いはある。それでも結束力が緩まないのは、村土の大半を占める森林を受け継いでいく林業立村の覚悟があるからだ。明日を山に求める村民の心の鼓動が響き始めた。
05年の台風14号で被災した村中心部に全国でも珍しい完全木造の商店街が誕生する。かさ上げ工事で4年間の移転、仮設営業を強いられたが、計11店が15年度までに再オープン。特産品販売店など村産材で建設中の主要4施設と合わせ木の街づくりを始める。
4年後の東京五輪も村にとっては好機。競技場や選手村など関連施設の木造化が検討されており、過去の五輪の使用例を踏襲すれば、村ぐるみで取得した国際森林認証材を含めて採用される可能性が出てきた。全国の認証率は7%ほどで国が五輪を念頭に普及に力を入れる。その国の事業委員会に村企画課の矢房孝広課長が出席している。
矢房課長は「先人が築いてきた山づくりの果実を生かす時。五輪はチャンスだが、その後を見据えて種をまいていく」と都市部の需要開拓を狙った仕掛けに動いている。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
