
合唱コンが好きすぎるって話
中学校で音楽科教員をしていました。
音楽科にとって、合唱コンクールの取り組みシーズンは1年で一番忙しい時期。
音楽科って学校に1人のことが多いので、1人で3学年分の合唱曲を分析して(大体15曲ぐらいかな)
毎日4時間全力で合唱指導して、そこから自分のクラスの学活(合唱練習)見て、放課後練習も見て、終わったら吹奏楽部見て…。
この1か月間は本当に、気力・体力ともに限界なんだけど、それでも私は、このシーズンが大好きでした。
「こんなに動く音楽科、見たことない」
と何度言われたか分かりません(動きすぎてたらしい…)
でも、もっと何度言われたか分からないのは
「松本亜衣は本当に合唱が好きなんじゃね笑」
「とんでもなく幸せそうな顔するよね笑」
ここね、"笑"が混じってるのがポイントで、要するに引かれてました笑。
多分、普段と別人すぎて引いてたんだと思う。
でも、だって、仕方ないじゃない。
クラス合唱で歌われる曲の歌詞なんて
「愛」「友」「ぬくもり」「優しさ」「輝き」「絆」「未来」「語ろう」「きみ」「ぼく」
思春期の少年少女が口にするには恥ずかしすぎる言葉のオンパレードで、しかもそれを「気持ちこめて歌え!」とか言われてるんです。
ある種のトランス状態に入らないと、少しでも冷静さを取り戻してしまったら、もう歌えなくなってしまうじゃないですか。
だから、前に立っている私が、誰よりも先に、誰よりも遠くまで、ぶっ飛んでないとね!と思っていたとかいないとか。(実際は好きすぎて壊れてただけだとか違うとか)
今年も学校中から歌声が聴こえる季節になりましたね。なんだか数年ぶりに合唱への想いがムクムクと湧いてきたので、【合唱の】ではなく【合唱コンの取り組みの】魅力を書いてみようと思います。
① 先生の哲学が見える
合唱コンほど、各先生がもっている"根底に流れる哲学"が見える取り組みはないのではないでしょうか。
例えば、パートリーダーの選出。
・毎度お馴染みのメンバーで固めるクラス
・「相応しくない人」が落選するクラス
・立候補した人が全員リーダーになるクラス
・意外な子がたくさんリーダーになるクラス
・仲良しメンバーがみんなでリーダーになるクラス
・立候補者がいなくて困り果てているクラス
例えば、パートリーダーの様子。
・上からガチガチに固めようとする
・不真面目なヤツは悪だ!と罰を与える
・「私は言わないんで先生お願いします」
・真面目さより楽しさ重視
・リーダー自身が遊びに行って帰ってこない
・ボーっとしている間に他の子が動く
これらはほんの一部ですが、これだけ見ても担任の先生の、年間における合唱コンクールの位置づけ、
取り組みを通してつけさせたい力、"リーダー"の定義などなど、学級を経営する上での信念、価値観、根底に流れる哲学のようなものが垣間見える気がしませんか。
実際には、もっとたくさんの要素から、もっとたくさんのものが見えてきます。
同じ1ヶ月の取り組みでも、根底に流れるものが違うとこんなにも違うのかと、毎年とても興味深く観察していました。
すべての学年、すべてのクラスの先生方の哲学をじーっと見ることができたのは、音楽科の特権でした。おもしろかったな。
きっとクラスごと、学年ごとに完全に分かれて行う活動だから、他クラスと一緒に活動することがほとんどない取り組みだからこそ、先生の色が濃く出るんだろうなと思います。
いろんな先生方の哲学に触れながら、自分の在り方を問い直す期間。
取り組みが終わる頃にはもう来年度の構想が組み上がってることも何度もありました。
音楽科って特等席なんだよなぁ。
➁ チームマネジメントを小さく体験できる
合唱の取り組みは学級活動の一環ではあるけれど、普段の学級経営とは少し違う。
クラスとは別の、何か新しいチームが立ち上がっているような感覚を覚えたことがある先生も多いのではないでしょうか。
きっと、ピアニストがいて、指揮者がいて、パートリーダーがたくさんいて…と普段とは違う顔ぶれが前に出ていること、1ヶ月毎日同じことに取り組むということあたりが関係しているのだと思います。
新しいチームが立ち上がる
1ヶ月後にゴールを迎え、解散する
この設定があるからこそ、チームはものすごいスピードで、急速に変化していきます。
普段、学級経営をしていると1年間かけて起こるようなことが、もっとコンパクトに1ヶ月間で起こるイメージです。(もちろん規模感は違うけれど)
チームができあがるのに1年かかってしまうと、関係係数が多すぎて、どこにどのような因果関係や相関関係があってこの現象が引き起こされたのか、判断するのはとても難しい。
でも、それが1ヶ月間なら
“歌う”というシンプルな取り組みなら
複合的な要因であったとしても、追える範囲で収まってくれることが多い。
だからこそ、チームをマネジメントする上で、見なければならないポイントはどこなのか、押さえるばきタイミングはいつなのか、どういう段階を経てチームが成長(あるいは崩壊)に向かうのか、体験することができると感じています。
余談ですが、以前勤務していた学校で、合唱の時期に職員室内で通信を発行していました。
【取り組みのフェーズに合わせたマネジメント】が主な内容で、そろそろこのフェーズ終わるよ〜とか、次はこういうフェーズが来るよ〜、だからマネジメントスタイル変えなきゃだね〜とか、そんなことを書いていました。
文化祭も無事に終わった打ち上げの席で、若手の先生が通信についてこんなことを言ってきました。
「あの通信、マジで怖かったです」
「予言なんすよ」
「書いてある通りのことが起こる」
彼が言っていたのは、例えばこんな内容の号。
そろそろモメます。
この層とこの層がモメます。
こんな理由でモメます。
でもそれって、クラスがこうだからですよね。
リーダーがこう動いてるからですよね。
防ぐ方法は、ありますよ。
そんな通信を読んだ翌週、書いてある通りの内容でしっかりモメたそうです笑
でもこれって要するに、フェーズごとに起こりやすい現象がありますよってこと。
毎年偶然に、サプライズで起きている現象じゃありませんよってこと。
こういうことが知識として伝播していくといいなと思って発行していた通信だったので、彼のコメントはとても嬉しかったことを覚えています。
と同時に、こういうことを教えてくれる人ってなかなかいないんだな、私自身も誰にも教えてもらったことないな、と改めて感じたこともよく覚えています。
チームがどんな段階を経て
どのように成長していくのか。
たった1ヶ月の間に10クラス以上のマネジメントに同時に触れることができる音楽科は、やっぱり特等席でした。
…と、【合唱コンの取り組みの】魅力を書こうと思いましたが、言いたいことがありすぎてもうまとめられないし、長すぎるので、この辺りでやめておくことにします。
まだ何も書いてないに等しいけれど…。
でもね、言いたいことはただ1つです。
めちゃくちゃ学びの多い期間だから
どの先生にも楽しんでほしい!
合唱コンの取り組みは長くて、辛くて、苦手意識をもってる方も多い。音楽の知識がないとできないと思っている方も、とても多い。
でも、そんなことない!
なぜなら合唱コンは、
歌唱力を伸ばす取り組みではないからです!
合唱コンクール、楽しんでほしい。
マネジメントも、楽しんでほしい。
子どもたちと、熱中する体験をつくってほしい。
今年もたくさんの子どもたちが
集わないとできない、スペシャルな体験に
出逢えますように。
\教員キャリアコーチング/
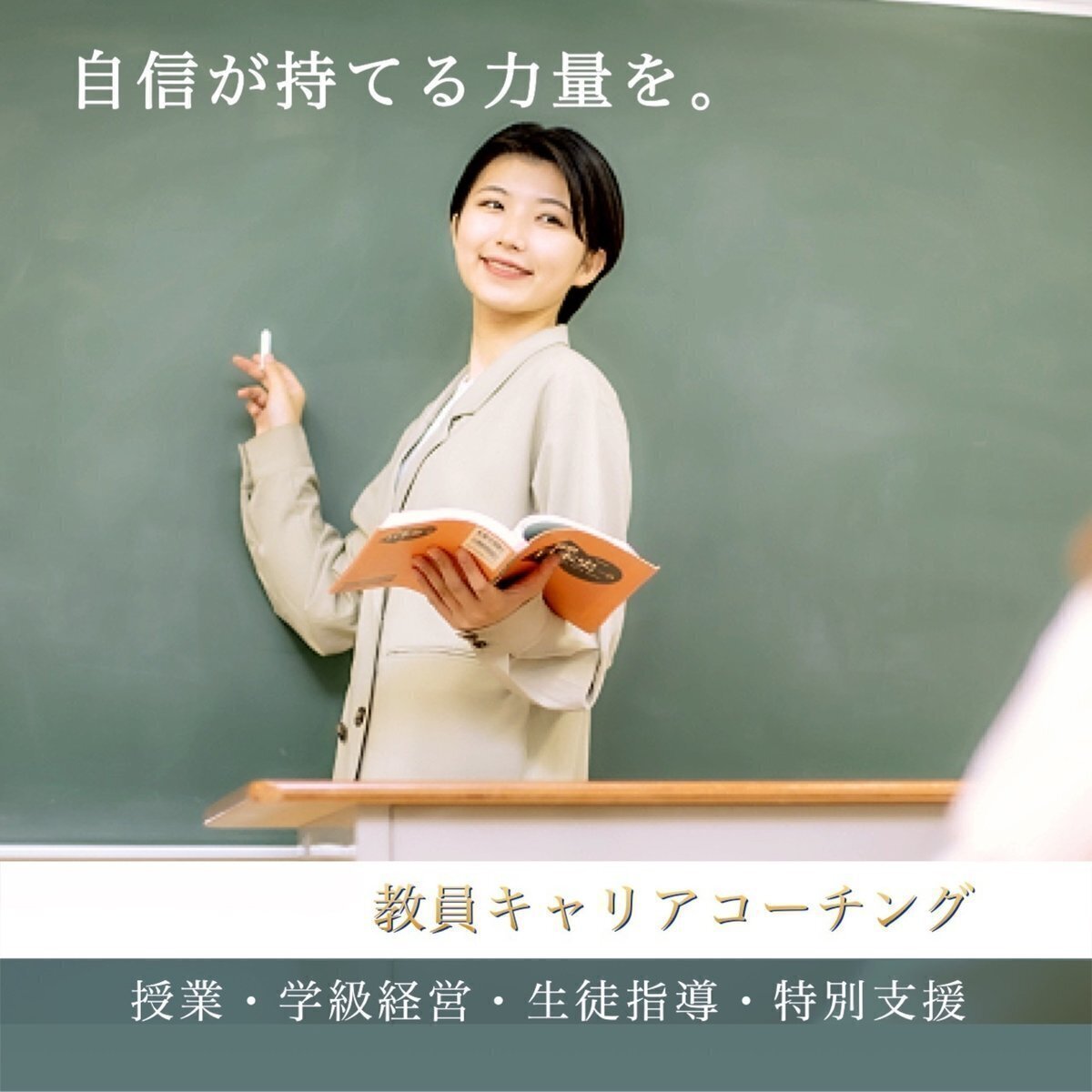
小学校・中学校の教員の方向けの個人コーチング。
「教育に自信が持てる力量を。」をテーマに
自分自身と教育活動を見つめ直しながら
教員としてのキャリアステージやポジションに合わせて
実践的にサポートします。
———————————————————
このような方におすすめです
———————————————————
☑自信をもって子どもたちと向き合いたい
☑児童理解や生徒理解を深めたい
☑より良い学級経営や学年経営を行いたい
☑保護者や教師同士の信頼関係を築きたい
☑教員として人間力、判断力、指導力を高めたい
☑自分の指導や実践を振り返る時間をつくりたい
詳細・お問い合わせ・お申し込みはこちらから
\いつもありがとうございます/
実践の場にすぐ持ち帰ることのできる武器をもらえることが他にはない価値だと感じています。安心と刺激のどちらの実力も併せ持つ、信頼できるコーチです。
(中学校教諭・30代女性)
学校内外の幅広い実務経験に基づいた多面的アプローチの提案、行動心理学的なアプローチの実装を得意とする、すべての教職員のスーパーバイザーです。
(中学校教頭・50代男性)
パーソナルコーチ│スクールカウンセラー
松本 亜衣
フォロー・スキ 嬉しいです!
Instagramもやってます!
