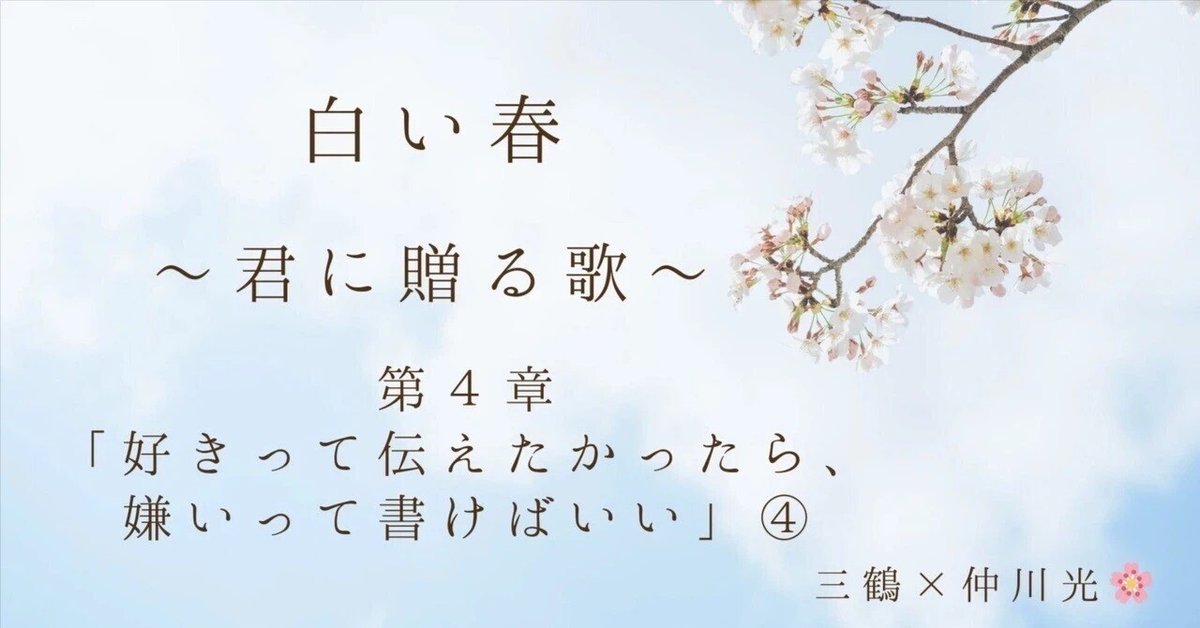
共作小説【白い春〜君に贈る歌〜】第4章「好きって伝えたかったら、嫌いって書けばいい」④
好きって伝えたかったら、嫌いって書けばいい【エッセイ】
髪を切ってもらいながら、美容師さんの好きな音楽について聴いていた。すると、あるバンドの名前があがった。私はそのバンドのボーカルを少し知っている。だが、黙ってそのまま聴いていた。
美容師さんの話は、だんだんと熱が入る。笑顔で相槌を打ちながら、Sさんのことを考えていた。
Sさんは日本武道館で歌っていた。
偉大なミュージシャンたちも、昔の恋人も、彼に夢中だった。
人は彼を、カリスマボーカリストと呼んだ。
多少の贔屓はあるかもしれないが、その詩と歌声は他のアーティストとは明らかに異なるものだった。
彼はいつでも、私のスターだった。
思春期の一人部屋の隅。ヘッドフォンを耳に当て正座する。バンドの激しい演奏の中、Sさんの鋭く繊細な歌声が聴こえてくる。これは私の現実逃避であり、一番救われる方法だった。
Sさんと共演することになったのは、二十四歳のときである。
彼のバンドは解散し、メンバーはそれぞれ違う道を歩んでいた。だが、一年に一回だけ再結成する日があった。メンバーの命日に行われる追悼ライブである。
その年は諸事情により、Sさんの弾き語りによるソロライブが行われることになった。弾き語りの演奏形態は、私も同じだ。彼と同じスタイルで、同じステージで歌う自分を想像してみた。あまりにも非現実的である。だが、想像は膨らみ、なんだかぞくぞくとしてしまう感覚が離れなくなってしまった。
十代からの音楽仲間であるYくんとの電話で、この思いを話してみることにした。
「気持ちはわかるよ。でもさすがに、それは無謀でしょ。そもそも断られるんじゃない?」
それはわかっていたが、いざ言われるとがっかりするものだ。冗談だったかのように笑って、電話を切った。
横になってぼんやりと音楽を聴く。やはりだめだ。鼓動が高鳴ってくる。居ても立っても居られなくなった。体を起こしてパソコンの画面を見た。ホームページに載っているアドレスを、コピー&ペーストする。自作曲の音源を添付して、あなたのファンであること、そして、前座として出演させてほしいことを長々とメールに打ち込んで、送り付けてしまった。
それからしばらく返事はなかったので諦めていたが、一週間後、Sさんのスタッフから返事があった。
私の「思い」については一切触れず、セットリストやセッティング、音響や照明の希望などを事務的に訊かれる。
だがそれは、現実にSさんと共演することを意味していたのだ。
ライブ当日、初めてステージの外にいるSさんを見た。狼のような、びりびりとした殺気がある。それなのに、つい何度も見てしまう華やかさと、すぐに壊れてしまいそうな儚さがあった。
挨拶とお礼の言葉を伝えるが、あまり目を見ることができない。彼も素っ気なく返事をしただけで、あまり近づいてはいけない雰囲気があった。私はさっとリハーサルの準備にとりかかった。
多くのライブのリハーサルは、逆リハと言って、出演順とは逆の順番で行われる。だが、Sさんのこだわりなのか、出演順にリハーサルが行われた。つまり、私が最初であった。
リハーサル中、モニターの音量についてPA(音響担当)に話しているときだった。
「いいねぇ」
フロア(客席)から聞き慣れた、よく響く声が聞こえた。明らかに私に向けたものであった。気づかなかったふりはできないため、軽く会釈する。本番ではないのに、汗が噴き出てきた。憧れの人が目の前にいて、私の演奏を聴いているのだ。意識するほど、声や手が震えてしまう。ギターのチューニングをし直すと、深呼吸した。
私のリハーサルが終わってしばらくすると、Sさんのリハーサルが始まった。サウンドチェックが落ち着き、軽く演奏すると、穏やかな顔をして前を見る。マイク越しにフロアへ向かって声をかけた。
「よお、ちょっと来いよ」
ぼんやりと見ていたら、私の隣にいたスタッフの人が無言で前へ促した。
「そう、お前だよ。さっきリハーサルしてた」
突然のことに驚いて、たどたどしい足取りでステージへ向かった。
彼の隣に立つと、マイクを握らされた。こっちのマイクからも音を出すよう、PAに合図を送っている。
「俺の曲、なんか歌ってみてよ」
私の目を見ている。信じられないことだった。頭が真っ白になる。
「何歌える? 何でも歌えるだろ?」
「いや……え、何でもではないです……」
「じゃあ、✕✕✕(曲のタイトル)にしよう。俺がコーラスやるから」
確かにその曲は私のお気に入りの一つで、過去にギターで演奏していたこともあった。
会場のスタッフが皆、手を止めてステージにいる私たちを観ている。これから貴重な演奏が聴けるという期待に満ちているのが、はっきりとわかった。
中学生のときから聴いていた曲が、それを作った本人のギターで奏でられている。すぐそばから、温度を伴って。
Sさんは歌が始まる一小節前で、私の方をちらっと見て合図を送った。
が、このような状況に圧倒されてか、出だしから音を外してしまった。途中で歌詞も忘れてしまう。歌は途切れたが伴奏は続く。Sさんはハモろうとしていたようだが、私がそのような調子だったので辞めてしまった。ワンコーラス終わると、ギターが止まる。
フロアから、ためらいがちな拍手が聞こえてきた。
私はSさんとスタッフにお辞儀して、苦笑いしながらステージを下りた。
あまりにも恥ずかしくて、顔を見られないようにしながらトイレへ入った。大きなため息が出た。
開場の時間になると、ライブハウスの外にできていた行列が中へと移動する。キャパ五百人近くの客で満員になった。
会場がどっと騒がしくなる。笑い声や叫び声、携帯電話の光。酒が会話を弾ませる。ほとんどの人がSさんの客である。
私は彼らに受け入れてもらえるだろうか。不安なイメージが膨らんできた。自分が作った曲、信じてきたものは、笑われてしまうのではないか。それどころか、聴いてもらえないかもしれない。
楽屋の大きな鏡の前にあるテーブルで、そんなことを考えて呼吸が苦しくなってきた。
突然、ドアをノックする音が聞こえる。Sさんだった。
彼は私を見て、少し笑った。
「あ……お疲れ様です!」
「おいおい、大丈夫か」
「はい、緊張はしてますが、大丈夫です。頑張ります」
私の隣に腰掛けた。
「自信持ちなって。すげえいいよ。歌もばっちりじゃん。それに、感性……んー、感受性かな。感受性が他のやつより頭一つ抜けてるね」
あんな失態を演じてしまったのに、こんな言葉をかけてもらえるなんて思ってもみなかった。まして、カリスマボーカリストからである。
私はずっと気になっていたことを訊くチャンスだと思った。
「あの、僕、Sさんの曲に何度も助けられてきたんです。本当に、尊敬してますし、恩人だと思ってます。僕もSさんみたいに、人の心に届く詩を書けるようになりたいんですけど、Sさんはどうやって詩を書いてるんですか?」
Sさんは私の目をまじまじと見ながら聴いていた。あまり視線を外さない。私は言葉が出てこなくなるのを耐えて、なんとか質問することができた。彼は少し横を向き、また小さく笑った。
「簡単だよ。好きって伝えたかったら、嫌いって書けばいい。そうすれば好きって書くより伝わるから」
開演時間になり、SE(入場時に流す音源)がかかる。頃合いをみてステージに上がったが、変わらずにフロアの声は騒がしい。私の演奏など観ようとはしない。
Sさんの言葉を反芻していた。
悪いが、今は私の時間だ。表現者としてステージに立つからには、彼らを黙らせないといけない。
手を挙げてPAに開始の合図を送る。SEがフェードアウトすると、一曲目から勝負を仕掛けた。前奏をカットし、サビ部分をアカペラで歌い始める。二十歳のときに作った曲である。
PAや照明のスタッフは戸惑っていたことだろう。打ち合わせにはないことだった。
思惑どおり、会場は静かになる。観客を飲み込めた手応えを感じた。そこからギターを弾き始める。
この日のライブは、過去最高の出来だった。
ライブが終わった後、宙に浮いているような感覚になった。スミノフアイスをぐびぐびと飲んで、自分のチケットを買って観に来てくれたお客さんたちへ挨拶に行った。
Yくんが真っ先に声をかけてくれた。
「いやあ、よかったわ。はっきり言って、みっちゃんのライブの方がよかった」
調子のいいやつだ。それに私の方がよかったなんて、それはさすがに言いすぎだ。と、頭の中ではわかっていて平静を装っていたが、心は舞い上がるのを抑えることで必死だった。彼だけではない、たくさんの人から声をかけられた。一緒に写真を撮り、サインを書く。CDはそこそこ売れた。
ファンやスタッフに囲まれているSさんのところへ挨拶に行く。私に気づくと会話を中断して乾杯してくれた。
「やっぱり、すげえよかった。また、やろうな」
Sさんが言うなら、リップサービスではないだろう。
一生この人のファンでいよう。そしていつか、追い抜いてみせる。そう誓った夜だった。
その後もSさんやスタッフの方と連絡を取り合い、約束どおり、再び共演することができた。が、私はもう、あの日のライブのような演奏ができなかった。
彼は掌を返したように、容赦なく文句を言った。
「はっきり言って、前の方がよかった。下手くそになったな。一年後にはメジャーに行くと思ってたのに……この数ヶ月、何やってたんだよ。練習が足んねぇじゃねえの?」
かなり落ち込んだ。自分でもうまくいっていないことを、よくわかっている。しかし、必死になってやるほど、結果はついてこなかった。ライブチケットも売れなくなり、ほとんど客の入らない状態で演奏することも少なくなかった。
そんな中、Sさんはよくパーティーに誘ってくれた。一緒に朝まで酒を飲んで歌う。でも酔うと必ず説教をされるので、肩身の狭い思いをしていた。
あるとき、一緒に参加していたYくんが、居酒屋のトイレで少し上を向いたまま言った。
「あの人は、すっかり師匠だね。みっちゃんの」
「師匠?」
「うん、みんなそう思ってるよ」
弟子入りしたつもりはなかったが、周囲からは師弟関係のように思われているようであった。それを聞いて少し嬉しいと思ったが、こんなに落ち込んでいるときに駄目だしばかりされる関係は嫌だな、距離を置きたい、とも思った。
師匠になったなんて一言も言っておらず、そんなつもりもなさそうなSさんにとっては、かなり迷惑な話だっただろう。
そして、数か月後。
私は人間関係のトラブルに巻き込まれてしまい、東京から帰らなければならなくなった。
そのことをホームページで報告すると、一番に連絡をくれたのはSさんだった。
「え、帰っちゃうの? 何があった?」
「えっと……」
このトラブルを知っているのは、関係者と両親だけだ。それでもSさんには隠せない気がして、自然と話している自分がいた。
「何でお前が帰らなきゃいけねえんだよ。おかしいだろ」
「すいません……」
「ああ、もったいないな。お前みたいな感受性を持ったミュージシャンは珍しいと思ったのにな」
どこか真剣味の欠けた話しぶりは、嫌みのようにも聞こえて、あまり真に受けなかった。
「すいません」
「この先の音楽シーンを変えてくれると思ってたのにな。……まあいいや。いいか、これだけ覚えておけよ。お前が次に東京に戻ってきたとき、待ってるファンなんて一割もいねえからな」
「……はい」
電話を切って炬燵に潜っていると、再びSさんから着信があった。
「今、ハコ(ライブハウス)を押さえたから、ちゃんと練習しておけよ」
「え……」
明日の昼、そのライブハウスで一緒にライブをやるのだと、無茶苦茶なことを言い出した。夜には、別のライブイベントが行われるため、ライブハウスのスタッフも相当に困惑したに違いない。
私自身、トラブルの影響で一ヶ月近く演奏していなかった。が、断るわけにはいかない。慌ててアルバイトの休みをもらい、出演することになった。
急遽決まったライブにも関わらず、会場には多くの観客が集まっていた。
私の演奏は、相変わらず散々なものだった。しばらく練習していなかったからか、ギターは弾けても声が出ない。
私は最後の曲に、Sさんの曲を選んだ。初めてライブで共演したときに、リハーサルでうまく歌えなかった曲である。
ワンコーラス終わったあたりで、フロアで観ていたSさんが、突然ステージに上がった。そんな打ち合わせなどしていなかったため、ギターを弾く手を止めてしまいそうになる。彼は隣でマイクを握った。私の口の動きを見ながら、ハモり始めたのである。
横を見ると目が合ってしまう。私はつい顔がほころんだ。少し間違えてしまったが、彼はそのまま合わせてくれた。
そして締めは、Sさんのライブである。
彼は最後の曲の前に、MCで語り始めた。
「相変わらず、下手くそなみっちゃんだった。これが俺との実力の違いだよ。わかったか」
この期に及んで、観客がいる場でも貶されなければならないのか。Sさんの顔を見るのが辛くなり、目を逸らした。苦笑いする。
「お前がステージに戻ってきたとき、また勝負しよう」
え? 勝負?
彼はステージから右手を客席に伸ばして、何かを待っている。私はフロアの後ろの方から観ていたが、周囲にいた人たちに肩や背中をぽんと叩かれた。
私がステージ前に来るまで、彼はずっと同じ姿勢でいる。私がようやく手を握ると、会場に盛大な拍手が巻き起こった。
あまり素直な笑顔を見せない男が、私の手を握りながら笑っている。不思議な光景だった。
彼の眼光は、いつものように鋭かった。
Sさん
お元気ですか。
あれから十二年が経ちました。最後に共演したライブもちょうどこの時期でしたね。
今の私を見たら、あなたは何て言うだろう。いつになっても、そんなことを考えて過ごしています。
怒られそうだな、と思ってずっと連絡できずにいることを、お許しください。そんな小さい男だって、あなたは知っているでしょう。
あなたは癌と闘いながらも、変わらずに活躍していることを知っています。過去の栄光が邪魔をして、今でも葛藤していることを知っています。
でもあなたは、いつでも今が最高にかっこいいのだと、私は思っています。
あなたの詩の秘密が、私の創作に今も影響していることは、何となく秘密にしていたのですが、ここに書いてしまいました。
そして、私はあなたの言葉にさんざん傷ついてきたのですが、それもあなたの詩人としての言葉だったかもしれない、と今になって思うのです。
いつかまた、私と勝負してください。
前回の物語はこちら↓↓
次回の物語はこちら↓↓
【白い春~君に贈る歌~】全編まとめはこちら↓↓
