
冒険するプロジェクトのつくりかた
MIMIGURIアドベントカレンダー Day14-2です。
テーマは#わたしたちの冒険 です。
弊社MIMIGURI Co-CEO安斎さんの新著『冒険する組織のつくりかた「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』の刊行記念ウェビナーには1,400名を超える方々にご登録いただきました。ご好評につき12/21に再放送も決定しました!
この記事では、『冒険する組織のつくりかた』を盛り上げるべく立ち上がった、社内プロジェクトの話を書いてみたいと思います。
改めまして、chimoです。
2023年5月からプロダクト事業部で働いています。
これまでは、システム開発の現場でエンジニア・プロジェクトマネージャー・スクラムマスターとして働いてきました。
そして、今。
多くの方に『冒険する組織のつくりかた』(ここからは略して冒険本と呼ぶ)を手に取って頂くためのあらゆる施策を企画実行する冒険本プロジェクトの、プロジェクトマネージャー(以下、PM)を担っています。
※補足: ビジョンを描くPOと、ビジョン実現に向けて道を整備するPMの役割があります。
ここからは、冒険本プロジェクトを冒険的に進めたくて色々と実験した話を、その頃の日記を引用しながら思い出していきます。
まだ道半ばではありますが、プロジェクトマネジメントを模索する方々にとって、何かの足しになると嬉しいです。
冒険するプロジェクトとは
プロジェクトを冒険的に進める、ってどういうことなんでしょうね。
冒険本プロジェクトのPMに名乗りを挙げた直後から、悩んでいました。
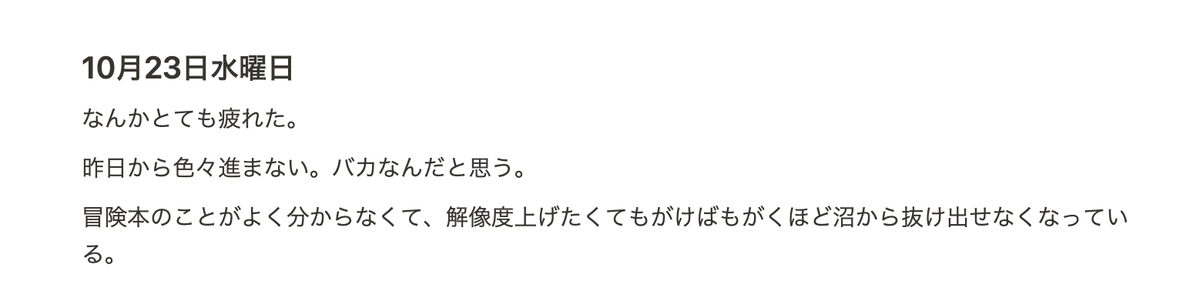
悩んでも仕方ないので、私の現段階の理解で定義を仮置きして前に進むことにしました。
冒険するプロジェクトとは、コミットメントしたい!と思う人たちが集まり自己組織的に進むプロジェクトのことである
悩んでいる時は、まず動いてみる派です。

ここから、2つの問いの答えを探す日々が始まります。
コミットメントしたくなる工夫とは?
自己組織的に動ける環境とは?
コミットメントしたくなる工夫を探す
ここではコミットメントを、主体的に動く、自分の意思で実行する、自らの仕事に責任を持つ、という意味で使っています。
たしかに、主体的に動く人たちが集まれば、上手く行きそうです。
とはいえ仕事なので、意欲に満ちたギラギラした人たちばかりが集まるとは限りません。
冒険本プロジェクトでは、仲間集めとコミットメント意欲をくすぐるために幾つかの工夫をしてみました。
1. 情熱のあるPO
情熱のあるPOの存在は、何よりも大事なポイントです。
冒険本プロジェクトのPOは、情熱とこだわりと野望を持ったshinyさんです。昨年のアドベントカレンダーを読むとshinyさんのこだわりが分かります。
プロジェクト立ち上げ初期に、shinyさんによるワークショップ型キックオフが開催され、その後も継続的にチームにポジティブな熱風を送り続けてくれています。

情熱のあるPOの元には、仲間が集まります。
ちなみに、POにshinyさんを推したのは私です。自分を褒めてあげたいと思います。
2. 簡潔で明確な目標
目標の抽象度が高かったり、定量目標の納得感がないと、WhatとHowを自律的に考え実行することが難しくなります。
冒険本プロジェクトでは、簡潔で明確な定性目標と定量目標を設定しました。

3. アイディア箱
正解のないプロジェクトでは、トップダウンで決めた施策を進めるのではなく、現場で自律的に実験サイクルを回すことが大事です。
今回は実験として、WhatとHowのアイディアを募集するためのアイディア箱を作ってみました。
みんなのアイディアを結集することで、面白そうなことや誰かと一緒にやりたいことが見つかるかもしれません。
今後、アイディア箱で生まれたタネが形になり、少しずつリリースされていくことになると思います。楽しみです!
自己組織的に動ける環境を探す
これまでもMIMIGURIでは、書籍プロモーションやウェビナーなど大規模イベントを開催してきましたが、主にマーケティングチームを中心として運営がなされてきました。
冒険本プロジェクトでは、マーケティング・コンテンツ・プロダクト・エンジニアが混成チームを組み、10数名から成る機能横断的な一つのチームとして進めることに挑戦しています。
初めて一緒にチームを組むメンバーが多いため、各々のリズムや好みが違います。
その中で、全員がパフォーマンスを発揮でき、尚且つ自己組織的に動ける環境をどのように作るのか、一番悩んだ部分でした。
1. 会議体は最小限で、すぐモブる
当初はスクラム開発のようなサイクルを組むことも考えましたが、やめました。最初からルーティンを作らず、必要に応じて自然とサイクルができていくスタイルにしました。

結果的に、週に3時間の固定ミーティングを設定するのみで、超スピードのリリースを繰り返しています。
もちろん、プロフェッショナルが集まっていることにより実現できているのですが、大きなポイントの一つは「すぐモブる」だと思っています。
モブる、とはその場で一緒に作業をするモブワークのことです。
素早く集まること、そしてSlackコミュニケーションのレスポンスの速さが超スピードのリリースの秘訣です。
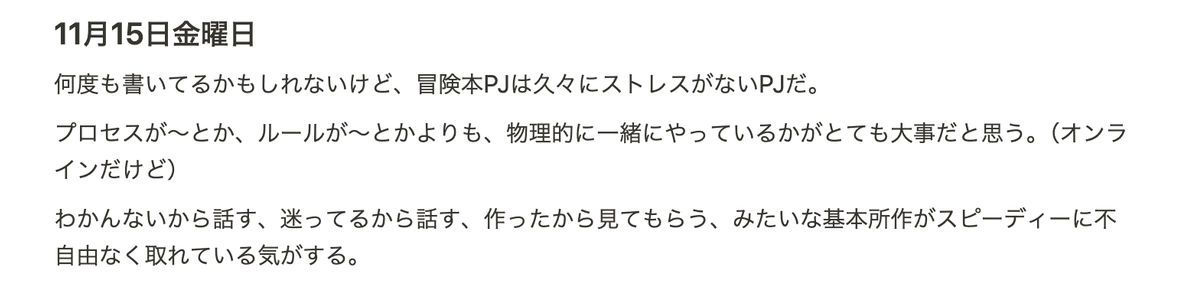

働き方のリズムや好みが違うメンバーが初めてチームを組むと、摩擦や動きづらさが発生します。
このような場合、普段はチームビルディングを丁寧に行なうようにしています。
でも今回は、チームを組んで即座にデリバリーまで走る必要があったこと、また全員がプロフェッショナル意識が高かったことから、自然に生まれたサイクルを育てるスタイルは、良い選択だったと感じています。
2. オープンな運営
複数の施策が同時並行で超スピードで進むため、クローズドなコミュニケーションを取っていると、お互いのステータスが見えず動きにくいだけでなく、クリティカルな事象に繋がることがあります。
それを解消するため、オープンな運営を意識しました。
全てのメンバーが、プロジェクトの流れと内容を俯瞰できるバックログ運用(Notionを活用した情報整理)
プロジェクトメンバー全員に、決定事項のお知らせだけでなく意思決定の経緯についても開示する。(Slackのメンショングループを活用)
ただ、デメリットとしてSlackのスレッドがカオスになり、要点を取り逃したり、長いスレッドを読む気が失せたりする現象が起こりました。
回避のためのルールを決めるなど工夫をしましたが、ここはまだ伸び代がありそうです。

オープンな運営により、各々の判断による自己組織的な動きが生まれ、それがチームのフロー状態を誘発し、さらに活気のある仕事に繋がっていくという好循環を作り出していたように思います。

3. オープンな会議
情報の透明性は、自己組織的な環境をつくるために欠かせません。
冒険本プロジェクトでは、全ての関係者が同じ場所で同じ情報に触れることに、こだわっています。
これにより、その場での意思決定スピードが早く、伝言ゲームによる認識齟齬や情報の不足を防ぐことができています。
大人数の会議は敬遠されることが多いですが、私は意味があると思っている派です。

4. 意思決定権限
最後にもう一つ、とても大事にしたことがあります。
それは、手を動かす人が意思決定をする権限を持つ状態にすることです。
冒険本プロジェクトでは、施策の根拠や大枠については週次のステークホルダー定例で共に検討をしますが、具体的なWhatやHowについては手を動かす人に意思決定権限があります。
これにより、各々がこだわり抜いた成果物をスピーディーにリリースすることが可能になりました。
私の考えるPMの役割
私は、PMの役割を環境クリエーターのようなものと捉えています。
プロジェクトに関わる人たち全員が、最高のパフォーマンスを発揮し、楽しみながら良いモノをつくるためには、どのような環境を整えれば良いだろう、ということに関心があります。
実験を積み重ねることで見えてきたものは沢山ありますが、もっと良い動きをするためには、何が分かると良いだろう?と考えています。
これが、私の2025年のテーマかもしれません。

おわりに
冒険本プロジェクトは、もう少し続きます。
冒険するプロジェクトとは何か?という問いと共に、歩んでいきます。
どんどんパワーアップするチームが、じゃんじゃんリリースしていきます!
楽しみに待っていて下さいね!
そして!
『冒険する組織のつくりかた「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』を12/31までにご予約いただいた方に、早期予約特典キャンペーンとして豪華特典をご用意しています!是非ご予約ください!
明日のアドベントカレンダーは…
MIMIGURIアドベントカレンダー15日目は…
ファシリテーターのtabaさんと、コーポレートのogawanさんです。
1日で2度美味しい!楽しみです!

