
『天晴!な日本人』 第61回 ひたすら己の信ずる道を貫いた硬骨漢、山本権兵衛 (2)
<さらなる海軍拡張へ!>
日清戦争開戦時の内閣は、伊藤博文内閣でした。外相は、カミソリの異名を取る陸奥、陸相は、これまた大人の大山巌、海相は西郷です。
大山と西郷は薩摩出身、同じ加治屋町の生まれで、親戚同士でした。
閣議では、西郷は山本に説明をさせていますが、陸軍も天才参謀と呼ばれた川上操六中将(参謀次長、のち参謀総長)をだして説明させています。
大山、西郷共に、あれこれ細かく話すことは得意ではありません。
川上は早くから桂太郎と共に陸軍を背負って立つ人材と期待され、桂と欧州視察旅行も重ねた逸材です。
ドンの山県は、軍令を川上、軍政を桂に担わせるべく、両者を競わせてもいました。
軍令は、作戦、戦闘配置、指揮命令などのことで、軍政は、予算取得と配分、軍のシステム構築、人員募集、教育、配置、軍法制定など、政治的な面を担当します。
この二つ、是非、覚えて下さい。いろいろな本に出てくる用語であり、知っておくべきことです。
川上、惜しくも早逝してしまいましたが、日清戦争勝利のために寸暇を惜しんで作戦を絞り出したせいで、一種の過労死でした。
日露戦争時には、「今信玄」と称された、天才参謀の村田怡与造も、直前に過労死していますが、明治の人間は、口先ではなく、自分の使命、国家のために自分の全てをなげうって尽くしたのです。
このように、己の内に芯、信念がある生き方だと知って欲しいですし、なぜ、それができたのか、よくよく考えて欲しいです。
現代の日本人の「やってます」などは、ほとんどのケースでやってるうちには入らないのです。
やってる、やるというのは、真摯にそのことに尽力する、没入するということで、これができるかどうかは、環境に関係なく、己の信念の深さによります。
閣議に山本を出した狙いは、それまでの「陸主海従」を改めるためでした。戦争において、主流は陸軍で、海軍はサブという「慣習」を対等にしようということです。
これは、どこの国でも「陸主海従」をめぐって陸海軍の争いがありました。この争いのせいで、大東亜戦争では、日本はわざわざ自滅した面もあったのです。
閣議では、「天才」の川上が陸軍の主派の正当性を滔々と述べました。
その後、山本は陸軍の派兵につき、朝鮮半島まで、橋でも架けますかな、とやんわり咎め、まだ一般に知られていなかった、「制海権(海上優勢)」の重要性を述べるのです。
川上は潔い人だったので、直ちにそれを認め、陸軍の参謀本部にて、それを並みいる参謀たちにご教示願いたいと申し出て、山本は陸軍参謀本部のエリートたちに教えています。
この川上の公正な振る舞いも見事です。
セクショナリズムを排して、国家のために善となれば、海軍であっても尊重し、部下のエリートたちに教えるという態度は、川上の立派な人柄を表わしています。
明治の軍人のことを知る度に、「なぜ、新興国の日本が瞬く間に強大国になったのか」がよくわかります。
このような有為な人材が数多、輩出していたのです。
輩出とは、優れた人材が続出することで、その芯となる各人の人間は、幕末から明治にかけての武士道や、質実剛健の気風のあった幼少期の教育、躾にあった、というのが私の見解です。
つまり、学校教育以外の、人間教育、倫理、気風が家庭や地域社会によって浸透させられた上に、知識の吸収があったのでした。
ここから先は
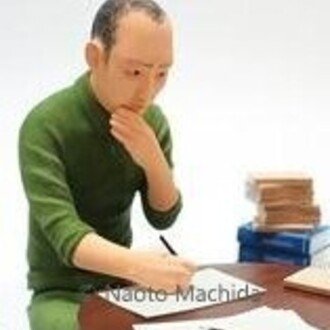
無期懲役囚、美達大和のブックレビュー
書評や、その時々のトピックス、政治、国際情勢、歴史、経済などの記事を他ブログ(http://blog.livedoor.jp/mitats…
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
