
『天晴!な日本人』 第99回 直情径行、野性のままの火の玉の女 松井須磨子(まついすまこ)(1)
<新劇とは>
今回紹介するのは、新劇女優、『芸術座』の大スターとして一世を風靡した、松井須磨子です。
新劇というのは、それまでの歌舞伎に対する呼称です。
日本の演劇は、明治の世になるまで、梨園と称される歌舞伎界の役者によるものでした。それが明治の中頃から、梨園とは全く関係のない一般大衆の間から役者や劇作家が現れ、そうした人々は自らを『新派』や『新劇』と名乗ったのです。
その魁としては川上音二郎がいますが、この人についても、時をおいて紹介します。
従来、歌舞伎役者以外の人が役者になることはタブーで、梨園の家系に生まれた人以外は歌舞伎役者になれないことになっていました。これは現代にも、ほぼ通じることです。
また、役者は「河原もの」「河原こじき」と呼ばれて蔑まれる存在でした。
そもそも歌舞伎の創始者は、出雲の阿国と呼ばれた女で、出雲大社の巫女だったとされています。彼女の演技が慶長年間(一五九六~一六一五)に流行ったことから歌舞伎が誕生したのです。
関ケ原の戦いが一六〇〇年、家康が幕府を開いたのが一六〇三年、二代目将軍に秀忠がなったのが一六〇五年、家康死去が一六一五年です。その後、一六二九年に三代将軍家光が、男女合同の狂言、これは当時の演劇のことですが、風紀が乱れるとして、女舞・女歌舞伎を禁止しました。
女が舞台に立てないことから、男が女を演じる女形が生まれたのです。
そうしたものが伝統、そこから既成勢力、既得権益となって、新派や新劇は、梨園、マスコミ、梨園を支持する上流階層から批判の嵐に遭いましたが、中流・下流階層の間に演劇を観るという、新しい文化、娯楽を普及させたのでした。
立役者は前述した川上音二郎、その妻で初の女優とされた貞奴ですが、多くの演劇人が続きました。
須磨子もその一人で、大きな貢献をしています。
これは今も言えるでしょうが、歌舞伎を観に行くというのは、上層階級、知識層にいる人で、文化レベル、所得が低い人は、そういう趣味はない人が大半のはずです。
明治の世もそうでした。昨今は、若者の間で歌舞伎を観に行く人が増えていますが、一種のステイタスというか、「私はイケてるでしょ!」のファッションの意味もあるでしょう。
知的な見栄、自分は文化水準が高い、ということもあると見ていますが、皆さんは、どう感じますか。
歌舞伎座で、大向こうから舞台の役者に向かって「音羽屋っ!」「成田屋っ!」などと声を掛けるのにも、「通」でないとやってはいかんぜよ、という閉鎖的な面もあり、スノビッシュな世界でもあります。
ちなみに音羽屋は市川一門、成田屋は尾上一門への掛け声で、市村羽左衛門への橘屋というのもあります。
ここから先は
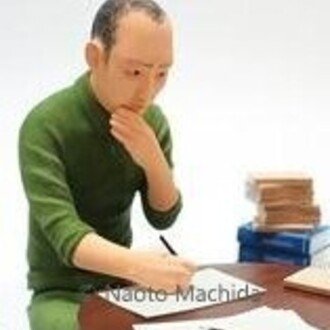
無期懲役囚、美達大和のブックレビュー
書評や、その時々のトピックス、政治、国際情勢、歴史、経済などの記事を他ブログ(http://blog.livedoor.jp/mitats…
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
