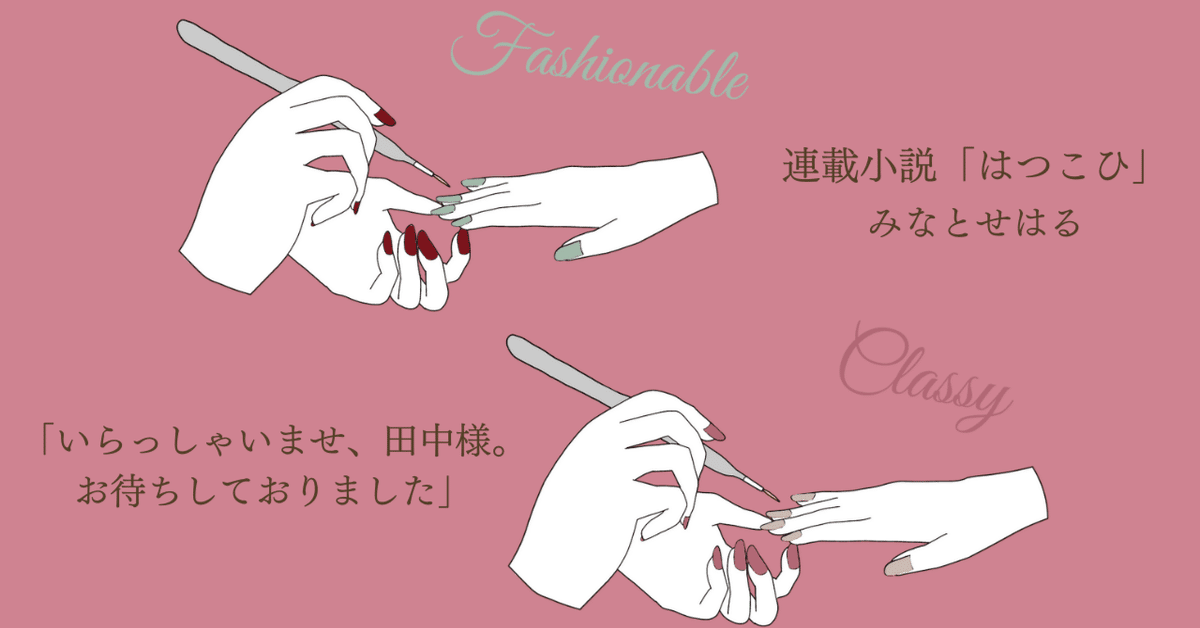
【連載小説】はつこひ 十七話
ぽつぽつと辺りの看板に明かりが灯り始めた頃、いつもより早めに店を閉めて裏側の母屋へと帰る。
寝室へ向かい襖の端を開けると、飯村さんは私が来たことに気づいて目を覚ました。
「蝶子ちゃん、会いに来てくれたのかい」
「ええ。やっと会いに来られたわ」
「本当に久しぶりだね。嬉しいよ。どうか、蝶子ちゃんの手に触れさせておくれ」
彼は金属製の手をこちらに伸ばしている。
幸い今晩は新月だった。私は皺の増えた手を二度さすり、二呼吸ほど置いてからゆっくりと右腕を差し入れる。
辿り着いた彼の手はひやりと冷たかった。小さく震える私の指先を、彼の大きな手で包み込む。
「明日も遊ぼうって昨日約束したのに、蝶子ちゃんが会いに来てくれなくて、僕は寂しかったよ」
「ごめんなさい。どうしても家を出られなかったの。許してちょうだい」
「今日は、何をする? また一緒に映画をみる?」
「……ねえ、飯村さん」
「なあに?」
「私の手は今、どんな風かしら」
彼は私の手を握ったまま、「なぜそんなことを聞くのか」と首を傾げた。
「蝶子ちゃんの手は小さくて、いつも柔らかくて温かい。それは初めて会った時から何も変わらないよ」
彼の手に少し力がこもった。
「ねえ、飯村さん。私、ずっと伝えたかったことがあるの」
「なあに?」
「あなたの手も、とっても柔らかくて温かい。いつまでも愛しているわ」
「蝶子ちゃん、僕も同じだよ。『オトナになれなくても、ずっと変わらない』」
「そうね。約束よ。『明日も、その次の日も、ずっと』よ」
「うん。『明日も、その次の日も、ずっと』だよ」
それは、古い映画の中でエイデンとメアリーが交わした約束。子供のままでいることを選んだ彼らに、果たして明日がやって来たのかどうかは分からない。けれど、彼らにとって明日が来ることはそれほど重要でなかったのではないかとも思う。
私たちの手のひらの重なった部分から熱が生まれている。
きっと、二人にとってもそれが全てだった。明日の保証がなくとも、この瞬間が何よりも必要だったのだ。
「……だから蝶子ちゃん、泣かないで」
涙を流していることを声から察知したのか、飯村さんは襖の陰に隠れた私の顔を心配そうに探している。
「これは、悲しくて泣いているんじゃないの。人間は嬉しい時にも泣くのよ」
「じゃあ、僕のもきっとそうだ。アンドロイドも嬉しい時に泣くんだよ」
彼は私の手の甲を頬に寄せると、両目からさらさらとした液体を流していることを教えてくれた。
その時、彼の頭の中で主記憶装置が「キュルル、キュルルル……」と音を立て始めた。
二人の「今」は終わりを告げ、彼はまた一人過去へと帰っていく。
飯村さんが寝息を立てていることを確認すると、静かに部屋の中に入っていった。掛け布団を肩まで掛け直すと、金色の前髪を分けて額にキスをする。
彼が同じ日を繰り返すようになってから途方もない時間が経ったというのに、こうやって触れれば私はまた恋をした。何度も、何度も、飽き足らないくらいに──。
*
二日後、カイヤさんの友達だという三人の少女が、開店と同時に賑やかにやって来た。
「いらっしゃいませ。清水谷様に妹尾様に曽川様。いかがなさいましたか?」
「あのね、田中カイヤちゃんが学校で言っていたの。ここのお店でネイルとトリートメント・メンテナンスをしたら、すっごくいいことがあったって!」
清水谷様が大きな目をパチパチさせながら、興奮気味にカウンターに身を乗り出す。
「良いこと、ですか?」
「そうなんです。カイヤちゃん、まだ将来の旦那様に出会ってもいないのに、『恋する気持ちが分かるようになった』なんていうの」
妹尾様はそう言うと、知的な印象のシルバーフレームの眼鏡を上下させて、「ちょっと落ち着きなさいよ」と清水谷様を椅子に座らせた。
「ねえねえ、そうなの? ネイルとトリートメントをすると、本当に誰かを好きになる気持ちが分かるの?」
曽川様は首を左右に振りながらツインテールに結んだウエーブの髪を揺らしている。両手の指を組んで乙女の祈りのポーズをする姿は、まるで往年のアイドルのようだ。
「確かにカイヤさんにはネイルとトリートメント・メンテナンスをさせて頂きましたが、『恋する気持ち』や『好きになる気持ち』というのは一体何のことだか……」
「ねえ、私たちにも同じことをやって! 私たちもドキドキしてみたいの。カイヤちゃん、恋は素晴らしいものだっていうのよ。ね、お願い!」
清水谷様が再び立ち上がると、妹尾様と曽川様も懇願の眼差しをこちらに向ける。透明な緑色から紫色へと変化する美しい瞳がずらりと並んだ。
「……保証はできませんが、お望みであれば……。けれど、お一人ずつ、順番ですよ?」
「やった!」と少女たちは一斉に黄色い声を上げた。
彼女たちがトリートメントを受ける順番をじゃんけんで決めている間に、十三歳の子供用の腕のレプリカを取りに母屋へと戻る。
カイヤさんから戻されたレプリカは、幸い傷もなく状態も良かった。肌の保護剤を夜の間にたっぷりと塗布しておいたが、半日陰干ししておいたのでちょうど乾いていて、どうやらこのまま貸し出すことができそうだ。
「飯村さん。あなた、何かした?」
寝室の前を通りかかり、小声で呼びかけてみる。しかし、今は眠っているようで部屋の中は静まり返っていた。
「恋する気持ちが分かるようになった」
あれは、一体どういうことだろう。さっぱり分からない。
現在のアンドロイドたちは、「自分がどういう人生を歩むのか」あらかじめシステムに組み込まれていて、恋になど興味を示さないものだと思っていた。
けれど、もしかしたら……。もしかしたら、飯村さんには「そういう力」があるのかもしれない。
彼に触れられると、きっと本当の恋を知ってしまうのだ。
私がいつまでも彼を忘れられないように、それは人間とアンドロイドの垣根も、時間さえも越えてしまう。彼の手はどんなところにも温かさを生み、愛は伝播する。
正直に言えば、彼の手のひらの温かさを、柔らかさを、他の誰にも知られたくはないけれど、いつか私の手が温かくも柔らかくもないことが露呈して彼が失望する日が来てしまうかもしれないと想像すると、あの日の私が救われたように小さな少女たちが救われても良いとも思う。
「おやすみなさい。また、今晩会いましょうね」
そっと襖に手のひらを触れた。
「はつこい」は、永遠に終わらない昨日。刹那の今日。
明日がやって来るその日まで、彼は十三歳の私の手を握り続ける。
(つづく)
(2667文字)
次回、最終回です。
第一話は、こちらから↓
いいなと思ったら応援しよう!

