
流動的な働き方が描く未来
2023年10月28日、29日の二日間にわたって開催された「北海道NPOフェスティバル(通称Nフェス)」の分科会の一つ「NPOで働く20代はキャンプ地でなにを語るのか?」をみなと計画(担当橋本)が企画させて頂きました。
後述するように、NPOで働く若者の現状や切実な声に触れるなかで、業界全体で課題を共有して若手スタッフが安心して働き続けられる環境を作らなければならないと考えていました。
そんななか、機会を頂いて、Nフェスでのこの分科会を企画することとなりました。

NPOは限られた予算でなんとかスタッフが働いている環境が多く、20代の常勤有給スタッフともなるとかなり少ないのが現状です。
もともとスタッフが少ない業界のため、常勤スタッフが代表と若手の二人体制も珍しい話しではありません。
なにが起きるのか?
若手スタッフが孤立しがちになります。
今回の分科会で登壇した3名はいずれも20代ですが、職場の中に20代がいなかったり、同じようにNPOで働く同期の友人知人がいなかったりします。
ファーストキャリアがNPOの場合、そもそも世間一般でなにが「普通」なのかもわからないので、特殊な働き方が特殊と分からないまま過ごすことになりがちです。
小さい組織だと、部署異動というものもないので、人間関係が悪化したり仕事内容が不向きだったりしても修復・改善が難しくなります。
そうして、孤立し、行き詰まって辞めてしまう。
好条件ではなくても、ミッションに共感をし、想いを持って、働くことを決めたはず。
もう少し早く誰かに相談できたら、もっと他の人や団体との交流を持てていたら、変わる未来があったのではないかと思えるケースを実際に見て来ました。
ニーズが聴こえ始める
そんなことを考えていたら、みなと計画に関わる若手や、他のNPOで働く若手スタッフから「同年代の横のつながりが欲しい」という声が同時に聴かれ始めました。
また、NPOで働くということの特殊性ではなく、自分がやりたいことをやろうとしたら結果的にNPOだった、という話しも共通して聴かれました。
これらの声からは、次世代の働き方が動き始めていて、NPO業界だけではなく、社会全体がその波に追い付いていないということが感じられました。

雇用ではない働き方
この業界に若い人材が「関わり始める」ハードルを低くし、持続的に安心して「働き続ける」環境をつくるにはどうすれば良いのだろうか?
仮説として、単独組織のみで「雇用」するのではない働き方を、業界全体で構築していくことを考えました。
例えば、プロジェクト単位で仕事を切り出し、その団体に関わりたいと思う若者に委託契約で働けるようにすると、次のようなメリットが考えられます。
▶共通すること
・一緒にプロジェクトに取り組むことで、お互いに相性が見えてくる。
・充分に理解し合えた状態で雇用につなげることが出来る。
▶働く側
・雇用契約ではない分、他の組織との兼業も容易になる。
・結果的に色々な働き方を見れて、同時に多様な人とのつながりを作れる。
・その蓄積によって自分自身の望む働き方を描けるようになる。
▶組織側
・雇用だとつい人材を囲いがちになるが、プロジェクト単位の委託契約なら他の仕事をすることに寛容になれる。
・結果的に、他の分野の視点を取り入れることができる。
こうして人材の流動性が高まると、人を介して組織同士がお互いの運営状況や課題感を共有することができて、業界全体が最適化されていくのではないでしょうか。
民間企業だと競合同士でスタッフが行ったり来たりはありえない話しかもしれませんが、特に北海道のNPO業界ならそれが出来る可能性を感じています。
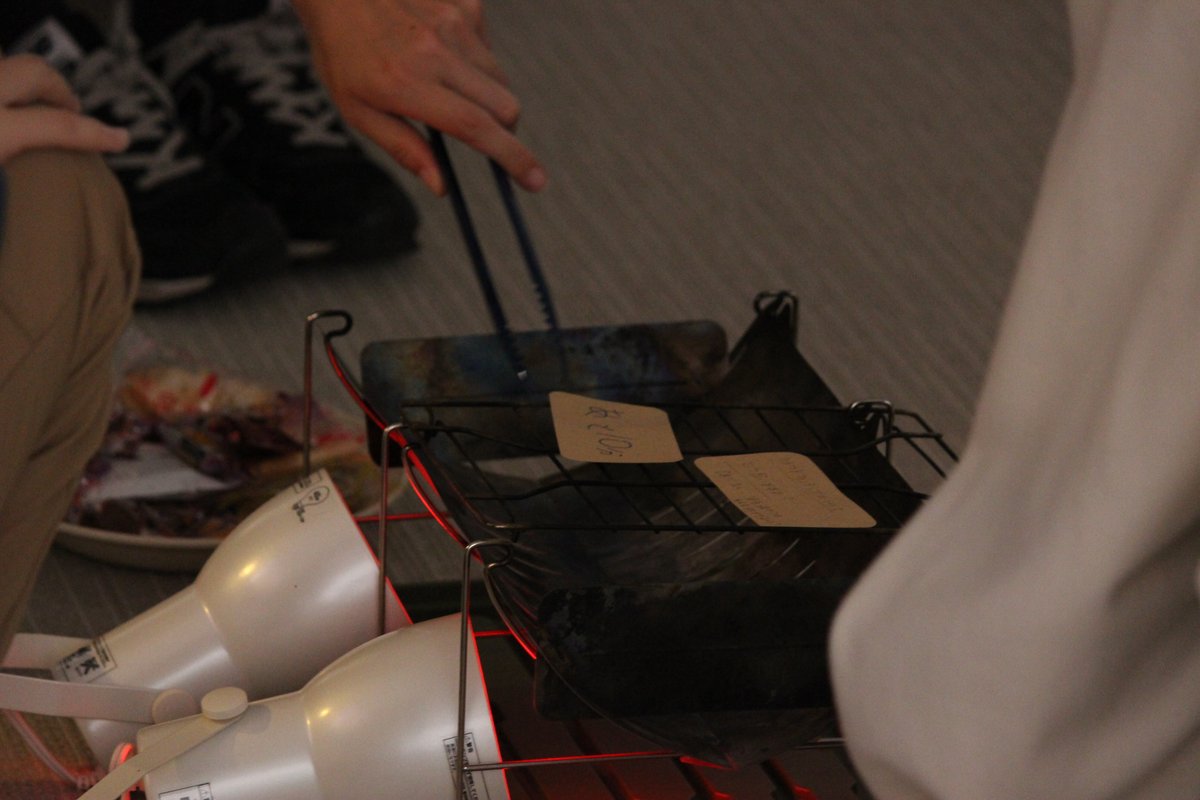
セカンドオピニオンが当たり前になる
みなと計画として考えるのは、若者自身の幸福です。
どうやっても人と組織には相性があります。
たまたまその組織のその役割が合わなかっただけで自信を失うのではなく、他の組織の役割が適任である可能性を当然のこととして考えて欲しいと思っています。
転職、兼業をどんどん重ねながら、自分自身のキャリアを模索していけることは本人にとって有意義なことであり、結果的に若者が関わりを保ち続けられることは業界全体にとっても重要なことになるはずです。
実現に向けて
それを実現するためには、若手同士がまずはつながること、若手と働く組織もその必要性を認めて職務として参加できるようにすること、この二つが重要になるでしょう。
このセッションの振り返りの会を先日行いましたが、そんな若手がつながれる場を自分たちで作っていく、その行程でこの輪がまた強くなっていく流れが聴かれました。
20代の輪は、当事者である20代自身で作られていくことでしょう。それをサポートしつつ、今現在若手が働いている組織に働きかけていったり、そのために必要になる環境を整備していくことが当方の役割になると考えています。
参考
登壇者3名がそれぞれにセッションに寄せた想いはNフェスのnoteからご覧になれます。
https://note.com/nfes2023
