
闘う偉大な指揮者と闘う宰相ピアニストの交響曲

フルトヴェングラーと交響曲──指揮者ゆえの苦悩
偉大なる指揮者である彼が、しかしながら自らを「それ以前に作曲家である 」と自認していたのは確かであろう。とはいえ彼が、決して積極的には取り上げず一定の距離を隔てし先達・マーラーとは比ぶるまでもなく、作曲家たるやと自覚するそが身、つまり「誇るべき在り方」を巡り、今日に到っても猶「顧みられざるを得ぬ」有り様を、彼岸にあって果たして如何に眺め思い遣るであろうか⋯⋯現代を生きる我々でさえ、評価が在り処をば那辺に求むるべきやと、つい遣り過ごしては途方もなくまた術なく、ただ目を瞑る悩ましさに口を噤むきらいすら否めないのではなかろうか。
とまれそんな彼とは誰あろう──ヴィルヘルム・フルトヴェングラーである。
「作曲家フルトヴェングラー」を巡る今日的評価が「正当か不当か」についてはとまれ措き、考え得る事由を試みに挙げるとするなれば、先ず各作品の「長大さ」が「顧みられざる」忌避の遠因ではあるまいか。なれど「長大ゆえ」顧みられないという言説は説得力に欠けると申し陳ぶるよりない。それゆえ演奏機会に恵まれぬとなれば、では先述マーラーがこの数十年、如何に「人気を誇るか」についての実証をすら覆そうとせる「嘘」にもなりかねぬし、やはり長大な交響曲を数多生み出しつも同じく人気を誇るブルックナーを語る術さえ失いかねない。つまるところ「長大さ」というのは(シューベルトの大ハ長調をも含め)根本的問題ならざるゆえ、オミットしてよかろう素因である。
さすれば他因に求めるよりないが、そこで浮上するのが作曲イディオムにおける古臭さ、黴臭さである。確かに彼の技法を中心にアナリーゼを施すなれば、取り分けヴァーグナーやブルックナーの「影」がちらほらと仄見えるは間違いない。それは否みようもない事実ではあれ、決して本質を穿つ命題ではなかろう。何故なら彼ヴィルヘルムのテクニカル上におけるイディオム自体、実際的には「表現主義的」作法の援用をも含め、比較的「同時代的」なるそれをも多分に──寧ろ積極的に行使をしたるノート群に明白ある以上、斯くなる評価もやはり失当とすべきであろう。
おそらく作曲家としての評価が定まらず今日へと到るは、飽くまで筆者の仮定に過ぎぬが、彼ヴィルヘルムの「指揮者としての」音楽への態度に起因するやに思われる。
曰く「ポピュリズム」が悪因的作用を及ぼしているのではあるまいか、と──そう推論してみよう。彼ヴィルヘルムは同時代ドイツ圏作曲家のみならず、ストラヴィンスキー やニルセン、バルトーク などをも積極的に取り上げているが、ある種の機会演奏会(国際現代音楽協会プログラムなど)を除けば、つまるところ「一般受け」し得よう演目=「安牌」へと配慮していたに相違なかろう。なれどそれは、平準的「同時代音楽」を敷衍するという「使命」を彼が懐胎していたなればこそ、所謂「表現者」としての「職業的指揮者」なる身であれば顧みざるを得ぬ「プログラミングにおける労苦」に過ぎぬのではなかろうか。
いずれ結果たるとて、それで彼とはニアイコールたる音楽「表現」が「古典派〜ロマン派期」の典型的「ドイツ音楽」に集約をされよう理解が「一般的見解」であるなれば、ラヴェルやドビュッシー、果ては「盟友たる」オネゲルをさえレパートワーとする彼の、極めて不幸ではあれ「現実的」イマーゴが最早「伝説化」したるとて表象せらるるポストWW IIが幻影を「栓なし」と看るや否やにさえ通じよう。
・フルトヴェングラーにみるラフマニノーフ性
要するところ、彼ヴィルヘルムは自ら「作曲家」を自認はすれど、ある種の「カリスマ性」を「担保せざるを得ぬ」指揮者としてのキャリアゆえに、コンポーザーたる「自身」をさえも等閑視せざるを得ぬ「仕事」を積み重ねし「結果たるやのイコン」としてその身を築き上げ、また我々もそを眺むるよりなき今日なのではあるまいか。そのように思うなれば、ある意味にて「ラフマニノーフ」とも相通じよう。
ラフマニノーフも兎角「誤解されがち」な作曲家であり、取り分け亡命後の彼がイディオムをして「古臭い」なる評価は、アメリカにて顕著であった。しかしである。良く耳を欹てて聴くなら、例えば亡命以前の合唱交響曲「鐘」は同時代的、否、先端を歩みし音楽であるは自明であり、最後期の交響曲第三番、交響的舞曲にせよ、一部「映画音楽的」烙印は否めずとも、充分に同時代的音楽である。斯くなる視点が許にフルトヴェングラー作品をも大局的に捕捉するなれば、往時ドイツの音楽にあっては、時に先進性など欠くとはいえ、此方も充分「同時代的それ」として我々の衷心に確たる「価値」なる美名を、彼が高名に相応しき記銘たるとて共に刻み得るのではあるまいか 。

・盟友オネゲルによる絶賛とシャスタコーヴィチとの一致点
まさに同時代人オネゲル(彼は交響的楽章第三番を、フルトヴェングラーとベルリナー・フィルハーモニカーに献呈している)が絶賛をする交響曲第二番は、作曲者自身が最も気に入っていた(否、執着をしていた)作品である。
第一番がヴィルヘルム自身の手により封印をされ(その初演は、完成から実に四十八年を経る1991年である!)、また三番を巡ってもフィナーレの扱いに逡巡をして挙句、解を得られぬままに帰天するよりなかった彼からすれば、ナンバリングさえも施されてはいない少年期のニ長調をも除く「唯一の交響曲」であったは間違いない。なればこそ、彼は生前、少なくとも6種の「第二番」をメディア=録音媒体として今日への遺産たれとて残すのである。
第二番を語る前に触れておきたい事実がある。筆者からするに不可思議であるは、第一番への彼ヴィルヘルムの態度である。何故、彼は一番を封印したのであろうか。

ある種の「当てずっぽう」的なる見方ではあるが、例えばやはり一時期「撤回」をされしシャスタコーヴィチの「第四番」あるいは初演まで漕ぎ着けるも、その「内容」が「共時的同調性」を否定するものとして当局より徹底批判されたる同「第八番」(八番を巡っては、戦中なる非常時ゆえ一大キャンペーンこそ打たれず、それで我々はつい看過してしまいがちであるが、実のところ後の「九番」「十番」以上の批判を浴び、シャスタコーヴィチは再びシベリア送り乃至は処刑をすら憂慮せざるを得ぬ事態へと直面する)──おそらくはそれらと相似的なる「事情」ゆえではなかろうかと推量する。つまるところ「国民社会主義ドイツ労働者党=ナチス」との複雑極まりない「関係性」から、自らの意思を以て撤回したのではなかろうか。この「第一番」という交響曲は、平準的なる「後期ロマン派的」作品に決して留まらぬ「時代が空気」に溢れ、俗に彼ヴィルヘルム作品へと「正鵠」たるやに押し付けられし「ブルックナー的」ソノリティも、実のところ皆無に等しい(否、僅かながらブルックナー的書式は援用されてはいるが)。第一番に関して猶も付言するなれば、寧ろ「非ブルックナー的」イディオムになる作品であると同時に「リヒャルト・シュトラウス的」後期ロマン派が王道を継承せる果実と讃ずべきであるは言うを俟たない。
・果たしてブルックナー的か否か?
いずれにせよ彼ヴィルヘルムの作品には、イディオムにおける近似性に──敢えて語弊を顧みずに喩うるなれば「致し方なく」認められしそれ以外、そも「ブルックナー的世界観」なぞなきものと思し召すが、より正しき理解への近道なのではあるまいか。
例えば「第二番」第三楽章を「ブルックナー的スケルツォ」なるそれと解説など施すメディアも数多である。確かにアントンを思わせる和声的進行なども見受けられるにせよ、実際には「スラヴ的非西欧主義音楽」と看做すが正しかろう。否、そう思惟顧慮するなれば、所謂「技法的」イディオムでさえ、慎重にアナリーゼを試みれば明白ながら、実態としては「ブルックナー的」書式を援用しながらも、それらは飽くまで非本質的要素に過ぎない。
斯く仮定の許に彼ヴィルヘルムが音楽に「ブルックナー的」それを見出し得るとなれば、おそらくは「第二番」フィナーレはコーダに「辛うじて」看取し得るか否かであろう。その程度に「フルトヴェングラーの音楽=ブルックナー的観念」とは無縁であると、明確にも口を酸く陳べておくべきではなかろうかと、そう筆者は敢えて断ずる。
尤も「ブルックナー性」をも含め、所謂「大ドイツ主義──Großdeutsche Lösung」なる幻影を我々は彼ヴィルヘルムの音楽に見出すよりなかろう。その上で「作曲家フルトヴェングラー」を正統なるドイツ的存在として「評価すべき」寄す処を探るとするなれば、偉大なる「同時代人」リヒャルト・シュトラウスをこそ、先述したる通り改めて想起すべき新たな命題そのものとして匕首宜しく突き着けられていると、そう規定し直すべきではなかろうか。あるいはシュトラウスに限らず、それら縁辺でも宜かろう。
明確に申し陳べよう。作曲家フルトヴェングラーという人は、同時代的大家たるリヒャルトと「比肩し得えよう」素質を孕む作曲家であり、掛け値なしで彼ヴィルヘルムの音楽をアナリーゼするなら、幻影としての「ヴァーグナー的」夢想のみならず、ある種の「レッテル」として捺されたる「ブルックナー」的世界観にせよ「ディリゲント=指揮者」として血肉と為したるがゆえに、それらをば偶々アウトプットされし身近なるイディオムの反映程度と認識するに止めるべきであり、まさしく「第二番」フィナーレにおける構造技法をも改めて顧慮するなれば、差し詰め「反語的」なる「エッセンス」が偶発的にも作用したに過ぎないと、そう看做すが穏当ではあるまいか。
いずれ彼は、自らを「小馬鹿にする」やの態度さえ示す高慢なヒンデミットへの弁疏をも含めその身を慎重に律すべく「ナチス」支配下のドイツへと留まり、悪名高き彼らと時に対峙しつもユダヤ系音楽家の亡命を援助、あるいはヴィーナー・フィルハーモニカーの解散阻止を始め「ドイツ音楽」を「内側」より護るべく闘うよりなかったのであり、否、それを「使命」とさえ見据え弁えていたのではあるまいか。実際のところ彼は、そのために当初は「枢密顧問官」なる役職を引き受ける危険さえ冒し、ナチス・ドイツが暗転を顕在化させつある43〜44年にはゲシュタポによる監視どころか、逮捕勾留、否、抹殺という「最悪の事態」すら想定せざるを得ぬ危急存亡へと到るまで、自ら身を賭し挺し暗闘していたは明白である。
「第一番」を封印せざるを得なき判断を下したのも、間違いなく「作曲表現」における「蹉跌」=宣伝相パウル・ヨーゼフ・ゲッベルス、何よりヴィルヘルムを親が仇の如く嫌うハインリヒ・ルイトゥポルト・ヒムラー(治安・諜報部トップ)周辺よりの「難癖と退廃芸術視=国家敵認定」を回避する上で、已むを得ざる「苦渋に満ちし」懊悩が挙句の結論であろう。なればこそ果敢にもソヴィエト・ロシアと闘い続けたシャスタコーヴィチとの相似性を、一番撤回という悲劇的挿話より嗅ぎ取る外ない筆者である。

斯く意味で「大作曲家」たる途を標榜しつつ「大指揮者」なる「人生」を選んだのやもしれぬ──そんなヴィルヘルム・フルトヴェングラーである。なればこそ彼の交響曲のうち、第二番を巡っては所謂「エッセンス」が結果ではあれ「汎ドイツ的」範疇にて「良心」的感覚をも留保し、斯く世界観を描出せると看做すべきであるは演繹的にも帰納法上にても容易く導き得よう解である。なればとて「ブルックナー的」なる「上っ面な」評価は絶対的に排除されねばならぬのではなかろうかと、そう筆者は思惟する 。
いずれにせよ、最も「ブルックナー的」書式に近しいフィナーレ(これは二番に限らず、封印をせし一番のそれにも見出すべきメタ的要素となろうか)でさえ、アントンの影は薄い。このフィナーレを特徴づけるパッセージの一部は、例えばブルックナー的書式の許に展開されるブラームス──マーラー的イディオムになるそれであり、コラールは時にクルト・ヴァイル的ですらある。確かにコーダから漂うブルックナー的構図は否めないが、それも「ブルックナー的」というよりは「ヴァーグナー的世界観」の敷衍が結果に過ぎず、あるいは同時代人リヒャルトとの連関性から「エルガー的」ソノリティをさえ現出せる音楽と呼んでも差し支えないのではあるまいか。ともなれば、フルトヴェングラーがドイツの戦況悪化も著しく絶望的局面に立たされよう1944年、つまり第一番を撤回したる直後に「価値の崩壊」へと直面しつも「Großdeutsche Lösung」を超越し、汎オイロパをさえ希求したる果実こそ「第二番」であると、そのようなる好意的評価を下して強ち謬りとはしない。
・同時代人ヨッフムのレクイエム──銘盤の数々
今般フルトヴェングラーの「交響曲全集」を網羅するは聊か骨も折れる。最も最近的それになるバレンボイム&シカゴ響「第二番」は、アマゾン辺りで検索をしても日本円にして三万円前後、安くとも4,000〜5,000円である(一方でアマゾンUK、アマゾンUSであれば、日本円にして概ね1,400〜1,500円より入手可能)。近年の大手レコード各社による買収を通じたるレーベル再編もあり、上記バレンボイム盤はいずれも廃盤までは到らずとも生産・受注ともに停止中であり、とまれ中古にて入手するよりない。ただしアルフレート・ヴァルター なる指揮者が録れし音源などは、より安価にて手にし得ようし、そのパフォーマンスも一部に低き評価にてお茶を濁す声はあれども、決して「悪いそれ」ではない。寧ろスコアリング、アナリーゼが結果たるとて捉え耳を傾けるなれば、模範的演奏であるとて筆者は推すに吝かとはしない。
モノラル録音でも構わない、となれば、何より先ずはヴィルヘルム自身がタクトを執る54年シュトゥットガルト放送交響楽団 によるライヴ盤をお勧めしよう。あるいは51年になる、ベルリナー・フィルハーモニカーとセッション収録 をせしそれも素晴らしい。また、作曲者が帰天をせし54年に本邦にても人気を博すオイゲン・ヨッフム&バイエルン放送交響楽団 が録音せるそれも、モノラルとは思えぬ明瞭な音質、何より盟友オイゲンの共感に満ち溢れる熱演が感動を呼ぶ演奏ゆえ推奨し得ようか。加えるなら、ヴィルヘルムはこのライヴ当日、オイゲンより招待を受け、プローべにも立ち会ったようであるが、残念ながらこのメディアに収められる演奏会の九日前に帰天をしてしまったという。結果的にオイゲンのこの折の演奏会はヴィルヘルム追悼のそれとなる(尚、BR-Klassikよりリリースをされているディスク・メディアの録音データを巡り、HMV-オンラインは、54年12月10日 としている。レイフ・グレイヴズによるWEB上の情報とは食い違うが、おそらく二夜連続での公演だったのであろうか?)。

とまれ「作曲家フルトヴェングラー」を巡っては、先ず「ブルックナー的」レッテルを剥がし、改めてアナリーゼを施したる上にて「あの時代か否かは措いて猶」正当的かつ真摯なる普遍的作曲家としての評価を下すべきである。
・大ドイツ主義か汎オイロパか
尚、第二番についてその概略を簡便に紹介するなら、およそ25分前後になる第一楽章、30分程に何なんとするフィナーレの両端楽章はソナタ形式を採る。
取り分け第一楽章冒頭、アウフタクトより開始をされたる「価値観の崩壊がゆえに何らをも見定め得ぬ夢遊病者が呟き」を想起させようファゴット、加えて2小節目アウフタクトよりクラリネットも加わりたる地に足さえ着かぬやに揺蕩うそれが、彼ヴィルヘルムとしては珍しく(おそらく必然的に)無調により提示されるも、そんな取り止めなき「夢か現か」を背景に、4小節目最初の裏拍より下降する両ヴァイオリンがホ短調にて「終え逝き去りぬる時代」を慨嘆する如くに奏でるは、往時が彼の「心理」を赤裸々に描き出していると捉えるべきである。これらはある意味にて「序奏=序章」的機能をも担う第一主題群であるが、前者からはクルト・ヴァイル的コラールなどが派生をし、如何にも黄昏ゆくロマンティシズムを体現する下降動機も、作品全体を有機的に統合する「ライト・モティーフ」なる役割を与えられる。その後、優美な第二主題などが確保をされつある種のレイジを表出して後、ゲネラルパウゼを挟み展開部へ移行する。極めて本質より外れたる話にはなるが、斯く「ゲネラルパウゼ=全休止」の存在もブルックナーを想起させるのであろう。しかしながらアントンのそれが、謂わば「オルガニストがストップを操作する」ために「必然として」挿入する「不可欠的装置」たるとて求められたる「技」より由来するのに対し、ヴィルヘルムの全休止にそのようなる機能は備えられてはいない。

CDレヴュワーの声には、ブルックナー的スケルツォをシャスタコーヴィチ的と捉える声も。
いずれにせよ第一楽章に認められし「影」は、アントンが亡霊よりは、リヒャルトを通じてのエルガー的ポートレート に集約されるのではなかろうか。細やかでいて穏やかなる第二楽章にも、やはりアントン的要素は本質的に影響を行使してはいないし、アタッカにて続け様に奏される第三楽章も、先述の通り「ブルックナー的スケルツォ」なるソノリティよりは寧ろ、ドイツ圏域を含む「中東欧」スラヴ的「響き」=ユダヤあるいはロマ的要素さえ目立つと、そう筆者は捉えるよりない。
フィナーレにしても猶、である。やはり先にも陳べし「コーダ」にアントン・ブルックナー的「世界」が仄見える程度であろう。
結局のところ、縷々申し陳ぶる「Großdeutsche Lösung」が導く相対化されし後期ロマン派的「ドイツの正統」を宣言しつも、剰え時代が要請(44年作曲開始〜45年10月完成)ゆえなる「汎オイロパ的」交響曲と看取すべきであろう。
闘う宰相ピアニスト──パデレフスキの交響曲
さて──。
ヴィルヘルムが好むと好まざるとに関わらず、後期ロマン派的枠組みになる交響曲を生み出す以上、それが「汎オイロパ的」性格を懐胎せざるを得ぬはある意味「宿命的」であったと顧みるべきやもしれぬ。何より彼が、ドイツ圏域を「祖国」としまた活動の核心的中心と捉えていた事実から照射すれば、殊更とも謂うべきであろう。
35年前の、所謂一連の「東欧革命」直後、ドイツにおいては「ツェントラル・オイロパ(Zentral Europa)=中東欧」なる概念を巡り盛んにも取り沙汰されていたのであるが、無論それは「領土的野心」とは最早係りなき新たな思想的概念になるスキームとも呼ぶべく提唱されたるのであり、当初的には分断国家「ドイツ」再統一へのスローガン的役割を担う枠組みであった。加うるに、ポスト「冷戦」後の地平に漸く貌を覗かせ始めし「太陽=汎オイロパ」思潮を担保せしむる、まさに「黎明が光」そのものでさえあった。
「中東欧=Zentral Europa」という概念の難しさは、今日ウクライナ問題の錯綜と膠着に暗き陰を翳すなる意味において極めてセンシティヴではあれ、近世そして近代的巨勢大国「台頭以前」を巡り思いを馳せるなら、言語・民族の差異は聊かあれど、例えばエスニック・グループ間における「連帯」と「離反」──謂わば離合集散を繰り返しつ、一定の共存共栄をも現出せる、ある種の淵源的「メルクマール」であるは確実である。そう、例えばトランシルヴァニアの平原やカルパチアの山地においては、マジャールやロマニアが混在をして猶、緊迫的なる「常在戦場」では決してなかった事実を我々は、オスマーン・トルコ進出前後たる緩衝地帯「ワラキア公国」(かのドラキュラこと串刺公ヴラド・ツェペーシュで知られたる圏域)における縁辺他圏との関係から、歴史的過程における「智慧として」辿るも容易かろう(ある種のトリヴィア的小話ではあるが、黒海沿岸という要衝を押さえしモルダヴィア公の末裔になるラフマニノーフには、ヴラド・ツェペーシュが血脈も混入をしている)。
斯く意味において、最も「象徴的」なる存在たるとて記銘すべき圏域こそWW II以前の「ポルスカ」(ポルツカ)ではあるまいか。
・闘う情熱が民ポルスカとエスニシティ──「消滅国家ポーランド」
まさに「大平原たる」かの地においては、往古よりスラヴ系、ゲルマン系が混在をし、やがてゲルマンの西遷に伴い、スラヴ系が中世初期より「中核的勢力」とて覇権を握る。取り分け、所謂「ローマ王権=神聖ローマ王権」には左右されず、寧ろ対等とも呼ぶべき位置にありしピャスト朝、次いでリトアニアとの連合王統たるヤギェウォ朝──貴族(シュラフタ)共和政体という絶頂期を迎える。
なれど近世以降、東からはロシア、西からはドイツ(更には南からはオーストリア)による侵略・蚕食が挙句、彼らが国家は地図上より消えるよりなき過酷なる運命を辿る。ゆえにか否かは措き、彼らは「誇るべき民族が歴史」を奪還すべく、情熱的にも根気強く「闘う」民族性を獲得したのやもしれぬ。それは様々な歴史的事象 が証明をする通りであり、近年的には前述「東欧革命」時における「円卓会議」という「叡智」をさえ生ましむるのである。
そんなポルスカ──情熱的にも闘う誇り高き人々を代表すべき偉人こそ「宰相ピアニスト」つまりは政治家にして音楽家たるイグナツィ・ヤン・パデレフスキであろう 。
「中東欧=Zentral Europa」とウクライナについては先にも触れたが、本来的には、現在ウクライナの西部圏域は「ポルスカ」そのものであった。今般ポーランド(WW II以降のそれ)という国家は斯くなる意味にて──否、近代期「第二共和政」をも含め、その国境線の「遷移」が著しく、圏域域内設定は「人工的」ですらある。なれど、これは結局のところ偶然の産物ではあれ、WW I直後に提案をされる、史学用語としての所謂「カーゾン・ライン」が、民族としてはポルスカとルーシ、宗教上ではカソリックと東方正教会との、まさに「此岸と彼岸」そのものであったは、これぞ「天の采配」と呼ぶべき必然が産物とも形容すべきであろう(リトアニアなど一部は除くが)。

とはいえ、ポルスカにとってはより東部圏域に至るまで「歴史的故地」なる主張は根強く、ポーランド・ソヴィエト戦争により「主張通り」の東部国境を確定する。確かにそうして獲得したる地には、ヤギェウォ朝以来の枢要なる都市ヴィリニュスも含まれていたし、リヴィウは無論、パデレフスキの故郷であり彼が家系(シュラフタ)の領有せるポジーリャ西部をも含む「歴史的東方」の限界までをも包摂するものであった。いずれ歴史談義は、この辺りで一旦切り上げるとして──。
つまりポルスカが貴族たるシュラフタの家系になるパデレフスキは、今日ウクライナ領たるポジーリャ(ポドリア)に生を享ける。
・衝撃的な最初の記憶
幼少期における彼の最初の記憶が、1863年一月蜂起に伴う父ヤンの逮捕・拘禁なる事実は、闘う宰相ピアニストたる彼の存在そのものをも象徴する挿話であろう。とまれイグナツィは、収監をされし父が不在であった頃よりピアノへと触れるのであるが、彼イグナツィとピアノとの直截的「出会い」が如何なるものであったかは措いて、父ヤンは当初、ヴァイオリンを学ばせるつもりであったという。ゆえに彼イグナツィの最初の教師はヴァイオリニストであり、結果たるとて満足すべきピアノ教育を受けられずにいたのは確かであり、それは十二歳にしてヴァルシャヴァ音楽院への入学を果たして以降も猶、暫く続くのである。尤も、作曲や楽理を巡る学習は順調であったという。

彼イグナツィがピアニストとして大成をせる契機へと与るは、ヴィーン音楽院はテオドル・レシェティツキへ師事したる過程が齎した結果ゆえと看做してよかろう。イグナツィは既に齢二十四──つまりは前史(ヴァルシャヴァ以前)をも含めるなら、二十年というかなり長い歳月を費やしたる、まさに「忍耐」が賜物である。実際のところ、ピアニストとしての彼は大器晩成であり、最初の成功体験は88、89年のパリでのリサイタルであり、翌90年のロンドン・リサイタルで、齢三十を数えよう彼イグナツィの名声は、愈々決定付けられる。

作曲家としても、この時期には充実したる成果を挙げつつあった。
そんな彼の、しかしながらほぼ最後の作品(実際には、最後より二つ目のそれ)こそ、1909年に公開をされたる唯一の交響曲つまりロ短調 op. 24「ポローニア」である。

写真は比較的最近、サリュソフォーンの製造に乗り出した独の楽器メーカー・エッペルスハイムの製品(新住区・管楽器専門店ダク様より拝借)。
今日確認をされている彼イグナツィになる管弦楽作品は、協奏的作品をも含めるなれば四タイトルと非常に少ない(オペラをも含めて猶、五タイトルに止まる)。しかしながらその管弦楽書式は、実にも天才的ソノリティで我々を驚嘆へと誘おう。実質的には三管編成を採る書式ながら三本のサリュソフォーン 、サンダーマシーン乃至はサンダーシート(スコア上ではトルトニオン。彼イグナツィの依頼により開発されたオリジナル楽器のようで、そのサウンドは通常のサンダーマシーン等より遥かに効果的である)をも含む数多の打楽器、更にはオルガンをも加えたる記念碑的大作である。三楽章構成になるが、当初はスケルツォに相当する楽章を含む四楽章になる交響曲として企図されるも、スケルツォ的楽章は一部スケッチが遺されるのみで最終的には放棄をされている。
・記念碑的大作「ポローニア」
その霊感的淵源は、彼にとっての原風景──最初の記憶と密接に結びつく。つまるところ1863年一月蜂起を背景とする「愛国的カリカチュア(風刺画) 」が描く、ルーシに支配されたる往時ポルスカの「惨酷なる現実」を通じ、過去、現在、未来への希望へ寄す謂わば「音詩」(無論、交響詩たるそれとは係りのない)世界を顕現したる作品であり、聊か「龍頭蛇尾=フィナーレ三楽章の陳腐なる」安直的手法を巡っては少なからず「謗りを免れぬ」側面はあれど、劇性豊かなる「ドラマトゥルギー」に溢れし傑作と看做すに謬りとはしない。
取り分け第一楽章冒頭序奏部の、サンチマンタリスム──感傷的なる表現は、ポルスカならでは、否、ポルスカたるイグナツィでなければ生み出し得ぬそれではなかろうか。まさしく「ロマンティシズム」の極致であり、当楽章がテーゼたる「古なるポルスカが映えある嘗てなる日々」を追憶せるノート群そして和声に修飾をされたるは「美」そのものであろう。余りに濃厚にしてかつ繊細を究めしそれは、時に儚げな「栄枯盛衰」を恰も慰るやに響く。これら序奏部に呈示されたる諸要素が、絶妙なるバランス上にて緊密にも第一楽章を構築していく。
感傷と憧憬に彩られし音世界は、練習番号7以降、ある種のレイジに包まれし容貌をやがて露わとし、作曲をされたる「同時代=実質的にルーシによる実効支配」を未だ被る二十世紀初頭つまり後期ロマン派風の共時的音楽へと発展する。

そして我々は気づくのである。
そう、後のヴィルヘルムに看る、リヒャルト・シュトラウスやエドワード・エルガーにも通じよう「豊穣なソノリティ」に──しかしながら、同時に我々は、その大いなる相違にも気づかされよう。
所謂「エスニシティ」との関わりである。
・エスニシティとインターナショナルの狭間で
「お国柄」とか「趣味観」というのは、街単位、あるいは所属したる階級階層単位にて時に表出をするが、俗に「国民性」なる謂われも存在する通り、メタ的に抽出するも可能である。例えばヴィルヘルムは大都会ベルリン出身であるが、ベルリン・ブランデンブルクはプロイセンの中核都市であり、プロイセン=「Großdeutsche Lösung」を標榜する「小ドイツ主義=Kleindeutsche Lösung」国家(つまりドイッチェラントそのもの)であり、そこから我々は「峻厳さ、生真面目さ」という性格性を、一般論として連想し得るやもしれない。他方で、そんなドイッチュとは混住をせる西スラヴ系──此処では差し詰めポルスカとチェスキのみを想定するが、チェスキは「峻厳さ、生真面目さ+冷静」なる顔を、対するポルスカは「峻厳さ、生真面目さ+情熱的」なる特性を持つと、筆者は斯く眺める(飽くまで各民族と接しての個人的知見=少なからず主観に立脚するは留意願いたい)。あるいはポルスカの場合、天文学や数学など理数系に強い、なるイメージをも抱かせようか。
もう一人の主人公・イグナツィの出身圏域であるポジーリャ(ポドリア)を巡っては、先ず筆者が連想せるはオスマーンをも含む「民族の坩堝・交叉路」という側面である。同地はキーウ・ルーシなどの東スラヴ系民族、あるいはアジア系のタタールやモンゴル、更には先述テュルク系たるオスマーン帝国などが、時に犇めきまた覇者となるという意味で文字通り「坩堝・交叉路」とも看做すべき地であるが、イグナツィが生まれたる十九世紀中葉は、父ヤンを始めとする支配者層たるポルスカ(シュラフタ)が許に、ウクライナ系の被支配者層が主に農業を生業の核たるとて生活を送る地域へと移行してはいたものの、やはり歴史──その記憶というのは、エスニシティなる概念が環境的要因に左右されよう指向性を示すが如くで、ゆえにイグナツィは生まれながらにして「インターナショナル」気質を備えていたのだとの理解も容易く導き得よう。なればとて彼は、政治家へと転身するWW I 以降、宰相つまり首相として、また外相として「タフ・ネゴシエーター」振りをも発揮し得たのではあるまいか。
然りながら「インターナショナル」という性向は、ゆえに反作用としての「ナショナリズム」をも良き意味にて煥発するのやもしれぬ。況してや「近世以降」国そのものを失いしポルスカたる彼イグナツィからすれば、アイデンティティを再獲得する上で、その帰属意識は誰よりも強烈であったは慥かであろう。ゆえなる「ネゴシエーター」とも言えよう。なればである。
唯一の交響曲に標題性──プログラム性を仮託しつ、誇るべき「ポローニア=ポーランド」と名付けたのであろう。
・「傑作」か──それとも「駄作」か⋯⋯闘う宰相の光芒
いずれ劈頭からして、先述の通りポルスカならではの風合い、香りを色濃くも反映するロマンティシズムに溢れし音楽は、第一楽章にては過去の栄光を、第二楽章では国を失いし今日(二十世紀初頭)ポルスカを、そして第三楽章フィナーレではポルスカにやがて訪れよう「幸いなる未来」を託し予言するやに、彼イグナツィは一大「散文的」叙事詩としての夫々を編む。齢四十八にしての大作である。しかしながら──作曲家としての彼は果たして、真に成功したと断じ得るであろうか。
イグナツィは、かのグスタフ・マーラーと同年の生まれであり、謂わば相前後したる「世代」なる意味にて、エルガーやリヒャルト・シュトラウス、ディーリアスともほぼ時代を同じくしている。斯く思うなれば、イグナツィ・パデレフスキの生み出したるこの交響曲に関して言及するなれば、充分に同時代的ではある。少なくとも第一楽章、加えて悲劇的ドラマを描きたる第二楽章に関してはそう評価を下して良かろう。なれど第三楽章フィナーレを巡っては、如何に判断すべきであろう。
筆者の耳には「聊か散漫、かつまとまりを欠く」それとして届いてしまう⋯⋯そんなきらいを、どうにも否めない。劇的であるは間違いない。トルトニオンの轟きも効果的であろう。ポーランド国歌(所謂「ドンブロフスキのマズルカ──別名「ポーランド未だ滅びず」)に基づく終盤の対位法的書式も感動と共感を呼ぶ。なれど先述せる「安直的手法」が結果の「散漫さとまとまりのなさ」が、つまり「謗りを免れぬ」要因であると仮定するなら、作曲家たるイグナツィの、あるいはこれが限界なのやもしれぬ。この交響曲の魅力は、確かに「交響的幻想曲」とでも形容すべき「比較的自由なイディオム」を駆使している点に明白ではあれ、結果たるとて聊か「まとまりを欠く」フィナーレであるとするなれば、曰く「画龍点睛を欠く」であろうか。
イグナツィ自身、何よりそれを理解していたのではなかろうか。
ゆえに彼は、その後「沈黙」を守りつ作曲から遠去かり、遂には政治家へと転身する直前、つまり1917年にものする、自作詩になる男性合唱とピアノ、管楽アンサンブルのための讃美歌「ヘイ 白き鷹よ」を最後に、作曲家としての自らへと「ピリオド」を打ったのやもしれぬ。とまれ──。
この「黄昏ゆくロマンティシズム」を体現するやの交響曲は、ポルスカであるイグナツィならではのオリジナリテと天才性が、謂わば「光芒」煌めき尾を引く⋯⋯そのような音楽であり、斯く意味にて彼の代表作であるは間違いない。
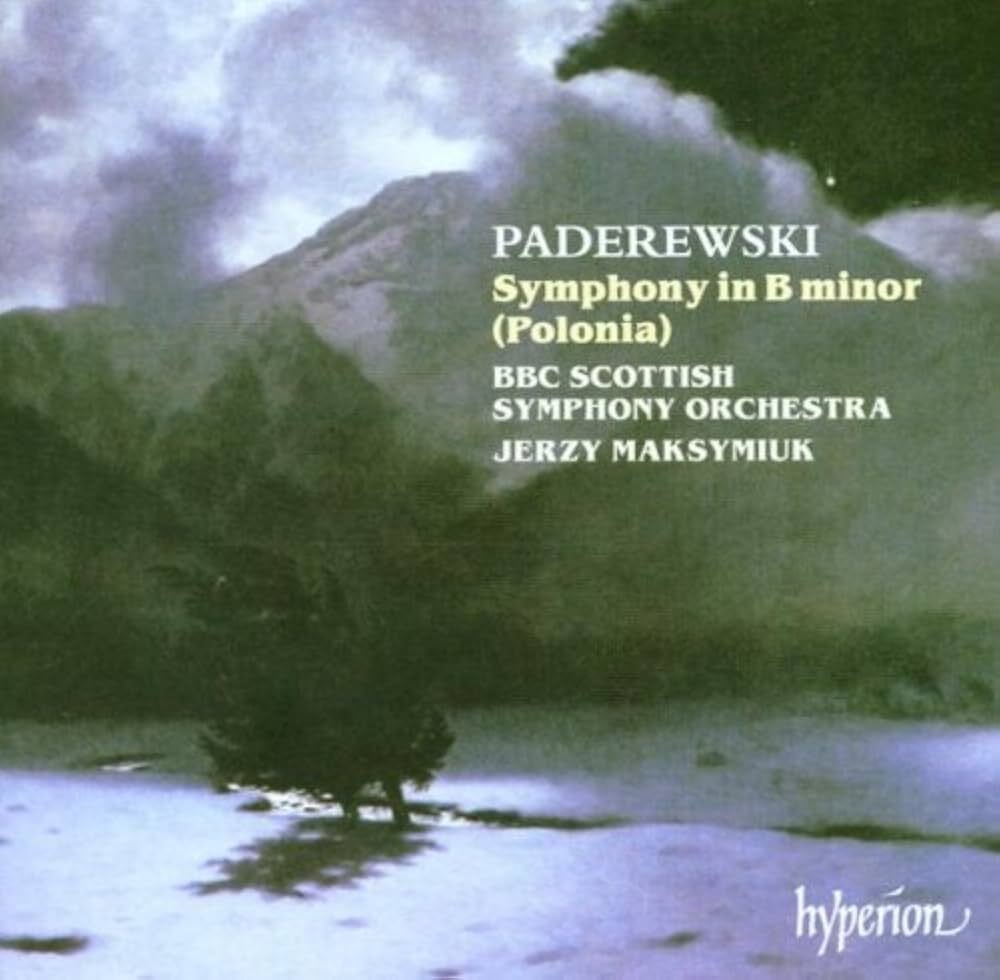
今日、この交響曲を巡っては少なくとも2種のメディアにて愉しめよう。永らく忘れられていたこの交響曲の「復活蘇演」に与りしイェジィ・マクシミウク&BBCスコティッシュ交響楽団 、グジェゴシュ・ノヴァク&ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 の2タイトルがCDメディアとして入手可能である。Apple Musicをご利用の諸兄姉であれば、加えてボフダン・ボグシェフスキ&リヴィウ国立フィルハーモニック交響楽団盤 をも、第三の選択肢とし得よう。
脚注
音楽評論家・史学者マーク・ブライドル。/http://www.musicweb-international.com/classrev/2002/aug02/Furtwangler_Symphony2.htm
作曲家レイフ・グレイヴズ。https://www.wtju.net/furtwanglers-2nd-gets-sympathetic-treatment/
1930年2月23、24日。ベルリナー・フィルハーモニカーとの演奏会メインプログラム。バレエ音楽「春の祭典」。また戦後53年5月18日ベルリナー・フィルハーモニカー演奏会では「妖精の接吻」を指揮、こちらはLP、CDなどにて過去に複数回リリースされている。
例えば1927年7月1日、フランクフルトで開催された国際現代音楽協会第5回演奏会。バルトーク自身のピアノによる「ピアノ協奏曲第一番」及びニルセンの「交響曲第五番」が取り上げられている。同じく戦後53年9月には、メニューヒンをソロにバルトークの「ヴァイオリン協奏曲第二番」をセッション収録している。
アルトゥール・オネゲルは少なくとも、フルトヴェングラーの交響曲第二番について「L'homme qui écrit une partition aussi riche que sa deuxième symphonie ne peut être discuté. Il est de la race des grands musiciens──これほど豊穣にして贅を凝らす音楽を描ける人物を巡っては議論の余地さえない。彼は偉大なる音楽の血脈を継承する存在である」と絶賛している。※フルトヴェングラー協会1992年7月ニュース:音楽プロデューサー、ステファン・トパキアン「フルトヴェングラーとオネゲル」(再掲:2017年5月)より。以下PDFは最終ページ、中段第四節を参照されたし。
https://furtwangler.fr/wp-content/uploads/2017/05/honegger.pdfクリストファー・フィフィールド「縁と繋がり」:ミュジカル・タイムズ Vol. 131. 1770──1990年8月号。426ページ。この珍品的北欧・ドイツ音楽の発掘に精力的な(本邦では馴染みの薄い)指揮者・音楽学者はフルトヴェングラーの二番を巡り、同誌上記コラムにて「ブルックナー並の長さであるが、ブルックナー的霊感を欠いており、それゆえに長大な規模を維持し得る魅惑的素材・敷衍とは縁も薄い」と、その評価は辛辣極まりないが、斯く論評が許されし理解的土壌を培い養う「ブルックナーとの相似性」を議論する風潮へと注ぐべき疑念の眼差しを、我々は楽曲研究を通じ求められていると気づかされよう。そのように眺めるなら、フィフィールドの「看過し得ぬ」誤謬に成り立つ論点は、フルトヴェングラー作品への理解が未だ浅薄である事実をも浮き彫りとする「好材料」として重要であるとも捉えて、如くはない。
アルフレート・ヴァルター&BBC交響楽団。1992年。マルコ・ポーロ。カタログ番号8.223436。
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー&シュトゥットガルト放送交響楽団。2005年。 ARCHPEL. カタログ番号ARPCD0276。
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー&ベルリナー・フィルハーモニカー。2024年。ドイッチェ・グラモフォン。カタログ番号UCCG-41200/1。
オイゲン・ヨッフム&バイエルン放送交響楽団。2010。BR-クラシック。カタログ番号900702。
作曲家レイフ・グレイヴズ。 https://www.wtju.net/furtwanglers-2nd-gets-sympathetic-treatment/
ヒャルト・シュトラウスは比較的初期よりエルガーを絶賛しており、生涯に亘り交友を温めたという。彼リヒャルトのエルガーへの評価は、ウィリアム・ヘンリー・リード「エルガー」(1946 。ロンドン。デント社)に詳しい。
取り分け記銘すべきは、ポーランド・リトアニア共和国が劣勢を回復したる時期たる1791年5月に発布、施行されし史上初の民主的成文憲法(所謂「5月3日憲法」)であろう。あるいは本文にて後述する1863年一月蜂起(パデレフスキの父は、同蜂起を契機とする一連の反ロシア闘争に参加、結果としてロシア当局により逮捕される)も同30年代蜂起と同じく象徴的なる歴史事象であろう。
彼の氏名はポルスカにてはIgnacy Jan Paderewskiと記綴され、本邦においては慣習的に「イグナツィ・ヤン・パデレフスキ」とカナ転写されるが、ポルスカにも、単に「記号符」が整備されていないだけで「長音」は存在しており、例えばアクセント(次末アクセント。語尾より二音節目に配される強勢アクセント)との係りから、実際には「イグナーツィ・ヤン・パデレーフスキー」のように我々の耳には聴こえよう。
アドルフ・ザックスのライヴァル的存在たる楽器製作者ピエール=ルイ・ゴートゥロー発案になる、金属製のダブル・リード式木管楽器。ソプラニーノから、三つの異なるキイになるコトラバスまで全9種の体系的楽器群として開発され、フランス陸軍軍楽隊長を務めしサリュースにより命名される。野外演奏におけるオーボエ、ファゴット各パートを補強あるいは代用する役割を担っていたが、今日ではコントラバスなど低声3種のみが稀に顧みられるのみである。
アルトゥル・グロトゥゲルなる画家による、漫画スタイルを採る8タイトルのシリーズに影響されたものと今日では考えられている。
レーベル、ヘリオス(Hyperion)。カタログ番号CDH55351。
レーベル、NIFC。規格番号NIFCCD065。
レーベル、DUX。品番DUX1636。
動画とタイムライン
https://www.youtube.com/watch?v=FSlXQ6Qf4rI
00:00:00 オープニング
00:00:38 ナヴィゲーションと解説1
00:04:12 フルトベングラー:交響曲第二番ホ短調第一楽章(解説)
00:27:12 フルトベングラー:交響曲第二番ホ短調第二楽章(解説)
00:40:15 フルトベングラー:交響曲第二番ホ短調第三楽章
00:56:03 フルトベングラー:交響曲第二番ホ短調第四楽章
01:26:20 ナヴィゲーションと解説2
01:32:16 パデレフスキ:交響曲ロ短調 op. 24「ポローニア」第一楽章(解説)
01:56:53 パデレフスキ:交響曲ロ短調 op. 24「ポローニア」第二楽章(解説)
02:11:26 パデレフスキ:交響曲ロ短調 op. 24「ポローニア」第三楽章
02:35:54 エンディング:参考文献
参考文献
Bridle, Marc. "Wilhelm Furtwängler. Symphony No. 2"
Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim
http://www.musicweb-international.com/classrev/2002/aug02/Furtwangler_Symphony2.htm
Fifield, Christpher. "Relationships", The Musical Times, Vol. 131, No. 1770 (Aug., 1990). Furtwängler,
Furtwängler, Wilhelm.”2. Symphonie”, Bruckner verlag. 1952.
Furtwängler, Wilhelm. "Notebooks, 1924–54”, Quartet Books. 1995.
Furtwängler, Wilhelm. “Symphony No. 2 in e minor(session)
Daniel Barenboim & Chicago Symphoby Orchestra”, TELDEC. 2002.
Furtwängler, Wilhelm. “Symphony No. 2 in e minor(Live)
Eugen Jochum & Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks”, BR-Klassik. 2010.
Furtwängler, Wilhelm. “Symphony No. 2 in e minor(sesion)
Wilhelm Furtwängler & Berliner Philharmoniker”, Deutsche Grammphon. 2024.
Furtwängler, Wilhelm. “Symphony No. 2 in e minor(live) Wilhelm Furtwängler & Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR”, ARCHPEL. 2005.
Furtwängler, Wilhelm. “Symphony No. 2 in e minor(Session)
Alfred Waler & BBC Symphony Oechestra”, Mrco Polo.1993.
Furtwängler, Wilhelm.”Ton und Wort”, F. A. Brockhaus. 1956.
Graves, Ralph. "Furtwangler’s 2nd gets sympathetic treatment”, WTJU. University of Virgina.
Mugmon, Matthew. ”Fun with Scales: Furtwängler's Second Symphony ──Unsung Symphonies”,
Prieberg, F.K. "Trial of Strength: Wilhelm Furtwängler and the Third Reich”, Quartet Books. 1991.
Reed, W.H. “Elgar”, London: Dent. 1946.
Topakian, Stéphan. “FURTWÄNENGLER ET HONEGGER“
https://furtwangler.fr/wp-content/uploads/2017/05/honegger.pdf
Lawton, Mary. Paderewski, I.J. “The Paderewski Memoirs“, London: Collins.1939.
Dorosz, Janina, Marczewska-Zagdanska, Hanna. "Wilson - Paderewski - Masaryk: Their Visions of Independence and Conceptions of how to Organize Europe,”, Acta Poloniae Historica. 1996.
Paderewski,Ignacy. Jan.“Symphonie“, MENESTREL , Heugel & Co.1911.
Paderewski,Ignacy. J.“Symphony in B minor op. 24 Polonia
Boguszewski , Bohdan. Liviv National Philharmonic“, Dux .2021.
Paderewski,Ignacy. J.“Symphony in B minor op. 24 Polonia
Maksymiuk, Jerzy. J. BBC Scottish Symphony Orchestra“, Hyperion. 1998.
Paderewski,Ignacy. J.“Symphony in B minor op. 24 Polonia
Nowak, Grzegorz. Royal Philharmonic Orchestra“, NIFC. 2020.
Strakacz, Aniela. “Paderewski as I Knew Him. (transl. by Halina Chybowska)“, New Brunswick, Rutgers University Press.1949.
イグナツィ・ヤン・パデレフスキ, メアリー・ロートン, 訳:湯浅玲子.
“闘うピアニスト パデレフスキ自伝(上下巻)“, ハンナ, 2016.
国立音楽大学附属図書館広報委員会, “生誕150周年 イグナツィ・ヤン・パデレフスキ“, https://www.lib.kunitachi.ac.jp/wp-content/uploads/2024/01/tenji1006.pdf
日本パデレフスキ協会公式サイト
三浦元博, 山崎博康, “東欧革命──権力の内側で何が起きたか“,岩波新書, 1992.
渡辺克義 , “物語 ポーランドの歴史──東欧の「大国」の苦難と再生“,中公新書, 2017.
